 初秋便り
初秋便り
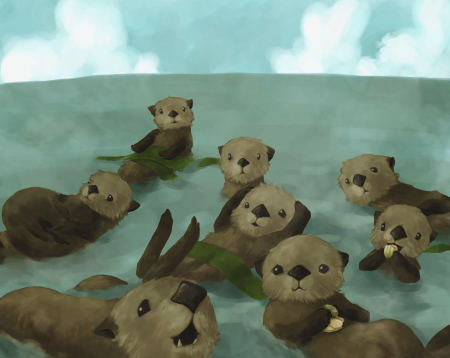 |
■ショートシナリオ担当:紺野ふずき 対応レベル:1〜3lv 難易度:普通 成功報酬:0 G 71 C 参加人数:6人 サポート参加人数:-人 冒険期間:10月26日〜11月01日 リプレイ公開日:2004年11月06日 |
|
●オープニング
ある山間に温泉宿が出来た。すっかり準備も整い、あとは来客を待つだけと言う時になって、若女将が裏庭にたくさんの犬の足跡を発見したそうだ。
裏庭は林から山へと繋がっており、以前から、鳴き声だけは聞こえていたのだが、こんなに直ぐ傍までやってきたのは初めてだと言う。
今のところ、被害は無い。
しかし、野犬なら腹を空かせて気が立っているだろう。
使用人達も不安がっているし、万が一、客が襲われたら評判もがた落ちだと、若女将は当惑した。
「飯炊きの匂いでも嗅ぎつけて来たのでしょうねぇ。とにかく、そんなものがうろうろしていたら宿を開けませんから、残さず倒してくださいまし。お礼と言ってはなんですが、一番初めのお客様として当館をご案内させていただきます」
風も涼しさを持つ秋。
虫の音を聞きながらの月見湯は最高だろう。
「お部屋の手配も、皆様のご希望があればご遠慮なく申しつけくださいましね?」
もはや温泉で楽しむことが冒険者達の目的となったようだ。
野犬退治はおまけである。
●今回の参加者
ea0214 ミフティア・カレンズ(26歳・♀・ジプシー・人間・ノルマン王国)ea0708 藤野 咲月(28歳・♀・忍者・人間・ジャパン)
ea3363 環 連十郎(35歳・♂・志士・人間・ジャパン)
ea5011 天藤 月乃(30歳・♀・忍者・人間・ジャパン)
ea5419 冴刃 音無(30歳・♂・忍者・人間・ジャパン)
ea6321 竜 太猛(35歳・♂・武道家・人間・華仙教大国)
●リプレイ本文
●敵は八十両水気の絶えない堀井戸の周辺は、地面が柔らかく湿っており、犬たちがやってきた痕跡を、はっきりと残していた。
冴刃音無(ea5419)が読みとった足跡は全部で四頭。林からやってきて、同じ方角へと消えている。
「何もしてない内から殺すのは可哀相だけど、危なくてお客さんが近寄れないんじゃ仕方ないよな」
「それが依頼主殿の希望じゃしのぅ」
歯切れの悪い音無の傍らに並んだ竜太猛(ea6321)は、裏庭から先に広がる山林に目を細めた。
朱、黄、黄緑、橙色。
鮮やかな落葉が敷き詰められた景色の中、満ち足りぬ腹を抱えた犬たちが去ってゆく姿を思い浮かべる。
「わんこさん‥‥越後屋さんで買ったら、すっごく高んだよね‥‥」
二人の背後で、少女は大きな溜息を漏らした。
華奢な肩をがっくりと落とし、振り返った二人へと青い目を向けたのは、ミフティア・カレンズ(ea0214)である。
代金に換算すると四頭で八十両。
その上、品書きはいつも『売り切れ中』と掲げられている。野犬や山犬は珍しくないのだが、家畜としての犬はとても貴重なのだ。
「餌をあげてみて大人しい子だったら、連れて帰れないかなぁ」
すがるような目で、ミフティアは音無と太猛を見上げた。
少しだけ。いや、かなり本気かもしれないその眼差し。
これには音無がギョッとして切り返した。
「まさか、飼う気なのか?」
「それは無理じゃろう。ミフティア殿も危なかろうし」
太猛が首を振ると、音無の問いに頷きかけたミフティアの顔は、そのまましょんぼりと項垂れた。
「ちょっとだけ‥‥様子を見るだけでも。懐いてくれたら殺さなくて済むよね?」
ただ、犬が飼いたいと言うわけではないミフティアの言葉に、二人は戸惑った。
果たして、そう簡単に野生の犬が手なずけられるのだろうか。手を伸ばした途端、食いつかれると言うことは?
だが、殺さずに済ますことができるなら、それに越したことはない。
「ちょっとだけなら良いかな?」
「仕方あるまいて」
二人は苦笑を浮かべると、懇願するミフティアに小さく頷いてみせた。
●山に生きる牙
一つ歩を進めるたびに、足の下で落ち葉がカサとなる。
時々、何かが砕けたような音がするのは、木の実を踏みつぶしたからであろう。
林の中の足跡探しは、落葉が邪魔をして困難を極めた。
「首が固まってきた」
ずっと下を向いていた音無が、渋面で首をさする。
その様子に、辺りの警戒役を担っていた藤野咲月(ea0708)は微苦笑を向けた。
「宿からは十分離れましたし、この辺りで誘き出せると良いですね」
後方を振り返っても、家屋の影すら見えない。
咲月の言葉を受けた音無は、荷物を下ろして保存食を取り出した。
「餌の代わりになると良いけど」
干物、豆、味噌、梅干しと言った携帯食が、ミフティアと咲月の分を合わせて三つ。
だが、犬を惹くには今ひとつ心許ないと、太猛は言った。
「干物を燻してはどうかのぅ。匂いを立てた方が早く気付くと思うのじゃが」
「それは良いな。風に乗れば、遠くまで届きそうだしなぁ」
木の幹に手をかけ一休みしていた、環連十郎(ea3363)の言葉に皆が賛同すると、天藤月乃(ea5011)は咲月と供に、早速、穴掘り作業にかかった。
「面倒臭いことは早く終わらせて、温泉に入りたいな」
「こうして働いたあとのお湯は、気持ち良いでしょうね」
土を掻き出しながら、咲月はくすりと笑った。視線の先には、とんとんと肩を叩く音無がいる。
「江戸へ帰ったら、効能も一緒に伝えられるかな?」
「ええ‥‥きっと」
頷いた音無の顔が、ふと物言いたげに咲月を見つめて止まった。
同じ行燈の灯を眺め、互いの声に耳を傾けて夜を過ごせたら。
湯煙を挟んだ向こうでその顔が笑っていたら、どんなに楽しさが増すだろうと。
そんなことが脳裏を掠める。
微塵にも口には出さなかったが、同じ男として連十郎は鋭くも何かを察したようだ。
「怪しいな。まさか、女湯に突撃しようなんて――」
「思ってない、思ってない」
この手の話は、弁明すればするほど窮地に追い込まれるものである。連十郎はしたり顔で頷きながら、音無の肩をぽんと叩いた。
「その気持ちは激しくわかるが、今日は止めておこう。女将を怒らせて、依頼料が没収されるとかなわんしなぁ」
「わかるんだ」
ぼっそり月乃に囁かれた音無の軌道修正は難しい。
静かに微笑む咲月を見下ろし、音無は参ったなと頬を掻いた。
「それじゃあ、やってみるね?」
まるで唄っているかのように、ミフティアは呪文を口ずさみながらヒラリと舞った。
皆がつけた人の匂いを、雨で消したいところなのだが、快晴の空には雲が少し増えただけである。何度、魔法を発動させても、それ以上の変化はみられなかった。
「駄目みたい。もっと天気が悪かったら良かったんだけど‥‥」
残念そうに空を見つめるミフティアを、太猛が穏やかに慰める。
「人がおっても宿には現れたことじゃし、儂らの匂いがついていても大丈夫じゃろう」
野に生きる獣は人を避けたがるが、腹を空かせている為、背に腹はかえられないのだろう。
雨を降らすことはできなかったものの、そう納得して、餌の準備に取りかかった。焚き火に串刺しの干物をかざすと、辺り一面に香ばしい匂いが漂い始める。
良く焼けた魚を数カ所に置いて、待つことしばし。
犬たちはやってきた。
皆から数尺離れた場所まで近づくと、地面と大気の匂いを嗅ぐ。やはり人の匂いが気になるのだろうか。
だが、その内の一頭が、警戒しながらも魚にゆっくりと歩み寄った。
「行っても良い?」
ミフティアの囁きに、太猛は素早く手を振って返す。
ただし、その顔はあまり芳しくない。
犬たちは汚れ、毛も固まってみすぼらしく、飢えて鋭い目をしていた。とても人に懐くとは思えなかったのだ。
木陰から現れた少女を見て、獣は激しい敵意を剥き出しにした。
「ウ〜」
低い唸り声をあげ、体を低く構える。
ズラリと並んだ牙が、木上の連十郎からも確認できた。
「わんこさん、一緒にこない‥‥? ご飯も毎日あげるし、お家もあるから」
対峙する一人と一頭を気にしながら、別の茶毛が餌に近づいた。匂いを嗅ごうとして、鼻を突きだした瞬間。犬が皆の視界から忽然と消えた。落とし穴に落ちたのだ。
驚いてあげた仲間の悲鳴に飛び上がった二頭の赤毛が、慌てて踵を返した。逃がしてなるものかと、連十郎が網を打つ。
「よっ!」
絡め取られた一頭が、もんどり打って転がった。
咲月と月乃が穴を掘っている間に練習した成果が、慣れない投網を成功させたのだ。
すかさず、太猛も投げ縄での捕縛を試みるが、胴に鞭打つ格好となって犬の逃げ足を早めてしまう。
次々と現れる人間の姿に興奮し、ミフティアを睨んでいた犬が牙を剥いて襲いかかった。
「下がって!」
飛び出した月乃が、二つの刃を喉笛に叩き込んだ。
音無は逃げる犬を追う。だが、死に物狂いで走る四つ足は早い。どんどん突き放されてゆく。
「音無様、伏せてください!」
咲月が咄嗟に投じた手裏剣は、犬の大腿部に突き刺さった。
ギャンと鳴いて倒れた赤毛に駆け寄りながら、音無は咲月に来るなと合図した。
剣を振るえば血が流れる。
咲月はそれが苦手であったのだ。
「直ぐ終わる」
咲月の後ろ姿に背を向けて、音無は抜刀する。
漏れた悲鳴に、音無も目を細めた。
穴の中の犬は前足をふちにかけ、狂ったように跳ねていた。近づいた太猛に、犬は激しく吠え立てる。
網を必死で振り払おうとしている赤毛も同様であった。連十郎の目を見上げ、歯を剥きだして唸る。
剣と拳がその体に沈むと、辺りはひっそりと静かになった。
「すまぬの」
「ごめんね。私たちの勝手な都合の巻き添えにして‥‥」
太猛とミフティアは、犬たちを覆い被した土に向かい、小さく呟く。連十郎も神妙な顔つきで手をあわせた。
「人里に下りたのが運の尽きだったな。ワンコ‥‥成仏しろよ」
だが、繊細な気持ちを見せたことが、照れくさかったのだろうか。
連十郎は、やおら皆を振り返ると、両手を腰に宛いふんぞり返った。
「俺だってなぁ、いつもナンパしたり、花街のねーちゃんと、懇ろになってばっかりじゃねーぞ! こういう優しい所だってあるんだからな!」
へぇ、ふぅんと一様に頷く一同。
墓穴を掘ったらしいと気づいたのは、そんな皆の視線を受けたあとだった。
●月、風、湯煙
「やっぱり温泉は、静かでのんびりできる場所が一番良いなぁ」
少し冷たい風が、ほてった頬に心地良い。
手にした杯の中で、揺れる月を眺める目が笑う。
白い湯煙に包まれながら、月乃はほぉと息を吐き出した。安堵の溜息である。
「幸せな気持ちになりますね」
満足げに酒の量を増やしてゆく月乃から、湯を二分する葦簀に咲月は目を移した。
凝り固まった首はほぐれただろうか。
葦簀の向こうにいる若い忍びを思って、咲月は柔らかな微笑を浮かべる。
「美味しい〜♪」
泳ぐことに飽きたミフティアは、用意しておいた柿を頬張った。井戸水に漬けておいた実は、良く冷えて甘い。
「このあとのお食事までに、お腹が一杯になってしまいませんか?」
咲月に笑顔を向けられ、照れくささと嬉しさの混じった顔で少女はニッコリと笑み返す。
「大丈夫♪ 食べることなら任せて☆」
両手で包んだ実と同じくらい、ミフティアの頬は赤く染まっていた。
一方――
隣の湯では、ホツリホツリと聞こえる娘達の声に、連十郎がなにやら怪しい想像をかき立てられていた。
耳を傾けては目を細め、いかんいかんと首を振る。
「突撃すると、女将に怒られる前に拳が降りそうだしな」
そう言って音無の顔をチラリと見た。
「一仕事のあとの温泉は格別だよな〜。極楽‥‥」
上機嫌で鼻歌を漏らし、ぬくぬくとした湯を満喫していた音無の目が、ふと女湯を見上げるのを連十郎は見逃さなかった。
傍らの志士が、忍びの娘であったら。
その考えを見抜いたのだろうか。
何か言いたげな顔でほくそ笑んだ連十郎に、音無はぎくりとした。
●秋夜
皆の食事が済んでまもなく、月を相手に、独り杯を傾けていた太猛は静かに腰を上げた。
そっと襖を開けると、仲間の部屋から灯りと一緒に話し声が漏れ聞こえる。
風呂の支度を整えて、太猛は軋む廊下を歩いた。
部屋割りは皆の希望通り。各々の時間を愉しんでいるらしく、太猛の耳に入ってくる言葉達も穏やかであった。
ギシギシと床を鳴らす太猛に、部屋の中から声がかかった。
「――お疲れさん」
犬に手を合わせたあと戯けた志士の顔が、頭に浮かぶ。
「良い夜をの」
「あぁ、あんたもな」
太猛の視界から、行燈の灯が一つ落ちた。



