 いつまでも
いつまでも
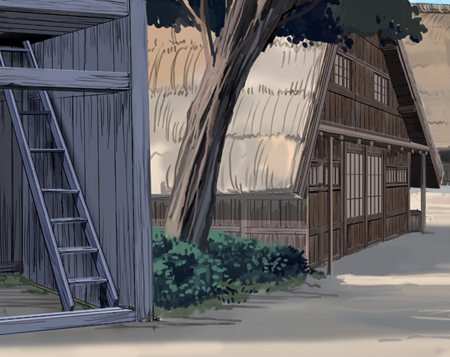 |
■ショートシナリオ担当:紺一詠 対応レベル:2〜6lv 難易度:やや難 成功報酬:1 G 87 C 参加人数:6人 サポート参加人数:3人 冒険期間:07月29日〜08月04日 リプレイ公開日:2006年08月06日 |
|
●オープニング
眠れない夜にこんな話はどうだろう。あるところに子どもとはぐれた母親がいたんだよ。好きではぐれたんじゃない、終わりの見えない戦乱が生産した、混乱、錯綜、そんなかでしかたなしにね。だけど、しかたなし、でどうしてかわいい我が娘をあきらめられようか? 母親は子どもを捜し続ける。昔話で銅の靴を履きつぶすことを運命づけられた少女のように、たしかなあてもなくさまよいつづける。
だけど見つからない。
疲労で道にくずれおちた母親を、一匹の鳥が川石のようにぬらぬらした瞳で見つめている。頸の長い異様に細い不気味な鳥だよ。鳥は啼く。まるで母親をさいなむように、啼く。ちょっと変わった鳴き声だ。いつまで、いつまで、ってね。それが母親には娘が泣きじゃくっているかのように聞こえてしまう。
『どうしていつまでも私を見つけてくれないの?』
「ごめんなさい」
母親はいうわけさ。
「ごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいあなたを見つけられなくてあなたの手を放してしまってあなたを抱きしめられなくてごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさい」
それでどうしたかって?
それでおしまい。母親は鳥に食べられちゃいました。あ、後日譚――というより前日譚みたいなものならあるよ。母親の探していた娘は、その鳥がおんなじようにして、とっくの昔に食べちゃってたのさ。見つかるわけないよね。
それがただのお伽噺なのかほんとうのことなのか、さぁ知らない。たしかめるすべもないだろうね。だけどどうしてだか、その鳥の名が「以津真天」だっていうことは伝わっている。
まだ眠れないのかい? それなら、とっておきだ。
妖怪・以津真天が出たってさ。それから、餓鬼も。場所はここ。さ、ぐっすりと一眠りして体をきちんと休めたら行っておいで。おまえのなすべきことをするために。
●今回の参加者
ea8151 神月 倭(36歳・♂・志士・人間・ジャパン)eb1900 縹 弦露(58歳・♂・陰陽師・人間・ジャパン)
eb2216 浅葉 由月(23歳・♂・志士・人間・ジャパン)
eb3736 城山 瑚月(35歳・♂・忍者・人間・ジャパン)
eb5009 マキリ(23歳・♂・カムイラメトク・パラ・蝦夷)
eb5228 斑淵 花子(24歳・♀・ファイター・河童・ジャパン)
●サポート参加者
渡部 不知火(ea6130)/ リュー・スノウ(ea7242)/ 津上 雪路(eb1605)●リプレイ本文
不死者といっても死人憑きだの怨霊だのばかりでない、今日、相手どらなければいけないのは餓鬼と以津真天――どんな悪党なのやら。城山瑚月(eb3736)は兎の仔をあずけるついでに、そこらをはっきりさせたく、リュー・スノウに仔細をたずねる。以津真天は大鷹を模す見た目どおり飛行の方法を有し、イツマデと聞こえる不吉な土器の声で、悔悟や痛惜の念を力尽くにひきあげる。
そして、餓鬼は――そういえば盂蘭盆が終わったばかりですね、と、リューのはなしは時節をおさえてはじまる。盂蘭盆には施餓鬼会が附されることもしばしばで、たしかにあれは、餓鬼の飢えをなだめる鎮魂の祭礼。
「餓鬼については、お寺を訪ねたほうが分かりやすいかもしれませんわね。六道の掛け軸を御覧になった機会はございませんか?」
「‥‥あぁ。おっかないお坊さんが、説法に使いますね」
瑚月に先んじ、神月倭(ea8151)が相槌を打つ。仏画をかかげながらの説経節を得意とする僧もいる、彼等を訪ねれば、慳貪の罪がどれだけ業の深いか、ひいては現世でいかにして妄執を遠ざけるか――いまだ醒めぬ妖夢のごとく真に迫って、語りつくしてくれるだろう。
餓鬼とはちょうどあんな案配。見えるものはなんでも食餌とみなすし、いったん口に入れたものはてこでも放そうとしない。ただ、さほど力は強いわけでもないし身の丈も児童ぐらいだから(そう、おおよそマキリ(eb5009)や斑淵花子(eb5228)ぐらい‥‥と聞くと、マキリは空恐ろしそうに肩をすくめ、花子はどんぐりまなこを一度ぱちくりさせる)、万が一には、誰かが手を貸してやれば振り切るのもそう難しくないだろう。
「めんどうくさいなぁ」
飛んでく矢みたいに、すっと貫き、まっすぐ向かってくる相手のがいいよ。マキリ、ふにゃりとくじけかけて――でも『立派なカムイラメトク』ならそういう好き嫌いはしないんだろうな、と、どうにかいつもの心持ちを取り戻す。好き嫌いというのはいささか語弊がありそうだが、勇士は眠らすべきものと向き合ったなら、たとえそれが月の輪だろうと火の鳥だろうと、惑わず眩まず、手入れのよくゆきとどいた弓に先鋭の鏃をつがえるだけだろう。そうと悟れば、マキリ、お気に入りの小弓の加減をととのえるのにいそしまずにはいられない。
「ちょっと怖いね」
けれど、愁色のゆれる花色の瞳を伏せて浅葉由月(eb2216)がつぶやく、惰弱の意思ではない。小柄なものの多い此度の冒険者一同では、餓鬼とはいえ蝶番をかけちがえば、足下を掬われることもじゅうぶんありうる。
「だいじょうぶだよ、俺ががんばるから!」
マキリが旗指物をぐるぐるするように弓を揚げると、由月はたよりなく笑んだ。
――‥‥依頼の村へは、道々、巷談をひろいながら進む。縹弦露(eb1900)は行き掛けの空をななめに仰ぐ、西にうつぶせる夕闇がほろほろと剥離して、式服にあまる黒味の素膚に、錆びがかった桔梗色をふりおとす。今日の有終のぬくみ。陰陽寮やの文庫へも立ち寄っていたせいか――だから、べつだん由月がしょっちゅう平らかなところでつっころんでいたからというわけでなく――少々進行にもたつきがある。
「どこかで一休みさせてもらってもいいかもしれんな」
夜陰のくらがりにてむかう愚はおかしたくなかった。廃滅の村だ、焦らなければならぬたぐいの依頼ではない。しかし、マキリの気に掛けたように、噂話の蒐集はさほどなめらかとはいかなかった――花子が長談義にくたびれる手前に終わったのは、まぁある意味で僥倖かもしれないが。村のだいたいの見取りを知れただけでも収穫だ。今宵はそこで仮の宿り。
場合によっては死人憑きよりも俄然容赦ない以津真天に餓鬼だ、半畳入れるような気持ちで近付いたものらは皆、悪霊どもにたいらげられたりどうかしたらしい。が、それはわるふざけの懲らしめにしてはあまりに重すぎ、のこされた親族は砂喰むものの虚ろな目をして、冒険者らにとりすがろうともしない。由月へそうしたように、マキリは自慢の弓をひらめかす。
「俺たちがぜったいやっつけてやるから!」
骨の抜けたような力のない、けれどほんとうの、笑みが相槌になる。
そうして明くる日――‥‥、
行き着いて、
風は泣くように、泣くような風が行き過ぎた。由月は振り仰ぐ、雲は少なく、今日もきれいに広やかな瑠璃色。一等の高みのそこには、なにも嘆き種などないように思える、だのに地上をさらう天空の眷属たる青嵐は、どうしてこんなにも寂しげなのだろう。どうして哀しいのだろう。
嗚咽か、咆哮か。
耳を突いて離れない、波を打つそれは、琵琶法師の鳴動を苦らせたのにどこかそっくりで。人々の涙を釣り込む、あの、絃声。
「だけど僕は、まだ泣かない」
由月、弱腰に手をあてがう。もしものときのためにあつらえた銀の短刀が濡れたようにひんやりとするのは、きっと彼の決意のすげかえ。
それを弦露、年嵩の本分として、由月の背をうしろから見る。声は掛けずに。大樹が若芽を見張るがごとく、墨色におおう陰陽師の肢体をどっしりと、幼い志士の後ろ手にかまえてある。
「では、」
「いってらっしゃい、なのですよ。不細工なクチバシの鳥なんかに、負けないで欲しいのですよ」
――クチバシが器量よし、とはどういうことだろう。
それはまぁ花子は二十二歳の女盛りで、河童族だし、河童といえばめだつ属性のひとつに黄色い口器、嘴があるのだ、さぞかし深淵かつ甚大なこだわりがあるにちがいなかろう――わけなく卑しめられめるのを嫌う瑚月だ、稀少の種族だからといって彼女の趣向をてんから否もうとは思わない。けれど、あれとそれとの侘び寂びの等差まで分かれというのは少々七面倒な相談、というよりはそも以津真天の姿をはっきりとしておらぬのだ、なので、瑚月はさしあたって花子の鼓舞のみ受け入れることとする。
弦露が二度目にテレパシーを成就させたのを機に、瑚月、残像のような身を村のなかにすべらせた。隠身の勾玉により鎮静された利き手に「惑いのしゃれこうべ」なる奇怪、それの脳天を思いの丈を籠めて打てば、亡魂の存在やその数に応じて歯並みをかつかつと打たす、まことに不思議。
ただ、この作戦には些細な問題もあった。
惑いのしゃれこうべ、これは、長時間の検索にはあまり向いておらぬ。心神を注入したその時分だけ、おるかおらぬかを判断するだけのものなのだ。まぁ、さほど大きくない村のこと。念話の範囲も考慮して、五度ほど試せば、おおよそそっくり調べ上げられるだろう。
「‥‥五度もちゃかぽこするのですか」
骨すらのこらず廃滅した村落で、彼等ののこした心許りの形見ともいうべき賤家の機嫌をうかがいながら偵察する――不謹慎ですね。苦い笑いがこみあげる。
さて、残されたものたち。弦露を伝達の仲介にして、斥候役の瑚月をじゅうぶんにあいだをたもって追跡する。彼がいないと断ずればそこに不死者はいないであろうから、この道行きは
「瑚月さんひとりに任せるのもしのびありませんから」
と、倭、ときどき家々の様相に目を配ってみたが、それはもう証左をあげつらうまでもなく、ただもうひたすらに、無惨。破れ、崩れ、朽ちる間際の、手の施しようのない患者のようなあれこれが倭の青眼に映り込むたび、彼の胸底に仄暗い歎息が降り積もる。まにまの損壊とはとても思えない。餓鬼の性質がリューに聞かされたとおりなら(そしてそれは、ほぼまちがいないだろう)、有機生命を食い尽くした彼等が、壁や梁まで、あぎとに砕こうとためしたと推量するのは容易だ。
――見なきゃよかったとも思わないけれども。
見届けることが、生なき建築どもの荼毘につながるのであれば。記憶を花束にして。邂逅を祈りにして。
右を見尽くした倭が首をねじると、ふと花子が建物のひとつに糸瓜のようにしがみついている――そうとしか見えないが、本人の意図はどこか異なるところにあるのだろう。水掻きの手で宙を泳ぐような仕草を二、三、試したあと、花子はなにかを諦めて、他の冒険者らにむきなおる。
「どなたか、あたしのお尻を持ち上げてもらえませんのですか?」
「え?」
「屋根に登ってみたいのです。もしかしたら、以津真天が出入りしている屋根穴とかが見付かるかもしれないなのです」
どなたかといったって、由月やマキリは小柄すぎるし、一寸見それなりにしっかりしているような恰好の弦露といえど陰陽師らしく力仕事はいまひとつ不得手だ、残るは倭しかいないではないか。むろん不死者退治の協力に吝かではないし、必要とあらばいくらでも手を貸す。ただ――そのぅ――花子の草色のししむらは実にみごとな完熟というか、腰のくびれは鞭のしなやかさ、臀部は新調したての鞠のように悩ましくはずみ――あれへじかに手を掛けろというのか?
「おねがいしますなのです、神月さん」
「え、いや、あの」
気がつけば、マキリはまごつく倭を邪心なしに不思議がっていたし、由月は替わってあげようか、という眼を彼に向ける――ぜったいに由月のほうが先に潰れる。弦露は――若人よ、なにごとも経験だ、視線のみで伝える。ええい、ままよ。決心もほこらしく、天道よ照覧あれ、と、天体を見上げたとき、
空。
神鏡のように傷一つない――なかった、空。
それに、いつのまにやら、針で突いたような黒点がひとつできていた。それは水を含むように、ぐんぐんと育っている。いや、なにかがすさまじい勢いで降下してくるのだ。放物のような自然でなく、強靱な意思――悪意をおもわせる確実性に。
――‥‥もしも、哨戒飛行におもむいていた以津真天がいたとしたなら?
天空は厖大すぎる、とてもしゃれこうべの直感が到達できるものでもない。そうして、広い空から文字通り鳥瞰すれば広いところが見えるのだ。逃れられない。すべてを察した倭が刀を抜く。はらりと溢れる、鉄の燐光。
「縹様、恐れ入ります。瑚月様を呼び戻してください、以津真天が出ました!」
瑚月が駆けつけたとき、すでに干戈の端緒はひらかれていた。懺悔を一度の舌打ちに封じ、とうにあらわになった短刀・月露の刃を、齧歯を千枚通しの要領で由月の腕に突き立てた、餓鬼の背にくらわせる。ぎゃ、と、あきらかに人のものでない苦悶をしぶかせ、餓鬼は醜い腹の瘤のほうからころげた。
「渡部殿、恥はかかずにすみましたよ」
きっちり片ぁつけた上で返しに戻ってこいよ?――そんな言伝とともに渡部不知火から借りた愛刀の「月露」は、ただしくその役割を果たした、いや、いまだ万の数奇は結末にいたったわけではない。罪のない真昼の下で、淡雪の溶けるに似たる露を散らせながら、奔ろうと――それの以前、紅の織綾が触れられたところからふわりと引き伸ばされて、瑚月の心理へ爆ぜるような剛勇をふりかける。弦露、解いたばかりの経巻をなおしながら、新たな経巻へ手を伸ばしている。津上雪路から借り受けたそれらは、はたらきはじめたら休む間もなく追い回される運命らしい。
「フレイムエリベイションだ。気休めだが、ないよりはマシだろう」
「助かります」
紡ぐ言の葉をもたぬ、喰らうだけしか知らぬ歯牙どもに向かい、ふたたび瑚月は矢よりも疾くすべる。本音は以津真天をまず片付けてしまいたいところだが、どうやら以津真天、高所の利をえらび、冒険者らが餓鬼にまったく縫い止められるまで悠然とはばたきを続けるつもりらしい。
しかし、すでに以津真天の一体は屠られていた。由月の氷輪に翼を切り落とされ、鳥の性質をなくして転落のところを、つぶすように倭が両断する。灰色に染み付く霞の刀を、間髪おかず、新たな餓鬼へ創痍をきずく。以津真天はまだ降りてきやしない、だがしかし啼きもしなかった。ゆったりとした螺旋の回遊
「私たちを見張っているつもりですか?」
生賢しいのはどっちだ。こちらとて餓鬼の拘束から逃れたばかりの由月がふたたびアイスチャクラをめぐらしていたし、マキリの弓矢とてあるのだ。
しかし、マキリは――‥‥、
「イツマデ!」
そのとき死の鷹が啼く。
少年特有の、空に染まって青みをひたかくす緑の黒眼が、あふれんばかりに水を湛えていた。噎んでも噎んでも流しきれぬ、罪が腹から胸までもひたひたと充ち、息の詰まりそうになる。それだけで、絶えそうになる罪悪感。薄もやの向こうで、蝦夷の家族が悄然と、マキリの忘れ物に話し掛けている。
「マキリ様、私たちを信じてください。以津真天の呼びかけなどでなく、私たちを!」
倭の声が、遠い。
だのに、地獄がとても近い――‥‥。
「とーう、なのですー」
と、
ばさり、と、鳥にしては大きすぎる真緑が、装束の翼をひるがえらせて、以津真天とは別の軌跡を下にたどり、マキリをついばもうと下降した以津真天をおおきく打擲する。
――‥‥これでも鬨の声である、いちおう。
花子だ。彼女の得意は、袈裟にかける重力を借りた衝き下ろし。が、それは天翔る獣らには通じない――ならば単純だ、自分がより天井に上がればよい。けっきょくどうにかして藁葺き屋根へよじのぼった花子、がむしゃらに体ごと落ち掛けたのだ。妙な喩えを用いれば、天国の銘の太刀は、たしかに天国からやってきた。
「落としましたなのです」
「あぁ。立ち会った」
弦露が、短く。
寸隙を縫って、ぼぅと地から生える炎柱は龍の奔流となり、以津真天の全体を飲み尽くす。
「‥‥同朋の袂を湿らせた罪は、重い」
迷うたものは土に還るが理でなれば、
弦露、開いたばかりのマグナブローの経巻の紐を結びかえす。
夕闇が、更に重ねて、漂流する。
――花に、骸は似付かない。
それが怨みとつらみの細切れならば尚更で。
これで、全部。由月は斃した餓鬼と以津真天を処置してから、村の一角に花を添えた。折りとったのでなく、根っこから掘り出してきたのだ。だいぶん手間はかかったけれど、死骸に死骸は要らない。花は腐食を苗床に咲き誇るだろう。あでやかに。みずみずしく。
「供養の祠や地蔵をたてたいですが、さすがにそこまでの時間はありませんからね」
行きにお世話になった村に頼むのもよいかもしれませんね、と、倭もてつだって、一輪のつもりだった花は、春の女神の撫でたようにうずたかく。それをかたわらで見まもるマキリ、北の地の春を呼び起こす。
――手紙でも書こうかな。
瑚月は――惑いのしゃれこうべ、
「‥‥いるはずありませんけど」
思ったより役に立たなかったような、それがわずかに癪に障って、こん、と、瑚月は始末にたたく。
と、カツン、と。ほんの少しだけ、しゃれこうべは咬みしだく。
は、と、いっしゅんの冷たい緊張、それがゆるゆると解けてゆく。
――二つの魂魄が、太陽の沈める方角へのぼってゆく。彼女らの去ったあとに、数種の玩具がころりと揺らいでいた。



