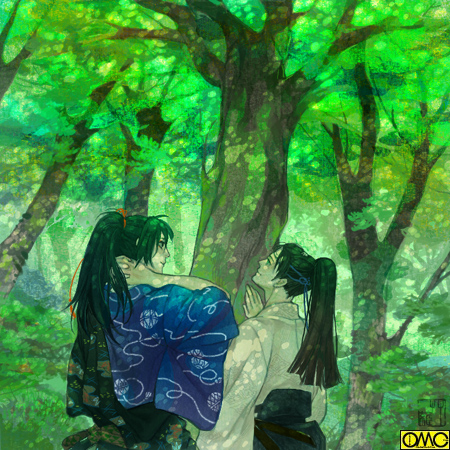上から下から
上から下から
 |
■ショートシナリオ担当:紺一詠 対応レベル:2〜6lv 難易度:やや難 成功報酬:1 G 69 C 参加人数:8人 サポート参加人数:-人 冒険期間:07月22日〜07月27日 リプレイ公開日:2005年07月31日 |
|
●オープニング
「土蜘蛛が巣をつくっちまってね。それをなんとかしてほしいんだが」「どこに」
「径だ。うちのちかくの雑木林をつっきるふうなかんじでな、いい近道だったんだけど」
あ、隣村との、と付け加える口調に、依頼人の、焦りも憤りも感じられない。それが京風とでもいうわけか、ひとつ云いきったかと思えばやたらに大きなあいまが入る。
「ただ、なんとかしてもらいたいのは、それだけじゃなくって。こう、こんなかんじに」
てのひら2枚で小型の天蓋をつくり、かぶせた側のてのひらを少しはためかせて、在ることを主張する。
「林道だから、うえのほうを樹影が覆っているだろ? 同じくらいの時期に、そこにも変なのがたかったもんで」
「何?」
「えーと、ほらなんてった? あの、顔だけの。びゅーっと降りてきてがーって人間喰っちゃうヤツ」
「釣瓶落とし」
「あぁ、たぶん、それ。同じところに出ちゃってよ。ったく」
「あら」
「だから弱ってんだよ」
依頼人はそこで初めて困ったような顔をするが、眉を寄せ顎に手をかける仕草もどうものんびりのゆったりで、内心はいざ知らず、外見にいまいち切羽詰まったところがない。
「土蜘蛛は地下に罠はるだろ? だからって、つい下のほうだけにかかりきりになっちまうと、上のほうから釣瓶落としにすきをつかれるって寸法でな。ちょっと厄介だ。こりゃ戦いなれたお人でも雇わなきゃやってられないだろうって、ここに来たわけよ」
「そりゃどうも」
「で、いるかね? 受けてくれそうなのは」
「そりゃあ、まぁ‥‥」
話を持ちかけられた人――既にご承知のことであろうが、ギルドの番頭である。聞き上手でなけりゃ勤まらないかもしれぬ仕事でも、云わなければいけないときに云うべきことはしっかり云う。
「心付け次第だろ」
●今回の参加者
ea2984 緋霞 深識(31歳・♂・浪人・人間・ジャパン)ea3880 藤城 伊織(36歳・♂・浪人・人間・ジャパン)
ea6419 マコト・ヴァンフェート(32歳・♀・ウィザード・人間・ノルマン王国)
ea7242 リュー・スノウ(28歳・♀・クレリック・エルフ・イギリス王国)
eb1559 琴宮 葉月(41歳・♀・志士・人間・ジャパン)
eb1565 伊庭 馨(38歳・♂・志士・人間・ジャパン)
eb1861 久世 沙紅良(29歳・♂・陰陽師・人間・ジャパン)
eb1865 伊能 惣右衛門(67歳・♂・僧侶・人間・ジャパン)
●リプレイ本文
梢葉がつもりにつもって、そうたかくもない緑の天蓋のしたは、へんに薄暗い。林道、のとば口にて。葉のあわいをくぐる光影は階子に似て、つたうなにかが降りてきそう。釣瓶落としが? それではあまりに華のない。リュー・スノウ(ea7242)は、しばし耳を澄ませた。林の虎口をおそれたのか獣も鳥もうたわず、ひとりぼっちの蕭条が耳殻を追いつめる。深緑の酩酊。騒然とまごうような沈黙に罅入れたのは、マコト・ヴァンフェート(ea6419)の一言だ。
「どうして釣瓶落としは、土蜘蛛を食べちゃわないのかしら。好き嫌いしないで、相討ちしちゃえばいいのに」
存外に挑戦的な言いぐさに、リューはついほころぶ。妖怪・化生のたぐいには造詣のふかいリューといえど、気持ちまではかることはできず、だから、ふいの思いつきをそのまましゃべる。
「土蜘蛛の巣穴は深いですからね、それに、」
「それに?」
「土蜘蛛は悲鳴をあげないからおもしろくない、とか」
「やだぁ」
ぞっとしない。マコトは骨のぬけたようにうずくまった。由無し事のつもりで口にしたリューですら、なんだかちかしい正答に思えてきて、ほのかに眉をひそむ。と、風向きをめざとく察した久世沙紅良(eb1861)が、蠱惑の笑みを塗く。
「だいじょうぶかい? 暑さにあたったならもうすこし休んでからにしようか」
「邪魔しちゃダメよ」
琴宮葉月(eb1559)が沙紅良をたしなめたのは、マコトとリューのあいまをわるな、ではなくて、マコトの呪文詠唱をはばんではいけない、という意味。土にちかづいたついでにブレスセンサーをとなえたマコト、漁火のような杲々に吐息の行方を知らされた。
「私は平気よ。‥‥ん。道もしばらくはだいじょうぶみたい、下はね」
土蜘蛛の総身は一尺半。それほどいかついものは、かんじとれない。葉月が「次は私がやるわよ」とマコトをねぎらう、呼吸と震動の捜索をたがいちがいにくりかえしていけば、気がついたら土蜘蛛の巣に引きずり込まれてました、という事態は避けられるだろう。これで「下」はいいとして、では「上」はといえば、
「いねぇな」
「いませんね」
藤城伊織(ea3880)と伊庭馨(eb1565)は言葉じりをあらためただけのおなじ台詞を順繰りにつぶやいたあと、そろっておなじ種類の溜め息でふさぐ。
「いないようですな」
伊能惣右衛門(eb1865)も、鷹揚に頭上をあおいだ。結葉――夏の季語をもちいて馨があらわしたように、おおぜいのこどもがいっせいにおじゃみでもはじめたような植物の陸屋根は、よくみれば緑だけでなく、白や黄もあわさって、人工ではあらわしきれぬ点描をかたどる。うつくしい――他に言葉を尽くす必要もないくらいに。ここを妖怪にとりあげられた村人はさぞこころのこりでしょうな、と、惣右衛門はふとなげく。
伊織も似たように考えたのか、額や頬に落ち葉衣のような光のまだらをうかせて、ぽうっとつぶやく。
「こんなところでのんびり酒なんか呑むのもいいかもなぁ」
「暑いですよ、虻がでるかもしれませんし」
「なんとかしろ」
「私に問題を丸投げしないでください」
「丸投げといえば、荷物も持ってくれねぇか。馨。じつは重くて動けん」
「‥‥どこからつっこんでいいんですか」
なんの解決になってないじゃないですか、と、馨、呆れたそぶり。むくれた、ふり。
「つうかな。ほんとに「上」はどうする?」
「私がしらべますよ」
緋霞深識(ea2984)がうやむやになりかけた追求の案をうながすと、沙紅良がめずらしくやる気のあるようなことを言いつのった。リヴィールエネミーをエックスレイビジョンで補助、という彼の了見を聞き、納得しそうになった深識、しかしよくよく再考する。
「透視だけでじゅうぶんじゃないか?」
人気のない林の木のあいまにひょっこり梟首がみつかれば、それはあきらかに釣瓶落としだろう。ただし、エックスレイビジョンは今回のような、樹木の密集した地所の場合、木の一本一本に術をほどこしていかねばならないので、それほど実用的ではないが。もひとつ。リヴィールエネミーはまずこちらが対象をきちんと視認したうえでの術だから、捜索の手段というよりは駆け引きの道具といったほうがいい。
しかし沙紅良は動じなかった。
「ご婦人方のまえで透視なぞ使用しては失礼かと思ってね」
「あら。心までのぞかれたら、どうしましょう」
育児経験まである葉月は、さすがにそれだけのことで激昂したりはしない。含み笑いながらの軽口で応じ、それをまた沙紅良は睦言でかえす。
「それは心配いらないね。すべての女性のきらめきのまえには、邪心の青白いほむらもかすむというもの」
「お上手」
深識はどつこうかと思った。沙紅良を。‥‥涼風送ってやる必要はないよな、な?
※
けっきょく「上」に対しては決定打といえるものがなかった。たんねんに注意をはらう、といった不確実ではあるが、それなりに持続性のある方法でつぶしてゆくしかないだろう。森闇人、の異称のあるとおり、エルフは森林のけしきにあかるい。リューの感性をたよるのが最善か。
「それではりゅーさん、そこに立ってもらえますかな」
惣右衛門の幸運招来の呪・グッドラックによって五感を研ぐと、途端、万象が拡大してせまる。が、リューの知覚をまっさきにとらえたのは草木のなす交響でなしに、深識がときたまふりあげる冴え冴えとした意匠だ。
「そのナイフ‥‥短剣は?」
「これ? 釣瓶落としが落ちてきたら、枝をむすぶ蔓をたちきってやろうと思ってな」
「でも、釣瓶落としは飛行しますよ」
「はい?」
なんておっしゃいました? べつに聞き取れなかったわけでもないのに、リューの台詞を逐一確認した深識、馨をふりかえる。
「知ってたか?」
「もちろん知ってました」
「なら、その、いつでも植物操作できるように準備していた印はなんだ」
「誘導です」
それだけでなかったり。慈母のごとく善意にみちたリューは、天河のような銀の髪をかたむけて、深識に語る。
「それに、銀製品は死者に対して特に有効、というわけでもないんですが‥‥」
「おぉ、そうでしたな。それぐらいなら私も知っております」
惣右衛門まで。
亡者に対して目のさめるような有効打をうちやすいという特質は、銀の武器には、通常はない。ただ通常の武具では微細の傷すらはしらせられないもの――たしかに不死者のなかにはそういう性質をもつものが多いが、あいにくというかさいわいというか、釣瓶落としはそれではなかった――にも、打撃をあたえられる、それだけだ。
「‥‥そっか」
なんだかもう、もろもろイヤになった深識「かえろっかな、俺」、地面に、のの字のの字、いや、ここまできてひとりで反転するほうが危険だから。
「いじけんな。終わったら酒わけてやるから」
自分もすこしだけ勘違いしていた伊織、それはすでに風に喰われた遺址だとでもいいたげに、しかつめがお。紫煙をしのんでの道行き口寂しく、なんだかみょうに人優しい。
と、
「みっけ。あと百歩くらい?」
マコト、具体的なのか・でないのかいまいちわかりにくい単位であらわし(「だってジャパンの規矩ってわかりにくいじゃない」規矩(ものさし)って言い回しのほうがふつうはむずかしいよ)、それから自分自身に疑問符を投げた。
「聞いてた数より、少ない気がするんだけど」
「そりゃ、この道幅だ。蜘蛛が好きこのんで、狭い長屋住まいもしないだろうさ」
伊織、てすさびで恋しい煙管を真似ながら、さとす。それもそうよね、マコトは納得するけれど、もひとつうんざりこともあった。
「じゃあ、まだやんなきゃいけないの?」
「私もおてつだいするわ、いっしょにがんばりましょう」
「ありがと、葉月さん」
「私もできるかぎりの力添えをしよう」
「‥‥沙紅良さん、これ?」
「そう」
びみょー、と、沙紅良にあたまを梳かれながら、マコトは思う。沙紅良は楽しげに慰撫を続行する。だいたい九寸の丈の差。深識は土にお習字つづける、いろはにほへと‥‥雅?
※
「百歩っていってませんでした?」
「『くらい』だってば!」
八十九歩。
先鋒は上方だった。葉擦れにしてはわざとらしく、風韻にしてはいとわしい、耳目を持ち上げるようなどよめき。リューは身をかためたが、墜落の襲撃には気付いただけで。我に返れば、矢のように降る、落ちる、下る、げびた解顔。
誰かに警告を投げるにも、十字架の交差に手をかけるにも、二、三の刹那がまにあわなかった。
「よっしゃあ、面目躍如!」
が、釣瓶落としのあぎとがついにリューをくだくことはなかった。息をまじえぬ牙を止めたのはなにげない木刀の、花と実によく似た色立ち、淡紅色の芯。釣瓶落としに桃の木刀をはませ、ねじり、地に伏せようとする。
なおも歯で切ろうとする釣瓶落としを深識「だいじな木刀喰わせてたまっか」とひっぺがし、飛び立つまもなく鞠のように転がるそれに、振り落とした、風・人造のななめの木枯らし。けれどリューはちいさく眉をひそませた。
「あの、よかったらですけれど、それはなしにしません?」
ソニックブーム。剣圧の三日月は、着弾のまえに対象外をつっきることだってある。林の木を傷つけたくないから‥‥なるべく木のある方向には打たないでほしい。それもそうだな、と、深識は気軽に応じた。
「分かった、努める」
「もうしわけありません。お礼も言わずに失礼なことを弁じまして」
「いいって。俺のほうがさっきは助けられたんだし、女性のおねがいを無視するわけにもいかんだろう」
「それはどちらかといえば、私の台詞だな」
そういう、べつにそうしなくてもいいときにも沈着をたもっていられるのが、沙紅良だ。知己の文でもしらべるように淡々と呪符をひらき、封じられた呪法をときほぐす――失敗した。俗な見方をすれば、精度とひきかえに利便性をたかめたのが経巻であるから、まぁしかたないといえばしかたないが、もちろんそういうときでも、沙紅良は沙紅良。
「いけない経文だね、かえったらおしおきだ。いや、それでは、これのもとのもとの主であるリュー君に失礼かな?」
「‥‥経文がわるいんですか」
まーいいんですけど害さえなきゃあ。
水晶の剣を薙ぎながら、馨は、ぼそり、と。土蜘蛛は、ほぼ釣瓶落としと同時にあらわれた。土蜘蛛は縦穴に住まう蜘蛛なので、糸ははかない。巣穴の近くを通りがかった獲物を麻痺毒でうごきをとめたあとで、ゆっくりと巣穴にひきずりこむのが彼らの狩猟だ。――逆にいえば、巣の縁からその黄と黒の不吉なだんだらがのぞいたときこそ、彼らを釣りあげる最良の機会でもある。土穴の底で一匹と一人、なんて状況ができあがってしまったら、いかな手練れでも身動きがとれなくなる。
伊織は双腕の剣を、ほぼ無目的にまわす。どちらの剣も筋にのしかかってくる、なかなかあらたかな技が決められない。では重さのわりにあつかいやすい剣――というと、
「馨、くれ」
水晶剣のことだ。はいはい、と馨、うけおい、利き手の指をからめて、しかし葉月が、はい、と先にさしだした。
「私の分があまってるけど」
「あ、もらう」
「待った。わざわざかっこつけた私の立場は」
どうなります、と、しめることもできない。土蜘蛛は二匹。夫婦なのかもしれない。未熟な知能にしてはいきのあった動静は、マコトの低く撃った雷針で裂かれる。鳴かない蜘蛛の代わりに、マコトがさけぶ。
「みんなー、前にたたないでねー。捲き込んじゃうからーっ」
‥‥さけんだ。
乱戦――いや、もっと下等に、混戦というべきか。土蜘蛛も釣瓶落としも、立ち回りのきく妖怪ではなく、耐久性も高くない。高波のおさまるように、昂奮と戦意がしずまってゆく。凪にあそぶ千鳥のように、冒険者たちの荒い呼吸が点々とただよう。
「たまには陰陽師らしいこともするとしよう」
沙紅良が織った内縛変形から、炎の鳥のように一条の炸裂が飛び立ち、仲間の純白を追う、それはリューの聖なる光珠。最後の釣瓶落としを灼いた。
土蜘蛛も一体は倒れ、あと一体、それこそ虫の息。甲にういた無数の傷から、厭な色の体液がこぼれる。
「そろそろ眠らせてあげないとかわいそうですね‥‥。藤城」
「あいよ」
馨は水晶の剣を肩ごと降ろす。ごつ、と抵抗までも斬り込んで。開いたところへ、伊織は同一の剣をねじこんだ。
「――‥‥終わったな」
「怪我をされた方はおられますかな?」
惣右衛門がきょろきょろと周囲をみまわした。どちらかといえば、疲労のほうが濃かったのかもしれない。単位面積あたりの数量の問題で、つまり濃密だったから。ぱら、ぱら、とまばらに手を挙げたものでも応急手当程度の処置でなんとかなりそうだ。けれども念のため、と、ほどこした惣右衛門はその念を説明する。
「では、進むとしましょう」
これで終わりじゃなかったんだ。
「こんなことははやく済ませてしまいましょう」
矍鑠。ふたたびのみちのりは、惣右衛門が闊達に案内をつとめる。
※
二回。
林道での戦闘の回数だ。一寸の虫であろうと――今回は一尺半はあったが――固有の領域をもっている。伊織がさきほど云ったように、すべてがいちどにあらわれるには、林道は少々せますぎた。そのわりにすくない数だったのは、釣瓶落としが土蜘蛛の巣のうえにかたまっていたから。
どうしてかしら?と、なにげなくつぶやくと、そうですねぇ、と馨が想像で答える。
「共棲してたんじゃないですか? 釣瓶落としが上半身もってって、土蜘蛛が下半身担当とか」
「やーだってばそれ」
「いやだね、でもおつかれ。がんばったね」
膝を折ったマコトを、沙紅良がなぜる。やっぱりびみょー、とマコトは考える。
折れた木の枝を、深識は拾いあげた。注意深くやってたつもりだったけれど、野太いの、一本、ぼきっとやってしまった。リューのせつない表情が、痛い。しかたないよな、俺のせいだし、と深識がひとりごちると、惣右衛門がそばによる。
「どうされました?」
「これで道祖神でもつくろうかとおもってな。道具もそろってないし、時間もないから、どれだけのもんができるか分からないけど」
「おぉ、おれはよい考えですな」
人にたいへんな迷惑はかけたけれど、亡者だってそうなりたくてなったわけじゃないだろうし、土蜘蛛だって居場所をもとめてそこへ流れてきただけだろう。リューが花咲くようにほころんだ。
「いいものを期待してますよ、惣右衛門さんの唱名に負けないようなすばらしいものをね」
馨もほころぶ。噴き出しきった汗をぬぐってゆく、薄布のような夏の風。止まる。
深識が考えていたよりその道祖神は、けっこう永く、そこ、にあった。リューが浄化したからというのもあるけれど、それ以上、長久に。新たな木立が林を癒すまで、そこに、あった。