 【龍脈暴走】 北斗七星・貪狼・白
【龍脈暴走】 北斗七星・貪狼・白
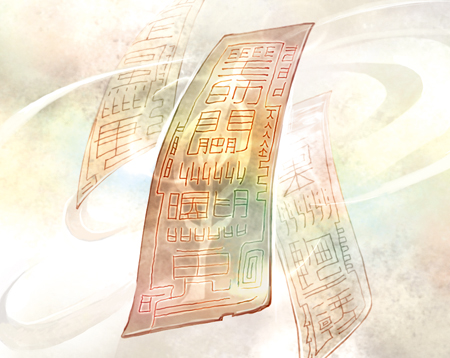 |
■ショートシナリオ担当:紺一詠 対応レベル:1〜5lv 難易度:やや難 成功報酬:1 G 35 C 参加人数:8人 サポート参加人数:7人 冒険期間:01月29日〜02月03日 リプレイ公開日:2006年02月07日 |
|
●オープニング
京の冒険者らにとって、狐どものくわだてにより御所が奇襲をうけた事変は、記憶にあたらしいところであろう。さいわいにしてすんでのところで身に過ぎた大望は阻止されたものの、たった一度きりの頓挫で、汲めども尽きせぬ彼らの妄念をたちきるなぞ、星を数えあげるような、所詮はいたずら。ぜんたいどういうつてをたぐったのだかそのへんの細目は省くが、奸計の糸を裏であやつる九尾の狐・玉藻は、『草薙の剣』の代用として『天叢雲剣』を手中におさめた。九尾はこれにより龍脈、すなわち地脈切断の呪法を成し遂げ、霊峰富士の眠れる護摩炉にあらたな種火を注がんとしくむ。
万が一にも富士が爆ぜ、噴煙が天象をことごとく煤けさせるようなようなことあらば、地動、地裂をはじめとして、日ノ本は未曾有の大災害によって海底ふかく轟沈する――上野国・金山城から発見され、九尾も目をとおしたとおぼしき宮下文書からは、そのような要旨がひきだせるという。九尾の目的がこれらの履行にあることは、白々として自明の理。
さて、龍脈の抑制をつかさどる封印結界は、京から江戸にかけて(江戸から京、でもいいのだけど)、北斗七星のかたちにひろがっていた。そこで抑止力を高めんがため、この七箇所でいっせいに、龍脈の安定をこいねがう儀礼がおこなわれることになったのだけれども――‥‥。
そのうちのひとつ。柄杓の、柄ではなく容れ物の側の一端、貪狼星をつかさどるのは、洛北・大原の地にある眇眇たる祠だ。それはありふれた地蔵堂よりもまだ小さいくらいで、香箱におなさけで屋根板をかぶせたような見掛けの、ひじょうにまずしい普請である。
この封印は、祠に七体の夜刀神を奉じ、土地の者により定期的に加持祈祷や献物をささげることでなりたっていた。それ以外の人々には見向きもされないようなたよりない祠ではあったが、それ故に寂静の平和はたもたれていたので、夜刀神たちは己の境遇に不満をいだくことはなかったし、貪狼の封印がゆらぐことはなかった。
これまでは。
九尾の活性による鬼気にでもあてられたのだろうか。土着の狼たちの乱暴により、貪狼の祠が破壊されるまでは。
夜刀神とはいかめしそうな名前こそしてるものの、じつのところ、けっこう意気地なしなのである。貪狼の祠の夜刀神たちは、終の棲家が瓦解したとみるや、ここはもはや安泰ではないと判じ、三々五々と逃散してしまった。お役目をすっかり忘れたわけでもなかろうから、たぶんそんなに遠くには行ってないのだろうが、しかし、このままでは貪狼の封印はもぬけの殻、九尾の妖術のしあげを待たず、龍脈は煮えたぎる背骨をうごめかせて、大原の足元から終滅はほどける。空の天幕がはらりと落ちてくる。
※
――‥‥さいわい地元のものたちの尽力により、仮の祠堂は早急に建立されたが、夜刀神たちはいまだもどっていない。
夜刀神とは、じつは、精霊の一種である。さまざまな属性の夜刀神がジャパンのあちらこちらで見られるが、貪狼をまもる七体の夜刀神たちははすべて地系だ。外見は、属性にしたがってはいるが、天然ではありえない妙な色の、十寸ほどの小蛇。一体が一種の魔法をつかう。どうもこれらの魔法を利用して、あちらこちらに逃げまわっているとおもわれる節がある。
だから、冒険者たちにはとりいそぎ夜刀神たちをあつめてほしい。ふたたび遁走しないような算段をもちいて、だ。貪狼の封印は狼によって破壊されたとは先述したばかりだが、その狼たちの暴走はどうやらいまもって潰えていないらしい、狼によって夜刀神が喰い殺されるよりも、とっとと、すみやかに。
ところは、大原の少々奥地。すこしばかり山あいへ分け入ることになるから、それなりの装備と覚悟は準備しておいたほうがいい。季節柄、雪中・寒中の用意もだ。狼たちの始末はべつの冒険者にたのむことになるが、かといって、たかをくくっていては痛い目をみるだろう。
だから、よろずの手配はぬかりなく。
●今回の参加者
ea6433 榊 清芳(31歳・♀・僧兵・人間・ジャパン)ea7725 シーナ・ガイラルディア(34歳・♂・神聖騎士・人間・イギリス王国)
eb0971 花東沖 竜良(34歳・♂・志士・人間・ジャパン)
eb1529 御厨 雪乃(31歳・♀・浪人・人間・ジャパン)
eb1630 神木 祥風(32歳・♂・僧侶・人間・ジャパン)
eb1872 瓜生 ひむか(22歳・♀・陰陽師・人間・ジャパン)
eb3837 レナーテ・シュルツ(29歳・♀・ナイト・人間・フランク王国)
eb3936 鷹村 裕美(36歳・♀・浪人・人間・ジャパン)
●サポート参加者
鷲尾 天斗(ea2445)/ 高槻 笙(ea2751)/ 小都 葵(ea7055)/ 霧島 小夜(ea8703)/ 結城 冴(eb1838)/ フィーナ・グリーン(eb2535)/ 李 麟(eb3143)●リプレイ本文
さく、さく、さく。雪踏む音は軽い、けれど足取りはいかにも深刻、粘りけのある泥沼を突っ切るがごとく。大原での行進は、かんじきをひっかけて、鷺の羽そっくりの処女雪をふわりふわりと褄捌き、散らしながら。
こんなとき、欧州ならば雪中移動のときはスキーだろう。だからシーナ・ガイラルディア(ea7725)はものめずらしく、ところがちがえば雪の質までことなるもので、おもてのところはまるで棒でも呑んだがごとく脇目もふらず一心に進んではいるが、ときどきは足頸をかえしてみたくてしかたがない。いったいどんな按配になっているのでしょう、と――‥‥。
「ぎゃうん!」
とそこへ喚声、すわ野獣の咆吼か――いいや、てんでまがいもの。
まっしらなただなかへだしぬけにうつぶせしていた鷹村裕美(eb3936)、鳥瞰すればそれは細りきった大の字で、横からながめたとしても、どうみたって陸に投げられた鯉の風情。
――‥‥あと数刹那そのままであったら、頬といわず額といわず、あらわな肌の部分はおそらくはすべて霜腫れする、それくらいのじっくりとした間隔をもちいて裕美はおもむろに顔をあげる。
「い、今、足元に蛇がいたような気がしたのだが」
「それはそれは。いかがでしたか?」
「‥‥すまぬ。枝のようだ」
花東沖竜良(eb0971)に助けられて、裕美は絡む雪片を払いながら、ひとしきり罪悪感にさいなまれた。転倒をじかに見られるのも困るが(だって裕美は、禄なしといえど、武士は喰わねど高楊枝)、あまりすなおにはぐらかされてもらうのも、なんだか自分がとんでもない素行をはたらいたようでならない。
でもいいや、必要悪ってことで。
裕美が立て直るまで、思いがけぬいっときの休息も兼ねた――裕美、やはり慣れぬかんじきの行がつらいらしい、起き上がりこぼしの起き伏しをまねたわけでもなかろうが、「ふぎゃぁっ」の断続を今しばらく。
じっとしていては踵から冷気がしみる――霊山での修行もたしかこんな具合だったろう。骨の髄までひたされそうな寒威凛烈を、ゆるゆるとした立ち歩きでだまくらかしながら、榊清芳(ea6433)はなにげなくつぶやいた。
「おかしな匂いがする‥‥」
「これではありませんよね?」
小柄な白妙がおとなびた口調で、瓜生ひむか(eb1872)が示したのは夜刀神信仰の村人からゆずりうけた祭物のたぐい、御厨雪乃(eb1529)が手回しした神代酒とはまた別で、枯露柿やあられ、きんとん――どうも甘党な神様だったようで。つくづく親近感をおぼえ、清芳は力を込めて否定した。
「いや。もっとずっと、不快なものだ」
「実は私もずっと気になっていたんです。それほど遠いところからではないようですが、」
ひむかは少々鼻がきく。白い鼻翼を子鹿のようにひくつかせて、正体と方向を、だがそれらは向こうからやってきた。夜刀神と、思いがけぬ再会をお供に連れて。
「‥‥おや」
「あ、あ、兄上。どうして、こんなところに!?」
神木祥風(eb1630)とその妹の――ほほえましくもあり、さわがしくもあり。
とりあえずいろいろあったような・なかったような、夜刀神、一匹(匹?)確保。
「狭隘なところであいすみませぬが、すぐに御同憂を御案内しますので、もうしばらくお待ちくださいませ」
ぱちん、と、籠のかけがねをおろす爪先まですら、また瀟洒。レナーテ・シュルツ(eb3837)が竹籠に夜刀神をしまうのを、雪乃は複雑な気持ちで見守る。小豆味だの抹茶味だの、文字列を打ち見やるだけですら唾が湧きそうになるのを(主に、清芳が)ことさらみすごし、あちらに行かれたのはなーんか合点がゆかぬ。
「せっかく甘いもん持ってきただに、わざわざ腐った魚の行ぐて、おがしなぁ」
「あれは腐ってるのではなく、醗酵というものではないでしょうか」
「うーん」
「そうそう、軒先の大根にぶらさがっていたこともあるみたいですよ」
竜良は聞き及んできたことを思い起こしながら、もしかしてただの食いしん坊だろうか、大原の夜刀神は。霞喰って生きられる精霊のくせに、仮にも「神」の字のつく生き物のくせに。
「俺が張り番に立ちますが、よろしくおねがいしますね」
竜良は律儀に挨拶を、けれど夜刀神はつんとすまして――レナーテのときはもうちょっと愛想よくかまえていたような――レテーナ自慢の瀧のようなみどりの髪に尾っぽをくるりと這わせたりして――どうして、けっこういい性格。
が、夜刀神が小胆なのもほんとうで、竜良がにらんだとおり、数を揃えての目撃証言もないわけではなかった。しかし、あくまでも往時のことだから、進行する現在もそうだとはかぎらない。
ひむか、過去見の奇蹟をためす。狩衣の上側から胸を押さえて、十二歳の冒険者としても駆け出しの陰陽師はまだまだ魔法も不慣れで、発動率もそれほど正確ではない。失敗したくない、と、考えるとそれで胸底がいっぱいになって、あふれんばかりに息苦しくなったりする――そして、とうとう目の前が昏くなったりする。
「焦ることはありませんよ、私の友人もいますし」
高槻笙が大気との対話や呼吸探知などをしてくれている――ただブレスセンサーは精霊には通じないのだけど。シーナは手近な石をくつがえしたり、積もった枯れ枝を払いなどしながら、ひむかに声をかける。
何事にも礼節を尽くす神聖騎士がそうであるように、シーナは年長者からのゆとりでなく、対等な立場の冒険者のひとりとして、おなじ依頼を為抜くための同輩として、青き、そろえた目線から声をかけた。いや、幾分不安はあるが、習いたてのジャパン語は果たして彼の云いたいことをあまねくくるんでいるのだろうか、と。
「私もこうしておてつだいしますから」
結城冴が念想を飛ばす。警戒の緩和をねがう声は色のない蝶のように、ひらひら、木々をすりぬけてゆく。
シーナ、次は、上空を。眺めたのは空でなく、折り重なる梢、もしかしたら狼をよけてそのへんの樹上にひそんでいるのではないか、と。残念ながら見あたらなかったが、なに、まだまだ、これから。
「‥‥はい」
一、二、三。
これで充分。
鎮まった感のあるひむかだが、年齢相応に、野山を駆け回るのも大好きなのだ。鹿が鳴き、雪におおわれる、京の真中のはなやかさとは似ても似つかぬ大原は寂しいところ――嫌いじゃないですよ、と、そうっとこわばる懐でつけくわえる。
「できました。やはり、ふたりで建てるとはやいですね」
竜良の手を借りて夜刀神をかくまう天幕をたてて、だが、けっこうな体操にはちがいない。はなはだあっけなく最初の夜刀神が見つかったので(別なものも見つかったけど)、ゆくりなし、祥風は捜索をとばし、はやばやと祈祷にたずさわるはめにおちいった。しかたがないといえば、しかたがない。
「それでは、今度はこの御酒をこのあたりにふりまいていただけますか? ‥‥人使いが荒くて、申し訳ございません」
「いいえ。俺はむしろ体を動かしたほうが気楽ですから、遠慮なくおっしゃってください」
竜良、形振りのつくりが幼稚なわけではけしてないのだが、透きとおった心根を映してか、いちいちくるめくおもつきとききびとしたはたらきとが幾分彼をいたいけにみせる。いや、ほんとうの彼は羽織にはじぬ立派たる一志士であることぐらい、祥風だって承知のうえだが、それにしたってこうつぶやかずにはいられない。
「私の妹もこんなすなおな時期があったのですけどねぇ」
――‥‥竜良、祥風より二つも年嵩だが。
これまた力をあわせて護摩木を段々に組み、火をともすと、じりじりと焦がしながらいつしかぽっと盛る。聖火にとっては失礼だろうが、とろかすような煖気がゆるやかに舞いあがり、竜良と祥風は人心地つく。
そこへ――‥‥、
デティクトライフフォースは精霊をとらえることがかなう。清芳がようやくたどりついたのは、多重の立ち枯れをかかえる木立の一角。雪乃は笠にしたてのひらの下からはるか彼方を見透かした。
「こんさきだっぺ?」
「たぶん‥‥三体か四体ほど‥‥ちらりと」
たぶん、としか、云いようがない。探知系の魔法はだいたいのことしか感ぜられないのだし、なにより、彼女らの視界を這うのは藪呼ばわりするにはあまりに雑駁な、かといって森林ほど壮絶に生い茂ってるわけでもなく、小蛇にとってはちょうどいい?くらいではないかというくらいの、高みはそれほどではないが広さは十二分、迷い森、フォレストラビリンス。
まぁ予想どおりではあった、だから雪乃はそれほど気にしてやしない、
「なーに。酒もおやつもあるだ。これを見せたら、きっと向こうから飛んでくるべよ」
「だといいのだが‥‥」
「清芳さがちゃあんと浄めてくれただしな」
雪乃は美禄を盃にうつし、それを献上するように膝をつき、目を下におろす。にゃむにゃむ、と、宗教も怪しい真言をとなえてみたり、けれど、こだまするのは肌寒くなるくらいの‥‥鬱蒼の沈黙。
「‥‥祠はすでに修繕した。戻ってもらえぬだろうか? 狼はきっととりはらう、もう安全だ」
とりなすように清芳も付け足してみたが、以下同文。
なにごとにも進取の気性、鷹揚で寛容な雪乃だが、ときには実力行使にうつってみたくなるときもあるのだ。桃唇ちょいとばかり三角に曲げたあとで、どっかり、育ちのかいまみえる胡座に体を代えると、「清芳さ、ほら」清芳へ酒杯をさしだした。
「い、いいのだろうか」
「かまわね」
いいのだ、こうなったら。
「夜刀神さんが出てくる前にぜんぶ飲み食いして、すっからかんにするべ。あーもったいないべな、こげにおいしいもんじゃに」
――‥‥。
藪はなにごとか深く考えているようである。
ばっくり口を開けた雪乃がたっぷり間をためこんだ最初の一口をはじめようとする直前、藪から、ひょい、ひょい、ひょい、と、小さいものがくねって寄せる。ひょい、と、もひとつ、合計四匹の夜刀神が、おずおずと、口をつけようとするところへ、疾風の黒塊がしっしっと矢継ぎ早に、けれど、身軽な二つの影がそれらのまえに立ちふさがる。
「まにあった!」
裕美、羽毛のような軽佻の刀剣をひるがえして、狼らに突きつける。
「無益な殺生は好かぬが、有益とあらば躊躇はせぬ」
「‥‥はぁ」
立木に背をつけ、レナーテはひどい疲労によく似た呼吸。樹木に背をまかせるのは死角をつぶすには悪くないが、都合よい位置に樹木がみつかるとはかぎらないし、移動を放棄することにもなるので、追い込みをみずから招きかねない。
「実戦はむずかしいですね」
新たに得た知識を宝物をかたづけるようにだいじに心の棚によせて、レナーテは左の剣に重力の斬撃をまとわせた。
――‥‥そこへ、祥風のもとにも、狼は姿をあらわした。はぐれたのだろうか、ただの一匹。竜良はななめに剣を備える。いざとなれば、骨身を楯にしてでも守り抜く所存ではあるが、むだな血や汗をきっと夜刀神はきらうであろう、そう気付いた竜良はまずは風迅の刃を醒まそうとしたが――‥‥。
だだだだだだ。狼とはとってもちがうなにかが風の先をとり、狼へ打つように斬り込んでから、かっかっとした口調で言い捨てる。
「兄上がぼーっとしてるからねらわれるんですよ! いいですか、この依頼がじっくり話し合いましょう!」
そして、また去る。だだだだ、と、土埃ならぬ雪埃が畦道のように長くたなびくのを、竜良は呆然と見やった。
「‥‥嵐のような妹さんですね」
「ノルマンの地で体調をそこねたけはいはありませんね、安心しました」
祥風はなにごともなく微笑み、ふたたび祈祷にかえる、炎はてらてらと彼らに赤い綺羅を映す。
けっきょく夜刀神が回収できたのは、攻撃班が狼を殲滅させたずぅっとあとだ。捜索というのは早々に終えられるものでないからまぁ、しかたがない。それよりは七体ぜんぶをまとめられたことを喜ぶほうがずっと前向きだろう。
「もう一度ピュアリファイをほどこしたほうがよさそうですね」
浄化の魔法はこぼれた血糊を無に帰すわけでもないが、やらないよりはきっとマシ。戦のなごりのなんともつかぬ香を、シーナ、白き魔法で融解するのを、ひむか、横目にながめたあと、籠にかさなっておちつきない夜刀神をなだめるように声をかける。
「約束はまもります」
ひむか、夜刀神を連れ戻すとき、約したのだ。しばらくなら控える、いっしょに遊んでもいい‥‥とゆうか、遊びたい。それでつかまった夜刀神の一体が嬉しげにぱたぱた動いて、だが一方で、裕美はそわそわとおちつきなく、重々しく言いかける、
「すまぬが、私は先に失礼してもよいだろうか」
「かまいませんが‥‥どうして?」
「ひとり消さなければいけない人間がいるのだ」
鷲尾天斗、彼にも夜刀神の捜索をてつだってもらっていたのだが、そのあいだに裕美の転倒を目撃されてしまったので。
――‥‥え?
申し訳なさそうながらも足早に京へもどる裕美の背を見守りながら、竜良は呆然とつぶやく。
「いいんでしょうか、せっかく平和になったところなのに?」
「――‥‥いや、まぁ、大原でやらなきゃいいのではないか」
そっちの平和まで、請け負ったわけではない。清芳、黒の信徒らしく、自分のことは自分でなんとかしろ、と、むろん清芳はひむかとともに居残るつもりだ。そうすれば、夜刀神におそなえされた供物の甘味を食べても罰が当たらない。
「お酒もだべな」
雪乃がにんまり、頬をゆがめる。



