 【龍脈暴走】 北斗七星・貪狼・銀
【龍脈暴走】 北斗七星・貪狼・銀
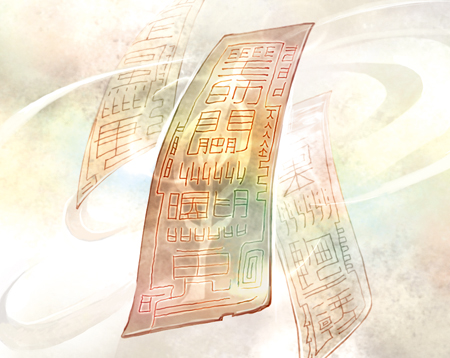 |
■ショートシナリオ担当:紺一詠 対応レベル:8〜14lv 難易度:難しい 成功報酬:4 G 15 C 参加人数:8人 サポート参加人数:5人 冒険期間:01月29日〜02月03日 リプレイ公開日:2006年02月07日 |
|
●オープニング
京の冒険者らにとって、狐どものくわだてにより御所が奇襲をうけた事変は、記憶にあたらしいところであろう。さいわいにしてすんでのところで身に過ぎた大望は阻止されたものの、たった一度きりの頓挫で、汲めども尽きせぬ彼らの妄念をたちきるなぞ、星を数えあげるような、所詮はいたずら。ぜんたいどういうつてをたぐったのだかそのへんの細目は省くが、奸計の糸を裏であやつる九尾の狐・玉藻は、『草薙の剣』の代用として『天叢雲剣』を手中におさめた。九尾はこれにより龍脈、すなわち地脈切断の呪法を成し遂げ、霊峰富士の眠れる護摩炉にあらたな種火を注がんとしくむ。
万が一にも富士が爆ぜ、噴煙が天象をことごとく煤けさせるようなようなことあらば、地動、地裂をはじめとして、日ノ本は未曾有の大災害によって海底ふかく轟沈する――上野国・金山城から発見され、九尾も目をとおしたとおぼしき宮下文書からは、そのような要旨がひきだせるという。九尾の目的がこれらの履行にあることは、白々として自明の理。
さて、龍脈の抑制をつかさどる封印結界は、京から江戸にかけて(江戸から京、でもいいのだけど)、北斗七星のかたちにひろがっていた。そこで抑止力を高めんがため、この七箇所でいっせいに、龍脈の安定をこいねがう儀礼がおこなわれることになったのだけれども――‥‥。
そのうちのひとつ。柄杓の、柄ではなく容れ物の側の一端、貪狼星をつかさどるのは、洛北・大原の地にある眇眇たる祠だ。それはありふれた地蔵堂よりもまだ小さいくらいで、香箱におなさけで屋根板をかぶせたような見掛けの、ひじょうにまずしい普請である。
この封印は、祠に七体の夜刀神を奉じ、土地の者により定期的に加持祈祷や献物をささげることでなりたっていた。それ以外の人々には見向きもされないようなたよりない祠ではあったが、それ故に寂静の平和はたもたれていたので、夜刀神たちは己の境遇に不満をいだくことはなかったし、貪狼の封印がゆらぐことはなかった。
これまでは。
九尾の活性による鬼気にでもあてられたのだろうか。土着の狼たちの乱暴により、貪狼の祠が破壊されるまでは。
夜刀神とはいかめしそうな名前こそしてるものの、じつのところ、けっこう意気地なしなのである。貪狼の祠の夜刀神たちは、終の棲家が瓦解したとみるや、ここはもはや安泰ではないと判じ、三々五々と逃散してしまった。お役目をすっかり忘れたわけでもなかろうから、たぶんそんなに遠くには行ってないのだろうが、しかし、このままでは貪狼の封印はもぬけの殻、九尾の妖術のしあげを待たず、龍脈は煮えたぎる背骨をうごめかせて、大原の足元から終滅はほどける。空の天幕がはらりと落ちてくる。
※
――‥‥さて、こちらでは夜刀神が逃げ出した原因をなんとかしてもらう。『貪狼』の名のとおり、狼があいて。分かりやすいね、にんにもかんとも。
けれどやっぱり問題がないわけなく、この場合のそれはなんといったって、数。狼の群体は多いか少ないかのひらきがはげしいが、貪狼の地で確認された群れは、なんとあわせて十八。最大級にちかい規模といっても、まちがいじゃあなかろう。野性の獣の集団がここまで培われたのには、むろんわけがある。
話はすこし横道にそれる。だいたい狼ってのはそこらの石部金吉よりよっぽど柔軟で、その社会性はなかなか合理的だ、たった一匹の強いやつが何事もとりしきるわけじゃあない。その場その場の状況にあわせて、牽引役を入れ替える。たとえば巣作りなら子を生むメスの意見が優先されるし、獲物を狩るときは若い狼が古老の代理で先鞭をになうこともある。
この群れには二頭の統率が確認されている。そして、そのどちらもがどうして、なかなか一筋縄ではいかないのだ。
一頭は、銀狼。ところによっては、見た目そのままの、銀毛種、と呼ばれることもある。銀毛種たってたいがいの能力に関しちゃ他の狼とたいして変わりゃしないんだが、ひとつだけ突出しているところがある。あたま、知能。人間には及ばないものの、獣にしてはかなりの怜悧・聡明で、これが指導しているからこれだけの多分がしんじられないくらいにきちんと足並みをそろえて、獲物へいっせいに襲撃をかけることができる。こいつらがその気になれば、羆だって負かしちまうだろうね。
もう一頭は、白毛の、雪狼。戦術を担当‥‥というところだろうか。こっちは厳密にいえば、たんなる獰猛な獣じゃない、吹雪から生まれたという雪狼は野獣よりも妖怪や魑魅魍魎にちかく、熱や炎でうけた以外の疵痕はすぐに回復させる、という特質がある。まぁ、野情じゃあほぼ無敵といっても過言じゃあないだろう。それがどうしてただの狼どものなかにまじったか分からないが、おそらくは狩猟時の効率のよさをくわだてたものじゃないか、とみられている。
少々厄介なこの二体だが、さかさまにいえば、この二体をどうにかすれば、あとはほとんど有象無象の、ふつうの狼ども。みずから尻尾を巻いて退散するやつもいるだろう、といっても油断は禁物だが――‥‥。
いったい何にそそのかされたものだか、こいつらがかたまって『貪狼』の祠を襲撃したものだから、たまったものじゃない。そりゃあ夜刀神だって、すたこらさっさ。狼どもをこのままにしておけばそのうち夜刀神だって食いちぎられるかもしれない。
だから、よろずの手配はぬかりなく。
●今回の参加者
ea4183 空漸司 影華(31歳・♀・志士・人間・ジャパン)ea5001 ルクス・シュラウヴェル(31歳・♀・神聖騎士・エルフ・ノルマン王国)
ea6264 アイーダ・ノースフィールド(40歳・♀・ナイト・人間・イギリス王国)
ea9150 神木 秋緒(28歳・♀・志士・人間・ジャパン)
ea9502 白翼寺 涼哉(39歳・♂・僧侶・人間・ジャパン)
eb0601 カヤ・ツヴァイナァーツ(29歳・♂・ウィザード・ハーフエルフ・ビザンチン帝国)
eb1565 伊庭 馨(38歳・♂・志士・人間・ジャパン)
eb2099 ステラ・デュナミス(29歳・♀・志士・エルフ・イギリス王国)
●サポート参加者
天螺月 律吏(ea0085)/ 八幡 伊佐治(ea2614)/ 鷹波 穂狼(ea4141)/ 藍 月花(ea8904)/ アルディナル・カーレス(eb2658)●リプレイ本文
「‥‥最近‥‥寒い所へ行くのが多いなぁ‥‥私‥‥」そろそろ私、雪だるまにでも変身できるんじゃないかしら。――‥‥なれるわけがない。けれどそれくらいの妄想でもいだかねばやりきれないかじかみは、まるくする呼吸でも曖昧にすることはできなかった。空漸司影華(ea4183)はもう一度ばかり、きゅうっと肩をすぼめて、合わせた両の手に息を吹きかける、一度だけ、それできっかり閉じきった。
およそ厳寒ほど、威のある箝口令はこの世にない。白翼寺涼哉(ea9502)が突く錫杖からの折々、寂静の音、高く波をたてる、それがまるで冬将軍の咆吼にもひとしく聞こえる。涼哉は退屈げに前髪をゆらした。
「温泉でも入りてェなぁ‥‥」
「寂光院畦にあるみたいね。味噌鍋が名物らしいわよ」
アイーダ・ノースフィールド(ea6264)、冷気に負けじのそっけない顔付きで披露するは地場での聞き込みのたまものの、しかしいったい何を聞き及んできたのやら。
使命を帯びる者どもは、往くも往くも、征ったり。
その足元にはいわゆるかんじきを履いて、踏み込むたびに、麻の布をすくめる音がする。だが、伊庭馨(eb1565)はそれへ耳をかたむけるいとまもなかったようで、
「これで戦闘するというのはとてもではありませんが、むりですね‥‥」
かんじきという機構は足裏の面積を拡大することによって、ふくよかな雪原へめりこまないことが最大の目的だから、「すべらない」「もぐらない」はできても、「雪上を身軽に飛び回る」といった効き目は見込みがたい。
「だから、かんじきで足場をかためて、そのあとは、これ」
ほら、雪駄もあるから。アイーダはとん、と、あつらえてきたうちの一組をそろえてみせる。草履の裏に張られた革で滑り止めと防寒を同時に期待できる雪駄のほうが、たしかに、奔走の予想される彼ら向きだ。鷹波穂狼のもってきてくれた藁靴でもいい。馨、してやられた感がいなめない。まさか異国の出自のアイーダに、ジャパンらしい智慧をみせられるとは思わなかったので。
「それはそれでいいんですけれど‥‥」
問題は、ひとつ解決できた。それは、いい。
――‥‥誰もが敢えて、これまで口にせずにきたことがある。
いったい、これは、出発からずっと彼らへ姿をみせずに付きまとう、ひるがえる毒気のような、だがそれよりずっと悪質なものはなんなのだ?
いつしか皆のものいいたげな視線が、ルクス・シュラウヴェル(ea5001)にかたまる。ルクスとてそれに気付けぬほど、無聊な女性ではない。ただ‥‥お題目を唱えるのは少々不得手で、言い訳などこしらえるのはもっての他で、だから渋面つくり結果から口にするしかなく。
「‥‥こらえてくれ」
と、それ、布でつつみ袋にかくしておいてすら瘴気に酷似したものをただよわせてるのを、あらわにすると、もはや凶器のおもむきで、
「友人に野生の獣を呼び寄せるなら、これくらいやらないと、といわれてな」
だが、とうのルクスですら顔を曇らせるほどの、熾烈な臭み、藍月花があつらえた餌料へは誰もがみな心中「やりすぎ」と――保存には最適の冬場で、これほどのものを短時間にしあげられたのは、匠の技かもしれぬが――‥‥。
と、
ぱくっと。
「‥‥」
「‥‥」
「‥‥釣れたぞ」
涼哉がシャラリと錫杖を鳴らして指す。干物に食らい付いていたのは案に相違して、鱗が反射光を小蛇、夜刀神だ。まずは一体――って。ルクスが腕をざかざかふっても根性のある夜刀神は、それでも保存食から離れませんでした。
「渡してくる」
「私も行くわ」
と、神木秋緒(ea9150)はルクスに遂だって、さてその後はその後――その前に――‥‥。
「ねぇ、待って。そのまえにちょっとだけ、触ってみてもいいかしら?」
どきどき、ちょっと。ステラ・デュナミス(eb2099)は防寒の衣裳の袖の下にくらました手を、夜刀神のほうへおずおずと、すると夜刀神は鎌首もたげて、牙はなく、鱗はさわさわしていてなかなか触れ心地はよろしい。かわいい?
「つかれたー」
ごてっ。カヤ・ツヴァイナァーツ(eb0601)はいちめんの雪原に今にもつっぷせんばかりだが、寝たら死んでしまうぞ冗談抜きで。
経典(スクロール)はたしかに便利な道具だが、反面、魔法にくらべて使いづらい点が多い。威力の調整がまったくきかないというのもそのひとつ、「専門用のスクロールで初級の威力を発動させる」等はできない。まして、ツヴァイは上級の精霊碑文字をおさめて日が浅く、フレイムエリベイションを点火させるまでだいぶん時間がかかった。ソルフの実を早々と呑み砕いてなお、ツヴァイの精神はくたくたに使い古された雑巾のよう。
「ねむたいなー。おふとんー、まくらー。天幕ー」
ツヴァイを見送った天螺月律吏も、彼のこんな姿をみれば草葉の陰から(←死んでない)泣いている――いや、その前に怒りでハリセンをぶちかましているだろう。というような言文を、馨は喉の奥側におしこめる。
「‥‥あれは祥風さんが夜刀神様のためにたてなすったものですよ。眠気覚ましなら、豆でも噛みますか?」
馨が袋からだしたのはこの時機にそぐって追儺の豆で、睡魔という名の邪気を払えるかと、けれどツヴァイはすげなくあしらう。
「ソルフの実じゃなきゃ、やだ」
「申し訳ありません。今、狼より先にツヴァイさんをかたづけてもいいかな、って気分になりました」
「おら、お子さまども。うるさくしてっと――‥‥」
今日のこちらの面子で「子ども」呼ばわりできるのは、十九歳の秋緒ぐらいだが(本人がどう思うかは別の問題として)、馨もツヴァイもいちおうはまったき成人のはず、けれど所帯持ちの涼哉にとっちゃ似たようなものだ。切れ長の目を前方に流して、
「おいでなすったぜ、お客さんが。‥‥お互い、泥だらけだねぇ」
世もつつがなしならいっしょに風呂でもと誘おうものを、
「悪ィ‥‥おたがい苦労するねぇ」
狼のしたたらせる黄色い唾が霧雪を灼く様子は、沼気からくみ上げた酸がこぼれるに似る。
たわわな胸間から迎神をこいねがうように組んだ指を開けば、ステラ、はたして荒ぶる炎霊は彼女の安らぎの魂魄のもとに降り立つ。高速詠唱は、刹那よりも刹那は、だがステラは幽思のおもむきをたもったまま、扇状の氷嵐を狼らの芯へとおくる。
まっしろく失せる円錐の視角から、野獣の、熱と光を慕う絶哭がかぼそくながれた。
「ごめんなさいね」
あなたたちをまったく傷つけないですむ方法を、私は知らないの。――‥‥それが殺生の釈明になるとは思えない。が、追いつめられての躊躇はさらなる非業のきっかけにしかならないのだ。ステラは碧の瞳を光らせて、狼陣の抜け目をさぐると、銀糸たなびかせてそちらに立ち回る。
そして、まろびでる影華が、
「どこ、銀毛種は!?」
牙をむく狼の一頭を、なでるような、薄い剣捌きにおとす。並みの狼の群れは地を這うくすんだ黒雲を思わせる。銀にしろ白にしろ際だっていいはずなのに、影華の鵜の目鷹の目でも、切れ切れすらつかまえることができない。
「どこよ、とっとと出てきなさい!」
「影華さん、ここは私が!」
新陰の、うしろに道はなく前にのみある、秋緒の上段からの刀は狼の腹を横から割った。しぶく血霧、断末魔、骨へ刃がぶつかれば、ごぎりと、こちらの骨までも同調してひびわれそうないやな共鳴――先刻納得済みのこととはいえ、なまぐさな実感は神霊につかえる身にはたえがたい。
「けれど、神域を荒らす施為ゆるしがたい。おとなしく刃に伏せなさい!」
だが、秋緒の刀剣は二頭の狼の連係を断ったが、片割れの悪意の汐先を彼女にさだめることもした。ひとつの刃でかぶれるのはたった一体の獣がせいぜい。秋緒の肩へ沈もうとする爪と牙をつなぐ肉塊に、寸前、疾風をひきながら眼窩にくらいつく、矢。アイーダの連撃。
ふたたび矢をつがえようとアイーダが梓弓を降ろすと、ひゅぅっと、矢羽根のふるえによく似た猛禽の鋭刃のいななきが耳朶のすぐそばに響く。改めて目をやらなくても、アイーダは音の主を理解していた。
「遅いわよ、もうこっちに来てるじゃない」
アイーダが空へ放していた迅羽、ヘイゼル。彼には狼らを捕捉したら教えるように指示しておいたはずなのだが、ヘイゼルの帰還の前にとっくに戦線ははなたれている。アイーダがにらむとヘイゼルは異議をとなえるように、風籟の声音で短くさわぐ。
「‥‥え」
ヘイゼルには悪びれたところが、ちっともない。むしろ彼は誇らしく、胸を反らせて、二度啼いた。それでアイーダも、知るのだ、二の意を。
「二手に分かれてるのね!?」
彼らはもともと大原を根城にしてきたのだ。ルクスは大雑把な地図をとりよせてはいたが、この時代の測量技術はまだまだ未熟で。アルディナル・カーレスの偵察もじゅうぶんにはまにあわず、土地を走り抜け振り回し引き寄せる狼らとの土地勘との差異を埋めるには、ちょっとやそっとの小細工ではすまない。
背後を、衝かれた。
仲間内を後衛と前衛に分けたのを、憎々しくも、逆手にとられた。アイーダの警告をまっさきにとったツヴァイが迷妄の夢を織り込み、きざしの一頭から狂乱をはためかせて、彼らはようよう先手をまぬがれる。涼哉は伸暢する錫杖で距離をはかり、あいだをとり、
「これを考えたのも銀毛種かね? いい性格をしてるよ」
「軽口をたたいてないで」
たたらを踏みつつ、十字のしるしから緊縛の鎖を投げかける。ルクス、が、許多をしりぞけられるほどの余地がないのはこれもおなじ。一匹一匹をからめていっても、結んださきからほどけて、嗤い、雪原の幻に消える。
「だから‥‥銀毛種を‥‥」
消耗戦に等しい状況に、馨は歯がみする。機械的な振りかぶりが、だんだんと彼の腕首を石にする。冒険者らの作戦は統率をあぶりだす具体性にいまひとつ欠けていた。こうして陣営をけずっていけば、いつかは銀毛種にたどりつくかもしれぬ、だがそのまえに馨の四肢は身じろぎもせぬ鉛におちいるかもしれぬ
それでは、遅いのだ。なにもかもが。
春の霞の碧の瞳を、今は、胃のもとめぬ飢餓に血走らせ、馨は群狼を見据える。銀の狼はどこだろう。色、彩のことなるのは――‥‥。
――‥‥色?
「みつけたーーーっ」
後方からおどりでる影華の「空漸司流暗殺剣‥‥閃空斬!」重みはすなわち剣気となる、影華がはじいた狼の、あふれる血流がそれのおもてをぬぐい、本来の鮮明をとりもだす。べったりと上乗せされた泥土から光芒をはじくのは、しろかね、反射は戦場をするどくつきぬけた。
「しゃらくさい、偽装なんて!」
「‥‥そっか、そりゃうちの奥さんのほうがふかふかであたりまえだ」
あ、痛。涼哉は額に手を置いた。
ある種の考察として、銀毛種が利発であるのは、自然界において、あまりに際だつ体毛の不利をおぎなうためともいわれる。ならば、損失そのものである身を取り繕うすべくらい心得ていたっておかしくなかった。
涼哉の緊縛にあわせて、影華と馨がそろえて斬撃を投げれば、銀毛種は反撃を封じ憎悪に燃え立ちながらも、目を閉じる。
それと知れれば、注視はたやすい。雪狼は銀毛種のほんの近くで疵を生産していた。もしかすると夫婦かもしれぬ、そんなたあいない想念が馨の心をさかまいた。――‥‥それは、ほんのいっしゅんで。
「伊庭さん、炎!」
ツヴァイの声にひきこまれた。生身の狼をあいてするが故に、流血に狂える性のあるツヴァイは外界とじかにゆききすることはならず、めかくしをしながら、火の柱をたてている。それを不意にすることこそが、罪であり罰であろう。剣に付け火を沿わせて雪狼へ、二の剣戟を。炎の矢があとから、走る。火を順繰りにくらいながら、雪狼は泡をふいてやがて人形の倒れるようにことりと横殴りに動転する。
「魔物ハンター、ハンティング、無事終了」
耳慣れぬ異国の言語をまじえながら、アイーダが弓をまわすと、拍ちもしないのに弦がぴぃんと振れる。
「おつかれ、なにか温かいものでもつくろうか?」
ルクスの申し出は、けれど、頑迷にこばまれる。
「うぅん。帰る。今すぐ、とっとと、なにがなんでも、地震がいますぐおきたって!」
いきなり壁でもたてられたように。日頃の淡々をかなぐりすてる秋緒の発憤に、ルクスは目をぱちくりさせる。
「‥‥どうした」
「お兄さんと気まずいらしいですよ。あちらは儀礼ですから、どうやらもっとひまが必要みたいです。終わるまえに姿をくらましたいって」
「馨さん、告げ口しちゃダメーーっ」
「あ、じゃあ、私あっちへおじゃましちゃおうっと。邪魔しないからいいわよね? だって、ほら、はぐれ狼がもどってくるかもしれないし」
おもに自分へむけて、言い訳じみてはいるが、ステラの言い分はごもっとも。はたからは野遊びにでも入るかのようにうきうきしてるようにみえても。
ところでツヴァイは、たぶんそちらであろうと涼哉の方向にあたりをつけて、
「‥‥で、僕はいつまでこのまま布をかぶってなきゃなんないの?」
「血の始末が終わるまでだな。だいぶかかるぞ、なんせ狼十匹以上いたからな。いっそ、そのままで帰ったらどうだ、絶対安心だろ」
「ええーっ!?」
「‥‥はぁ」
影華は剣を抱いてうずくまる。ひさしぶりの実戦、どうにかこうにかかんばしい結果をのこせたようだ。腕をふりまわして喜びを叫びたい気持ちではあったが、しかし、実際にはこんな低空のしわざしかおこなえない。
「守れたんだよね、私たち」
しかし、きっとほんとうのことはそれからなのだ。純白に広がる雪景色をほほえましい遊戯にもちいるも、血の染みをつけるも、紙一重であるように。次の剣はいったいどのように使われるのだろう、と、影華の思いは雪のなごりにとけかかる。



