 【シ】 枝
【シ】 枝
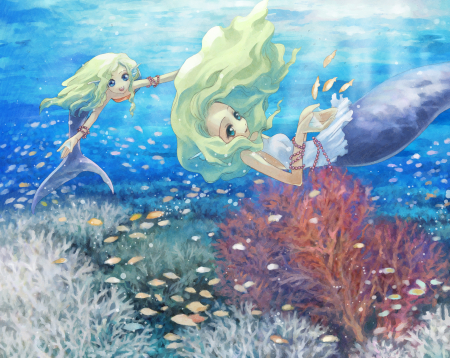 |
■ショートシナリオ担当:紺一詠 対応レベル:1〜5lv 難易度:普通 成功報酬:1 G 18 C 参加人数:8人 サポート参加人数:6人 冒険期間:03月09日〜03月15日 リプレイ公開日:2006年03月18日 |
|
●オープニング
●□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
たすけてください
さより
●
ひょっとして、文字をきちんとさらったことがないのかもしれぬ。どうしようもなくほつれた糸をがむしゃらにほどいたようなひどい字体で、それも全体がおぼろににじんでいるせいで、大部分は判じられなくなっているが、主旨であろう一文と刻銘だけはどうにかこうにか読み取れた。
生成りの――白というには黄の多い、朴訥というあしらいで質の悪さをおぎなう――安物の布地に、これまた安物の墨で書き入れられた、書状と呼ばうのもためらわれるちゃちな、それは単体であったわけでなく、木の枝に結わえ付けられてあったそうな。梅ヶ枝。いじらしくかぐわしい花をつけるわりには、歴戦の勇士を思わせるごつごつとした硬骨な樹肌。
「ある日、俺の生きる村の浜辺にこれが流れ着きました。はじめは子どものいたずらだろうと思ってとりあわなかったんですが‥‥なんとなく気になってきちゃって。俺は漁師です。俺のでる海域の潮流なら、なにがどこにあるか、手に取るように分かる。その枝がどこから流れてきたかも、おおよそ見当がつきました。だから俺、それを書いた『さより』を探してみることにしたんです」
依頼人はこんがりとほどよく日に灼けた若者で、言の葉をほとばしらせるたびに、夏の雲そっくりのまっしらな歯が容赦なくぱちりときらめいた。
「それはたぶん、俺の村から五里ほど離れた島から流れてきたんだと思います。それまで俺は、その島へ一度も足を踏み入れたことがありませんでした。そんな必要はいままでなかったですから。しかし、これを書いた『さより』がいるかもしれないと思って‥‥俺は村を訪れました」
物憂い。溜息。語るしらべが混濁した低さで。
「‥‥さよりなんて子はいないと云われました。そうかもしれません。なにもかも俺の勘違いかもしれません。潮の流れを読み違えたのかもしれない、不幸を未知の海溝に託さなければならない『さより』なんて子はいないほうがいいに決まってる。けれども!」
渓谷を一気に飛び越すように、若者の気勢はだしぬけに右肩上がりになる。
「俺は気になって、その村を観察してみました。おかしいんです、まったく子どもが見あたらない。もしかしていないのじゃなく、家のうちから出てこないだけかもしれない。でも、それだってぜったいおかしいことじゃありませんか。ねぇ?」
続けて若者は、村の地理を説き始める。東には幻のような砂浜をいだく海岸、対する西は島の中央へ向かい、手入れのゆきとどかぬ平原がうっちゃられ、それは扇をあけるように南までだいたい似たような按配でひろがるが、けれど北はちょっとばかり独特で、羚羊(かもしか)の雁首そっくりの輪郭のかなり大きい岩壁がすっくとのびあがる。岩壁というととんでもない障害にも思えるけれど、ほどよい傾斜、坂道がとりつけられているから、人間が上り下りすることもじゅうぶん可能。
それだけでなく、八合めあたりのいくらか開けたところにちょっとした祠堂まで据え付けられている。海神を祀っているのだそうで、明け方にはそこから銀にかがやく海洋がのぞめるようだ。ようだ、と推定にならざるをえないのは若者もそこまで立ち入れなかったからだけれども。岩壁の祭道は村の行き交い路にのみつながっていて、しつこく「さより」を尋ねて村人をむくれさせた余所者が気楽に邪魔できるような雰囲気ではなかったらしい。
「俺が村へ行ってから、どうもそっちの警戒が強くなってきたように思えるんです。かといって祠堂を大事にするそぶりもない。‥‥上手くいえないけど、ちょっとこう、妙‥‥胸が焦りでせき立てられるってゆうか」
依頼としては、申し分ない。しかし、ただの好奇心の発露にしては、若者の所作はどうもていねいすぎる。それを指摘すると、若者は歯を隠し、負けた猫のようになさけなくほほえむ。
「だから気になって‥‥。べつに甘やかな期待をだいているわけじゃありません。誰も悲しんでいない、それを知りたいだけなんです。それとも俺の予感があたってほんとうに誰かが泣いているのなら、たすけてあげてください。‥‥よろしくおねがいいたします」
たすけてあげてください。
一生の宝物をあずけられたがごとく、それだけが聞くものの心をくしけずる。
●
たすけてください。
たすけてください。
たすけてください。
「‥‥ひとりは、いやだよ」
ほんとうは泣くのもイヤなの、だけど泣くしかできないの、たすからないの、それも知っているの、あきらめなきゃいけないの、だけどもさよりはちいさくて。ほら、水をもらえぬ枝のようにがりがりになった手と足は、泥をあびたわけでもないのにおかしな茶色。こんなみにくいさよりにはだれもかまってくれない、わかっているのだけれども。
「‥‥ひとりは、いやだよ」
たすけてください。
●今回の参加者
ea6534 高遠 聖(26歳・♂・僧侶・人間・ジャパン)ea7125 倉梯 葵(32歳・♂・浪人・人間・ジャパン)
ea8151 神月 倭(36歳・♂・志士・人間・ジャパン)
eb0971 花東沖 竜良(34歳・♂・志士・人間・ジャパン)
eb3297 鷺宮 夕妃(26歳・♀・陰陽師・人間・ジャパン)
eb3587 カイン・リュシエル(20歳・♂・ウィザード・ハーフエルフ・ビザンチン帝国)
eb3722 クリス・メイヤー(41歳・♂・ウィザード・エルフ・イギリス王国)
eb3916 ヒューゴ・メリクリウス(35歳・♂・レンジャー・人間・エジプト)
●サポート参加者
アシュレー・ウォルサム(ea0244)/ 天城 烈閃(ea0629)/ ゼルス・ウィンディ(ea1661)/ 水葉 さくら(ea5480)/ 伊庭 馨(eb1565)/ 結城 冴(eb1838)●リプレイ本文
●三月の海の、物柔らかなこと、しめやかなこと。――‥‥露草色の千波万波を真珠色のうねりがそっとふちどり、海面にたまる日は次の波に千々にくだけ、涙となる。
咎人のように永遠の従僕、波、波、倉梯葵(ea7125)は沈黙をたもち俯瞰する。この浜辺に梅の枝が流れ着いたのだ、と聞かされてみる波打ち際は、無数のわらべがなにかをせがむようでもあり、容赦ない反復と鳴動が白昼夢を遠ざける。
天城烈閃、ゼルス・ウィンディ、彼等の砕心の拾い歩きの果てにも、めぼしい発見はなかった。それはそこにある、昨日も明日もそうであるがまま。
「海神宮というのは、こんな碧海のむこうにあるのかもしれませんね」
神月倭(ea8151)は、無邪気に回転をくりかえす汐風のなかに後れ髪がたわむれるのをそのままに、葵の隣、ひっそりとたたずむ。明度高めの瞳に、照り返しは少々強すぎ、しばたきを幾重にも強いられた。
出かけに結城冴や伊庭馨の助力もあり、倭は陰陽寮の書庫をさぐってはみたが、その地方にのみ固有の信仰、宗教の形態というのは見受けられなかった。島の歴史、災害記録、その他島にかかわりそうな素材までかたはしからあたってみたものの、やはり成果は似たようなもので。
クリス・メイヤー(eb3722)の目の付け所は、あ・かるくても四十路間近なところを発揮させ、もうちょっと実務的といおうか。彼はちかくの市場へ話を付けに行った、漁獲によって身をたてているなら、交易がおこなわれているはず、と、気がかりがひとつばかり。
「最近、あの島と取り引きはないんだって」
「どういう意味だ?」
「先方、あ、島のほうね、が出荷を抑えめにしてるみたいなんだってさ」
文明から線を引けば、孤島の内側だろうと経済の循環もなりたつだろう。が、依頼人はそういう口ぶりを見せてはいなかった。きゅうきゅうではあるかもしれぬが、なんとか文化的生活をやりくりしていると思われる――だのに。
「‥‥近海で魚がとれなくなったような話は、聴かなかったがな」
漁夫たちのあいだに、懸念をかんじさせるような言い草はなかった。島の人間らが市場へ顔も出せないほど、引きこもらねばならぬ原因はなさそうだ。
地場のものからは隣島を愁う声は上がっていない、現時点では、漁労をいとなむ風体は目撃されていたし、そんなこともあるだろう、程度の旨意らしい。
「不安を感じているのは俺たちだけか‥‥。無駄な杞憂か、必要な配慮か」
皮肉を汐に呑ませて、葵、体を捩じ向け、そろそろ出掛けよう、ということになる。
「うみー」
「クリスさん、はしゃぎすぎると舟から落ちてしまいますよ」
「おいら、いざとなったら飛べるもん」
リトルフライの魔法で、えいっとばかり。云うがはやく、クリスは空色をともし、一寸ばかりの高みへ。それだけの高次からでも、真実は断岸に落ちくぼんだかのように、ちっとも見えてきやしないのだけど。
●
鷺宮夕妃(eb3297)は、花東沖竜良(eb0971)とカイン・リュシエル(eb3587)に連れられて、島の東に降り立った。どうってことない捨て値の砂浜、小蟹がしゃりしゃりと蹴爪で流砂をかき、骸と呼ぶにはつつましすぎる貝殻が、雑駁な日常に置き去った懐かしさをふとおこす。
断りのない上陸は、蜜にむらがる蟻のように、島の衆人を呼び込む。冒険者らが、罪人がこの島に逃げ込んだので捕まえに来たのだ、と、でっちあげの実情を語ると、
「都からか? じゃあ、あんたらは誰の手回しで、捕り物に来たんだい?」
用心深さに胸まで浸かる村のこと、それくらいの素性の確認は、当然だったろう。悪行の申し立てがいちいち真に受けられたなら、この世はあっけなく冤罪天国だ。
が、冒険者等は身分の証明について、ほとんど考えをめぐらせてなかった。咄嗟にカインが声を荒げて、
「が、外人なんです! 浅黒い肌をして、金色の髪の、頬に塗り物のある男です。ヤツは僕が生まれてすぐ、僕の両親を‥‥」
「僕はカインさんの親の敵でしたか。二十六年生きてきて、初めて知りました」
カインの生年は、暦年齢、三十一歳(ハーフエルフだから、実年齢は十五歳)。些細な食い違いは、このさい意味のないことだ。
ヒューゴ・メリクリウス(eb3916)、まぁ当たらずとも遠からずといったところですけれど、とひそやかに付け加える。高遠聖(ea6534)は、ヒューゴの世迷い言にどう答えてよいか分からず、彼の使命ともいえる黒の裁きを提言した。
「ブラックホーリーで、たしかめます? 二分の一の確率ですけど」
「やめておきます」
夕妃たちと乗り合わせてはいたものの、彼等、諸共には降りなかった。依頼人に舟をまわしてもらい、島の北、岩壁のそばからの漂着。カインの叙述を立ち聴きできる(‥‥とうとうヒューゴ、国一つをほろぼしていた)くらいには、浜辺へ程近い。ふと髪際をなにかが打ったような気がして、ヒューゴは顔を上げる。
梅の木だ。物理的な肌触りはただの幻想で、実際にはそこからこぼれる、色付くような香気が彼を張っただけである。木の枝に紛れて、板張りがうっすらと木漏れ日にうかがうのを見、あれですね、カインは承知した。
「ここからの登攀は、難しいみたいですから‥‥では、聖さん。カインさんたちが引きつけてくれているうちに、村のほうへ行ってみましょうか」
「おねがいします」
聖との同行は、隠密のおとないには不向きだろう。が、行き先はジャパンの祠堂、ジャパンの古い説話や因習等についての知識のある聖との検索のほうが、まちがいはすくない。
ヒューゴをまねて、聖も仰向く。ここからではかたちまではよく判じられなかったが、古そうだ、そんな気がする。
あなたに信心はやどっておられますか? あなたは慈愛をさずけていますか? ――野晒しの白骨のように、それは黙して語らず、代わりに、聖が空言を真剣につく。
「人間は必要であれば、いくらでも嘘がつけるものと思います。信仰は己が心の内にあればいいのであって、外見は然程関係ない‥‥僕たちは、いったいなにが真実なのかを見極めねばなりません」
「そうですね。精霊も神様も金銀財宝なんぞどうでもいいでしょうし、なら僕におとなしく渡しやがればいいんです」
それとこれとにはだいぶ事情のずれもあるが、まぁ、さておき。
一方でカインの煮え立つ熱弁は、どうにかこうにか、受け入れてもらえたらしい。ごめんなさい、ごめんなさい。だしぬけに廃滅した祖国へ内心、必死の慚愧をたむける、ヒューゴへは――ここにいないのだからよしとしよう(しっかり聞いてたのだけど)。
「はやく小さなお子さんを避難させないと」
「そういえば、子どもさんの姿がみえないようですが、何故でしょうか?」
竜良の吟味に、島民一同に動揺がつらぬいた――ように夕妃には見える。竜良から夕妃へ、どこか小心翼々としながら移る視線に、悪意はみられない――と、夕妃は思う。眼識は、為政に末端とはいえたずさわる志士である竜良のほうが上等、が、夕妃はきちんと自身で見ておきたかったのだ。愛情だろうと遺恨だろうと、他人任せにはしたくない。それらを一度、すべてなくしたから。
ほんとうのことをいうと、テレパシーを使って村の内部をさぐりたかったのだけど、魔法にはどうしたって発光現象が付き物で、これを遮るにはどこかの物陰へ潜り込むかしなければならぬ。いったん島民のまえに姿をさらした以上、間隙をぬうのは難しそうだ。
が、仮に魔法をつかえたとしても、それでも事態に変則はもたらされなかったろう。テレパシーは、不特定多数を対象にできないのだから。「子ども」という夕妃の指定は、曖昧で大雑把すぎる。
――‥‥あかん、あかん。うちがたじろいだりしたら、かえって竜良はんらに迷惑かけてまう。
夕妃は小柄な体が鉤に曲げて、きゅぅっと竜良の袖にとりすがる。ようやく己を持ち直した島民たちのひとりが、斑声をあげる。
「今はみんな昼寝をしてるのさ」
「『今』‥‥? じゃあ、しばらくしたら逢わせてもらえるのでしょうか」
「変なことを云うね。あんたらは罪人を捜しに来たんだろう。子どもたちと、なんの関係があるんだい?」
押しては引き、引いては押す、足元の潮汐にもよく似た応酬、これ以上は彼等を引きつけてはおられない、と、みなしたカインは踏ん切る、推測のひとつを披露する。
「危険なので会わせないように、家から出さないんじゃないですか」
竜良の一言より、それは覿面、糊で洗ったように彼等を凝りかためる。だが、
「沈黙は肯定とみなしていいのか? それとも、否定か。どっちつかずは困るな」
射掛けられた、鏃のように辛辣な一言。葵、むろん残りのものもいる。倭はまるで敷物の上側をすべるように移動して、
「連絡がないようだから、様子をうかがいに参りました。どうされました?」
依頼人の梅ヶ枝を片手に、倭は舟を下りる、匂うような白銀の周囲にたちのぼり――そういう天女のおはなしを聞いたことがありますよ、とは、カインの後日談、あとあと彼等は回顧する。
そのときは、それどころじゃなくなった。
突如、わーっ、と、戦場の鯨波ともおもえる、だがずっと小振りの連呼が、岩壁の方角から、彼等のはざまにそそがれたからである。
――‥‥ヒューゴはよくやった。肉体を透過させるインビジブルの魔法、忍び足、が、この二種を基本とする以上、迅速な振る舞いはなかなか得難い。くわえて隠密の苦手な聖ともいっしょだったのだ、道の半ば、ここまでなにごともなく来られただけでも上出来としよう。
「聖さん、こうなったら走りましょうか」
「はい。‥‥でも、」
聖は杖棒兼用だった錫杖を、しゃん、と、短い祈りとともに垂直に立たせる。と、追っ手のひとりの厳顔がみるみる墨にでも沈んだかのようにけぶってゆく。ディスカリッジ。
「行きましょう」
「お見事」
浜辺の冒険者らは、荒立ちに心当たりがむろんある。彼等へ追いつこうとすれば、彼等がこれまでに相手していた島民らも彼等に組み付こうとする、ち、と、舌打ちとともに印を結びかけたクリスを、葵が制する。
「不用意に傷つけて、あとでギルドに請求書の束がとどけられても困る」
「そりゃそうだね」
刀をもつものは鞘に収めたまま、魔法を知るものは示威的に腕を振り上げて、めざす、別れ別れになったであろうものたちも向かっているであろう行く先に。
そして、彼等はようよう達する、間一髪で追っ手から抜け出したヒューゴたちが祠堂の扉を開け放つところへ。
けれども――‥‥。
聖に震い付いてきたのは――聖がいったんは竦みながらも「だいじょうぶ」と抱き返したのは――皮膚のごつごつと変質した、ごっそりと髪も抜け落ち、見た目にとても童女、いや神の造型とすら思えぬ――しかし、まぎれもなくそれが「さより」である。
●
「えやみだよ」
えやみ――疫病、流行病、
「‥‥あんたらは平気だろう、体力のあるおとなはかからん。けれど、誰かが近付けば、そいつを仲立ちにしてそいつの子どもが感染する。だから、閉じ込めるしかなかったんだ」
死の病魔がこれ以上はびこらぬよう。
風媒によってすら感染するかもしれぬ、だから他の子どもたちには外へ出ないよう言いつけ、村から距離のある祠堂へさよりを隔離した。水と食事は、むしろたっぷりと、豪勢にあたえた。願いもできるかぎり、聞き届けた。墨や布はそのときのものだ、が、島民たちもまさか結び文には使われると思っていなかったので、依頼人の来訪は心底島民をおどろかせ、そしておびやかしもした。えやみのことが知れれば、村八分どころではない、島全体が爪弾きになる。だから、依頼人をすぐさま追い返し、病害の発生を勘づかれぬよう、島のものたちは外部との接触を自主的につつしんだ。
島民は淡淡と語った。覚悟を決めた敗者は、どこまでも疲れていた。
「しかたがないの、病気だから。それは分かってるの」
泣きじゃくる、嗚咽する、病的な謦咳がさよりの喉を嗄らす、
「でも、最期までひとりはいやだったの。誰彼といっしょにお話をしたかったの、顔を合わせて」
ごはんもずっとひとりで食べていたの。啾々とどこか獣じみて啜り泣きするさよりの、
「‥‥そうですか、つらかったですね」
カインは彼の知るかぎりの礼儀をつくして、さよりの手を取る。西洋の貴婦人へそうするように、唇をそっと沿わせた、膿や痣でいっぱいになったそれをいつくしむように。
「でも、僕たちはあなたに逢いに来ました。あなたを心配した、あなたの書簡を受け取った人に頼まれて」
「せや。うちら、助けに来たんや! みんなでやで。ひとりじゃあらへん。な? なんなら今からいっしょに宴会でも‥‥」
夕妃の誘いに、さよりはうっすらと微笑む。
夕妃は悟る。冒険者らはまにあった。これがさよりの願い、さよりが助けてほしかったこと、ひとりでなくなること、愛してると云われること、抱きしめてもらうこと‥‥。
冒険者らは、ほんの間際で、まにあった。
西へかたぶく日が汀線に融けこむころ、ひとりの少女が、ついえる。ヒューゴの携えた水は死に水となり、さよりの唇を糸となって伝うが、それで神話のように再生がかなうわけもなく、さよりは枝の姿のままで、朽ち果てた。
●
島からの去り際、クリスはしまいまでぐずぐずした。云おうかどうか、ずっと悩んだ。けど、けっきょく選ぶ、暗黙よりは口授を。
「おいら、陸の市場で聞いてきたんだけど、へんな病気は起こっちゃいなかったよ。だから、あんたたちの心配りは実ったと思う」
こんなふうに、この村での方法を認めてしまうのはイヤだ。が、さよりは最期まで病苦をひとりで耐えたのだ。ならばそれがムダではなかったのだ、ということを、誰かに知って欲しかった。
さよりはほんとうに、命を懸けた。
島のものが送ってくれたので、冒険者らは皆いちどきに帰還がかなう。横へ上へ放埒にゆすぶられながらそれでもきちんと前進する舟は、人生の道行きにどこか生き写しで。
竜良は腰に帯びる剣へ、爪をかける。どれだけ悪漢を蹴散らそうと、疾患も飢餓も天災も‥‥名のしれぬ不運は尽きやしない。
「俺の剣がいつか、哀しみを幸せに変えられる時が、本当にくるんだろうか‥‥」
人は生まれながらに強慾で、肉や草やをもむさぼらなければ生きてはいけず、未来への命脈をつなげられるのは今日に組み伏せた命脈だけ。
「‥‥」
竜良は剣を、片方の手のなかで、抱く。恋人とはちがい温みのないそれでも、こうしていれば竜良の魂を移して、どしどし鼓動をうちはじめる――そんな気がした。



