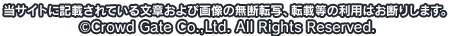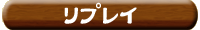 五月の西下
五月の西下
 |
■ショートシナリオ担当:紺一詠 対応レベル:フリーlv 難易度:やや易 成功報酬:0 G 65 C 参加人数:8人 サポート参加人数:2人 冒険期間:05月10日〜05月15日 リプレイ公開日:2006年05月18日 |
|
●オープニング
神聖歴千年仲冬――江戸の大火。八百八町を見舞った受難の仔細については、あちらこちらで反復されたことだ、いまさらぐずぐず細かいところをあげつらう真似はすまい。ここで今一度しかとさせておきたいのは、武蔵国は少なからずの人民をうしなった、その事象である。‥‥べつに日射しを知らぬ国への旅立ちに尽きるばかりではない。人買い、国抜け。江戸から離れざるをえなかった生者の実数は、数千人にのぼるという。
なかで源徳をみかぎった武士の多くは、武勇の腕をもてあましてか、擾乱の色濃い上野国へながれたというが――、
「それが近頃、西へむかう方が増えているのですよ」
「西?」
「上方――京のあたりですね」
「京洛か。なにかあっただろうか」
「さぁて? あたらしい京都守護代がお就きになったそうですが。なかなか施政に熱心な方だというお噂ですし、仕官先の逓増を期待してのことではありませんか?」
ま、それもよかろう、かと。
「江戸でふらふらごろつかれ、挙げ句の果てに悶着起こされるより、そのほうがだんぜんよろしいですけどね」
仕事がないから成らず者に身をやつすのだ。働き口があるならおとなしくそちらにおちついてくれれば、八方丸くおさまり、めでたしめでたし。とんからりん。
けれど、問題は、ある。そりゃあ人が死ぬ、国が亡ぶ、といった由々しき大事にくらべれば、一紙半銭のとるにたらぬ、根無し草のようにくだらない些末事かもしれないけれど。
さて此度の依頼人は、江戸から京への水運にたずさわるもののひとり。
「‥‥船上の風紀がよろしくなくなっておりましてね。血気盛んな方が多いものですから」
念のために弁解してやるなら、彼らとて、乱暴をしよう、台無しにしよう、などと、はじめからもくろんで乗船してきたわけではない。が、気の短い彼ら、ちょっとの行き詰まりが発破の因縁となる。ところどころで仮泊するとはいえ、手狭な閉鎖系での数日の水上生活は、神経をとがらせぎすぎすした関係へおいつめるらしい。
「こんなことが続けば一般の方々は乗船を敬遠されますし、旅程もムダに長引くことが多くなります。どうか、おなじ船にのって、彼らをなだめていただけませんかねぇ?」
むろん船賃はいただきませんから――‥‥、とのお墨付き。
五月。
日毎、緑花の香気ふくらます通り風にさそわれての船旅も、また一興。ま、やることはきちんとやってからだけれども。
●今回の参加者
ea0050 大宗院 透(24歳・♂・神聖騎士・人間・ジャパン)ea0708 藤野 咲月(28歳・♀・忍者・人間・ジャパン)
ea0980 リオーレ・アズィーズ(38歳・♀・ウィザード・人間・ビザンチン帝国)
ea3863 シア・アトリエート(22歳・♀・バード・エルフ・ノルマン王国)
ea3886 レーヴェ・ジェンティアン(21歳・♂・バード・エルフ・ノルマン王国)
ea5419 冴刃 音無(30歳・♂・忍者・人間・ジャパン)
ea6649 片桐 惣助(38歳・♂・忍者・人間・ジャパン)
ea6780 逢莉笛 舞(37歳・♀・忍者・ジャイアント・ジャパン)
●サポート参加者
大神 森之介(ea6194)/ アウレリア・リュジィス(eb0573)●リプレイ本文
●『御影が江戸に向かったから留守を守る必要はねぇ。ちょうどいいからこっちに来い。断じてやっちゃったわけではない。俺は、富士山の根雪よりも、潔白だ』
「‥‥なにをしたんですか、兄さん」
かさり、と、片桐惣助(ea6649)はそれを内懐へしまいこむ。シフール便のつたえたばかりの、わけてもしまいの部分、あたりまえにあべこべにして受け取っていた。
「兄さんに云われたから、帰るわけじゃないんですよ」
誰にともなくつぶやけば、空に環を描く海鳥、こぅ、と了諾するように掛け声ひとつきり落としてゆく。
――大神森之介が、彼の奉公する家格の分家筋の少年が『そうまでして呼ぶのはよっぽどのこと』と云ったから、西へくだるのだ。彼が負けん気な児童をなだめるようにひどく緩やかな目をしていたから、そうするしかないではないか。
こぅ、こぅ、と海鳥らの翼影ふたたび。桟橋にぼつぼつと乗客らが寄り集まるのを、からかうようにさわぎたてては、離れて、また還って、遊んで。あいまあいまに波の戯れ、ざざん、ざざん、と、鼓動そっくりの余韻。
「わー、海。わー、波」
懐手に港湾をやる都市、江戸、に居着いてははや年単位。だから冴刃音無(ea5419)にとってはのたりのたりの海原はなにもめずらしくはないはずだったのだけれども、今からここへ繰り出すのかとおもえば、藤野咲月(ea0708)の腕の柴の仔犬(だったけど、のちに船上で育ったらしい)より尚更きゃらりとさざめいて。だから、咲月は問うてみた、あなたとあなたの御主人様とはどちらが悪戯者でしょうかねぇ、まだまだ世間知らずの柴犬・律はきょとんと咲月を見返すばかり。
「音無様。そんなにしてると、のぼせてしまいませんか?」
「どうしてもすませてすませてしまいたいことがあるんだ」
リオーレ・アズィーズ(ea0980)は船を見上げて、一度はジャパンの西へ行ってみたいと思いお足に悩んでいたところ、渡りに船(あ、ほんとうに船だ)、で、この依頼を受けた。
「リゼロ、どんな旅になるのでしょうか」
むろん快適な旅路への努力は惜しみません、と意中誓えば、それを見晴るかしたか、リゼロ、なかなか貫禄あふるる驢馬――驢馬の貫禄ってどんなものかはさておき――ほっくりほっくり並み足、刻み足。
シア・アトリエート(ea3863)とレーヴェ・ジェンティアン(ea3886)とが同一の依頼になるのは年の瀬以来だ(むしろ双方ともに冒険へでかけるのがしばらくぶりだった、という表し方もある)。
「またお逢いできて光栄です」
「こちらこそ。あのときは対抗戦でしたが、今日ははじめからいっしょになれるようですね」
エルフの二人。シアが、ジャパンで過ごすようになってから身に付いた礼節、枝を折るようにぱきんとした会釈、をしめすと、レーヴェはさしだしかけた右手に換えて真似をする。そうしてふたり、ぎこちなく腰をのばしてから目と目を行き合わせて、うすく、寝待ち月の光のようにうすくほころぶ、吟遊詩人。そろそろジャパンには慣れましたか?
「折角ですから、よい船旅をしたいです‥‥‥‥」
漆黒のロングドレス、西欧風の出で立ちの大宗院透(ea0050)――江戸といったって、東洋人種が洋装をまとえばひとかたならず奇異の目でみられるであろうに、透にはかえってそのほうがおちつくようだ。もっとも雪花から吸い出したような銀の髪、それよりずっと冴えて青い視線、凍えるようなまっしろい皮膚となればしかたのないこと。
――十五歳の「少女」ではなく「少年」、たまにトール・エルな、大宗院透、合いの子であるが由の不思議がもたらした、隠しても隠しきれぬ見目形、風変わりこそが醍醐味なのかもしれぬ、それが証左に、彼女もとい彼の云いのける、
「足袋でゆく耽美な旅、度々‥‥‥‥」
くすりともせず、淡々と、そう。
――ところでこの場合、耽美ってなんだろう。なんだろうってば。
●
『お酒とお菓子だよ。道中で、あ、歩くんじゃなくってお船なんだっけ。船中で食べてね。お土産は京都のおいしいお菓子をよろしくー♪ 三倍返しだよ?』
アウレリア・リュジィスが、がやがやがやと、おおよそ食物の委譲とは思えぬ擬音をうしろに手渡したのを、逢莉笛舞(ea6780)は輪っかにつくった腕で抱え込みながら律義に保護する、巨人族のすらりとのびやかな肢体そびやかして船板をかつかつと歩き回りながら。でも、かすていらって江戸の名物だったか?
――食べるときまで背嚢にしまっておけばよい、と、心付いたのは、おびただしく磯波かさねられたのちである。
船旅は最初こそは景色や船等もの珍しく興奮しますが次第に飽きがきます――そうとりあげたのは惣助だけれども、まさに体現、瓢箪から駒(←まちがい)、医学の教本に症例としてとりあげたくなるくらい、乗船以前とは打って変わってげんなりしだしたのは音無である。首以外をだらんと船板にひろげて、まるで地上の重力にへばった魚類。
自分ってもしかして乗り物に弱かったのかしらん。音無、これでも忍びなのだからそう認めるのはなかなか癪だ。しかし安心していい、たんにはしゃぎすぎたのが所以なだけ。
「音無様、だから申し上げたのです」
「うー、面目ない」
咲月のあてがう濡れ布巾がぐらぐらしたところまで冷ます、どこからもってきたのだかリオーレが扇(種明かしをすれば、透がたまたま持ち込んだ涼風扇。「涼風扇を利用ふるねん‥‥ほんとう「するねん」が順当なのですが‥‥むずかしいです‥‥」意外なところで意外なものがお役立ち)でばたばたあおる、惣助が支度してきた棗茶を少しずつすする。三人と半人前がかりでようやく人心地つく音無、骨身をたしかめつつ、
「‥‥だいぶ楽になったみたい。リオーレさん、俺はもういいよ。あっちの方行ったげたら?」
音無が這々の体で示す方向にはたしかに幼児が父親らしき男性と、あともうひとりとがいて、しかしリオーレは彼女の真性にあまりそぐわぬ、どこか小狡い笑みで提議をかきけす。
云えない。
まさか「この船上きって子どもっぽくはしゃぎそうなのが音無様ですから、ここにいるのです」とは。
べつだん差別も区別もするつもりもないけれど、音無のいう向こうには父親もいて、もうひとりもいて――リオーレに扇を貸し出した透、「烽火ではなく放下(大道芸のこと)です‥‥」などと十八歳以上も未満もおことわりの事項をぽそぽそとつぶやきつつ、火花を踏まえる奇術を見せているからおとなしいものの、音無とその仔犬ときたらそろいもそろって風に吹かれるように危なっかしいから、お隣の紅椿のお姫様、つまり咲月、御行儀のよいほほえみたやさず甲斐甲斐しく世話を焼いているのが、かえって痛々しくみえてくる。
これはちゃんと云ってあげるべきかしら、とも思うけれども――リオーレは教師ですから、教え諭すのが職業ですから、でも見守るだけの有益も知っている。なら、ずっとしまいまで見尽くしますよ、そういう大人の笑みである。
「あちらは音無さんとちがって平気なようですし、そう焦らなくてもいいんじゃないですか。それより鳴り物は?」
惣助がリオーレの本音を気遣い、話をするりと入れ替えてやると、あぁ、と、音無も合点がゆく。
シアとレーヴェ、音が障ってはいけないから、と、張り上げるのをそれまでひかえていたのだ。シアがひゅぅっと刹那、横笛を響かすと、レーヴェ、ぺん、と、おなじく三味線を刹那つまびく、ままごとのように、ささやかな音合わせ。音無、もういいよ、の意で首をうなずかすと、レーヴェ、情動のとぼしい面持ちを、彼のてのひらで組み敷く糸のようにかぼそくふるわせ――‥‥。
先に、弦。
撥ではじくのは能動にあらず、それの欲するところを汲み出すだけのこと。だからあふれるではないか、湧き水のようにこんこんと、星霜しみこみ絶え間なく。高い音は風となった。低い音は汐となった。中程は人と人とを飛び回る鳥となり、ひらひらと羽根が彼等をつなぐ。
シアが横笛に朱唇をそぅっと落とすと、天籟、伎芸天のささやきがふわりと出ずる、が、それははなはだ勿体無いことであるけれど、レーヴェのように永久無垢とはいかないのだ。しかし悲しむことはない、それよりもっとうつくしいものがあとに用意されている。
シアは、口から笛を放すと、
「御覧のように、私たちは異国の出であり、この地の音楽の数を知りません。よろしければ、どなたか私たちに詩吟をおおしえいただけませんか?」
歌うようにさえずるけれど、彼女がほんとうに歌うのはまた異なったおもむきがあるのだろう。謎の尽きぬ子どものようにそれを知りたがる人々で、船頭が注意を発さなければ、あと一歩で船は片側へ反転の憂き目をみていたかもしれぬ。
――それはそれでものすごく困る、舞はあいだをおいたところから様子をみて考える。水難救助の報酬まではギルドから請け負っていないのに。
噂に聞こえる西洋の自動人形がごとく、迷盲のささぬ足取りをいったん止める。金銀、ではなく、右に茶左に碧を、それぞれの瞳に配する彼女、しかし色違いのつがいがとらえるものはそらおそろしいまでに合わさる斉奏。シアとレーヴェはときに嵐の海を、ときに鏡のように凪ぐ海を、無口な饒舌で歌い上げる。アウレリアの酒とつまみをようやく用立てるときが来たようだ。ジャイアントとは思えぬ小ぢんまりした礼儀作法で、ちびりとあおぎ、ちびりと喰む。
教えられた旋律を縦軸に、これまでの技量を横軸に、シアとレーヴェの調和は卵のようにふくらみあがる、じっとしていた音無もこらえがきかなくなったようで、帯しから横笛をもちだし、二人の方向に駆けつけようとする。
「よろしいのですか?」
「ん、完全復活」
「それはたいへんようございました」
たんなる受け答えの一環ではなく、咲月は心底音無にたむけている、どうしてかといえば、
「春花の術でむりやり寝かしつけるような羽目にならなくて」
「‥‥ごめんなさい」
「それで足りなければ、アイスコフィンやストーンもおまけにつけますよー」
とはリオーレ、物騒な提案あくまでも若き二人の導き手に徹するもの。ほほえんで、云った。
●
惣助は少々手持ちぶさたである。植木の携帯までは許されたものの、ひとりがそれをやるととどめがきかなくなるから、ということで、船上での商売は禁じられたのだ。それをめあてに乗っかったわけではないから腹をたてはしなかったが、鉢植の面倒なんぞはそう長々つづけなければならぬものでもなく、残りのものが楽の宴にいそしんでいるとき、仲間にくわわれないのをすまないと思いはしても、胡座をかいてゆっくりと愉しむという心持ちにはなかなかなれなかった。
――案外、貧乏性なのかもしれません。本格的に休めということでしょうかねぇ。
そんなふうに思いたくなるのをいったんとどめて、いや、これは骨休めの旅路ではないのだから、と、我ながら薄ら寒くうそぶいて。
「逢莉笛さん、お茶はいかがでしょう?」
「‥‥では、一杯もらおうか」
舞が惣助に突き付けたのはまだ酒精のいくらか残った杯で、ぷん、と濃い芳醇が下のほうから匂い立つから、惣助はいっしゅん惑ったけれど――これはまちがいだろうか、それとも茶と酒とをいっしょくたにして啄む趣味でもあるのだろうか――舞がぜんぜん身動ぎする気配もさせないので、けっきょくとくとく注ぎ込む。――舞はそういう味音痴ではない。たんじゅんに器を別けるのは贅沢だと思うのだ。
と、
「るせぇっ。やる気か!?」
「上等だ、おもてにでろ!」
――望まれぬ来訪者、いや前からいたけれど。
「はじめから船のうえじゃないですか‥‥」
人間、頭に血がのぼるとまわりどころか自分のことすら分からなくなるものもいたようで、しかたがない人たちですね、と、惣助は首をすくめる。これをどうにかするのが依頼だと割りきってはいたが、忍びが人前で術を、それも主以外のために行使するのは気が重い、くじけそうな指を振るえたたせて合わせようとする矢先――、
舞、
酒気を繰り入れたようにはとてもおもえぬ颯爽した足付き、あいかわらず、で彼等のもとへさっさと近付いたかとおもえば、詫びも断りも一口もはさまず、黒衣に忍ばせた腕を巧みの技で、どこでどう学んできたか、はて、裏表を入れ替える。と、両の男の着物がしどけなく前合わせからはだける。全幅はまばたきのうちにおさまった。
「‥‥私は手品が得意だ」
沁みひとつなく真っ白になったとこへひびいれるのは、ぱん、ぱん、と冷めた喝采。惣助、大ガマの術のために支度した指を、そのまま別の用途にもちかえたのだ。
「お上手ですね、おかげで俺は『手品』をしなくてすみました」
「悪いことをした」
ぼそり、と、顔の筋をどこもゆるめず云いのける舞、真剣とも冗談ともつかなかった。
●
夜分、皆が寝入ったころ。島国ジャパンの水運は陸続きにおこなわれるから、夜通し船をはしらせるということはあまりない。
音無と咲月は、ならんで船板に座している。咲月の京の、伊賀という国の夢語り、しばらくは夢にも忘れそうだった家族のこと、咲月がつらつらとつむぐ――縫い目のようにそれがふととぎれたときである。
――これやるよ、と、音無はとうとうさしだす。昼間はしゃいだ原因の、白くて薄くて硬いもの。
「昼間、俺の笛に合わせて踊ってくれただろ? あ、貝殻なんていまさらすぎた?」
咲月の頬、彼女をつつむ紅よりあざやかな朱をきざむ。
――音無の笛に合わせて、ひらり、ひらり、と蝶をめざして舞った舞踊は、彼にはどんなに写っただろう。蝶であるのが上々だけれど、毛虫のごろごろでもいい、音無の気に入りを邪魔さえしなければそれでいい。
きっとこの場にリオーレいれば、めっとしかりつけたことだろう。むろん音無は蝶だと思っている――それをすなおに返す遣り様を心得ていないだけで。
「‥‥いいえ」
天からの授かり物のように、貝殻よりもやわやわした手のひらとてのひらのあいだに、咲月はそれをおしいだく。
明日は、なにがあるのだろう。
どんな音楽が、耳朶をくすぐってくれるだろう。どんな舞踏が、視野をあざむいてくれるだろう。
起床時とさほど寝入りのなかでレーヴェは今日の音を思い返し、シアは明日に約束した文化の祭典をまどろみにえがく。弦と笛のつながりは、どんな約定よりもたしかにあいだを結んでいる。
「あなたがたに旅の”才覚”があれば、他の”西下”と”差異化”できます‥‥」
実はちゃっかり二人のずっと後方から盗み見みたりする透、なんかもいたりして。
その日残念なことに星は流れなかったけれど、いつまでも流れぬものこそたくさんあって、ここに、隣にいてくれる、唯一かつ許多のものが、音無の言葉になおせぬ希望をかなえてくれるような――そんな気がした。