 乙女の特権〜宵闇のお楽しみ
乙女の特権〜宵闇のお楽しみ
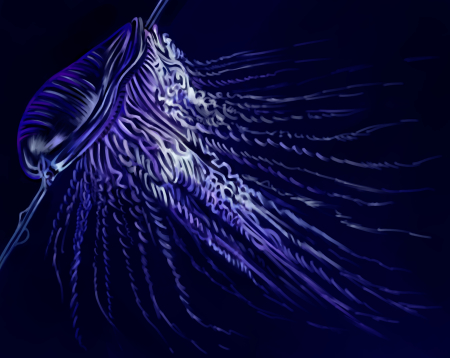 |
■ショートシナリオ担当:マレーア4 対応レベル:8〜14lv 難易度:やや易 成功報酬:2 G 49 C 参加人数:5人 サポート参加人数:3人 冒険期間:08月03日〜08月06日 リプレイ公開日:2006年08月07日 |
|
●オープニング
だいぶ日差しもゆるみ、吹く風にも涼しさが増した頃。珍しく自宅でシェスティンと二人きりでお茶を楽しんでいたハイデマリーが、ふと訪ねた。
「今年の避暑はいつものところへ?」
「ええ。でもその前にやりたいことがあるの」
いたずらっ子のようなシェスティンの瞳は、傾いた太陽の光を反射し、琥珀色に輝いている。
そんな表情にハイデマリーも何かを察したのか、飲みかけのカップを置いて口元に楽しそうな笑みを淡く作った。
「やはりせっかくの夏ですもの‥‥見たいわよね」
「うん‥‥見たいね」
セリフの後には見えない音符がある。
「夏と言えば怖い話よね。別にそれがメインじゃなくて、そこから生まれるロマンスの果てにあれやこれやで可愛いウサギちゃんがグルになったオオカミさんをすっかり味方と思い込んで、ピンチなのに甘えて頼りきったりして」
「ちょ、ちょっとちょっと。暴走しないでー」
あさっての方をキラキラした目で見つめてブツブツ言い出したシェスティンを、ハイデマリーは慌てて止めた。何を言っているのかまるでわからない。
制止の声に我に返ったシェスティンは、ごまかすように小さく咳払いをすると簡単に考えを話した。
「えーとね、今回は同じ学校の一年生と三年生で肝試しっていうのが見たいのよ。実は三年生はその一年生に片思いなんだけど、彼の友人が肝試しをネタに協力するってかんじで」
「あ、それでウサギちゃんとグルのオオカミさんなのね」
「そうそう。何も知らない怖がりなウサギちゃんは仕組まれてるとも知らずにすっかり先輩を頼りにしてるの」
「肝試しってからには当然真っ暗よね。そう‥‥暗闇で‥‥」
シェスティンとは逆に、静かに妄想に浸るハイデマリー。
額を突付いて呼び戻し、シェスティンはまとめにかかる。
「それじゃ、いつも通り舞台と招待状は私のところで用意するわね。当日に会いましょう」
そう約束をして、シェスティンは帰っていった。
●今回の参加者
ea3486 オラース・カノーヴァ(31歳・♂・鎧騎士・人間・ノルマン王国)eb2554 セラフィマ・レオーノフ(23歳・♀・ナイト・ハーフエルフ・ロシア王国)
eb4096 山下 博士(19歳・♂・天界人・人間・天界(地球))
eb4249 ルーフォン・エンフィールド(20歳・♂・天界人・人間・天界(地球))
eb4844 毛利 鷹嗣(45歳・♂・僧侶・人間・ジャパン)
●サポート参加者
エルマ・リジア(ea9311)/ ニノン・フリューヴ(eb0508)/ アルフォンス・ニカイドウ(eb0746)●リプレイ本文
●セッティングセラフィマ・レオーノフ(eb2554)に会場内に案内された貴族令嬢達は、その会場演出にざわめいた。特に何度も見に来ている者はいつもとの違いに今回は何があるのかと目を輝かす。
会場である屋敷の一室を提供したシェスティンは、薄暗い室内を見回した。
テーマに肝試しを出したため、窓にはカーテンの他に暗幕もかけられている。そのため会場内には蝋燭が灯されていた。しかし、それもかろうじて相手の顔が判別できる程度だ。
舞台には石膏の彫像が並べられ、天井近くには丸く穴をあけたもので囲ったランタンが吊るされていた。その側には釣竿のようなものに引っ掛けられた布もある。
それらを見てシェスティンは一人納得していた。
セラフィマに暗幕や彫像はないかと尋ねられた時は首を傾げたものだったが、こうして見るとなるほどなと思う。それ以外に貸した数本の鋸も、きっと何かに使うのだろう。朗読劇に協力を頼んだお抱えの楽士と鋸で何をするつもりなのかは疑問だが。
そんなことを考えているうちに、セラフィマによる開演の挨拶が始まり、シェスティンは舞台に集中した。
●罠にかかったウサギ
夜の学舎内。マルセルは蝋燭を掲げながら暗い廊下を一人歩いていた。昼でも厳格な雰囲気の学舎内は、夜にはいっそう重く締め付けるような空気を漂わせている。
暑いのに、寒い。
マルセルはそんな不思議な感覚を覚えながらも、満足そうな笑みを浮かべていた。
「よしよし。これなら物音の一つでも立てれば、あの一年ならイチコロだな。そうすればアイツも自然といい感じに振舞えるだろう。フ、ちょろいな」
などと呟きながら向かうは学舎内に入るために開けた窓。あらかじめ昼間のうちに開けておいたのだ。
マルセルの脳裏には、近い将来に起こることがはっきりと描かれている。その未来を掴むためなら、下準備などたやすいものだ。
全ては、大切な親友のため。
「でもまぁ、最終的には肝心なことはちゃんと口で言わないとならないんだけどな。そこんとこ、わかってんのかなウルは」
窓を乗り越える時、どこか遠くで物音を聞いたような気がして耳をすませたマルセルだったが、しばらくしても何もないのですぐに学舎を後にした。
翌日、マルセルと親友のウルヴァリン、一年生のバーニィで他愛のない話をしていると、タカがやって来て妙に深刻な顔でマルセルに耳打ちした。タカはマルセルとウルの親友でもある。
「ちょっと前の話なんだが、会場の近くで亡くなった卒業生の亡霊を見たんだ。気のせいと思って言わなかったんだけど、さっき、それっぽい噂を聞いてな‥‥」
と、そこにウルが不思議そうな顔で何の話かと加わってきた。
マルセルとタカは一瞬躊躇した。その亡霊とウルは縁があるからだ。余計な噂話など聞かせて、悲しませてしまうのではないかと。
しかし、結局「言わないと離さない」とがっしりと腕を掴まれてしまったので、しぶしぶながらタカは自分が見たものと噂話を話して聞かせた。
心配そうに三人に見守られていたウルが発したのは、意外にも明るい言葉だった。
「あの人、戦地に赴いたっきり帰ってこないんだよな。その人が幽霊になって帰ってきたって言うんだ? バーニィ、見に行こうぜ」
突然の物騒な誘いにバーニィはヒクリと頬を引きつらせた。
そんな後輩の様子に、ウルは意地悪そうな笑みで顔を覗き込む。
「それとも‥‥怖いのかな?」
バーニィは、ぐっと唇を噛み締めた。
●気になる? 先輩の憧れの人
暗く静まり返った学舎内。ウルヴァリンとバーニィは幽霊が出ると噂の石膏彫像の並ぶ広い教室へ侵入していた。
足元を照らす程度の頼りない明かりのみでは、彫像たちはたとえ幽霊がいなくとも何やら薄ら寒い。そしてこんな時に限って月精霊の輝きは雲に隠されている。
バーニィは引きつり気味の表情でウルの後ろをついていく。本当はウルの服の裾でも掴んでいたいところだが、またあの意地悪な笑顔でからかわれると思い、自分の服の裾を握り締めることで不安を押し殺した。
一方ウルはというと。
バーニィとは逆にどこか楽しげで、神経が太いのか鈍いのかといったところだ。後ろでビクビクしている後輩に気付いているのかいないのか、足取りも軽く先を行く。
「ところでねぇ、先輩」
バーニィはついに耐えられずに声をかけた。
立ち止まらずにウルは不気味な陰影を落とす彫像を一つ一つ見ていく。
「どうした?」
「僕、さっきからなんだか寒いんですけど?」
「風邪か? 大事にしろよ。夏風は性質が悪いらしいからな。辛いなら座ってるか?」
「いえ、そういう寒さではなく‥‥その、なんか、時々小さな物音がしませんか?」
「さあ。聞こえないけど」
話している間にも、ウルは彫像を軽く叩いたりしながら幽霊が出ないか調べている。
「先輩、ちょっと待ってください。本当にここ、何かやばいですって。さっきから首のあたりがざわざわして‥‥」
「何だよ、やっぱり風邪じゃねぇの?」
振り向いたウルはバーニィの額に手を伸ばす。
その手がバーニィに触れた瞬間、彼はこぼそうなほどに大きく目を見開いた。
尋常でないその様子にウルは眉をひそめる。
急に呼吸が荒くなったバーニィは震える指でウルを指す。
「何?」
「せっ、せ、せせせせせせせ」
「新種の早口言葉? 確かに、『せ』は言いにくい‥‥」
「先輩、後ろーっ!」
学舎中に響くような大声で叫んだかと思うと、バーニィは何を思ったかウルに体当たりをして突き飛ばした。
不意をつかれたウルは壁に激突し、一瞬息が詰まる。
「大丈夫ですか、先輩っ」
慌てて駆け寄るバーニィ。
「お前なぁ‥‥」
「いや、その、だって‥‥」
ちらちらとある方向に怯えた視線を送るバーニィ。
ウルもその方向を見やると、後輩がこうまで恐怖する原因をやっと確認することができたのだった。
「あはは‥‥せ、先輩。あれ、ナンデスカ」
彫像から生えるようにしてこちらを見ている『見てはいけないもの』に、バーニィのセリフは棒読みになっていた。
しかしその現実にありえないものは、何とも美しいものだった。生前そのままに。
ウルはとても懐かしそうに顔を歪める。
「先輩、本当に先輩なのか‥‥」
かすれるように呟かれた言葉に、バーニィは驚きの目でウルを見た。昼間、タカが言っていたことを思い出す。
男性にしては柔らかな顔立ちの幽霊は、ウルに向けて妖しく微笑み、招くように手を差し伸べた。
「俺の唇の感触、忘れたのか?」
「え? 唇‥‥!?」
どういうことか、とバーニィはウルと霊を交互に見やった。
「ずっと、待っていた。卒業後、俺はずいぶん遠くへ行ったけど、おまえを忘れたことは一日もなかった。‥‥おまえは?」
「カミーユ‥‥先輩」
幽霊をそう呼んだウルの顔は、バーニィが見たこともないような哀しさに満ちていた。はるか遠くのものを想うような目。
カミーユと呼ばれた霊はホッとしたように目元を和らげる。
「良かった。俺の独りよがりかと思い始めていた。自惚れてもいいかな。‥‥来いよ」
カミーユがさらに手を伸ばせば、ウルはふらりと立ち上がりその手を掴もうとする。
なすすべもなく見ていたバーニィだったが、二人の手が触れ合おうとした瞬間、何とも言えないものが胸中に沸き起こった。
●気付いたら、すがっていた
気がつけば、バーニィはウルの名を叫んでいた。
しかしウルには届いていないのか、今はもうこの世のものではないカミーユの手を取り、切ない瞳を向けている。
「ウルヴァリン先輩!」
体中からその名を呼ぶと、ようやくその名の持ち主がゆっくりと振り向いた。彼の瞳は必死に自分を留めようとする後輩を捉えるが、それはどこか儚く遠い。
「先輩‥‥行かな」
「さよなら、バーニィ」
呼びかけを遮り、一方的に告げられた別れにバーニィの頭は真っ白になった。
その後、何があったのか、バーニィの記憶はひどくぼんやりとしている。何となく覚えているのは、滅茶苦茶に叫びながらカミーユが憑いていた彫像を持ち上げて投げ捨てたことだけ。その彫像はとてもバーニィの力で持ち上がるようなものではなかったが‥‥想いの力というものだろうか。
彫像が破壊された瞬間、カミーユの亡霊は消えた。
ウルは砕けた彫像を放心したように眺め、その場に座り込んでいる。
荒い呼吸をおさめ、バーニィはおそるおそるウルに近づいた。
「‥‥先輩、怪我は?」
ウルは首を振る。
「僕、余計なことしちゃいましたか?」
拒絶の言葉が怖くて、バーニィはあと一歩、ウルに近づけない。あと一歩近づけば手は届くのに。
ウルはわずかに目線を下げた。
バーニィは次の言葉を覚悟したが、言われたのは全く違う言葉だった。
「本当は怖かった。先輩がじゃない。バーニィ、お前より先輩を選んでしまいそうな自分が怖かった」
カミーユはウルより二つ上の先輩だった。見目麗しく文武両道に秀で、学校でも特別な存在だった。自然、皆が憧れる。ウルにとっては決して手の届かない高嶺の花。
しかしある日、ウルはその先輩に呼び出され、夜の学舎へ。
緊張と抑えきれない胸の高鳴りを抱え、待っていると現れたカミーユに唇を奪われてしまった。何があってそういうことになったのかは、すっかり舞い上がっていたため会話の内容など覚えていない。甘い口付けと熱い吐息だけが鮮明に残っている。
実際のところ、カミーユのその行動が単なる気まぐれだったのか、それとも本気でウルに思いを寄せていたのかはわからない。
けれど、ウルの心の奥深くに、切なくしびれるような思い出として刻まれたのは確かだった。
「臆病だった俺は、結局先輩の気持ちを確かめることはできなくて‥‥そうしたら、あの人は亡くなっていて。だからあの時、亡霊とわかっていても、先輩に会えて‥‥」
「もう、いいですよ」
今にも崩れてしまいそうなウルを、バーニィはごく自然に抱き寄せていた。
いつも意地悪ばかりされているのに、こんなふうに弱った姿を見て慰めようとする自分は、底抜けのお人好しだろうかと苦笑するバーニィ。
ウルはバーニィに抱き寄せられるままになっている。
「先輩は、もういないのに。亡霊にすがったところで待っているのは破滅で‥‥先輩は、あの彫像のように冷たそうで‥‥。お前は、あたたかいな」
最後の一言にバーニィはついに堪えきれなくなり、ウルの首に顔をうずめるようにして泣いた。
「良かった、先輩が無事で本当に良かった‥‥!」
「バーニィ、抱きしめていいか? お前のぬくもりを分けてくれ。せめて、暁が虹色に空を染め上げるまで‥‥嫌だと言っても離さない」
苦しくなるほどにお互いを求め合う二人の周囲の空気が、風もないのにかすかに震える。
ウルの体の下、意識が飛ぶ寸前にバーニィはひどく穏やかな声を聞いた。
「幸せになれよ」
ぼんやりとした目で声の主を追ったバーニィは、白く淡い光に包まれてカミーユが優しく微笑んでいるのを見たような気がした。
●終劇後
割れんばかりの拍手の中、朗読劇は幕を下ろした。
そして恒例の観客・役者そろってのお茶会が始まる。当然、そこで役者達の紹介も始まる。
舞台の向こうから現れた五人の冒険者達。そのうち二人だけは何故か疲れ果てていて仲間に肩を貸してもらっていた。舞台裏で何をしていたのだろうか。
全てを知っているセラフィマは苦笑しながら彼らを紹介していった。
「改めまして、本日はお暑い中お越し下さいましてありがとうございます。せっかくですので、役者を紹介いたしますね」
貴族令嬢達から再び盛大な拍手が巻き起こる。
「はじめまして。カミーユを演じた毛利 鷹嗣だ。お楽しみいただけたのなら幸いだ」
熱い視線を受けながらも落ち着き払っている毛利鷹嗣(eb4844)。さすが大人の余裕と言うべきか。
続いてオラース・カノーヴァ(ea3486)が自己紹介をする。
「マルセルを演じたオラースだ。今日は来てくれてありがとう」
どことなく素っ気ない口調だが、いまだ劇の余韻がある令嬢達は、献身的なマルセルとオラースを半ば混同しているので全く気にしていない。
次にルーフォン・エンフィールド(eb4249)が挨拶をする。
彼を見たとたん、令嬢達から驚きと感嘆の声がもれた。劇中からウルは十七、八を想像していた彼女達だったが、演じていたルーフォンは聞けば十一歳だと言う。見事な演技力だった。
最後に山下博士(eb4096)がにっこりと微笑んで挨拶をする。彼もまたルーフォンと同じくらいの年齢だ。
「あの、お二人はどうしてそんなに疲れ果てているの?」
シェスティンが不思議そうに首を傾げる。
「あ、あははは‥‥」
雰囲気出すためにヒンズースクワットをしたところ、ルーフォンも対抗意識を燃やして腹筋に励み、お互いやりすぎた、とは言えず博士は笑ってごまかそうとした。
その様子にさらに不思議顔になるシェスティンに困った博士に、オラースが助け舟を出す。
「まあまあ、それは企業秘密ってやつ。迫真の演技だったろ?」
そう言われてしまえばこれ以上追求はできない。
「では、鋸は何に使ったの?」
「カミーユ登場シーンの何とも言えない音に使った」
「なるほど‥‥」
シェスティンは感心したように頷くと、彼らに飲み物を勧めた。
地の文を担当していたセラフィマは特に喉が渇いているだろう。
一息ついたセラフィマは、にこやかに営業スマイルを作ると、今回の劇を小説化したものを令嬢達にくれると言う。思ってもいない贈り物にシェスティン達は喜んだ。これでいつでも今日の朗読劇の雰囲気に浸れるというわけだ。
「ところで‥‥」
思い出したように舞台を見てハイデマリーが言った。
「あの彫像だけ向きが変わっているんだけど、誰か動かした?」
彼女が示す方を見れば、窓に背を向けて並べられていたはずの彫像の一つだけが、窓の方を向いていた。何度も確認したし、こんなつまらないミスをする者などいない。さらに誰も触れていない。
その場の者達は、何とも言えない表情で視線を交し合った後、いっせいに扉へ殺到したのだった。



