 【乱の影】彼の名は、高杉晋作
【乱の影】彼の名は、高杉晋作
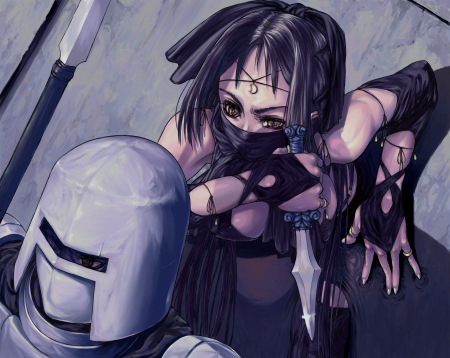 |
■ショートシナリオ担当:御言雪乃 対応レベル:6〜10lv 難易度:やや難 成功報酬:3 G 9 C 参加人数:7人 サポート参加人数:6人 冒険期間:10月27日〜11月01日 リプレイ公開日:2006年11月07日 |
|
●オープニング
血に濡れた責め棒を放り出すと、新撰組副長・土方歳三は蔵から足を踏み出した。「どうでした?」
「だめだ。うんともすんとも‥‥口を割るどころじゃねえ」
こたえると、土方は問いかけた男にちらりと眼を遣った。
男は昼間から酔っ払っているのか、一升徳利をあおっている。しかし不思議にその眼に酔いの色はなく――
新撰組十一番隊組長・平手造酒である。
「で、どうします?」
「どうしようもねえだろう。何も吐かねえんじゃあな」
土方が苦々しげに吐き捨てた。すると平手は彼らしくもなく暗鬱な眼で、
「鬼の副長の責めにも吐かねえとすると‥‥斬りますか?」
「それしかねえなあ。このまま放っておくと他の隊士の手前、示しがつかねえからな」
「そうですか‥‥。斬りますか‥‥」
つぶやくと、平手は再び徳利を口に運んだ。溢れた酒が彼の喉元を濡らした。
杯を卓におくと、若者はよく光る眼をあげた。
「それは確かか?」
若者が問うと、男は小さく頷いた。
「確かに。土方と平手が話し合っていたので間違いはありません」
「ほお」
ニンガリ笑うと、若者は杯をとりあげた。そして揺れる酒をじっと見つめつつ、
「新撰組組長代理を処刑するとはなぁ‥‥」
呟いた。薄闇の中に、ただ若者の刃の光をやどしたかのような眼ばかりが煌いて――
我知らず、男は身の総毛立つのを覚えた。眼前の若者が眼を光らせて黙した時、恐るべき知略がその脳髄の奥で渦巻いていることを男はよく承知しているからだ。
そして幾許か。
やがて若者は酒を飲み干した。
「面白いことを思いついた」
云って若者はニッと子供のような笑みを浮かべた。
やはり、と思いつつ男は若者の顔を見返す。若者の貌は長く、異相というもので――彼の名は高杉晋作といった。
「‥‥殿。大蛇丸殿」
呼ばれ、総髪の浪人ががばと身を起こした。
彼の名は大蛇丸。賞金稼ぎである三蛇の生き残りの一人である。
「誰だ?」
半身をたてた時、すでにその手は枕元の刀を引っ掴み、彼の全身は戦闘態勢に滑り込んでいる。
「そこか?」
さらに問うと、大蛇丸は闇を透かし見た。
夜に沈む竹林の間に朧な影がひとつ。気配はない。
「誰だ、きさま」
問いつつ、しかしすぐに大蛇丸は驚愕にかっと眼を見開いた。雲間から覗いた月の光に青く浮かび上がった顔は見覚えのあるものだからだ。
「きさま、確か新撰組の‥‥」
「神代紅緒です。もはや新撰組ではありませんが」
「なにっ?」
戸惑は一瞬、刹那の判断で大蛇丸を刀の鯉口を切った。
大蛇丸は過去、蛇童と蛇眼坊とともに新撰組十一番隊隊士を襲っている。何人かを傷つけ、代わりに彼は二人の仲間を失ったのであった。
「俺を斬りにきたか?」
「いえ」
薄く嗤うと、紅緒は頭を振った。
「先ほども云ったように、私はもはや新撰組ではありません。ですから貴方を斬る理由も、そのつもりもありませんよ」
「ならば、何故ここに来た?」
「面白いことを教えに」
「面白いこと?」
大蛇丸は眉根をよせた。
「何だ、それは?」
「新撰組組長代理が処刑されます」
「なに?」
一瞬大蛇丸の眼がぎらりと光った。が、それのみで――
「それがどうした? 新撰組の組長代理が処刑されようと、俺の知ったことではない」
「それが十一番隊の組長代理でも、ですか?」
「うっ」
今度こそ大蛇丸は息をひいた。それを見透かしたかのように紅緒はすうと朱唇をつりあげ、
「もうお分かりでしょう。組長代理が処刑されるとなれば十一番隊が出て来るかも知れません。それに、これはここだけの話ですが、組長代理の身を奪おうとする動きもあり――」
「な‥‥それは本当か。どこのどいつが、それを企んで」
「そこまでは貴方が知る必要はありません」
紅緒が云った。その時になってようやく気づいたが、紅緒の姿が遠くなりつつあるようである。そして声も遠く――
「その騒動にからんで貴方がどうするかはお任せします。仲間の敵をとるもよし」
「ま、待て」
大蛇丸は声をあげた。しかし紅緒の姿はすでになく――
ややあって大蛇丸は刀を腰に落とした。あげた彼の満面には毒蛇のような笑みがにぃと浮いていた。
●今回の参加者
ea1636 大神 総一郎(36歳・♂・侍・人間・ジャパン)ea4236 神楽 龍影(30歳・♂・志士・人間・ジャパン)
ea6201 観空 小夜(43歳・♀・僧侶・人間・ジャパン)
eb1624 朱鳳 陽平(30歳・♂・侍・人間・ジャパン)
eb2408 眞薙 京一朗(38歳・♂・侍・人間・ジャパン)
eb2919 所所楽 柊(27歳・♀・侍・人間・ジャパン)
eb3834 和泉 みなも(40歳・♀・志士・パラ・ジャパン)
●サポート参加者
リュミエール・ヴィラ(ea3115)/ ゴールド・ストーム(ea3785)/ 堀田 左之介(ea5973)/ 月風 影一(ea8628)/ 橘 一刀(eb1065)/ 片桐 弥助(eb1516)●リプレイ本文
「そう。処刑されてしまうの‥‥」慨嘆したのは背筋に刃のつらぬきとおったかのような凛とした女性である。
観空小夜(ea6201)。そして、彼女の前に片膝ついているのは江戸から呼び寄せたパラの少年忍者、月風影一である。
「新撰組隊士の言にも耳を傾けたから、間違いはないかと」
影一の声にもやや翳りの響き。
一時は仲間として戦ったことのある新撰組隊士。いかような理由があれ、処刑の憂き目にあうのが喜ばしいはずがない。
が、今はそれどころではなく。
「でも、それだけではなく、伊集院静香をめぐって何やら不穏な動きがあるようなんです」
「不穏な?」
「どのようなものかは、まだわからないんだけど」
「そう」
頷くと、小夜は沈思した。そして幾許か。
やがて、すらりと小夜は立ち上がった。
「長様、どこへ」
問う影一に、小夜はいつになく厳しい面をむけた。
「新撰組屯所へ。平手殿に会います」
●
その日は、もう神無月も過ぎようとしているのに妙に暑く、照りつける日差しは白々としていた。
その日の下、屯所を訪れた影は七つ。ともに玄関から平手の居室にむかい、しばらくして、うち二影は屯所中庭から蔵へ、また一影はさらなる奥へと向かった。
「おい」
呼んだ。
「‥‥」
「おいってば、よ」
再び、呼んだ。が、呼ばれた方の勝気そうな若者はそっぽをむいたままである。
呼んだのは十一番隊組長・平手造酒であり、呼ばれたのは元十一番隊隊士・朱鳳陽平(eb1624)であった。
「陽平、何拗ねてやがんだ」
「‥‥別に拗ねてなんかいねえよ」
「拗ねてんじゃねえか」
「拗ねてんじゃねえ。俺ァ、怒ってるんだ」
平手を見据え、陽平が怒鳴った。
「何で俺達にまで生きてたことを黙ってたんでぇ。ホントのことを話してくれてたら俺達も苦労せずにすんだし、紅緒も逃さずにすんだかも知れねえんだぜ」
「うんうん」
腕を組んで頷いて見せたのは、これは散る花をまとったかのような芸妓姿に身をやつした所所楽柊(eb2919)である。
「まあ、陽平サンが怒っても仕方ないよなぁ〜」
「そういうなよ、柊」
顔を顰めて、平手は頭をがりがりと掻いた。
「敵を騙すには、まず味方からって云うだろ。それに陽平にもらしたらどうなると思う。こいつ、すぐ顔に出ちまうからな。目論見なんぞばればれになっちまう。だから仕方なくだな‥‥」
「うんうん」
柊がまたもや頷いた。
「それもしょうがないなぁ〜」
「所所楽、おめえ、どっちの味方だ」
「俺はどっちの味方でもない。‥‥それより、組長に聞きたいことがある」
「何だ」
「俺らの処遇だ〜」
「処遇、だと?」
平手の眼がわずかに見開かれた。
「ああ。入隊も追放も、腕を磨くきっかけの意味では悪い事じゃなかった。この半年強、死なねぇためにがむしゃらにやってきたしな〜。だが今の宙ぶらりんな立場じゃ使い所が無ぇ。組長、俺はあんたのやり方が気に入って、ここに来てたんだ。‥‥また組長が居るなら戻りたいと思ってな〜」
「戻りたい、か」
「そうだ。勘ぐり過ぎで唐突で、更には無鉄砲な自覚はあるが‥‥組長なら、こんな俺を使えるだろ〜?」
くくっと。柊の紅をはいた朱唇から忍び笑いがもれた。見返す平手の口辺にも片えくぼが彫られている。
「確かに、おめえのようなド外れた野郎を使えるような奴はめったにいねえよな。ってか、おめえらを除隊させたのは静香が勝手にやったことで、俺が認めたことじゃねえ。戻りてえんなら、いつでも戻ってきな。端から十一番隊なんていう厄介な組にはおめえらしかねえと思って引き入れたんだ」
「ところで」
と、平手と二人の元隊士の会話に口を挟んだのは、和泉みなも(eb3834)であった。その落ち着いた語調に、平手も表情をあらためる。
一見、女童としか見えないみなもの態度は堂々たるもので。それもそのはず、氷の志士たるみなもは御歳三十一歳。平手よりも年上なのである。
「自分からもお尋ねしたいことが」
「何だ」
「伊集院静香と神代紅緒のことです。どのような経緯があり、新撰組に入ったのか」
「経緯か‥‥。入隊時の事は、俺も実は良く知らねえんだ。試験を受けて入隊したのは確かなんだがな。おめえら知っている通り、奴らは手練れだ。入隊はすぐに認められたらしい。が‥‥」
「が?」
みなもが眼を眇めた。
「何かあったのですか」
「ああ。土方さんが紅緒と怪しいと睨んだ。いや、これは何も根拠のあることではなく、土方さんの勘のようなものであったらしい」
「では、どうしてすぐに除隊させなかったのですか」
「一度入隊させた者を、勘だけで除隊させられるもんかよ。で、土方さんは処遇に困った。そんな時だ、十一番隊設立の話が持ち上がった。で、土方さんは面倒な紅緒を俺におしつけたってわけだ」
「なるほど‥‥」
みなもが小さく息をついた。
正体のわからぬ者は野に放すより、手近において眼を光らせる方が手っ取り早いと土方は考えたのであろう。それも一理ある。が、それなら静香の方はどうなのだろう。
「静香の方は寝耳に水だ。直前まで、さすがの俺も気がつなかった。怪しいとは睨んでたんだが、証をつかめねえうちに、これさ――」
云って、平手が腹を刃で刺す真似をしてみせた。
「それだけですか?」
「それだけ、とは?」
「いえ‥‥二人の伍長といい、此度伍長となられた蘭子殿といい、十一番隊は女性の抜擢の多い隊だと思いまして。‥‥まさか平手殿の趣味だったりしませんよね?」
「な、何をいう‥‥」
平手、妙にどぎまぎ。
――こいつは、怪しい。みなもに睨みつけられ、さらに平手は表情を強張らせた。
その平手の窮地を救ったのは、他ならぬ小夜である。
あの、と彼女が口を開けば、何だとばかりに平手が飛びついた。
「観空小夜‥‥おめえさんとは初めて会うよなあ」
「はい」
ふわりと肯首した。
とはいえ、小夜と十一番隊は浅からぬ因縁がある。影一を通じ、小夜は十一番隊の顛末にほとんどの場合、影のようにかかわっていたのであった。
「此度は伊集院静香殿が処罰をうけられるとの事。僧侶の私としましては知らぬ間柄ではなし。せめて、その場に立ち合わせていただきたく」
「おめえさんを、か?」
「はい。いかな罪業であれ逝ってしまえば皆仏‥‥弔わさせて下さい」
「いいだろう。どのみち誰かが弔わなくちゃならねえんだ。奴も一時は新撰組。冒険者に弔ってもらえば本望だろうぜ」
云って、平手は眼をあげた。
けぶるようなその眼に映るのは、はたしてどんな景色か。黙したまま、ただ平手は徳利を口に運んだ。
●
刃のような土方の視線の先、しかし大神総一郎(ea1636)は威風堂々としていた。
平手の口利きで土方との面会の機会を得て、すでに幾許か。土方がわずかに身動ぎした。
「それを、どこで聞いた?」
土方が問う。総一郎はわずかに顎を上げ、
「片桐弥助というものから」
「片桐弥助?」
「我が一族の者です」
「ほお」
土方の眼が底光りした。
「それが真実と思っているのか?」
「疑う理由はない。京の現在は張り詰めた糸の如し。新撰組に薩摩が手を伸ばし失敗した‥となれば薩摩と並ぶ動きのある長州が黙っているか。そう思い、弥助に調べさせたところ、高杉晋作なる者に何やら不穏の動きあり」
「なに、高杉!?」
さすがの土方の冷厳な面にも動揺の色が過ぎった。
「それをどうやって‥‥」
「というところをみると、新撰組でも、その事実は掴んでいるようだな」
「ああ‥‥」
首肯くと、土方は吐息をついた。
「どうやら隠してもむだなようだから教えるがな、どうやら伊集院静香を処刑前に奪おうとする動きがある」
「やはり‥‥で、首謀者は誰だ? 高杉か?」
「おそらく、な。証拠は何もねえから、今のうちに高杉をどうこうするわけにはいかねえが」
「そうか‥‥」
総一郎は眼を伏せた。
襲撃の際、おそらくは高杉が出てくるであろうと彼は踏んでいたのだが、この分ではそれはなさそうである。高杉は今、新撰組の監視の内だ。その中で虎の口に手を突っ込むような迂闊な真似をするはずがない。
「よくわかった。では、私は私のことをするとしよう」
告げると、流れるような挙措で総一郎は立ち上がった。
●
蔵の柱からのびた枷に、女はとらわれていた。
伊集院静香。元十一番隊組長代理である。
「伊集院殿」
声に。静香は俯かせていた顔をのろのろとあげた。
汗と血に汚れ――それでも静香は美しかった。
「だ‥‥誰だ?」
静香の眼は、逆光の中、蔵の入り口に立つ二つの影を見とめている。
「お忘れでございますか」
云って、影の一つが足を踏み出した。そのためか影の顔が顕わになり――影は鬼の貌をした面頬をつけている。
「神楽龍影(ea4236)、か」
「はい」
影――龍影が肯いた。
「うぬが‥‥どうしてこのようなところに」
「伊集院殿が処罰されると聞き、平手殿のお許しを得て参りました」
「物好きな」
静香の面に乾いた笑みが浮いた。
「で、私に何の用だ?」
「特に用というものはございませんが」
面頬をずらし、すいと龍影は静香に顔を近づけ――突然、静香の唇に、己のそれを重ねた。
薄暗い静寂の中、ただ舌のからまるようなくぐもった音が響き――
やがて龍影の唇が離れ、光の糸が煌き、切れた。
「何の真似だ」
「ご安心ください」
龍影が静香の耳に口を寄せた。
「今のは熊の肝です。それより信じる信じぬはお任せ致しますが‥‥私は今、薩摩に協力しております」
「なにィ」
「お静かに‥‥それより、是非にお聞きしたいことが」
「‥‥」
ちらり。沈黙のまま、静香の眼が動いた。それを察し、龍影が続ける。
「紅緒殿が間者であった事はご存知でしたか?」
「聞いた。が、私は知らぬことではあったがな」
「では薩摩のことを‥‥。薩摩は神皇家の御為に働いていると申されておりました。もし‥‥もし静香殿もまた神皇家の御為に此度の事を働いたと申されるのなら――」
「助けると、というか」
「‥‥」
龍影は語らない。
本当のところ、彼は助けられるものなら助けたいと思っていた。が、新撰組、さらには冒険者の監視の下にあってはさすがにそれはかなうまい。
「せめて託けなどあれば、お聞き致します」
「ありがたいが、今更――」
「本当にそうか」
声が――
ともに、もう一つの影が前に進み出た。それにつれて、その影の顔もまた視界の内となり――静香の眼がわずかに見開かれた。
「うぬは――眞薙京一朗(eb2408)!」
「静香殿、お久しぶりです」
云って、京一朗がニンガリと笑った。
「俺が京に在る時は必ず静香殿が無茶を為さる‥妙な縁ですな」
「まさに」
静香もまた笑う。
以前、伊集院静香はたった一人で豺牙組なる山賊集団に斬りこんだことがある。その折、静香を救った冒険者の中に京一朗の姿があった。その時も似合わぬ無謀の主と嘆じたものだが、またもや――
「それよりも、本当にとは、どういうことか?」
「そのことですが」
京一朗の黒曜石に似た瞳がじっと静香を見下ろした。
「亡霊を残す気はありませんか?」
「亡霊?」
「そう。亡霊です」
「亡霊、なぁ」
静香がニヤリとした。
「やはり京一朗、うぬは面白い。あの平手が是非にと望んだだけのことはある」
「それはありがたいお言葉ですが‥‥で、亡霊を残されるおつもりは」
「らん」
静香が云った。
「ら‥‥ん、ですか」
「‥‥」
もはや静香はこたえない。血まみれの顔で、ニンマリと京一朗を見上げている。
「承知した。その亡霊、しかし平手殿にお渡しいたしましょう」
京一朗はくるりと背をむけた。
「眞薙殿」
呼び止められ、京一朗は蔵の前で立ち止まった。
「どうした?」
「いや、静香殿のことですが‥‥」
躊躇い、しかし龍影は続けて、
「もし何者かが逃したとしたなら、私は疑われるでしょうね」
「‥‥逃がすつもりなのか?」
「さて――」
龍影が呟き、唇に指を這わせた。
その唇には、今も静香のそれの感触が残っている。
――もう、己の心を決せねばならぬ、か‥‥。
新撰組につくか、薩摩につくか。いや、それよりも――
遥かな地平を眺めるように、龍影の眼は無意識的に細められた。
●
冒険者達が新撰組屯所から出てきた時、表には三人の冒険者が待っていた。
「遅かったな」
「左之さん」
陽平が手をあげた。すると堀田左之介は破顔し、
「そのぶんじゃ、どうやら落ち着いたらしいな」
「まあな。何とか十一番隊には戻れたよ」
「そいつぁ良かった。それより――」
蒼く氷が凍結するよう。左之介の表情が厳しくなった。
「またぞろ蛇が動き出すぞ」
「蛇? ――大蛇丸か!?」
声をあげたのは総一郎であった。十一番隊と三蛇という賞金稼ぎの確執は、御影一族分家である彼も承知している。
「しかし、何故この時期に大蛇丸が‥‥」
「わからねえ。噂では伊集院静香処刑の話をどこぞで聞き込んだものらしい」
「聞き込んだ? いったい誰から――」
問いかけて、柊の脳裏に翻然と浮かんだ名がある。
神代紅緒。新撰組を裏切って逃走した、元十一番隊伍長だ。
「だとしたら、ヤバイかもなぁ〰」
「なあに、どのみちいつかはケリをつけなくちゃならねえんだ」
いつもの通り、陽平は不敵な面構えだ。今は元通りの十一番隊隊士。もはや恐いものなどない。
と――
その様子を、違う色で眺めている者がいる。京一朗だ。
伊集院静香の一件をもらしたものは、本当に神代紅緒のみだろうか。長州は様々なところに間者を送り込んでいるという。もし、その間者が新撰組に潜んでいるとしたら‥‥。繋ぎを含め、最低でも二名は潜り込んでいるはずだ。
●
昼下がりの陽の光を受け、小柄の若者と女童が連れ立って歩いている。
と思ったら――
女童はみなもであり、若者は橘一刀といい、これもパラの浪人であった。
さらに一人。やや後ろを歩いているのはゴールド・ストームというエルフで、彼は先ほどから、面倒くせえとぼやき続けていた。
「ゴールド殿、これも仕事のうち。処刑の屋敷までの下見は是非にも済ませねばならぬ用件だ。そうそう文句を云うものではない」
「そりゃあそうだが‥‥」
そっちは楽しいだろうぜ、と、今度はゴールドは胸の内でぼやいてみせた。何故なら――
みなもと一刀は先日婚約したばかり。いくら仕事とはいえ恋の道行きだ。楽しくないはずがない。
見よ、その証拠に一刀はにこやかに、みなもに至っては終始頬に紅を散らしている。それを見せつけられるゴールドこそ、いい面の皮であった。
「この辺りで俺は別れるぜ。別の道を調べてくる」
「そうですか」
恥じらいながら、みなもがこたえる。でも、とっても嬉しそうだ。
と、同時に、みなもの眼には凄みがあった。
処刑場となる屋敷までの道中。賊の潜み隠れられそうな箇所はないか。――先ほどから、みなもはそれを探し求めている。
●
処刑当日。
それはあまりにも高く澄んだ蒼天の日であった。
「来い」
隊士の一人に、静香が引き出されて来た。
中庭。
用意された駕籠の傍に、平手の姿がある。
「‥‥」
「‥‥」
互いにかける言葉はない。ただ、平手のみは徳利を口に運ぶ。
それを凝然と見つめているのは、直接駕籠につく龍影と京一朗だ。ともに蔵へと入り、静香と最後の言葉を交わした二人。今また、ともに静香と屯所を後にする。
「さあ」
隊士が促し、後ろ手に縛られた静香が駕籠に身を入れた。ただ寂たる朝の景色の中、 駕籠かきが駕籠を持ち上げる。
「平手殿」
「どうした?」
徳利を口から離し、平手が京一朗に酔眼をむけた。
「何か、用か?」
「ひとつお聞きしたいことが‥‥蛇の頭は壱つと踏まれるか?」
「蛇の頭?」
平手が濡れた唇ぐいすと拭った。その眼が薄く光っているようである。
「京一朗よ、やっぱおめえは面白いなぁ。どうだ、腕もあがったようだし、十一番隊に入る気はねえか。今の十一番隊には、おめえのような奴が必要だ」
「動き出したぞ」
「そうだな」
駕籠を見送りつつ、隠身の勾玉を発動させた陽平と柊が身を起こした。さらに後ろには、剛弓を手にしたみなもの姿も見える。その姿が朧に映るのは、彼女もまた隠身の勾玉を発動させている故であった。
「大神サンは〜?」
柊が問う。先ほどから総一郎の姿が見えぬことに気がついたからだ。
すると陽平は口の端をややつりあげ、
「総さんは先行しているはずだ。あの人はぬかりねえから、心配はいらねえよ」
「なら良いけどな〜」
敵は長州、高杉だけではない。三蛇の生き残り、大蛇丸も動いているのだ。
その意味で、迂闊に柊達は出てはいけぬ。彼らが出れば、余計な大蛇丸まで現れる恐れがあるからだ。それ故にこそ、守り手は一人でも多いほうが良い。
「そんなことより」
陽平が駕籠から柊に眼を転じた。
「駕篭かきは大丈夫なんだろうな」
「そいつは心配いらない」
柊がこたえる。すでに彼女は駕籠かきの身元を確かめていた。
「あの‥‥」
声に、ぎくりとして二人が振り返った。見ると、いつの間に近寄っていたのか、みなもが背後に突っ立っている。
「観空殿はどこに?」
「あの女性か」
陽平が再び駕籠に視線を戻した。見失っては元も子もない。
「あの女性は今頃――」
その頃、小夜は処刑場となる屋敷内にいた。
すでに屋敷内並びに周辺を見回り、何度目かのブレスセンサーを終えたところであった。
結果として――
何の異常も見受けられなかった。今のところ、屋敷周辺に怪しい人影もない。
では、やはり襲撃するとなれば移送の途中か。と聞かれれば、素直に頷くこともできない。処罰が無事終わるまで、下手な予断は足枷となる恐れがある。
不安を抱えたまま、小夜は屋敷中庭を見渡した。
庭木と白砂の簡単な中庭だ。が、ここがもうすぐ新撰組組長代理をつとめたことのあるほどの人物の処刑場へと変貌する。
ある種の感慨をもって小夜が中庭を見つめた。
五条の乱を待たずとも、新撰組内の粛清は行われていた。その噂ぐらいは小夜も聞いている。
しかし、よく知る人物の処刑に立ち会うのは初めてであった。あの伊集院静香の処刑に。
おそらく、事ここに至っては静香が処刑を免れることはあるまい。たとえ斬首は逃れようとも、割腹は確実であろう。
小夜は空を見上げた。
抜けるほど蒼い空が、そこにはあった。
駕籠は粛々と進んでいく。
付き従うのは龍影と京一朗、それに浅葱の羽織を脱いだ数名の隊士である。
ちらりと京一朗は駕籠の隙間から覗く静香の面に視線をはしらせた。
落ち着いた、ふてぶてしい面つき。それが何に所以するのかはわからぬが、妙に不安をそそる。襲撃の噂を聞いて神経質になっているだけなのかも知れないが。それにまだ。みなもが見つけ出してきた襲撃予想位置は遠い。
それは龍影も同じとみえ、火のついたように周囲を見回している。が――
気がつけば、時々考え込むような仕種をする。
「どうした? 何か気にかかることでもあるのか。みなもが見つけ出してきた襲撃予想位置はまだ遠いぞ」
「い、いえ」
慌てて、龍影は頭を振った。
「何でもございません」
嘘だ。この時、襲撃を阻止するを他に、龍影の胸を占めていることがある。
それはひとつは静香に対する感慨であった。実のところ、彼は今までに四度静香と仕事をともにしてきた。一度は友とも思った相手。その気心が知れた者が、あと数刻後には処刑されてしまうのだ。これが嘆かずにおれようか。
そしてもうひとつ。それは薩摩であった。
昨今の薩摩の動きを見るに、勤皇の志は確かに見受けられる。が、うかとそのまま信用しても良いものか、どうか。そこのところが、まだ定まってはおらぬ。とはいえ、このまま新撰組にかかわっていたとしても、それほど勤皇の志は満たされはしない。
では‥‥
薩摩か新撰組か。考えるだに、龍影の心は千千に乱れるのである。
その時、龍影の脳裏にリュミエール・ヴィラの言葉が蘇った。
高杉は電光を発するかのように頭の切れる男。彼は、そう云っていた。そして周布もまた薩摩の手口を甘い、と。また高杉晋作が在京している、と。
まことに高杉が周布以上に頭が切れる男なれば、この機会を見逃すであろうか。いや、見逃すまい。
薩摩と長州の対立は思ったよりも深刻そうである。ならば、長州が事を有利に運ぶ為、伊集院静香の身柄を手中にしようとすることは鏡にかけて見るが如く明白だ。
今は、高杉――襲撃阻止のみに集中するべき。
京一朗の注視の前で、龍影は妖々とした鬼面頬をあらためて被りなおした。
「ふむ」
総一郎は足をとめた。
気がつけば、思いの外駕籠から離れている。気が急いている故かも知れぬ。
「やはり、長州だな」
決然たる思いで、後方の駕籠を見遣る。
左之介の情報より、陽平と柊を狙って大蛇丸が動き出していることがわかった。そうなれば三つ巴の乱戦になることは眼に見えている。
それこそが高杉の狙いではないか。何者が大蛇丸に働きかけたのかはわからぬが、それが高杉であれば納得はできる。
それ故にこそ、眼が逸れてはならない。乱戦の中、必ず長州の動きを見極めねば。
総一郎は長槍をびゅうと振った。
山城国金房。
この名槍ならば、きっと役に立つだろう。
その時――
●
どよめく声があがった。
はっとして振り返った総一郎の眼前、駕籠に数名の侍が群がり寄っている。
襲撃!!
総一郎は槍を舞わせて馳せ向かった。と、同時に、陽平と柊、はてはみなもまでもが飛び出している。
「長州か!?」
槍を風車のように旋回させつつ、総一郎が躍り込んだ。すると炎を燃え上がらせつつ、
「わかりませぬ。が――」
龍影が息をひいた。
今斬り込んできた侍の掛け声。そして剣筋。それは薩摩示現流ではなかったか。
はたと龍影の身が硬直した。
何でそれを見逃そう。侍の一人が龍影に斬りかかった。舞う剣風は、避けもかわしもならぬ龍影をおしつつみ――
あっ、と侍は身を仰け反らせた。その胸に一本の矢が突き立っている。
さらにヒュンヒュンと。数本の矢が飛来し、次々と侍の眼を、喉を貫いていく。
みなも。
達意の彼女と強弓の組み合わせは、ほとんど無敵とも思われる。
刹那――
突如散りしぶいた日の光に、ほとんど反射的に陽平が飛び退った。
「ほお、やるな」
声は、侍達に混じった総髪の男からした。
男――見忘れもしない。三蛇の一蛇、最も猛毒の牙をもつ大蛇丸だ。
「来たな、大蛇丸!」
柊が叫ぶ。すると大蛇丸は口の端を釜野うに吊り上げて、
「というところをみると、俺が来ることを予想しておったようだな。よかろう。此度こそは始末してやるぞ」
「とは、こっちの台詞だ」
陽平がニヤリとする。
「今まで待たせたな、これまで耐えてきた分いくぜ」
●
弧を描いた光流が閃いて、襲撃者の首筋から鮮血が噴いた。すぐさま山城国金房を放ると、総一郎は抜刀する。
白兵戦においては、かえって長い槍は不利。そうとみてとっての得物の交換だ。
分家とはいえ、さすがに一族長子の大神総一郎。やることにそつがない。
その時、炎が立ち上った。まるで獣のように襲撃者に襲いかかる。
あっと声をあげて、襲撃者が割れた。龍影の術に驚いた故である。
そしてみなもは――
道端の木々の間を走り回っていた。
陰に隠れ、一矢放ち――襲撃者が幣れたのを見定めると、再び疾り、木陰に飛び込む。そして、また狙いをつけて一矢――
突如飛来するみなもの矢は、まさに晴天の霹靂。死神の指、そのものだ。
「来い、小僧」
大蛇丸が刀の鍔に手をかけ、すうと身を低くした。鼠を襲う猫の如く。
対する陽平は上段。示現流得意の構えだ。
今、陽平と大蛇丸、剣をとって相対す。
「ちぇすとぉー!」
凍りついた殺気の渦を砕くかのような掛け声を発し、陽平は袈裟に剣流を薙ぎおろした。ほぼ同時に――いや、一瞬早く大蛇丸の腰から白光が噴出する。
きらと日の光が散りしぶいた時、陽平は脇腹をおさえてよろめいた。腹におしあてた指の間からは鮮血が滲み出ている。
「馬鹿め。まだ俺には勝てぬわ」
一旦鞘に戻した刃を、再び大蛇丸が抜き撃った。刹那――
鋼と鋼の相うつ音が響いた。横からさっとのびた刃が、大蛇丸のそれをはじき返したのである。
「そうはさせない」
「小娘、貴様‥‥」
ぎろりと大蛇丸が柊を睨みすえた。その前で、柊はすすうと剣を青眼に構えなおした。
「なかなか強くなったようだが、俺に勝てるか」
「‥‥」
柊には声もない。
其れ剣は瞬速。つまるところ、剣で勝つためには相手より迅く斬れば良い。その定理からいえば、大蛇丸の居合いが有利だ。
が、柊は我流。時として正剣は奇剣に惑うことがある。それこそが柊の付け目だ。それに、今はオーラエリベイションも施してある。
柊の眼に、かすかに笑みの翳がゆれた。
それに衝き動かされたか、大蛇丸が抜刀した。ほとんど同時に柊も真一文字に斬り下げ――
空に真紅の花が開いた時、大蛇丸がどうと崩折れた。
斬った! 大蛇丸を!
心中、柊は快哉を叫んでいる。これですべての借りは返した。
その間、駕籠はその場を逃れつつあった。
「ゆけ、早く!」
追いすがる襲撃者の背を、総一郎は日本刀で斬って捨てた。
●
どれほど走ったろうか。
付き従っていた新撰組隊士が駕籠をとめた。
「もう、ここいらで良いだろう」
「何を云っている。屋敷まで一気に走るんだ」
京一朗が怒鳴った。しかし隊士はどこ吹く風と言った風情で、
「このままでは駕籠かきがもたん」
「馬鹿な。ここで襲われたら、俺達がもたん」
「そうかな」
その言葉の終わらぬうち、びゅっと隊士が刃を薙ぎつけてきた。咄嗟には避けえず、京一朗の胴に刃が叩きこまれる。
「馬鹿め」
隊士はせせら笑うと、倒れ伏した京一朗を見下ろした。それからもう一人の隊士と目配せし、駕籠かき二人を無慈悲に斬り捨てた。
「伊集院殿」
京一朗を斬った隊士が駕籠に声をかけた。
「今、お助けし申す」
「早くしろ」
「はッ、すぐに」
「させぬ」
「なにっ!?」
声に、愕然と隊士がうめいた時、ゆらりと京一朗が身を起こした。彼は身代わり人形によって一命をとりとめていたのである。
「新撰組に間者が混じっている可能性があると思っていたが、そうか、二段構えでくるか」
「きさまっ!」
隊士が刀の柄に手をのばした。が、それより早く、京一朗の刃が逆袈裟に薙ぎあげられた。
「くわっ」
隊士が血煙にくるまれる。それを突っ切るように、京一朗はもう一人の隊士に迫り、抜き胴――柳生得意の捨て身の剣法で切り捨てた。
「静香殿、残念でしたな」
「うぬら冒険者がおったこと、我が身の不運であったわ」
駕籠の中から静香の声がした。それは乾いた、何の抑揚もない静かな声音であった。
●
日は中天。
白い日の下、これもまた白砂の上に逆さに返した畳二畳がおかれ、その上に白無地の小袖に浅黄色の無紋麻布製の裃をまとった伊集院静香が端座していた。
それを見守るように、黙然と総一郎は立っている。
静香も武士。理由の如何にとわず、静かに見送ってやるのが礼儀ではないか。
そして龍影、柊、みなもの三人は、周囲を警戒しつつ、やはり静香の姿に眼を吸い寄せている。
その時、ばさりと布音が響き――
はっとして全員の眼がむいた先、 陽平が浅葱の羽織をまとっている。
「俺は俺の誠を背負う」
誠の文字、幻影の如くに浮かぶ羽織の裾はためかせ、陽平が云った。
「静香ちゃんの誠とは違ったが、貫いて逝けるなら本望か。最後まできっちり見届けっから」
「伊集院殿」
小夜が静香に歩み寄る。
「後世‥‥いえ、今の世に残す言葉があればお引受け致します」
「辞世の句などはないが‥‥平手殿に一言、伝えてもらいたい」
刃にのばしかけていた手をとめ、静香が云った。
「平手殿に? なんと?」
「あの時、止めを刺さなかったは生涯の不覚でありました、と」
云った。
一度、小夜は静香の顔を見返した。が、そこには皮肉の色はなく、どころか、童のような自然の笑みを静香は浮かべている。
「これで宜しいのですか」
「‥‥」
静香は無言で頷いた。
そして刃に手をのばすと、一気に腹に突きたて――
介錯の隊士の振り下ろした刃影が、天光を一瞬翳らせた。
●
「‥‥そうか」
とだけ、平手は呟いた。後は寂寞と酒を含む。
告げた小夜は、そっと平手の猪口に酒を注ぎ足した。
時は秋。冬は、もうそこまで来ている。
●
「伊集院静香が死んだな」
漆を流したような闇の中、淡々とした声が流れた。するとくつくつと嘲り笑う声が響き――
「あの人は間抜けであった。仕方のないことです」
「そういうお前もしくじっておきながら、よく云うわ」
とは第三の声。
「そうでした」
「何がそうでした、だ。せっかく庄治八郎を犠牲にしてまで新撰組にもぐりこんでおきながら、馬鹿が」
「あははは」
闇の中、剣風が唸り、何者かが飛び退った。
「あまりうるさいと、殺しますよ」
云って、声の主が足を踏み出した。その姿が月光に蒼く濡れて――
その者の名は、神代紅緒といった。



