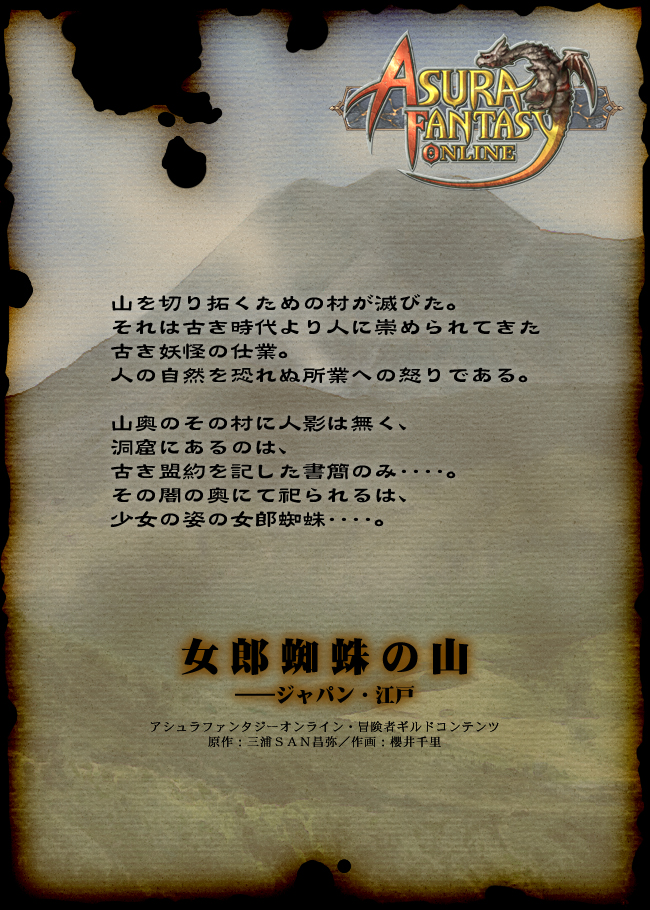女郎蜘蛛の山――ジャパン・江戸
女郎蜘蛛の山――ジャパン・江戸
 |
■ショートシナリオEX&担当:三ノ字俊介 対応レベル:1〜5lv 難易度:難しい 成功報酬:1 G 35 C 参加人数:7人 サポート参加人数:-人 冒険期間:08月22日〜08月27日 リプレイ公開日:2004年09月03日 |
|
●オープニング
ジャパンの東国『江戸』。摂政源徳家康の統治する、実質の日本の主都である。政治色の強い都市で、帝の都(みやこ)である『京都』よりも精力的な都市だ。
だがそんなことよりも、人々の関心はその日の生活に向いていた。なにぶん、人間は食わなくてはならない。平民の暮らしはあまり裕福とは言えず、毎日ちゃんとご飯を食べるのも大変だ。
そして、化け物の存在はもっと深刻だった。
江戸から東へ3日ほど行った場所に、樵(きこり)の村があった。あった――というのは、今その村は無いからである。
5戸ほどしか人が住んでいなかったその村は、壊滅した。山に住む女郎蜘蛛の手によって。
「今回の依頼は、江戸大手の材木問屋から来てるわ」
そう言ってキセルをくゆらせたのは、冒険者ギルドの女番頭、“緋牡丹お京”こと、烏丸京子(からすま・きょうこ)である。漆を流したような黒髪が艶やかしい妙齢の女性で、背中には二つ名の由来となる牡丹の彫り物があるという話だ。
京子がキセルを吸いつけ、ひと息吐いた。紫煙が空気に溶けてゆく。
「依頼内容は、山に住む女郎蜘蛛を退治すること。この女郎蜘蛛は、以前山に入植して村を立ち上げた人たちを襲っていてね。その時、何人か村人が食われて死んだわ。ただその女郎蜘蛛は、もともとその村のあった山を住処にしていて、縄張りに入ってきた人間を排除しただけみたい」
京子は表情に、やれやれという微笑を浮かべた。
「人間ってこれだから始末に負えないと思うけど、これがあたしたちの仕事だし。ともかくその女郎蜘蛛が居なくならないと商売が出来ないって、大店のご主人がカンカンなのよ。そこで、あたしたち冒険者の出番ってワケ」
タン!
京子が、キセルで火箱を叩いた。火球が、灰の中に転がる。
「女郎蜘蛛は人間にも化ける強敵よ。地の利も向こうにあるわ。手下に土蜘蛛とかも居るみたい。大変だけど、なんとかしてね」
京子が地図を出し、表情を改めて言った。
【地図について】
地図には、南の村から北の山に向かって、A〜Fの6ヶ所のポイントがあります。そこ以外は深い森林です。
A:村:さして広くない。5戸ほど。壊滅している。
B:山道:山へ向かう道。伐採した木を下ろす道でもある。
C:伐採場:切り株がたくさんある。
D:古刹:伐採場の奥、仏像が奉ってある。
E:洞窟:幅3メートル×高さ3メートル。内部は一本道で、50メートルほど奥で行き止まり。
F:広場:使用目的不明。直径30メートルほどの円形の広場。中央に祭壇のようなものがある。
●今回の参加者
ea0085 天螺月律吏(36歳・♀・侍・人間・ジャパン)ea1160 フレーヤ・ザドペック(31歳・♀・ファイター・人間・神聖ローマ帝国)
ea1966 物部 義護(35歳・♂・志士・人間・ジャパン)
ea2406 凪里麟太朗(13歳・♂・志士・人間・ジャパン)
ea2722 琴宮茜(25歳・♀・志士・人間・ジャパン)
ea2841 紫上久遠(35歳・♂・浪人・人間・ジャパン)
ea4141 鷹波穂狼(36歳・♀・志士・ジャイアント・ジャパン)
●リプレイ本文
女郎蜘蛛の山――ジャパン・江戸●蜘蛛神
土蜘蛛とは本来、古代大和政権に服属しなかった先住の人々のことを、未開の土着民というほどの意で呼んだ蔑称である。『古事記』『日本書紀』『常陸国風土記』などに見られ、しばしば神格化され、他に比類なき強力な化け物として登場する。
朝廷にまつろわぬ『もの』――彼らは古代から『鬼』や『妖怪』、『妖魔』と伝えられ、権力者からは忌み嫌われ、悪神として調伏される存在だった。かつて東国などは悪鬼の巣窟などと呼ばれ、その王者は鬼として扱われている。鬼は政治と宗教の境界面にも存在するのだ。
そして当然人間ではない『もの』、本物の妖怪や妖魔たちは、朝廷どころか人間にもまつろわぬ者として、文字通り『敵』として扱われている。彼らを好事家に売りさばいたりする廻船問屋なども居ることはいるが、そういうのはごく少数で、そのような化け物たちとは生存領域をめぐってせめぎあっているのが現状だ。
だがそんな中でも、妥協して調和を図ろうとする動きもある。版図を広げるために、それら土着の妖怪と『取引』を行うような場合だ。
今回の女郎蜘蛛の件は、まさにそれであろう。かつてそこにあった村は女郎蜘蛛を『蜘蛛神』とあがめ、いけにえを差し出すことで永らえ、繁栄した。いけにえというのは、もちろん人間である。通常は、幼い少女が捧げられる。
その村に何が起きたか、今となっては知るすべなど無い。残された古刹にあった文献などから断片的な情報を探るならば、人間は『何か』をして蜘蛛神の怒りを買ったのだろう。それが何かは、今となっては語るものもいない。
そして、その後新たに建設された村は、滅びた。
過去の約定を律儀に守っていたのは、蜘蛛神のほうである。旅人が何人か襲われていたかもしれないが、それは事故のようなものだ。何かの意思を持って、襲い掛かったわけではない。
しかし、人間は業も欲も深い。手が届くものは、全て手に入れようとする。それは古刹や祭壇の存在を無視し、思考を麻痺させた。『何かある可能性』を否定したのだ。その報いは、命。
しかし、人間は引き下がらない。因果がめぐってきても、それを打破しようとする。それは人間の美徳であり、欠点でもあるだろう。
今回、この蜘蛛神の退治を請け負ったのは、次の冒険者たち。
ジャパン出身。人間の女侍、天螺月律吏(ea0085)。
紅の長髪が目印の女武者。家族を大切にする家庭的な一面と、クールで男のような出で立ちをする反面とを持つ、複雑な人物。常に最善を尽くす姿勢は大切だが、あまり自分を追い込まないほうが良いだろう。
神聖ローマ帝国出身。人間の女ファイター、フレーヤ・ザドペック(ea1160)。
レオン流正統派武芸者。武器の収集癖があり名剣などに目が無いが、正義は幻想と考えているためか、振るう剣にはつねに厭世感がつきまとう。迷いが無いと言えば聞こえが良いが、何もかも投げ出しているとも言える。
ジャパン出身。人間の志士、物部義護(ea1966)。
目が切れ長の優男で、今売り出し中の冒険者志士。扇をいつも手にしている洒落者で、人相は悪いかもしれないが純情な面もある。寝起きが悪いのが玉にキズ。
ジャパン出身。人間の志士、凪里麟太朗(ea2406)。
まだ10歳の少年志士。無邪気で天真爛漫。悩み事なんか無いように見えるが、なにやら複雑な家庭の事情があるらしい。10歳で立志するのはたいへんなことだが、これからが楽しみである。
ジャパン出身。人間の女志士、琴宮茜(ea2722)。
銀髪碧眼の少女志士。14歳だが、童顔のため10歳ぐらいにしか見えない。マイペースな性質で周囲の波に取り残されがちだが、自分自身については一本通った筋というものを持っている。
ジャパン出身。人間の浪人、紫上久遠(ea2841)。
不惑の用心棒。強さを求めて殺人的な修行を繰り返し、怪我をしては温泉へ旅立つということを繰り返している。妹が一人いるが、どう思っているかは微妙である。
ジャパン出身。人間の女志士、鷹波穂狼(ea4141)。
船乗りを生業とする変り種の志士。海に強く水に強く、機嫌が良いときはよく鼻歌を歌っている。肉体派と思われがちだがわりと知的で、神皇から下賜された精霊魔法を操る。
以上、7名。相手にとって不足なしと言ったところだろうか。
一同は以前の事件の報告書をしっかり頭に叩き込むと、手早く打ち合わせを行い、それぞれの役割を決めて旅立った。
●死せる村
村は、やはり死んでいた。
おそらく山の獣に食われたのだろう。牛の死体などは無くなっていたが、廃墟となった建物や田畑は、そのまま残っていた。田畑にはすでに雑草がはびこり始め、早くもこの地を元の自然に返そうとしている。
「見ると聞くとでは大違いだな」
赤毛の侍、天螺月律吏が、周囲を見渡して言う。確かに、報告書を読んだのと実際に現場を見るのでは、雰囲気がかなり違う。自分たちがこれから相手にするのが、本当の強敵であるということが実感できた。
「仕事をしよう」
フレーヤ・ザドペックが言う。
「俺たちの仕事は、ジョロウグモを倒すこと。それだけ考えればいい。後の事は、後から来るものたちに任せればいいんだ」
自分に言い聞かせるように、フレーヤが言う。戦いに、必ずしも正義があるとは限らない。自然の摂理を曲げようとする人間にも問題はあるのだ。
だが、『弱肉強食』も自然の摂理である。フレーヤたちが、たとえその報酬が二束三文の金だとしても、彼女たちが強ければ『許される』のだ。せめてそう思いたい。
「俺は打ち合わせどおり、洞窟を調べてくる」
物部義護が、扇を取り出しながら言った。
「古刹の方は頼む。例の蜘蛛を、誰がどうやって『くくった』のか、なんとか見つけ出してくれ」
義護が言って、馬を進めた。それに凪里麟太朗が続く。
「本当は人間側が非礼を詫びて再交渉を申し入れるべきなんでしょうけど‥‥山の主という矜持がありますから、簡単には許してくれはしないでしょうしねぇ‥‥」
麟太朗が、暗澹とした表情で言う。
「俺も洞窟へ行く。何か見つかることを祈ろう」
紫上久遠が言った。刀を鳴らして馬を進めた。
「土蜘蛛はこちらで始末しておきます」
琴宮茜が言う。
「皆さん、ご武運を」
そう言って、茜が会釈した。
「さーて、こっちはこっちでちゃっちゃとやるかい?」
鷹波穂狼が言う。彼女はすでに、土蜘蛛の生餌となる野ウサギを数匹捕まえていた。これから『狩り』が始まるのだ。
●洞窟
「思っていたより新しいな‥‥」
土壁を叩きながら、義護が言った。
洞窟は土壁の洞窟で、あまり古い感じはしなかった。むしろ新しく掘ったような印象がある。これは報告書には無い情報だ。
そしてこれは報告書どおりに、奥は行き止まりになっていて小鬼の死体があった。腐乱しており、正視にも耐えない。
――何かあるはずだ。
何かはわからないが、何かがあるはずだった。小鬼は集団で行動する生き物である。2匹しか居ないのは不自然だ。
「むっ?」
義護は、小鬼の死体の手に注目した。何か光るものを持っている。たいまつの光を反射するそれは、石のようだった。
「石仏だ‥‥」
白い玉石の小さな菩薩像が、その手に握りこまれていた。年代はわからないが、結構古そうだ。おそらくジャパンへの仏教伝来のころまでさかのぼるのではないだろうか。
それには、亀裂が入っていた。義護が手に取ると、それは割れて二つの破片になった。
「確かに『あった』が‥‥」
久遠がつぶやくように言う。
「『これ』をどう解釈したらいいんだ?」
久遠が言った。
「古刹のほうへ行けばわかると思う」
義護が言う。
「これは、『鍵』だ。この地域の支配者を支配者たらしめる」
義護が言って、一同は洞窟を出た。
●古刹
「さて、何を探せばいいのやら‥‥」
律吏がつぶやく。
古刹は、古く狭く、人が住めそうな場所には見えなかった。
「つまりうこの大きさは、『人が住む場所ではない』という意味ではないのでしょうか」
土蜘蛛退治を終えた茜が言う。穂狼も腕を組んでうなずいていた。
「ここには坊さんも神主さんも来る必要が無いってことなんだろうね」
穂狼が言う。
余談だが、神道と仏教が分けられる神仏分離が行われるのは、現代で言う明治時代になってからである。それまでは神様も仏様もごった煮のようになっていて、例えば偉いお坊さんがものすごい『神通力』を持っているということで神様に奉られ、寺の隣に神社が建つなどということもしばしばであった。それは神聖暦999年の現在でも変わらない。
ともあれ、仏具神具書簡など、古刹の中に残っているものを片っ端から、一同は探しはじめた。こういうとき盗賊が居ればと思うのは無いものねだりではあるが、真正面からあの女郎蜘蛛と戦うのは無謀である。
コンコン。
フレーヤが何気なく仏像を叩くと、軽い音がした。
「仏像というのは空なのか?」
ざわっ。
一同が色めきたつ。
仏像は乾燥木を使って作られる。わざわざ中身をくりぬくことなどなく、むくの木で作られるのが普通だ。
一同は仏像を調べた。すると台座の下がふたになっていて、中を開けることができた。
「書簡か‥‥」
律吏がつぶやいた。
そこから出てきたのは、緑色の表紙の巻物であった。開くと、古い木の匂いがした。
「うわ‥‥達筆すぎて読めない‥‥」
なにやら漢字のたくさん書かれた文章がある。和漢字ではなく、華漢字であった。華仙教大国の言葉で書かれているのである。
絵図と漢字を組み合わせておおよその事情を紐解くと、次のようなことらしかった。
昔、松趙上人という僧侶がいた。その僧侶はこの土地に流れてきて、村人に仏教を教えていたらしい。
当時、その土地には強力な蜘蛛の化身が住んでいて、村人を脅かしていたそうだ。松趙上人はその化け物を調伏せんとした。だが上人の力は及ばず、化け物をこの土地にくくり、約定を定めて被害の拡大を留めるにとどまった。以来、村は人間を差し出して村の安全を図るということを繰り返していたらしい。
巻物の物語は、ここで絶筆となっている。上人がその後どうなったか。蜘蛛がどうなったか。村がどうなったかについては分からない。ただこの古刹より先は、人の領域ではないという定めがあったらしい。
おそらく、その後『何か』が起きて、村は一度壊滅したのだろう。そのとき上人が生きていたかどうかは不明だ。
●腹をくくる
一同は探せるだけの情報を探し、村の、元村長宅と思われる場所に集合した。まだ破壊の後はそれほどなく、生活臭の消えたたたずまいだけが残っている。
「つまり、その僧侶が『何か』をして蜘蛛の力を弱めたという解釈でいいのかな」
義護が、囲炉裏の灰をかき混ぜながら言った。
「おそらくは。華国人が居ればもう少し何か分かるかもしれないが、上人と呼ばれる階級の僧侶が使ってくくった呪法だ。おいそれと真似できる者が居るとは思えない。結局、選択肢はあまり無いと考えていいだろう」
目を閉じて、律吏が言う。
「そちらの成果は何かあったのか?」
フレーヤが、義護に問うた。それに義護は、例の玉石で出来た石仏の欠片を取り出した。小鬼が握りこんでいたものである。
「洞窟は、わりと最近出来たもののようだ。情報通り小鬼が居て、それがこんなものを握りこんでいた。どう解釈して良いかわからない」
義護が言う。その後に、久遠が続いた。
「意外と、あの洞窟は蜘蛛神の住処なのかもしれない。小鬼の死体をほうりっ放しというのが気になるが、それなら新しい洞窟なのもある程度うなづける――うん、美味い」
囲炉裏にかけられた鍋の汁をすすりながら、久遠が言った。ありあわせの残り物と保存食を材料に作ったのだ。
「事情はおおよそ把握できた。しかし状況は変わっていない。今ここに徳の高い僧侶はおらず、武人ばかり揃っているのだ」
麟太朗が言う。
「手がかりは途絶えたと見ていいだろう。過去を知る者は、もはやその巻物しか居ない。しかし、その巻物の内容はわからないときている。となれば、私たちに選択肢は二つしかない。押すか、引くかだ」
「引くわけにはいきません」
茜が口を開いた。ちなみに先ほどの鍋は、彼女の手になるものである。
「すでに、被害は現実のものとなっています。人間側の無礼は重々承知していますが、この戦いは生き残りを賭けた戦いです。明日の為に戦うのなら、今がその時でしょう。私たちがここに来てこの情報を得、ここに揃った事は偶然ではありません。もしも私たちがやらなければ、この地域の人間は絶えてしまいます」
いつになく饒舌になって、茜が言う。その意見には、確かに賛成だ。女郎蜘蛛――いや、蜘蛛神は決して無害な存在ではない。腹が減れば縄張りを移動するかもしれないのだ。松趙上人という人物が何をしたのかはわからないが、それが永遠に続くとも思えない。
その兆候は、確かにあるのだ。砕けた玉石の仏像。今回の事件と、何かの因果関係があると考えたほうが自然である。
結局、一同は、腹をくくるしか無かった。戦うのだ。正面から、女郎蜘蛛と。
「気が進まないねぇ‥‥生贄差し出しての平和なんて、長く続かないって事だな、所詮。でも、琴宮は絶対傷つけさせやしないからな」
穂狼が言った。フレーヤが、苦りきった表情をしていた。
●神域への道
山道は、険しかった。
森の中、明らかに作られた道ではあるが、そこはおそらく役目を持った者たちのみが出入りしていたのだろう。巻物の中にも、輿に乗せられて運ばれる女性の姿が描かれている。
そこを、冒険者一行は進んでいた。いや、切り拓いていた。血路を。
カサカサカサ。
微細な足音を立てて、蜘蛛たちが居る。表情の無い黒い8つの眼でこちらを見ている。その数は、十数匹。おそらく女郎蜘蛛の眷属の者と思われた。
「むん!」
律吏がオーラソードを振るって、蜘蛛を斬る、斬る、斬る。光の剣の前に、蜘蛛は臓腑を撒き散らして四散した。
「どいたどいた! 雑魚には用は無いんだよ!」
穂狼が<ダブルアタック>を放つ。蜘蛛は黄色い体液を散らして果てた。
「くっ‥‥」
茜が蜘蛛の糸に捕らわれた。だがその糸を、麟太朗が燃やして切った。神皇から下賜された精霊魔法<ファイヤーコントロール>である。
「感謝します!」
茜が糸を放った蜘蛛に斬りかかる。蜘蛛はフェイントの混じった攻撃に翻弄され、痛打を受けた。
「むん!」
久遠が<ソニックブーム>を放つ。それは蜘蛛の吐く糸を切り飛ばし、蜘蛛に打撃を与える。
「くそ! 効いてるのか!?」
義護が<バーストアタックEX>を使うが、うまく敵の防備を破ることが出来ない。意外と装甲は厚い。
「‥‥‥‥」
黙々と。フレーヤが蜘蛛たちと切り結んでいた。着実に戦果を挙げてゆく。
『よい』
その時、森の中に声が響いた。女性の――少女の声だった。
『そのものたちを中へ』
声が言うと同時に、蜘蛛たちが引き始める。その姿は、すぐに消えた。
一同は警戒しながら、神域へと向かっていった。
●神域
女郎蜘蛛は、白装束のつややかしい黒髪の女性であった。年齢は14〜17ぐらい。紅を曳いた唇がなまめかしく、そして美しい。毒花の美しさではない、超然とした美の顕現。それが女郎蜘蛛の姿だった。
そこは、神域だった。森の中、円形にしつらえられた空間の中にある祭壇。そしてその中に立つ少女。
何もかも、出来すぎな光景であった。
『妾に――』
女郎蜘蛛が、冒険者達を見て言った。
『妾に用があるようじゃな。つちくもをずいぶん手にかけたようじゃが‥‥』
女郎蜘蛛が言う。
「死合う前に二、三聞く。その体、本当に御主の体か? そして御身に名が有るのなら聞いておきたい。‥‥後々祀るにしても名が必要だろう」
物部義護(ea1966)が、油断なく刀を構えながら言う。
『祀る?』
女郎蜘蛛が頓狂な顔をする。
『妾は神ではない。山を住処とする蜘蛛』
すっと手を伸ばす女郎蜘蛛。その指先から糸を出し義護の腕を細い鋼線のような糸が絡め取る。
「ぐっ」
うめく義護。剣を封じられたのだ。
『ひとは妾と約定を交わした。この約定ある限り、妾は無益に人を襲わぬ』
薄く笑いながら、手をなでる様に振る女郎蜘蛛。天螺月律吏とフレーヤ・ザドペックが、武器を構えながら油断なく周囲を見る。
周囲に細い鋼線のようなものが漂い始めていた。蜘蛛の糸である。
ぎり、と律吏が唇を噛んだ。
「確かに」
律吏が言う。
「人間の方が愚かなのかもしれない‥‥しかし私は人だ。人を喰らった物を生かしてはおけないのだ。それに私にも待つ者がいる‥‥だから負けられぬ」
「正義など幻想だ」
フレーヤが言った。
「しょせん正義など相対的なものでしかない。我々にとって貴様は『悪』なのだ。だから、滅んでもらう」
『『悪』とな?』
女郎蜘蛛が嗤う。
『ならば、妾の住処に土足で上がりこみ、眷族のものを殺し、約定を違えて妾を殺しに来る者は何なのだ?』
ぐわっと、女郎蜘蛛の背中から8本の蜘蛛の足が飛び出た。その色は、鬼蜘蛛の黒と黄色の毒々しい縞模様だった。
「‥‥‥‥」
凪里麟太朗と琴宮茜の二人が、背中合わせで周囲に目を配っていた。周囲に散ってきた蜘蛛の糸を気にしているのだ。
「あなたは強敵といっても、単に残忍で強いだけ。母上や師匠と比べたら、あなたは菩薩のようです。これは己の生存を賭けた戦い。生存競争という自然の摂理に従うだけです」
麟太朗が、不敵な表情で言う。
「はい、簡単にはやられません」
凛とした表情で、茜が言った。
「はじめるぜ!」
紫上久遠が<ソニックブーム>を放った。剣撃がかっ飛び、女郎蜘蛛の張った糸の結界を寸断する。そしてその剣圧は、女郎蜘蛛にも届いた。女郎蜘蛛の頬に血の筋。女郎蜘蛛の目の色が変わる。本気になったのだ。
「うるああああああっ!」
鷹波穂狼(ea4141)が日本刀と小太刀を持った姿で突貫する。そして<ダブルアタック>! しかし女郎蜘蛛は足を交差させてその攻撃をがっちりブロックする。
『甘いな』
女郎蜘蛛が言う。組合いになると8本足がある女郎蜘蛛が有利になる。穂狼が不利を悟り間合いをあけようとするが、糸に絡め取られてしまった。
「しまった!」
「たーっ!」
突貫する茜。身体には青雷をまとっている。精霊魔法<ライトニングアーマー>だ。身体ごとぶつかるような攻撃を、再び脚でブロックする蜘蛛。しかし今度は足を1本、雷に焼かれてしまう。だが茜もカウンターを受けて、胸に重傷を負った。
「大丈夫か!」
「大丈夫です!」
麟太朗の言葉に、血を吐きながら気丈に返す茜。
「いくぞっ!!」
天螺月律吏とフレーヤ・ザドペックのコンビネーション攻撃。律吏は手からオーラソードを出している。フェイントで囮になる律吏に体勢を崩され、フレーヤの<スマッシュ>の一撃を受ける女郎蜘蛛。左の肩口をばっさりやられ、脚も2本切り飛ばされる。
どかどかっ!
脚の攻撃を受けるフレーヤ。カウンターできまったその攻撃がフレーヤの胸と腹をうがつ。
どざあっと地をすべるフレーヤ。苦悶の表情を浮かべるが、生きている。
「もらったっ!」
物部義護が<ポイントアタック>で蜘蛛の顔を狙い、そして紫上久遠が同時に居合いで女郎蜘蛛の胴を凪いだ。チンという音と同時に時間が止まったような間が開いた。
女郎蜘蛛が、安らいだような顔になったそして倒れる。その死体はチリになり、そして消えた。
一同は、その様子をただ見ていた。
●終わりに
村は再建された。木が伐採され、そして人の営みが営々とつづられてゆく。
「女郎蜘蛛、安らかな顔をしていたな」
律吏が言った。
「長く『くくられ』ていることに疲れていたとか‥‥そんなことを言うのもおこがましいかもしれないか‥‥」
フレーヤが言う。
「帰りましょう」
茜が言う。
「任務は果たした。あとは、後の連中がどうにかしてくれるさ」
穂狼が言った。
その後、女郎蜘蛛の退治された山には人間が入植し、何事も無かったかのように村は運営されている。やがてこの事件も風化し、ひとびとの記憶から忘れ去られることになるだろう。
風だけが、この物語を知っている。
【おわり】