 【聖夜祭】新年のお届け
【聖夜祭】新年のお届け
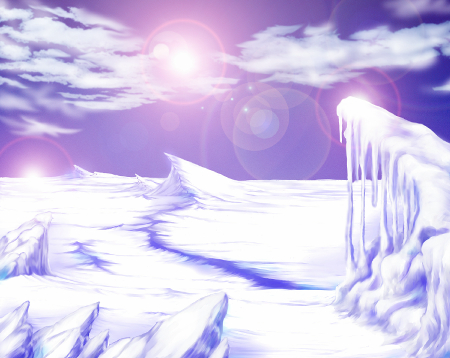 |
■ショートシナリオ担当:宮本圭 対応レベル:2〜6lv 難易度:普通 成功報酬:2 G 4 C 参加人数:8人 サポート参加人数:-人 冒険期間:01月03日〜01月10日 リプレイ公開日:2005年01月10日 |
|
●オープニング
聖夜祭。ふたつの年をまたいで行われるこの祭りで、ノルマンの街中はいつになく華やいでいる。今年最後のかきいれ時と声を張り上げる商売人、新年のための買い物に行きかう奥様方、寒さに身を寄せ合いながら幸福そうな恋人たち。――そんな街並とは打って変わって、やっぱりいつもと変わらず門戸を開いているのが、ここ冒険者ギルドである。
「配達のご依頼ですねー。はいはい」
一体なにが楽しいのやら、ギルドの係員はにこにこと依頼書を書き付けている。仕事中だというのに、鼻歌を歌いながら羊皮紙の上でペンが軽やかに躍っている。手元を覗き込んでも、字の読めない依頼人には何を書いているのか判然としない。やや不安になって呼びかけた。
「あの‥‥聞いてますか?」
「ええ聞いてますですよもちろん」
いいかげんな相槌ににますます不信が募る。目を眇めて係員を見ても、相手の表情は石で彫った彫像のように変わらない。本当にわかっているんだろうなと思いつつ、念のためもう一度最初から依頼内容を繰り返した。
「離れて暮らしている甥に、新年の贈り物を届けてほしいんです」
「ええそうでしたそうでした」
「本当は直接渡してあげたかったんですが、どうしても仕事で行けなくなってしまいまして」
「なるほどなるほど」
「道中にオークの群れが出るという噂もありますし」
「物騒ですなあ実際」
「‥‥あの、本当に聞いてるんですか?」
「冬は野生の獲物が少ないですから、オーガどもも人間を襲うことが多くなるわけですなあ」
ようやく実のある返答を引き出せて、依頼人は少々溜飲を下げた。咳払いをして続ける。
「それで、届けるものなんですが‥‥目を離さないよう、充分注意してほしいんです」
「ほほう。というと、高価なものなんですか?」
「いや、そういうわけでは」
「とても壊れやすいとか」
「違います‥‥いや、そうとも言えるのかな。まあ、見てもらったほうが早いですね」
床に置いておいた金属製の小さな籠を持ち上げて、カウンターの上に置いた。寝床を揺らされて目覚めたのか、籠の中で丸くなっていたものが首をもたげる。まるい瞳で係員を見ると、見慣れない人間に向かって一声、にゃあ、と鳴いた。
「以前から甥が、子猫が飼いたい、と言っていたもので‥‥」
秋生まれらしいちいさな『届け物』は、真っ白い毛並みに青い目をしていた。
●今回の参加者
ea2100 アルフレッド・アーツ(16歳・♂・レンジャー・シフール・ノルマン王国)ea2938 ブルー・アンバー(29歳・♂・ナイト・人間・イギリス王国)
ea3674 源真 霧矢(34歳・♂・ナイト・人間・ジャパン)
ea3844 アルテミシア・デュポア(34歳・♀・レンジャー・人間・イスパニア王国)
ea6044 サイラス・ビントゥ(50歳・♂・僧侶・ジャイアント・インドゥーラ国)
ea6337 ユリア・ミフィーラル(30歳・♀・バード・人間・ノルマン王国)
ea6592 アミィ・エル(63歳・♀・ジプシー・エルフ・ビザンチン帝国)
ea8553 九紋竜 桃化(41歳・♀・侍・人間・ジャパン)
●リプレイ本文
問題の子猫は、依頼人が依頼のときギルドに持ち込んだ鳥籠に入れて運ぶことになった。そのままでは冷えるだろうということで、籠の中に敷物として古い布の切れ端を詰め、籠そのものも毛布で軽くくるんでいる。確認したところ目的地まではそう遠くない距離なので、ゆっくり行っても期間内に充分往復できるだろう。「子猫ですか‥‥可愛いなあ」
ブルー・アンバー(ea2938)がちょっと毛布をまくって覗き込むと、白い子猫は鉄籠の中、前肢で古布を一心に揉みしだいている。ああっ、と身を軽く震わせ、ブルーはさらに籠に顔を近づけた。
「に、肉球‥‥ちょっと触らせてもらえませんかね‥‥?」
「駄目、駄目! むやみに触らないの」
ユリア・ミフィーラル(ea6337)が素早くブルーの手から籠を取り上げる。
「せっかく毛布でくるんであげてるんだもの。必要もないのに、籠から頻繁に出入りさせたらかわいそうだよ」
「‥‥それに‥‥子猫は、人が構いすぎると‥‥却って弱ってしまいます‥‥」
アルフレッド・アーツ(ea2100)の言葉に、ほかの冒険者たちも同意して頷く。まだ未練げにブルーが籠を眺めているうちに、荷を積み終えた自分の馬をそれぞれ引いて、アルテミシア・デュポア(ea3844)とサイラス・ビントゥ(ea6044)がやってきた。
「お待たせ。テント積むのに意外と手間取っちゃって‥‥どうしたの?」
「ううん、なんでも」
何やらひと騒ぎあった様子に首をかしげるアルテミシア、籠を抱えたまましれっと答えるユリア。こほんと源真霧矢(ea3674)が咳払いをして、まあ何や、と話題を変えた。
「全員揃ったみたいやし、そろそろ出発しよか」
「うむ、いつでも良いぞ。今日は実に体が軽いのだ」
サイラスが鷹揚にうなずき、それが出発の合図ということになった。各々が荷を持ち、あるいは愛馬の手綱を引いて、街の門のある方向へぞろぞろと歩き出す。
「なんか嫌な感じの雲だよね。降らないといいなあ‥‥」
「せやなー。雨にしろ雪にしろ、降り出すと足が鈍るし‥‥早う届けんと、松の内が終わってまうわ」
「新年の贈り物か‥‥今度私も息子に‥‥いやいや、成人するまでは」
「‥‥サイラスさん‥‥息子さんって‥‥インドゥーラに、いらっしゃるのでは‥‥?」
「うむ、今八つのはずだ」
「‥‥成人って、新年そうそう何年先の話なのよそれは」
冒険者たちはそれぞれ吐息を白く染めながら、他愛もない話を始めている。その最後尾で、ブルーは寒そうに防寒着の襟をかき合わせ、一人孤独な呟きを落とした。
「ああ‥‥肉球‥‥」
気持ちはわからなくもないが、少々おとなげない。
目的の方向にはなにやら灰色の怪しい雲が出てはいたのだが、一日目はどうにか天気が保ってくれたらしい。街道からあまり離れていない場所に、大きく枝の張った木を見つけたので、とりあえずその日はその下で野営することにした。アルテミシアやサイラスがテントを持ってきてはいるものの、頭上からの雨露は少ないにこしたことはない。夜の間に雪でも降れば、積もった雪でテントが倒壊する危険もあるからだ。
「とりあえず、最初の見張りはアミィ殿とアルフレッド殿‥‥あとはユリア殿に頼もうか」
「わたくしもですの?」
サイラスに名前を呼ばれアミィ・エル(ea6592)が眉をひそめると、九紋竜桃化(ea8553)が軽く彼女をたしなめた。
「見張りは大事な役目ですわ。いかな手練であろうと、眠っている間は無防備ですもの」
「ギルドの話では、このあたりにはオークが出そうだということでしたしね」
ブルーもその意見に賛成する。
「ええ。いざというとき、敵襲を察知して仲間を起こせる者がいなくては、たやすく全滅してしまいます。それに冬の野営は、火があったほうが皆ゆっくり眠れます。焚き火の番をする者が必要なのですわ」
侍として兵法に長けた桃化の言には説得力がある。アミィは軽く嘆息して肩をすくめた。
「仕方ありませんわね。そうまで言うなら、見張り番を引き受けてさしあげてもよくってよ」
「ありがとうございます」
アミィの返事に桃化が嫣然とした笑みを見せ、他の見張りの順番を決めていると、薪を拾いに行っていた霧矢が戻ってきた。
「しかし、やっぱり冬はあかんなあ。食いもんの確保が難しいわ」
薪拾いのついでに夕飯に手頃な兎か鹿でもいないか探したらしいが、冬だけあって動物もそうは姿を見せない。春や夏なら探さずとも見つかる野生の香草も目につかず、その夜の夕食は冒険者御用達の保存食だけということになった。野営の間の味気ない夕食に皆慣れてはいるが、やはりなんだかわびしい思いである。
「なんかこの仔のほうが、手間のかかったもの食べてるわよねえ」
一方の子猫のほうは、霧矢の提案で、細かくちぎった干し肉を温かいミルクでふやかしたものを食べている。アルテミシアの言葉も無理はないのだが、さすがに自分も猫の餌を食べようという者はいないようだ。
●二日目
夜半から小雨がちらつくようになり、明け方頃にそれは雪に変わった。頭上の枝ぶりのおかげで焚き火が消えることはなかったが、アルフレッドが起きだす頃には、三番目の見張りに立っていたアルテミシアと桃化の髪に霜が降りていた。
「おはようございます‥‥。見張り、ご苦労さまです‥‥」
「おはようございます。よく眠れましたか?」
桃化の言葉に、アルフレッドが曖昧な表情を見せる。
「それが‥‥ゆうべは冷え込んで‥‥なかなか寝入ることができなくて‥‥」
「まあ。大丈夫ですの? お風邪を召されますわよ」
今は真冬。テントに入ってさえいれば夜を過ごせるような、生易しい気候ではない。焚き火の周囲にテントを張るのは当然として、せめて自分の毛布、万全を期するなら寝袋と毛布の両方を用意しなければ、安眠というわけにはいかないだろう。
「私ももう寒くて寒くて凍えそうで眠れなかったわよー。暖めてクリスティっ」
愛馬の鼻面に抱きついてほおずりしているアルテミシアも、今回寝具を用意しなかったためあまり眠れていない。おまけに明け方のいちばん冷える時間帯の見張りに割り当てられたため、唇が紫色だ。重いテントを運んでくれるアルテミシアのクリスティやサイラスのヴァリトラなど、馬たちのために燃やしている火に、見張りの間はそれこそかじりつくようにして当たっていた。
「猫さんは‥‥大丈夫ですか?」
アルフレッドが女性陣のための天幕に声をかけると、ちょうどその猫の鳴く声が聞こえてきた。中にいたユリアが布をめくって顔を出し、子猫がテントから出てよちよちとテントの裏側にまわっていく。その様子を見ながら、桃化が首をかしげた。
「放っておいてよろしいんですの? ユリアさん」
「大丈夫だと思う。依頼人さん、下のしつけだけはしてくれてたみたいで助かったよ‥‥」
なにしろ、閉め切ったテントの中で粗相をされてはたまらない。
朝食を済ませたあと火の始末をしても雪はやまなかった。最初が雨だったので地面が湿っており、積もる気配は今のところない。降りが激しくなるようならば明るいうちにどこかで休もうと決めて、ひとまず出発した。
この日は、猫を毛布にくるんで抱いていくことにした。籠は金属製なので、こんな日は見ているだけでも寒々しい。もちろん逃げられてはいけないので、抱いているあいだは決して目を離さないように‥‥という取り決めが行われた。
「今のところ積もる気配はないが、もし雪の上を逃げられたら見分けがつかんからな」
とりあえず目印がわりにと、サイラスの無骨な指が猫の首にレインボーリボンを結ぶ。
「女の子かどうかはわからんが‥‥」
「あぁら。まだ確認していなかったんですの? その仔、オスですわよ」
ゆうべは子猫と一緒のテントで眠ったアミィが、呆れたような顔でサイラスを見る。
「なに? それはいかん、やはり外したほうが‥‥」
「いいじゃありませんの、嫌がってるわけではありませんし。ほら、可愛らしいですわ」
桃化の言葉通り、首に結ばれたリボンを嫌がるでもなく、子猫は見下ろしてくる人間達を不思議そうに見返していた。仕方があるまい、とサイラスがかぶりを振る。
「それでは、まずどなたが抱いていきますの?」
「あ、じゃあ、僕が‥‥」
「‥‥ブルーさん‥‥。くれぐれも、構いすぎないように‥‥」
アルフレッドに念を押されたものの、念願の肉球でてのひらに触ってもらってブルーは満足そうだ。
行程を進んでいる間に、頭上から降りてくる雪はだんだん小降りになってきたようだ。相変わらず積もる様子はないが、地面があちこちぬかるんでいるので馬たちの歩みは遅い‥‥そろそろ夕方になり、どうやら大幅な遅れにはならずにすみそうだと皆が安堵していた頃、周囲に警戒しながら進んでいたアミィが、はっとした顔を見せ弾かれたように身を低くした。
「お伏せなさい!」
意味を理解するより早くとっさに伏せた一行の頭上を、ぶうんと低い唸りを上げて何かが飛び去っていく。一体何がと目で伺った先、ひょろりと立った細い木の幹に、木っ端を飛び散らしながら錆びた手斧が斜めに突き刺さった。
街道の両側、繁みをがさがさと慣らし、でっぷりと肥った巨体がいくつも飛び出してくる。
「オークだよ! 皆、気をつけて!」
ユリアが叫ぶと同時に、身を起こした霧矢や桃化が刀の鞘を払う。ブルーから子猫を受け取ったアルフレッドが、その体を抱いて‥‥体が重くて飛べないのに気づき、脱ぎ捨てようと重い防寒服の前を開いた。その間に道の両側からオークたちが迫ってくる。
アルテミシアの放った矢がオークの一体の足元に突き立った。本当は足を狙ったのだが、睡眠不足で昨日の疲れが残っていて狙いがうまくつけられないらしい。その反対側からやってくる群れの先頭めがけて、まだ伏せたまま詠唱を始めていたユリアのコンフュージョン。魔法をかけられたオークの勢いがゆるみ、呆けたように口を開けたまま他のオークに次々と追い越されていく。
接敵する頃には前衛組はすでに準備を終えている。
また別の方向から飛んできた手斧を、今度は桃化の盾がかるがるとはじいた。盾を持つのはジャパンの剣術としては邪道だが、このさいあまりなりふり構ってはいられない。振り下ろされた剣を半身になってかわし、オークの鼻面を容赦なく切り伏せる。かたい毛皮の表面を浅く斬りつけられ、血の珠を地面にこぼしながらオークが反撃してきた。かわしきれずに肌が裂け、血が着物ににじむ。次ぐ攻撃を盾で受け止めると、半分錆びてぼろぼろになった剣の重みががつんと腕に伝わった。
猫を預けたブルーが武器を手に駆けていくのをよそに、アルフレッドがようやく防寒具を脱ぎ終えた。まだ雪のちらつく冬の空気は震え上がるほど冷たい。ぎゅっと猫の体を抱きしめて、上空を目指す。
前衛を担える者は計三人だが、オークの群れはそれより多い。魔法使いであるユリアやアミィのほうにも当然お鉢が回ってくる。サンレーザーを唱えようとして、夕方にはその魔法は使えないのだと気づきアミィは舌打ちした。ダガーを抜く。
「むんッ!」
アミィが身構えるより早く、彼女の背後にいたサイラスの低く鋭い気合の声が響く。ぶうん、と振り回された杖の先端は狙いを過たず、鈍い音をさせてオークの横っ面をしたたかに殴り飛ばした。ジャイアントの彼は、アミィよりユリアよりずっと背が高い。
「悪霊、退散ッ! 喝!!」
ふたりの頭上を、岩のような拳が唸りながら通過する。出会い頭の一撃でふらついているオークにかわす術などなく、数珠を握りこんだ拳は、豚に似た鼻先を見事に叩き潰した。続くアルテミシアの矢、ユリアのムーンアローがその体を次々と貫いて、どうと地を揺らしオークが轟沈する。サイラスが軽く瞑目し、重々しく告げた。
「これぞ、『物理的退魔の法』である」
ただのパンチだ。
一方の霧矢は、オークの攻撃を刀でするりと流す。こちらの相手の得物は短剣。毛皮が分厚くて刀ではなかなか思うように傷を与えられないが、間合いの関係上向こうは接近しなければ攻撃できない。ライトニングアーマーの雷は、向こうがこちらに近づくたびに着実にダメージを蓄積させていく。向こうの攻撃につかまらないよう充分注意して、持久戦に持ち込めば勝ちは確実だ。
ぎぃん、と重い音が響き、桃化が相手の得物を跳ね飛ばす。
「示現流の技の冴え、その体でしっかり覚えていただきますわ」
ふ、と唇に軽く笑みを形作った女は、そのまま鋭い呼気を吐き出して走った。
渾身の力で突き下ろされた刀は、オークのでっぷりとした体を一直線に串刺しにした。半数以上を倒されオークたちが身を翻して逃げていったのは、この直後のことだ。
●三日目
魔法薬で傷を手当てしたあとは、特に何事もなく旅を続けることができた。雪は襲撃のあった日の夜にやみ、翌日は快晴。子猫を元の籠におさめて、無事村に到着した。目的の家を訪れて事情を説明すると、くだんの甥らしき男の子が玄関まで走ってくる。
「おっほっほ! この程度の依頼、わたくしには物足りないくらいですわ」
「おばちゃん、猫持ってきてくれたんでしょ!? どこどこっ」
「おば‥‥!?」
実年齢はどうあれアミィは外見は若々しい姿をしているので、面と向かってそんな言葉を浴びせる命知らずはそうはいない。思わず固まったアミィをよそに、どうぞ、とブルーが籠を差し出した。
「わあ、かわいい! ありがとう、冒険者のおばちゃん!」
「‥‥あの、アミィさん。子供のいうことだから」
ユリアがなだめる科白をかけ、アルテミシアは馬にするようにどうどうと背を叩いている。アミィは軽く深呼吸して、そうですわねと理性の証にひきつった笑みを浮かべた。
「いいかしら? わたくし達がこのプレゼントを届けるのに、どれだけ苦労したかあなたにおわかり?」
それでも言わずにはおれず、アミィは軽く息をついて少年に念を押した。
「その猫を大切にしなかったら、このわたくしが承知しま‥‥聞きなさい!」
まだ年端もいかない子供は見も知らぬ『冒険者のおばちゃん』のことなど構っていられず、籠の中で丸くなって眠る新しい家族をにこにこと眺めている。
歯噛みするアミィを抑え、ものはついでと子猫のためにマタタビを置いて家を辞去したあと、冒険者たちはパリへと一路戻った。帰りはなぜか天気に恵まれ、行きのあの苦労はなんだったのかと冒険者全員が肩を落とすことになる。



