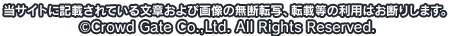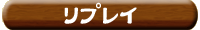 武闘バカ一代
武闘バカ一代
 |
■ショートシナリオ担当:小沢田コミアキ 対応レベル:1〜3lv 難易度:易しい 成功報酬:5 参加人数:6人 サポート参加人数:-人 冒険期間:09月19日〜09月24日 リプレイ公開日:2004年09月29日 |
|
●オープニング
7年前――。俄かに黒雲が沸き起こり空を染めた。
ドサアッ!
「起きろ!」
怒声が板張りの稽古場を揺るがし、呼応するように遠くで雷鳴が鳴り響く。
「‥‥!‥ぅ‥」
「いつまでそこに転がっているつもりだ。その体たらくでは我が瑞峰流を継ぐこと断じて許さんぞ! さあ、立て!」
稽古着姿の男が、まだ年端も行かぬ少年を見下ろしている。
「こんなん続けンのに何かイミあんのかよ! 答えろよ親父!」
「親父ではない、師匠だ。もはや貴様を息子だなどとは思っておらん。さあ、立て。稽古はまだついておらんぞ」
二人は父子だ。武芸、技芸、遊芸、ありとあらゆる芸の道は険しく厳しい。師弟の契りは肉親の絆よりも重い。師が拳を握る。
「貴様には我が技の全てを叩き込む。いずれこの瑞峰流を継ぎ、行くゆくは天下に並ぶところのない‥‥」
そこで不意に師は言葉を止めた。稽古場に雨まじりの強い風が吹き込んだ。振り返るとそこには黒衣に身を包んだ背の低い男が立っていた。一見すると単身痩躯の風にも見えるが、硬く引き締まった筋肉は鋼を連想させた。それが雨水に濡れ、黒く光っている。
「誰だ貴様は」
突然の訪問者はその言葉には答えずに稽古場を一瞥し、次に師を値踏みするように足先から視線を泳がせると、やがてこう口を開いた。
「その無骨な筋肉の鎧、だが硬さだけでなくしなやかさをも持ち合わせた体躯、流れるように柔らかな所作の中にも凛とした強さを芯に持つ身のこなし。さぞや高名な武闘家とお見受けする」
男の頬を伝った雨水が顎から転々と床を濡らしている。男は荷物をその場に投げ捨て、拳を掲げた。
「我はこの拳で九十九の武芸者を屠ってきた。同じ武闘家として立会いを所望する」
「何か勘違いをされているようだが、伝統と格式ある瑞峰流としっての狼藉か。ここはそのような血塗られた拳を振るう場ではない。無論、君と立ち会おう気などこの私にはない。お引取り願おうか」
眉根を寄せ、師が男を無言の視線で睨めつける。少年が不安げに二人の姿を見守っている。再び雷鳴が響き、男が唇の端で笑った。
「フン、ならばその気にさせるまでだ!」
先を打って蠍のように鋭い拳突きが繰り出された。虚を突かれ、重い拳が師の胸を直撃する。
「さあ立て、これでも立ち会う気はないとでも言うか? 貴様の拳は飾り物か? 磨いたその技は只の踊りか??」
「待て‥‥わ、私は‥‥」
「せめて最後は武闘家らしく往かせてやろう」
苦しげに吐き出した師のその声を襟首ごと締め上げて殺し、男は再び拳を握った。先までとはまるで違う握り、ぴったりと狙いを定めて心の臓を抉ろうとするように二本の指を突き出した異様な型だ。男が動いた。
「お、親父‥‥‥‥やめろ――ッ!」
絶叫と雷鳴とが交錯する中、差し込んだ稲光に照らされ電光の四連突き。大きく肢体が跳ねたかと思うと、師の体は冷たい稽古場の床板に打ち付けられた。
「ほう。お前、この男の息子か」
急所を射抜かれてうめき声をもらす師を足蹴にし、男が振り返った。
「お前では敵わぬ。やめておけ。武の道を志す者ならば実力の差は分かるだろう」
「な、何を言ってやがんだよ手前ェ‥‥」
そう口にした少年の声は震えていた。
「立会いとか只の踊りだとか武の道だとかってよォ?‥‥わ、ワっかんねぇンだよ。そんな拳振るったからって何になンだよ! 俺には関係ねぇ。チクショ‥‥何か答えろよ手前ェッ!」
「‥‥十年に一度、天下一の技芸者を決めるという武闘会が開かれるという話を耳にしたことがある。我もまた武を志す者。同じ道を歩む者同士、いずれ会うこともあろう」
踵を返し男は稽古場を後にした。その背を雨が打ち、呆然とそれを少年が見詰めている。ふと、男が振り返った。
「そう、いずれお前は再び我の元に現れるだろう。待っているぞ、お前が強敵となってこの前に立ちはだかるのを、この我の――父の敵のな!」
その言葉を耳にし、雷に打たれたように少年は父の元へ走り寄った。だが抱え起した父の体は重く、動かない。雨の降りしきるその音がざあざあと、ただ鳴り続けていた。
「親父? おゃ‥‥‥‥親父ィ――――――――ッ」
そして、雷鳴が木霊した。
「ちょうど、七年前の今頃のことでした。先代は男の拳で命を落とされ、二代目は家を出てしまい、以来行方が分かりません」
ギルドに依頼を持ちかけた男は瑞峰流を名乗った。先代の息子と共に技を習った弟子であるという。
「ほー。で、あんた一人でこれまで。そりゃスゴイね」
「はい。私がこの道を続けていれば、いつか必ず先代の敵にも出会えるとその思いでこの七年間ひたすらに芸を磨いて参りました。そしていつか二代目がお帰りになられる時に立派に我らの流派をと。しかし‥‥」
悔しそうに体を震わせて男は包帯に包まれた右腕を差し出した。
「男の口にした大会は、とある流派が他流を交えて実際に行っているものです。私もこの瑞峰流を代表して出場する予定でおりました。ですがこの腕では」
「で、代わりに我々にその大会に出場して欲しいと。心配御無用ってな? なに、冒険者にもイロイロと変わった技に長けた奴もいる。で、日時は?」
「あーっと、ちょっと待って。こっちに資料があるから」
別の冒険者がその問いに代わって答えた。パラパラと紙の束を捲り上げ、顔を顰める。
「んー、マズイわ。一週間とないね。今からで人が集まるかなー」
「どうか、お願いします。金子は経費分しかご用意できないのですが‥‥その代わりといっては何ですが、優勝の暁には賞品をそっくりそのままお渡しします。あ、いえ、由緒ある大会ですから賞品といっても然るべき所に出せば十数Gの値はつく代物ではと」
「「お受けしましょう!」」
二人の冒険者が声を揃えて頭を下げ、そして顔を見合わせる。
「あ、有難う御座います!!」
「早速その大会のことなんだけど」
「はい。大会では5人ずつの予選が行われて本戦へ独楽を進める4人が決められ、その後は勝ち残り戦となります。勝敗を分けるのは技の切れ。一朝一夕にとは行きませんが、我が流派の看板を背負って戦うにはせめて最低限の修練は――」
「で、何?」
「は?」
「報酬だよ、報酬。その賞品って、ナニ?」
「あ、それなら」
男に代わってもう一人が答えて言った。それならこっちに書いてあったよ。えーっとね‥‥
「扇」
瑞峰流の舞いの要諦は、みずみずしさを現す「瑞」を支える「峰」の字の雄々しさにある。雅で柔らかな一つひとつの動きの中にも、しなやかな力強さを内に秘める凛とした美しさこそが瑞峰の舞踏。
志半ばに倒れた先代家元の夢を継いで瑞峰の名を天下に並ぶところなきものとするため、天下一を決めるこの大会、避けて通ることは出来ない。並居る舞踏家を押し退けて、見事、勝って瑞峰流の名乗りをあげよ。この際踊れないことは気にするな!
●今回の参加者
ea1636 大神 総一郎(36歳・♂・侍・人間・ジャパン)ea6381 久方 歳三(36歳・♂・浪人・人間・ジャパン)
ea6437 エリス・スコットランド(25歳・♀・神聖騎士・人間・イギリス王国)
ea6656 ラヴィ・クレセント(28歳・♀・ジプシー・人間・エジプト)
ea6923 クリアラ・アルティメイア(30歳・♀・クレリック・エルフ・イギリス王国)
ea6977 ヨシュア・グリッペンベルグ(47歳・♂・ウィザード・人間・ロシア王国)
●リプレイ本文
「違う違う、そうじゃない‥‥!」「もっとそこの動きはメリハリをつけて伸びやかに‥」
「拍子が遅れてます、もっと音を良く聞いて、そう、その調子で――」
「ってそれじゃダメですー! ‥‥‥っああぁ‥」
先代のお弟子さんの気が気でない様子で見守る中、予想通り予選敗退を決めて久方歳三(ea6381)が早々に戻ってきた。
「まあ所詮は付け焼刃でござるからな」
薄く汗を滲ませたその笑顔が爽やかで、手習いとして舞うのならそれでも良かったかも知れないが依頼主としてたたまったものではない。数日の稽古では上辺の動きを真似るのが精一杯といったと所だ。他に集まった冒険者達も似たり寄ったりで、既に勝ちは諦め観戦を楽しむといった雰囲気になりつつある。
「はわー。ぶとーですよー」
クリアラ・アルティメイア(ea6923)も次々と披露される舞いに見入っていた。
「まあそれはさておき、頑張りますよー。踊りを頑張る人は、大いなる父様のおっしゃられる賢人さんですよー。応援するですよー。はいー」
「って、クリアラさん。さっきから何を食べておられるんですか」
依頼主に怪訝な顔を向けられ、何やら果物を無心で口に運んでいたクリアラが思い出した様に手を止めた。
「知らないんですか? 葡萄ですよー、依頼主さん」
史実に照らすと栽培ブドウの伝来は12世紀の初め頃、中国からだとされる。葡萄の歴史は古く、欧州では紀元前三千年以上にも遡る。月道の存在するAFO世界におけるジャパンでの受容の過程を考えれば、知名度に置いてはたとえば現代ではモロヘイヤの様なものだったとも考えられる。
「いや、そういうことではなくて‥‥」
「それはさて置き、気になるのは、その腕ですよー」
瞬く間に一房を平らげてしまうと、依頼主の腕を取ってクリアラが彼の目を覗き込んだ。
「練習中に折ったとかなら良いですけれどぉ、もし誰かの妨害とかなら、私も他の皆さんも危険ですよー?」
「あ、いえ。これは稽古場の掃除をしている時に私の不注意で」
「つまりー、稽古場の掃除をしている時に敵の妨害により不注意でやってしまったんですねー?」
何かを言い掛けた依頼主はサックリ無視してクリアラが腕をまくる。
「ここは一つ、その真相を探りますよー」
どうもすっかりその気になってしまった様だ。
「踊るだけじゃつまらないですしー」
「思わず本音が漏れちゃってる気もするでござるが、先代の仇探しを兼ねて拙者も協力するでござる」
衣装を脱ぎ捨てて身軽になった久方がそれに並び、二人は肩を並べて会場の裏手へと消えて行った。
「ダンス大会ですピョン。踊って踊って、優勝して、お宝ゲットだピョン」
遠く海の向こうエジプトに生を受けたラヴィ・クレセント(ea6656)はジプシーとして放浪し流れてきた先の日本で神楽の舞と出会った。この神秘的な東洋の舞い姿に好奇心旺盛な彼女が惹かれぬ筈はなかった。以来彼女は神楽の修練を積み、遂には神楽舞を生業とするに至ったのだった。
「だから、ウチは伝統の神楽の舞を披露するです」
「‥‥いや、ちゃんと瑞峰の舞を踊るでござるよ」
「あ、それからウチの語尾がおかしいのは、アラビア語の方言なのですピョン」
「って、なんでそこで目線逸らすんですかー」
腕前はともかく早くもがっかりムード漂う瑞峰陣営。とまあラヴィと久方達が賑やかにやっていると、そこへやって来たのは他流の家元。
「瑞峰も落ちたものですな」
「何!?」
「先代が亡くなり二代目も行方知れずと聞いておりましたが、どこの馬の骨とも知れぬ異国の娘を出してくるとは、余程人材に欠けると見える」
値踏みする様にラヴィ達を一瞥すると、癇に障る物言いで吐き捨て男が踵を返した。
と、その時。
畳み掛ける様な鼓の音が響き、その拍子に合わせて一人の若武者が舞台を舞っていた。しなやかに張りのある凛とした動き、動から静へ、そしてまたその逆へ。緩急から伸びやかに舞うその舞い姿は幽玄でありながら瑞々しい力強さに溢れている。
(「私は私の舞を――いざ」)
彼は、能役者の家に生まれ時期家元として育てられた。大神総一郎(ea1636)、齢二十五にし神楽舞として舞の道を歩む。瑞峰流の舞いに乗せて踊るのは堂々たる己自身の舞い。基本を準えた動きの一つひとつを貫くのは静謐さ。その身に纏う一種荘厳な佇まいは天性のものだ。いつの間にか誰もが言葉を失いそれに魅入っていた。
いま、鼓の音が再び激しさを増した。舞いは最高潮を迎える。総一郎はひたすらに音曲に乗せ自らを舞わせている。其処には天地の境も無であり唯、理があるのみ。舞いの動きに身を委ね、心をも委ねる。舞台の上で、役者はただ踊ることで己を離れ舞いそのものになるという。言わば舞に埋もれることで人は神に近づく。
総一郎が両手を広げた。足先を僅かに開くと、能装束が重く揺れる。そして。ゆるりと体を回し、音曲が止み、やがて総一郎は動きを止めた。
ぱち ぱち ぱち
「なるほど、切れのある良い動きだ。相当修練を積んだと見える」
余韻引けやらぬ会場に手鼓の音がこだまし、皆が一斉に振り返ると会場の入り口に男が一人立っていた。
「誰だ、お前は」
その問に男はニィと笑い、外套を投げ捨てた。その下に現れたのは胴着に纏われた傷だらけの肢体。
「帰りなさい、ここはお前の様な者の来る場ではありません」
他流の家元の言葉に従って制止に入った門下生達を振り切って男は一人を鮮やかに打ち倒すと、会場を見渡して一喝した。
「武の頂点を決める場だと聞き及び足を運んでみればこの様はなんだ。型をなぞることばかりに捕らわれ、強さがまるで伴っておらぬ。貴様らのやっていることは、ただの踊りだ!」
その一言に思わず会場中が唖然となった。その中で、家元がふるふると身を震わせている。
「ただの踊りとは聞き捨てならんぞ‥‥! 強さだけでなく、繊細さや優雅さや備えてこそ舞にあわれや情けといった機微が表現できるのだ」
「武に情けは無用! 武闘に求められるのは、躊躇いなく敵を屠る冷徹さだ!」
「ええい、お前のやっているのは舞踏ではなく、武道だ!」
家元が遂にその一言を言い放つと、男は漸く気がついた様に、場違いなものを見る周囲の視線を眺め渡した。そしてその目が最後にクリアラの元に留まる。
「‥‥へ? 私ですかー?」
きょとんとしながら、クリアラが思わず葡萄を口に運ぶ。
「――我を愚弄するか! 我の技など、日ノ本に入ってきた外来種の様に、華国の技を真似ただけの内実の伴わぬ種無しブドウ同然とぬかすか!」
「ちょっと待って下さいー。葡萄を馬鹿にしてはいけませんよー! 葡萄には四千年以上の歴史があって一般に言う中華三千年よりも一千年も重みがあるのですー」
口に葡萄を頬張りながらクリアラが力説しだすと、これ以上ややこしくなられては困ると見兼ねた久方が割って入った。
「いろいろ勘違いがある様でござるが、我々のやっているのは『舞』、貴方の言っているのは『武』でござる」
今度こそはっきりとそう口にすると、男の目を見据えて久方は言い放った。
「そして、確かに『舞』には『武』に通じるものがあるでござるが、貴方の『武』には『舞』がないでござる!」
「なにィ‥‥ここで戦わば、我の武には分がないと言うか!」
「えーい、話が噛み合わないです‥‥もう黙るピョン!」
とうとう我慢の限界に達したラヴィが絶叫する。どこから取り出したのか鞭で床板を叩きながら彼女は人差し指で男を手招き、挑発した。
「とにかく、何でもいいから早く決着をつけるですピョン。それとも舞台に昇る度胸もナイですか? 期待外れでーす」
「小娘めが‥‥分かった、いいだろう。全員まとめて我が武で屠ってくれるわ!」
「「「こいつ分かってねー!」」」
男が身を屈め攻撃の構えを見せ、咄嗟に久方が腰のものに手を掛けた時だった。傍に立っていた行灯から突如として炎が吹き上がり舞台を赤く染めた。咄嗟に男が飛び退き、守りの構えを取る。火炎の舌先が男の肌を舐め赤く皮膚が爛れている。すらりと空を切って、そこへ刀を手にした総一郎が舞い躍り出た。切っ先を水平に滑らせ、そして双眸を閉じ硬く動きを止める。厚い能装束の下で力強く筋肉を震わせ、それに炎が呼応して揺れる。やがて総一郎が目を開いた。剣舞だ。
視線の切っ先が男の双眸を捉えていた。あくまで“舞う”姿勢を貫くことが自らの勝利だと言う様に。睨み合いが続き、両者は動けない。炎が揺れた。影が瞬き、その虚をついて刃の切っ先が男の喉を抉る様に総一郎と共に舞った。だがその動きでは男の先を取ることは出来ない。既に敵は迎撃の体勢に入っていた。
「ぶとーの達人のしなやかな動きはぁ、まるで腕が伸びている様に錯覚させる事さえあると聞きますしー。はいー」
錯覚ではなくクリアラのミミクリーで本当に伸びてる訳だが、どこからか伸びてきたそれが男の背を打ち、注意が逸れた。
「‥‥大会規則的には良いんでしょうかねぇ、こういうのー?」
ダメだと思う、たぶん。
「さて」
男の背に回った総一郎は、喉元へ刀を押し当てて囁いた。
「お前の負けだ。勘違いを認め、悔いるがいい」
「完敗だ。何と無様な思い違いよ」
そう言うと男は素早く身を屈めて体を入れ替え、総一郎から逃れた。
「この程度の武で功が成ったなど我は思い上がっていたのか。だが、次こそは更なる修練を積み打ち勝って見せる!」
それ切り男は会場を走り去り、会場に残された皆は呆然と呟いた。何だったんだアレ、と。
「何だったんだ、アレ」
魔法で操った炎で咄嗟に総一郎を援護したのはヨシュア・グリッペンベルグ(ea6977)だった。総一郎を有名にしたいが為勝手に出場させた彼はお返しに急遽エントリーされる羽目になっていたのだが、この騒ぎで何だか依頼は有耶無耶になった様で彼は内心ほっとしていた。
「私は出場の予定ではなかったのだが‥‥おかしいね。まぁ、よしとしようか」
なぜなら彼、この中で唯一踊れないからだ。役目を終えヨシュアはそっと会場を後にしようとする。が、その背を呼び止める声が。
「お、ヨシュア殿。これから出番でござるか? 優勝目指して頑張るでござるよ」
「も、もちろんだ」
自尊心の高い彼からすれば踊れない事を人に知られるのは到底許せない。ヨシュアは他の参加者の動きをそれらしく真似て舞台に足を進めるが、その先までは続かなかった。久方の期待の視線を受けつつ、彼は音楽に身を任せて何となくゆらゆら身体を動かして見たりする。
「音に乗り身を音に委ねる‥‥これこそ舞の本髄」
「「「おおおお‥‥!」」」
が、上がった歓声は彼にではなく、もう一人の冒険者に向けられたものだ。まだ踊り続けていたラヴィが舞装束を脱ぎ捨てたのだ。
「楽しくピョンピョン踊るです!」
「というか、ラヴィ殿、まだ踊ってたんでござるか‥‥?」
その下から出て来たアラビアの踊り子の衣装に手早くウサミミの髪飾りをつけてラヴィは軽快に飛び跳ねている。突如現れた欧風ウサギ娘に会場萌え萌え。審査員も萌え萌え。
「しかも優勝してるしー」
当時まだ雑多な芸能を内包した身分化な技芸であった能は、この『萌え』の要素を導入した新しい音曲を志向し後に民間芸能からの脱皮を図ることとなる。更にこの百数十年後に、卓越したろりぷに感を持った観阿弥の登場を待って遂に芸術性を確立し、日本の伝統芸能である能楽として成立する。
「以後、能楽は世阿弥の様式を踏襲し、やがて今日の『萌え』の隆盛へと導くのだった――」
「って勝手に適当なナレーションしないで下さい」
思わず突っ込んだラヴィだが語尾からつい『アラビア訛り』が抜けている。クリアラが彼女を覗き込んだ。とりあえず目を逸らすラヴィ。
「下さいー?」
「‥‥ピョン。」
結局大会はなし崩し的に閉会となり、集った舞の諸流派も思想の相違から決別、賞品も優勝者も有耶無耶のままとなった。その後のAFO世界における能楽と萌えの歴史が実際はどうなったか我々の知る所ではないが、風の噂で聞く所によると男は己の技を究めるため後に華国に渡り中華舞踊を修めたのだとか。