 日に焼けた手紙
日に焼けた手紙
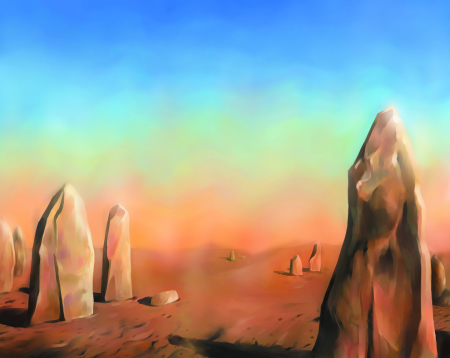 |
■ショートシナリオ担当:白樺の翁 対応レベル:1〜5lv 難易度:やや易 成功報酬:1 G 35 C 参加人数:6人 サポート参加人数:-人 冒険期間:05月01日〜05月06日 リプレイ公開日:2005年05月09日 |
|
●オープニング
日中は今日も暖かい。その日、ギルドの門を潜ったのは、16〜17才くらいの、目の大きな快活そうな女性と老人の2人連れであった。
老人は恐ろしく年をとっていて、どのくらいの歳なのか想像がつかない。
「カスト孤児院に勤めてます、メリー・ドローワといいます。 いつもお世話になってます!」
大きな声で女性はそう言うと、老人の足取りに気を使いながら受付までやってきた。
「こんにちわ」
「あの、このお爺ちゃんが、人探ししてるんです。お願いできますか?」
メリーは、老人の荷物をもってやり、肩を支えてやる。
「誰をお探しなのでしょう?」
その言葉に、老人が沢山のしわの中に隠れた瞳を見開いて、なにか呟いた。
「え?」
聞きなれない言葉である。
「あー、あのね、アラビア語らしいんです。カスト院長の昔の知り合いの船長が連れてきたんですけどね。 ちょっとまって」
メリーはメモらしいものを出すと、そこに書かれていることを読み出した。
「老人の名前はハーゼ、探してほしい人はホレー・バロウズ、老人が10歳の時に頼まれた手紙を渡してほしいらしい」
「10歳?!」
「ええ‥‥ で、バロウズはガンタレーという貴族の依頼で、エジプトに秘宝を求めてやってきていた冒険者だったらしいね」
「エジプト!」
呆れた依頼である‥‥そんな昔の、そんな遠方からの手紙を、どうやって送り届けるつもりだったのだろう?
「それがね、このお爺ちゃん10歳の時に故郷を出発したんだけど、船が遭難したり、奴隷商人に捕まったり、鉱山で働かされたり、無人島に流れ着いたりで‥‥ 今までかかっちゃったんだって」
「そうなんですか‥‥」
本当だろうか? 本当だとしたら、ぜひとも人生をかけた使命を果たさせてやりたいところである。
「手紙はリドっていう、エジプトの遊牧民のお姫様かららしいですね」
「お姫様ねぇ」
ハーゼ老人は、このリドという単語を聞くと、何かまた呟き、懐から大事そうに包みをだして、カウンターの上においた。
「なんですか? これ‥‥あっ!」
受付の目の前で包みは解かれて中から小さめの髑髏が出てきた‥‥。
「も‥‥もしかしてリド‥‥姫様?」
老人は深々とうなずいた。老人が子供の時の話である‥‥うら若き姫君も、こうなってておかしくない。
「ああ、そうだ手紙はアラビア語じゃないんです 手がかりになるなら読んでも良いって」
マリーはそう言うと、荷物の中から手紙を取り出し、老人に一度見せてから、受付に手渡した。
「えーと、ああ、たしかに読めますね。リド姫からホレー・バロウズ宛になってますね‥‥」
手紙にはまず、砂漠の太陽のような、熱烈な愛情表現が書きつづられている。
バロウズはどうやら、副隊長ナーマンの裏切りで、手に入れた財宝、全てを奪われ、砂漠に置き去りにされたらしい。
その窮地を救ったのが、土地の遊牧民の姫君リドだったようだ。
ハーゼ老人は、その時の道案内の少年だったらしい。
手に入れた財宝は、この遊牧民の先祖の墓で、バロウズは自分の行いを悔いて、財宝を取り戻し、本当の持ち主の手に返す約束をしていたようだ。
しかし、遊牧民のもとで健康の回復を図っている間に、ノルマンでは状況が一変した。
財宝のあまりの量に目が眩んだ雇い主ガンタレー卿が、ナーマンを殺し財宝を独り占めしてしまったのだ! そして、なんとその犯人としてバロウズを手配した。
「酷い話ですねぇ」
マリーも厳しい表情でうなずいた。
バロウズは、名誉の回復と、財宝の奪還のため、リドのもとを旅立った。
ところが‥‥1年たって、とある貿易商人がバロウズの噂を持ち帰った。
彼は港で捕まり、公式な場に姿をあらわすこともなく、ガンタレー卿の館の地下牢に繋がれていると言うのだ‥‥。
「そして‥‥ 姫はいても立ってもいられなくなって、ハーゼ少年を連れて地中海を渡ったんでです」
手紙を読み終えた受付に、補足するようにマリーが付け加えた。
「この手紙はいつ書かれたのです?」
「ええ、航海の途中で姫は病気になって、手紙を書いて少年に託したみたいです‥‥心残りだったでしょうね」
マリーは老人の肩を撫でながら、目に涙をためている。
手紙には、ナーマンが殺害された日に、バロウズがノルマンにいなかった事を証明するリド姫の一族と周辺4部族長の連判の署名が同封されている。
また、奪われた財宝の目録や返還を要請した文章などもある。
「きっともう、財宝とかは売り払われてしまって、返還は無理だと思うんですよ。バロウズさんだって生きているかどうか‥‥ねぇ。でも名誉の回復はできるんじゃないかと思うんです。お願いできないでしょうか?」
無一文の老人に代わって、マリーとカスト孤児院が、依頼主になるそうである。
「わかりました。募集してみましょう‥‥ところで、ハーゼさんはおいくつなんですか?」
「ははは‥‥それがね、本当かどうか知らないけど‥‥110歳だって‥‥」
マリーは、うつむいて髑髏を抱いている老人の背中を優しげに見つめた。
●今回の参加者
ea3184 ウー・グリソム(42歳・♂・レンジャー・人間・ロシア王国)ea8866 ルティエ・ヴァルデス(28歳・♂・ナイト・ハーフエルフ・ノルマン王国)
ea9481 マッカー・モーカリー(25歳・♂・レンジャー・エルフ・イギリス王国)
eb0896 ビター・トウェイン(25歳・♂・クレリック・ハーフエルフ・ノルマン王国)
eb1205 ルナ・ティルー(29歳・♀・ファイター・人間・ノルマン王国)
eb2204 江見氏 喬次(31歳・♂・陰陽師・パラ・ジャパン)
●リプレイ本文
ギルドに集まってきた一同を、一人の物静かな女性が出迎えた。「マッカーさん ビターさん そして皆さん こんにちわ」
女性はうやうやしく、レディーの挨拶をした。 そして‥‥。
「お兄さん お久しぶりです」
「ああ、ソーラ 久しぶりだね」
ルティエ・ヴァルデス(ea8866)は、やさしく笑いかけると、少々大げさで、貴族的な挨拶で答えた。
「ソーラさん? へー ルティエさんって妹がいたんだー」
ルナ・ティルー(eb1205)はその様子を見ていて、さっと女性の前に歩み出ると、今見たばかりの貴族的な挨拶を再現する。
流石、役者志願! 一度見ただけで見事に演じて見せた。
「見事見事! こちらのソーラ嬢は かの名門! カスト家の長女でいらしてな、社交界ではそれはもう‥‥有名な‥‥」
こんどはマッカー・モーカリー(ea9481)が、執事のような口調になって、女性の素性の解説を始めた。
ふむふむと関心しながら聞いているルナを見かねて、ビター・トウェイン(eb0896)が割って入った。
「マッカーさん! ダメですよ! 嘘教えちゃ! ルナさん、嘘ですからね」
ビターが、以前この女性‥‥ ソーラ・カストこと、カスト孤児院のもと孤児であったメリー・ドローワ達からの依頼で、貴族の家族の真似事をした話をした。
「そうなんです! ちょと調子に乗っちゃったかな? 私も貴族の令嬢になりきるのにお兄さん‥‥ あ、つまりルティエさんにお世話になったんですよ。 皆さんまた会えてうれしいです! 調査よろしくお願いしますね! あー 肩こっちゃた」
メリーはそう言うと、その正体‥‥ 普通の町娘に戻った。
「うむ! じゃあさっそく、調査にかかろうか! 私は図書館の古い資料を当たってみる」
「あ! 僕も行きます。 ウーさんの一人で図書館は危険です! では、手分けして情報収集といきましょう」
ウー・グリソム(ea3184)の一言が、思い出話に突入しそうになっている、一同を現実に引き戻した。
通りへと出て行く、グリソムをビターが追いかける。
「じゃあ僕もー」
その後をルナが追い、他のメンバーもそれぞれの心当たりへと散った。
「この辺りのはずじゃねーかにゃ?」
江見氏 喬次(eb2204)とマッカーは、手紙の宛名のメモを見ながら、バロウズの家を探して、ごみごみした下町の界隈を眺めている。
「そうじゃのう それらしい建物はないようじゃな 聞き込みでもしてみようかの?」
「そじゃにゃ」
二人は、外国人や怪しげな商人達がたむろする界隈へと入り込んでいった。
100年前、この辺りがどんな場所であったのか、まったく検討がつかない。
二人は歩き疲れ、建設中の大きな倉庫の前で、腰を下ろした。
「引っ越したのか‥‥ はたまた死に絶えたのかもしれのう」
「ん〜 うん? モウやん? そのレンガ!」
喬次に言われてモーカリーは立ち上り、足元のレンガの山に目をやった。
「おお! バロウズ? レンガの製造元のなまえじゃろうか?」
レンガにはただバロウズと刻印されている。 もしかして??
二人は立ち上がると、建設現場の責任者を探した。
「ぷすぷすしゅー‥‥」
「すごいなぁ‥‥ 7秒くらいですかね?」
本を開いてわずかな間に寝てしまったルナを見て、ビターが感心する。
「俺は上の階を見てくるから、ビターはここを頼む」
図書館についた、グリソムとビター、そしてルナは、それぞれ分担して? 調査作業を開始した。
ルティエは、貴族達が集まるさまざまな場所を歩いていた。
大貴族が主催する集まりが多かったが、中には新興大商人が影で後援しているものもある。
「ガンタレーという家名なのですがね」
優雅な物腰で、ほかの客達と違和感なく接しているルティエだが、実はこういう場所が好きになれなかった、豪華で煌びやかなのだが、どこか虚無感を感じてしまう。
上流社会の生まれであるがゆえに、その中で育ったがゆえに、農民達の生活の実態を知ったときの驚きは大きかった。領主や貴族達はどこまでその実態を知っているのだろうか?
「ガンタレーね」
老婦人が、やっと知りたい情報をもたらしてくれた。
「もうずいぶん昔ね、私が子供の時の話よ ガンタレー老人は大変な資産家だったそうだけど、そのときはもう病気になってたみたいね」
「病気ですか?」
「ええ、そりゃあんな所に住んでいたら病気にもなるわよ。 異国の不気味な神様の金のお面やら、棺桶でしょう‥‥ ミイラもあったわね。 私子供だったから怖くて泣いちゃったわ」
広い舞踏会会場の隅で、一人腰掛けていた老婦人は、若い魅力的な騎士の登場をかなり喜んでいるようだ。
瞳の輝きだけは少女の当時に帰って、屋敷の話や人間不信になって、周囲から孤立していったガンタレーの話をしてくれた。
「ガンタレー老人の最後は、幸せではなかったようですね」
「そうね、可哀想な老人でしたよ。 臨終の時にも地下室から声がするとか言って‥‥ 何かいやな思い出でもあったんでしょうね、すっかり脅えて、ほんと可哀想だったわ」
地下室‥‥ バロウズが閉じ込められていたのは、地下牢であった、バロウズはもしかすると今もそこにいるのかもしれない。
「バロウズレンガ工房‥‥ ここかにぁ」
喬次とマッカーが、小さな工場の中に入ると、恰幅のよい背の高い男が出てきた。
いろいろ話した結果、冒険家のバロウズ氏と、この工房の主人は縁戚であることがわかった。
しかし‥‥
「そんな気持ちの悪いもの受け取れませんね 死んだ人の手紙なんて縁起でもない! ここは客商売なんですぜ!」
取り付く島もなく、男の剣幕に追い出されてしまった。
「100年は長すぎたようじゃな」
「ガンタレー一族は、断絶しているな‥‥ 親戚では、姪が一人30年ほど前まで生きていたようだが、熱病で死んでいる」
「まるで、呪われた一族ですね」
「そのものだよ! 遊牧民のご先祖様は怖いな」
「やはり呪いだと思いますか?」
グリソムはビターの問いにいきなりニヤリと笑うと。
「いや、思わんな! 大金が突然転がり込んだのだぞ きっと、親兄弟で謀殺合戦があったのだろう‥‥そっちの方が理にかなっている、人間は醜いものだよ‥‥」
グリソムの表情からは微笑みは消えない‥‥ この人はちょっと怖い人だな、とビターは思った。
「さて、皆を集めてガンタレー屋敷の跡地へ行くか」
グリソムの声にルナが目を覚ますと伸びをした。
廃墟は辛うじて屋敷の壁だけが残っていた。
中へ入ると、食堂らしいつくりの部屋だった、そこには一抱えもあるような大木まで生えている。
時より、足元で食器らしいものの破片が割れて音を立てる以外、鳥の声もしない。
100年は長すぎた。 ここにはもう何も残っていない。 遊牧民の姫君の思いは、冒険家の名誉は、そしてこの手紙に生涯を掛けたハーゼ少年の思いは、もうどこにも届かないのだ。
「遅れてごめんなんだよー!」
ハーゼ老人とマリーを連れに行っていたルナが、やっと追いついてきた。
「じゃーん! リド姫だよ!」
なんとルナは、遊牧民の姫君の格好をしている。 やや寒そうだが‥‥ ハーゼ老人が事細かに服装を指定してくれたおかげで、かなりそれっぽい。
「バロウズさん幽霊にでもなって、出てこないかな? そしたら一緒に踊ってあげるんだよー!」
ルナは冗談を言っているのではない、何もしてやれなかったバロウズに、せめて楽しい思いをさせてやりたいと思っているのだ。
と‥‥ ピーーー‥‥ どこかから口笛を吹くような音が聞こえる。
「? なんだにぁ?」
辺りには人影はない、見回す喬次、ハーゼ老人だけは、何かを思い出したように、指を口に当てた。
ピーーー! ピーーー! 老人の口からさっきの音によく似た口笛の音が発せられた! そしてなにやら早口で言う。
マリーが、老人に向き直って、今の行動の意味を身振り手振りで聞いている。
すると‥‥ ピーーーー‥‥
「こっちです! この辺りから音が出ている!」
ルティエが地面の一角を指差す。
「合図ね? 合図てことね? 皆さん! 今の口笛は遊牧民の合図なんだって!」
マリーは、老人がそういってるらしいとみんなに説明する。 しかし、まさか? 口笛で合図を送っているのはだれ?
「馬鹿な! 信じられん! 100年も地下牢に?」
グリソムは、半ばあきれたような表情になる。
「この穴からです! 地下室があります!」
ルティエがいり口を見つけたようだ、地下室は、天然の洞窟を一部改造して作られていた。
半分土砂に埋もれて、中は真っ暗である‥‥ しかし、僅かだが風が吹き出している。 どこかに通じているのかもしれない。
ピーーーー‥‥
「また口笛だにゃ! えーと‥‥ あ!!」
「どうしたのじゃ? む! ‥‥うーむ」
崩れた地下室へ最先頭ではいっていた喬次は、絶句すると立ち止まった。 マッカーも、一言唸ると動きを止めた。
「どうしたんです? マッカーさん 喬次さん」
「バロウズ氏じゃ‥‥ ここでずっと待っておったんじゃな」
照明を持ったビターが中に入ると、地下室、いや牢獄に、数十年ぶりに光が差し込んだ。
ピーーーー‥‥
また音がする、しかしこれは口笛ではない、そこに有るのは白骨であった。
バロウズ氏の変わり果てた姿だ。
髑髏の隙間に流れ込んだ風が、この音を出している‥‥ おそらく、もう何十年も合図を送り続けていたに違いない。
ビターは、はたと思いつくと、老人からリド姫の髑髏を借りて、バロウズの髑髏の横に並べてやった。
すると‥‥ あの物悲しい音がぴたりと止んだ。



