 【聖夜祭】精霊が謳う夜に
【聖夜祭】精霊が謳う夜に
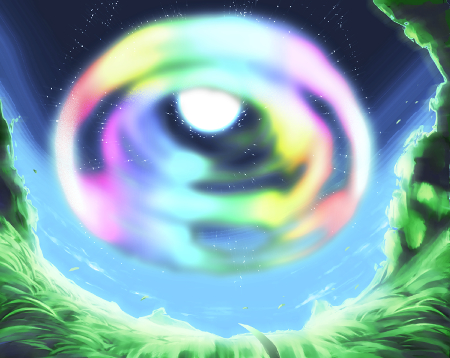 |
■イベントシナリオ担当:月原みなみ 対応レベル:フリーlv 難易度:普通 成功報酬:4 参加人数:15人 サポート参加人数:-人 冒険期間:12月21日〜12月21日 リプレイ公開日:2008年12月30日 |
|
●オープニング
「これで雪でも降れば完璧なのにね」ホワイトクリスマス。
そんな言葉が脳裏に浮かんで、彩鈴かえでは満面の笑顔だ。
聖夜祭のパーティー会場となる通称「珍獣屋敷」。そのダンスホールに、冒険者達によって飾りつけられたツリーを庭から眺め、陽精霊の時間が終わるのを今か今かと待つ彼女の隣には滝日向の姿もあった。
「いい夜になるとイイやぁね〜〜♪」
バシバシと背中を叩かれて激しくむせた。
「けほっ。‥‥っ、つーかおまえの言い回しは怪し過ぎる」
どこの方言だと眉を顰めて言ってやるも、当の本人には何のその。
「こっちに来て何年経つと思う? 久々にクリスマスパーティーが出来るんだよ? これを喜ばないで何を喜べって言うのっっ!」
「‥‥ま、気持ちは判らないでもないけどな‥‥」
えへへへと顔を緩ませる相手を見ていると流石の日向も力が抜けてしまい(「楽しそうだからまぁ良いか」)と肩を竦めて周囲を見渡した。
子供の頃に見たアニメの世界で主人公達が楽しげに踊っていた城のダンスホール、まさにそんな景観の珍獣屋敷が冒険者達の手によってクリスマスカラーに彩られた。
ホールを行き交うパーティー準備のメイドさん達はミニスカサンタ。
個人的にはこの発案者に「グッジョブ!」とMVPを贈りたい心境だ。
「しかし、何人くらい集まるもんだか」
「いっぱい集まってくれるといいよね!」
既に興奮しきりのかえでは、馴染みの受付係りに頼み込んでギルドの掲示板にもこのクリスマスパーティーのチラシを貼らせて貰い、面識のない冒険者達にも気軽に来て貰えるよう試みたのだ。
「ま、せいぜい働かせてもらいましょ」
肩を竦めて笑う日向が袖を捲るのを見て、かえでは目をぱちくり。
「なに言ってンの? 今日の日向君はお客様だよ?」
「は?」
「女の子誘っておいて、パーティー会場で一人にするとかありえないしっ、いくら日向君がお手伝いでメイド服を着たいって言ってもミニスカサンタになりたいって言っても今日ばっかりは断固阻止だよ!?」
「誰がンなもん着るかっ!!」
それは見て楽しむものだ、と声には出さなかったけれど。
屋敷の外で騒がしくしている二人の声は、珍獣屋敷を訪れようという冒険者達を出迎える鐘の音のようだったとか――。
●今回の参加者
アシュレー・ウォルサム(ea0244)/ ケンイチ・ヤマモト(ea0760)/ 長渡 泰斗(ea1984)/ 信者 福袋(eb4064)/ ルエラ・ファールヴァルト(eb4199)/ シャリーア・フォルテライズ(eb4248)/ キース・ファラン(eb4324)/ リール・アルシャス(eb4402)/ 華岡 紅子(eb4412)/ リィム・タイランツ(eb4856)/ アルジャン・クロウリィ(eb5814)/ 物見 昴(eb7871)/ ラマーデ・エムイ(ec1984)/ ソフィア・カーレンリース(ec4065)/ レイン・ヴォルフルーラ(ec4112)●リプレイ本文
冒険者達によって飾りつけられたツリー。立食パーティーのスタイルで各テーブルを飾るのは鮭と野菜のマリネやポークソテーのワイン煮込みなど、こちらも冒険者達によって考案、具材から集められて調理された品々だ。
王都ウィルの「珍獣屋敷」として親しまれている(?)ウルティム・ダレス・フロルデン邸。そのダンスホールは今日のために奔走した皆の手によって、地球と呼ばれる異世界のクリスマスそのものの光景を人々の眼前に広げていた。
「ありがとだよ、みんなっっ」
興奮した口調で握り拳を作り感謝の言葉を述べるのは発起人の彩鈴かえで。衣装はミニスカサンタにフリルのエプロンでメイドさんもどき。実はミニスカサンタを一度は着てみたかっただけ、‥‥なんて事はない。たぶん。
「ありがとうはいいんですけどっ」
「やはり短いよ! この格好は‥‥恥ずかしいぞ、かえで殿‥‥!」
訴えたのはレイン・ヴォルフルーラ(ec4112)とリール・アルシャス(eb4402)で、その隣に並び笑顔なのがソフィア・カーレンリース(ec4065)だ。
「お二人とも、とってもよくお似合いですよー」
そう言う彼女もとても愛らしいミニスカサンタ。お持ち帰り用は通常のそれ一着だが、ミニスカサンタコンテストで使われる衣装は色もデザインも様々だ。
「さて。コンテストに出るもパーティーを楽しむも自由だけれど、そろそろ本格的なおめかしをしようか? 選りによりを掛けて美人に仕上げるからね。皆、恋人をしっかりと見惚れさせないとね」
メイクセットを両手ににっこりと笑むアシュレー・ウォルサム(ea0244)。着付けに化粧と、それだけを聞けば普通なのだが、彼の笑顔には裏があるような気がしてならないのは何故だろう。
「日頃の行い‥‥」
「何か言ったかな、かえで?」
小声で囁いたはずなのに、しっかり聞こえている西萌不敗様。かえでの首根っこ捕まえて更衣室に。
「さぁ、かえでも変身してもらうよ」
「あたしは裏方ーーっ!」
ダンスホールに響く絶叫はいとも容易く封じられたとか。
「いま、蛙が首を絞められたような声が聞こえた気がしたが」
辺りを見渡しながらアルジャン・クロウリィ(eb5814)が呟くと、傍にいた滝日向が「なんだそりゃ」と苦笑。同時に、その隣に並ぶ華岡紅子(eb4412)が、ホールから数人の女性陣が姿を消しているのに気付く。
「ふふ、もしかして捕まっちゃったのかしら」
面白そうに呟く彼女に男二人は小首を傾げるが、それきり。
「しかし紅子は綺麗だな」と日向に意味深な笑みを向けるアルジャンに、日向は「自分でそれだけ出来るってのは器用だよなぁ」と頓珍漢な台詞を返した。ロイヤルホワイトにクリスタルパンプス、白薔薇をイメージした口元に引いたパールルージュ。気付いて欲しいのに、と。そんな思いは欠片も見せずに「ありがとう」なんて微笑う紅子に、アルジャンは苦く笑うのだった。
「ほぅ‥‥」
「何ですか」
会場の一角、いち早くアシュレーのメイクアップから解放されてホールに戻って来た物見昴(eb7871)を迎えた長渡泰斗(ea1984)は、顎に手を置いて上から下まで一通り見遣る。その視線が昴には居た堪れなかった。この相手が、仕事とはまったく無関係のイベントに誘ってくるなどと珍しい事をするから、昴もらしくなく着飾ってみたのだが。
「‥‥何かと聞いているのですが」
「いや」
シルクのドレスにハイヒール。忍び姿以外は滅多に見ない姿に泰斗は何を思ったのか。
「‥‥馬子にも衣装だな」
「っ」
言うに事欠いてそれかと反論すべく一歩を踏み出す昴だったが、慣れないヒールの高さに体は前傾、見事に転倒。
「それでも忍びか」
くっくっと笑いながら差し出される手を、不本意ながらも借りて立ち上がり、‥‥「誰のせいか」と言うに言えない文句を心の中で掻き消した。
「いいか、香代。おまえに必要なのは素直さだ!」
「余計なお世話よっ」
パラの兄妹、石動良哉と香代の傍にはリラ・レデューファンの姿も。
「‥‥無理を言うつもりはないが、せっかくの聖夜だ。楽しまねば損だろう」
「っ‥‥リラにまで言われたくないわ‥‥っ」
真っ赤になって目を吊り上げると、そこに届く声はキース・ファラン(eb4324)だ。
「来てたんだな!」
いつもの朗らかな笑顔を向けて来る彼の横には綺麗に着飾った女の子が並んでいた。‥‥女の子?
「き、キース、その子はまさか‥‥っ」
良哉が声を震わせて疑いを持ち、香代もリラも目を瞬かせるが、当の本人は何のその。
「あぁ、彼女リィム・タイランツ(eb4856)っていって、昔からの知り合いで」
ただの知り合いかと更に疑いを強める彼らに、キースは思い掛けない言葉を続ける。
「実はさ。良哉に紹介しようかと思って」
「――」
「や、よろしくね?」
三人絶句。
「は‥‥」
何だって? と、新たな叫びが響き渡る。
●
「レディース アーンド ジェントルマーン!」
壇上で声高にパーティーの司会進行を務めるのは信者福袋(eb4064)。宴の発起人であるかえで達と同じ天界出身の彼は、丸めた布をマイク代わりに、先ほどから恋人達のために音楽を奏でるメンバーや、その曲紹介を行っていた。
「それでは最初はやはりこの方々! アシュレー・ウォルサムのバイオリンとケンイチ・ヤマモト(ea0760)の竪琴で『ワルツ』でございます」
最初の独奏はケンイチ。緩やかに始まった旋律が次第に確かな世界を創り上げてゆく中に、アシュレーのヴァイオリンの音が重なる。弦と弦の二重奏。それは精霊の世界で行われる聖夜にこれ以上なく相応しい、美しい音色だった。
「‥‥失礼」
その音楽に背を押されるように、先ほどから不機嫌そうな顔を微かにも崩す事無く壁際に佇んでいた男に声を掛けたのはシャリーア・フォルテライズ(eb4248)だった。
「もしよろしければ、‥‥一曲、いかがでしょうか」
こちらも緊張した面持ちのシャリーアが細い手を差し出せば、その相手ことアレックス・ダンデリオンは僅かに目を見開いた後で眉間の皺を深くした。しかしその変化は、決して彼女からの誘いを不快に感じたからではなく、むしろ――。
「では、一曲」
彼女の手に手を添えてホールの中央へ。
「‥‥その装い、とてもよくお似合いです」
「っ」
「アレックス殿?」
「だ、大丈夫だ‥‥」
何もない場所で転びそうになった彼が慌てて普段通りに振舞おうとする仕草を、シャリーアは柔らかな微笑みで見つめていた。
「へー。クリスマスってダンスもつきものなの?」
テーブルを所狭しと飾る料理に手をつけながら、ラマーデ・エムイ(ec1984)は不思議そうな顔。
「村祭りでやるような、皆で輪になって踊るんじゃなくて、貴族様が舞踏会でやるようなのを天界の人達もやるのね」
口元に付いたソースを指先で拭ってぺろり。誰が作ってくれたのかは判らないがソースまでとても美味しい。
「チキュウの天界の人達って、みんな貴族様みたいにダンス習うのねー」
「そのようですね」と返したのは傍にいたルエラ・ファールヴァルト(eb4199)である。どちらも生粋のアトランティス人。かえでがダンスを知っていたのはあくまで彼女の人生経験故なのだが、‥‥まぁ、そのような誤解が生まれても大きな問題にはならないだろう。たぶん。
「ルエラさんは踊らないの? せっかく綺麗なのに」
彼女が身に纏ったサンライズドレスの、裾の火炎色から胸元の深紅へのグラデーションは、クリスマスカラーに彩られた会場内でもまったく引けを取らない美しさ。それを見て言うラマーデに、ルエラは「そうですね」とホールを見渡す。当初は裏方の手伝いを第一目的にしていたため、発起人に半ば強引にホールに連れ出された彼女は、正直に言えば時間を持て余していたのかもしれない。
時間にすれば僅かだが、ルエラの沈黙から何かを察したらしいラマーデは最後の一口を飲み込む。
「踊りましょうか」
手を差し出して、笑顔で。
「ちゃんとしたダンスなんて知らないけど、気にしない気にしない。こういうのは音楽に乗って楽しんだもの勝ちよね?」
「同感ですね」
「!」
不意に掛かった声が誰かと思えば、先ほどまで司会進行役を務めていた福袋だ。
「どうですか、一曲ご一緒に」
両手を二人の女性に差し出してにっこり笑顔の福袋。
女性二人は目を瞬かせて、けれど、彼の手に手を置いた。
「喜んで」
そうして中央に進む三人に「おやおや」と笑むのは、ちょうどバイオリンの手を休めていたアシュレーだ。
「正に両手に花、だね」
ケンイチの独奏に隠れるようにパシャリとシャッターを切るのは、もはや彼の必需品と言っても過言ではないデジタルカメラである。
「さすがアシュレーさんもケンイチさんも、とってもお上手ですね〜」
ワイングラスを片手に、笑顔で呟くソフィア。
「あのお兄ちゃん達、お姉ちゃんのお友達だよね?」と声を掛けるのは、ソフィアが誘った顔馴染みの子供達だ。
「そうだよ」
「すごいなぁ、お姉ちゃんのお友達は、こんな大きなお屋敷に暮らしていたり、素敵な音楽を聞かせてくれたり、‥‥すごいなぁ」
ぐるりと天井から床までを見渡す少女の言葉に、果たしてこの屋敷の主人を友人と呼んでいいものかどうかと思案。確かに友情に近いものはあるが、普通は友人相手に電撃攻撃やら銀のトレイで一発入魂、ヒールの踵で踏み付けたりなどエトセトラ‥‥、恐らくしないと思うのだが。
(「それも新しい友情の形‥‥なのかなぁ?」)
でもなぁと小首を傾げる彼女の様子から何を感じ取ったのか、少年クリスが頬を膨らませてソフィアの手を取った。
「お姉ちゃん、踊ろう?」
「ん?」
「ねっ」
小さな子供に手を引かれては、さすがに断れないソフィア。ブラックプリンセスの裾をひらりと舞わせながら、彼女もまたホールの中央へ。
●
音楽は一曲目を終えて二曲目へ。楽師を変え、楽器も変わり、穏やかで優しい音色は自然と男女の距離を埋めてゆく。
「っ」
「すまぬっ」
足を踏まれて一瞬だが息を飲んだシャリーアに、アレックスは慌てて足を退け謝罪する。だが、彼女の方は決して笑みを絶やす事無く、触れた手を離す事もなかった。
「はは、失礼。こういう場は、私も勝手がよくわかりませんで」
「いやしかし、今のは私の」
「気にされる事はありません」
そうして微笑まれると、アレックスは不自然に動悸が早まるのを自覚しないわけにはいかなかった。
(「これはどういうわけか‥‥」)
眉間に深い皺を刻んで黙り込んでしまうと、そんな彼にシャリーアが不安顔。
「あの、私と一緒で退屈してはおられぬでしょうか‥‥?」
「! 否、そのような事は無い。寧ろ、若干動悸にあてられてしまっていてな」
慌てて弁明する彼の説明の仕方は些か妙なものであったが、退屈ではないと、それが判っただけでもシャリーアの心は晴れる。
そうしてはにかんだような笑みが零れれば、それを見たアレックスの動悸は更に激しく、彼が彼女の足を踏んで再び動きが止まるまで、あと僅か。
踊ろうと誘って、素直に応じてくれるとはキースも思っていなかった。
だから友人が良哉を連れて遠ざかるのを見送り、呆気に取られていた香代に最初に告げたのは謝罪の言葉。
「この間はごめんな、香代の気持ちを考えなくてすまなかった。‥‥だけど、香代を思う気持ちは本物だぜ?」
そう告げた彼に、香代は息を飲む。
真っ赤にした顔にそっと手を伸ばし、しかし一度止めて、避けられないのを確認してから静かに触れる。
「‥‥一緒にダンスを踊ってくれないか?」
「キース‥‥」
今にも消え入りそうな声で彼を呼ぶ香代の背を、ポンと押したのはリラ。
「私はリール殿を迎えに行って来るよ」
「ぁ‥‥」
笑みを浮かべて去って行く友人を、しかし呼び止める事は無く、香代は深呼吸を一つすると、俯きがちではあったが、キースの手に、手を置いた。
「‥‥巧くは踊れない、けど‥‥」
「! 大丈夫、俺がリードするよ」
ゆっくりと手を引き、ホールの中央へ進み出る。薄紅色のドレスの裾が緩やかに波打つ。さすがにサンタクロースの衣装はね、と冒険者の少女達が見立てた衣装だ。
「とても良く似合ってる」
「っ‥‥」
褒められて、普段ならば顔を真っ赤にして逃げ出すところだけれど、今日はぐっとその衝動を抑える。最初、彼が女の子を伴ってきた時に感じた衝撃を思い出せば、それくらいは出来ると思えた。
「‥‥キースも、その衣装‥‥とても似合っていると、思う、わ‥‥」
決して目線を合わせて来る事はなかったけれど、必死に素直であろうとする姿はひどく可愛らしく、キースはキースで抱き締めたくなる衝動を抑えるのに大変だったとか。
そんな二人を、少し離れた処からハラハラと見守っていたのは兄・良哉だが、彼をダンスに誘ったリィムとしては、このまま妹の事ばかり考えさせてはおけない。
「こら、妹さんばっか気にしないの。相手はボクなんだからね」
「うぉっ」
ぐいっと接近してみせれば、エンジェルフェザーの胸元が彼の視線の真下。
「ちょっ、待てっ」
慌てて体を遠ざける。
「君っ、俺ら今日会ったばっかり! 初対面も同然の男にそういう態度は危ないぞっ」
「気にしない気にしない」
「いや、気にするべきだ!」
晩生な男――いや、ジ・アースのジャパン出身者としては至って普通であると自認している良哉は必死で説くのだが、リィムは気にしない。
「ね、良哉君って呼んでイイ? ボクの事も好きに呼んでいいからさ」
「ぁ、な、ねって‥‥」
だからな、と抑止のために伸ばした手が、不意に別のペアが背後からぶつかって来た拍子に前傾、リィムの柔らかな部分に接触。
「!」
「やん。もー何処触ってるのさっ、大胆だね〜☆」
「!!!」
にっこにこの笑顔でぎゅっと抱きつかれれば、さすがに限界の良哉。立ったまま気を失った彼は、この日以来、散々仲間にからかわれる羽目となるのだった。
「あっちも大変そうだね」と、立ったまま気絶の良哉を後々のネタにとカメラで撮影したアシュレーは、ダンススーツとパッションシューズで完璧紳士。
福袋が両手に抱く可憐な花二輪に近付くと優雅に一礼。
「一輪、俺が攫ってもいいかな?」
そんな文句で手を差し出せば、ルエラが一瞬だけ目を丸くするも「喜んで」と手を取った。福袋が「そろそろ食事に行きたいと思っていた」と告げれば、ラマーデもそちらに付き合うと笑顔。
彼らは二組に分かれた。
「‥‥意外ですね。他の方々に悪戯をして回られるかと思っていたのですが」
「ん? そんな事しないよー、みんなカレシ持ちだしね」
基本、相手のいる女の子をからかいはしても、その恋人達に不快な思いをさせるつもりなど毛頭ないのがアシュレーの弄り方。むしろ恋人達の前では最高に可愛らしく着飾らせてあげたいのが本心。
「まだ着替え中みたいだけど、楽しみにしててよ。みんな可愛いよ?」
ホールに姿の見えない仲間の姿を思い浮かべて告げるアシュレーは、貴族の一人としてダンスもほぼ完璧なルエラを見事にリードしながら一言。
「せっかくなんだから、ルエラにもメイクしてあげたかったな」
「‥‥口が巧いのは相変わらずですね」
くすくすと苦笑を零したり、会話をしながらでも決して乱れぬステップは周囲のペアの視線を引きつけた。
ルエラの赤い髪に、サンライズドレスの深紅。
アシュレーの銀髪に見事なリード。
まるで舞台を独占する主人公達のような存在感は、曲の終わりと共に大勢の拍手喝采に包まれるのだった。
そんな会場の拍手を耳にしながら、トントンとリラがノックしたのは、アシュレーが女性陣を集めてメイクしていた部屋である。本人はもう会場に戻り、楽器演奏に食事、ダンスと楽しんでいるが、メイクの後に着替えをしていたリールとレイン、それにかえでは、いまだ会場に戻って来ていなかったのだ。
「入っても大丈夫だろうか?」
まだ着替え中であれば驚かせてしまうと気遣ったリラに、中から応えたのは、かえで。
「うん、大丈夫だよー、入って入って♪」
妙に弾んだ声音を不思議に思いながら扉を開ければ、ちょうど休憩を取りに来たケンイチが。
「まだホールに入られていない方がいらっしゃるんですか?」
「ああ。女性が数人だが」
「何かあったのでしょうか‥‥?」
ケンイチも不思議そうな顔で、心配なので一緒に構いませんかと揃って中に。すると、中ではリールが友人の結わえられた髪に小さな白い花を散らしているところだった。
「ぁ‥‥すまないリラ殿、お待たせしてしまって」
彼の来訪を知ったリールが慌てて謝れば、彼女に花を掛けられていた友人ことレインが自分のせいだと詫びる。
「アシュレーさんに、今夜に一番似合う花だから着替え終えた後に髪に散らしてって言われたんですけど‥‥っ」
如何せん理美容技術には乏しいメンバーである。どんな具合が適当なのか判らず四苦八苦していたらしい。
「‥‥ならばアシュレー殿をもう一度呼んで頼めば良かっただろうに」
リラが苦笑交じりに言えば、三人が口を揃えて彼にもパーティーを楽しんで欲しいのだと返答。加えて、女三人が揃って不器用だと知れるのは些か恥ずかしかったようだ。
「色々と複雑だな」
「複雑なんだ」
呟きながら近付くリラの横から、そっと手を差し出したのはケンイチ。
「それを、お借りしても構いませんか?」
「ケンイチ殿はお得意なのか?」
「得意というわけではありませんが‥‥」
ケンイチが言いながら受け取ったのは、細い茎から下がった幾つもの小さな白い花。恐らく「雪」を演出しようと言うのだろう。ケンイチは花を茎ごと手に包み、決して花を傷めないよう拳を握る。そうして取り出した茎を持ち、花の部分をレインの頭上に置いて、手を手で叩いた。
「あ‥‥!」
すると、弱っていた花の根元から花びらが舞い落ち、レインの髪を飾る。正しく雪のように。
「‥‥これでどうでしょう」
「ケンイチ殿、すごいな!」
「いえ、このようなアイディアを思いつかれるアシュレーさんにはとても敵いません」
しかし芸術家の感性は流石ということなのだろう。
「ありがとうございます!」
レインも笑顔で感謝の言葉。
「いいえ。お礼など結構ですから、早く行って差し上げてください。もう三曲目が始まりますし、アルジャンさんもお待ちです」
「は、はい‥‥!」
「あまり走らぬように、な。せっかくの花が落ちてしまう」
「はいっ」
二人の男性に声を掛けられたレインは早歩きで外へ。
「ん。これでようやく準備完了だね」
ほっと一息つくかえでに、リールも微笑んだ。
「アルジャン殿、吃驚されるだろうな」
嬉しそうに語る彼女に、今度はリラが手を差し出す。
「‥‥よければ、リール殿も私と会場に」
「! ぁ、ああ‥‥」
すぐ傍で触れられる手に、リールは手を出しても、躊躇する。ダンス練習で幾度と無く触れたはずなのに、いざとなると妙に緊張してしまって。
「リール殿」
優しい声に鼓動が高鳴る。
「‥‥よろしく」
そっと手を乗せて告げ、微笑めば、リラも微笑う。
「はい、お二人さんも行ってらっしゃい」
かえでの笑顔に見送られた。
●
「お待たせしました‥‥!」
早歩きに、息を切らしてやって来たレインに、アルジャンは少なからず驚いた。確かに待ちはしたが彼女を急がせるつもりはなく、‥‥だが実際に正面から彼女を見つめて更に驚く。
水の乙女と呼ばれるに相応しい、青いロングドレスにアクセサリ。結わえられた髪を飾る雪の花。
「‥‥驚いた、な」
「え‥‥」
「とても綺麗だよ」
「ぁ‥‥」
顔を真っ赤にして俯く彼女に笑み、その手を取る。
「少し休んでから、一緒に踊ろう」
「はい‥‥っ」
そんな二人の様子を見て、ほっと安堵の息を吐いていたのは紅子。彼女は三曲目に合わせて日向とダンスの最中ではあったが、練習の甲斐あって周りを見る余裕も持てるようになっていた。
「良かった、レインちゃんに何かあったかと思ったわ」
あまりにも会場へ戻るのが遅かったため心配していたのだが、いざ会場に現れた彼女は水の精霊と言われても頷けてしまいそうな程に美しい姿。
「‥‥あんなに綺麗になっちゃうと、お父さんとしては心配かしら?」
「誰が父親だ」
からかうように言う紅子に、若干だがムキになって返す日向は、‥‥けれど少し考えた後で紅子の手を引いた。
「? 滝さん‥‥」
会場を後にし。
バルコニーに出て、大勢の人々の声や、音楽も遠く、冬の夜風が二人を包む。
「あの、さ‥‥」
「?」
言い難そうにしている自分を見上げてくる紅子に、日向は頭を掻きつつ、目を逸らして一言。
「‥‥綺麗だよ、すごく」
「――」
「‥‥こういう事をな、その‥‥人前では、‥‥言えないからさ」
俺は生粋の日本男児だと言い訳のように言う彼の言葉を聞き、思わず言葉を失くしてしまった紅子も、時が経てば胸の内側から込み上げてくる思い。
「‥‥それを言うために?」
「さっきは、すぐに言えなくて悪かった」
気付いていた。
それでも言えなかった事を、悪いと思って。
「‥‥っ」
そんな彼の言葉に、仕舞っておくつもりだった気持ちが、今にも零れ落ちてしまいそうになる。
「‥‥滝さん、これを」
そうして差し出したのは、クリスマス用に包んだ贈り物。中身は「聖なる守り」と呼ばれる首飾り。相手の幸せを願うもの。
「それと、‥‥夏祭りに渡し損ねたモノ、よ。‥‥ありがとう」
「――」
背伸びして触れた、彼の頬にキスを。
「‥‥これって‥‥」
耳元に囁かれる微かな問い掛けに、言葉での答えなど要らなかった。瞳を閉じる、ただそれだけで――。
●
会場では四曲目が流れていた。
ケンイチが奏でる優しい竪琴の音色に、他の楽師達も各々の音を合わせて、ダンスの曲調は更にバリエーションを増やす。
「私やユアンにまで、聖夜の贈り物をありがとう」
「どういたしまして。二人が喜んでくれれば、それだけでいいんだ」
練習の成果か、流れるようにステップを踏むリールとリラ。
「‥‥そのドレスは、ケイトの?」
「ああ。‥‥それに、リラ殿に選んで頂いた靴を‥‥、似合う、かな」
緊張した面持ちで尋ねる彼女に、リラは穏やかに頷き返す。
「とてもよく似合うよ」
「――良かった‥‥!」
心から安堵するリールは、ふと同じ会場にいる人々が「雪だ」と声を上げたのに気付いた。
「雪‥‥」
「外に出てみるか」
「いいのか?」
「君がそう望むなら」
「ありがとう‥‥!」
そうして満面の笑みを零すリールに、リラも笑い、二人は外へ出た。
誰かが言っていた通り、ちらちらと雪が舞い降り始めた、ウィルの聖夜。
「‥‥寒くはないか?」
「大丈夫だ」
応えた後で、リールは夜空を見上げ、‥‥語る。
「以前、雪の降る夜、辛い事があって‥‥、少し苦手だったんだが、‥‥今夜の事を思い出せば、これからは楽しみになりそうだ‥‥」
ほんの少し遠くを見つめるようにしていた彼女が、しかしすぐに笑むのを、リラはどう思っただろう。
「‥‥戻ろう。風邪を引く」
そうして差し出された手に、手を置いて。
「ああ」
二人、会場に戻る。
その手を、リラから離す事は決してなかった。
「雪ですよ、アルジャンさん」
同じ頃、やはり外に出ていたアルジャンとレイン。
両腕を広げ、舞い落ちる微かな雪を何としても受け止めようとするような少女に、アルジャンはくすくすと微笑う。
「雪は、綺麗だが‥‥レイン、君の雪の方がずっと綺麗だよ」
「私の‥‥って、アイスブリザードとかですか?」
「いや」
自分の魔法の事かと聞いて来る彼女に歩み寄り、髪を飾る雪の花に触れる。
「こちらのことだ」
「‥‥っ」
アルジャンの指先に髪を抱かれ、少女の頬は赤く染まる。
「えっと、あの‥‥っ」
これしきの接触でもこれほどに恥らう彼女が、自分に想いを告げてくれた時にはどれだけの勇気を振り絞ったのだろう。あの時の事を思い出すたび、アルジャンの心には嬉しさと同じくらいの申し訳ないという気持ちが募る。
「レイン」
だから今日は、自分が。
「‥‥レイン」
「? アルジャンさん‥‥?」
近付く姿。
柔らかな髪を手に抱き、耳元に落とす囁き。
――‥‥愛しているよ‥‥
その、貴い一言を。
●
宴もいい具合に盛り上がりを見せてくると、当然の事ながら酔い始める者も出てくるわけで、何故かその中に混じってしまったのは昴だった。
「いい加減に目を覚ませ」と泰斗が水を差し出すも、昴は無言で目元を腕で覆ったまま。大して強くもない酒を飲み過ぎてこんなになってしまったのは、‥‥二人で過ごす時間がだんだんと落ち着かなくなってきたからだ。
「‥‥大丈夫か?」
「平気、です」
思い出せば何とも妙な夜だった。
慣れないダンスに見よう見真似で挑戦してみれば、意外と出来ない事もなかったが、二人手を合わせて踊っていると、周りの男女の様子がだんだんと変わっていくのだ。体を密着させて踊る二人がいれば、奏でられる音楽の曲調まで変わって。
それらを誤魔化そうとする都度、何故だか会話の中心は「茶」になり、何か違うと思い始めた時には酒を飲み過ぎていたのである。
そのため、館の主に部屋を一つ借りての休憩中。
「まったく‥‥、やはりこういうイベントは似合わんな、お互い」
軽い息を吐いて苦笑する泰斗は、しかし胸中に思う言葉を、何とか最少で伝えようと試みていた。
「‥‥だが、俺の背中はおまえに任せる」
きっと伝えたい言葉はやまほどある。
伝えなければならない言葉も。
けれど気の利いた、歯の浮くような台詞なんてガラではない。そこのところはガキの頃からの馴染みなのだから伝わるだろう、と。
それも胸中でのみ告げて。
「頼んだぞ」
最後に付け加えた言葉に。
「‥‥そのお言葉、真実ととって‥‥よろしいのですね?」
硬い返答に、泰斗は笑う。
「年が明けたら家に来い。新茶とは言わんが良い茶を立ててやる」
それが、彼ら二人にとっては最も相応しい応えなのだ。
●
「やっぱり発起人は最後にトリを勤めないとね、責任者として」
「ちがーうっ、あたしは裏方って言ったでしょーっ」
叫ぶかえでは、気付けば装い完璧でアシュレーに連れられて来ていた。ダンスが得意なら是が非でも踊るべき姿だ。
しかしこれを拒む彼女に、ソフィアが子供達と一緒に笑い掛けて来る。
「せっかくですからかえでさんも踊りましょうよ〜、この子達、とっても巧いんですよ〜?」
とはいえ大人の男女が踊るようなダンスではなく、甘い雰囲気には程遠いのだが。
「‥‥っ、お、俺だって、あと十年も経てば立派な大人なんだから‥‥!」
ムキになって返すのはクリス少年。はてさて、その胸中や如何に?
「‥‥ソフィアちゃんや子供達と一緒なら踊る」
それが最大の譲歩と言い切るかえでに、不服そうなアシュレー。
「えー?」
「えーじゃないしっ」
会場はいまだ賑やかに、朗らかに。
アトランティス、ウィルの国の聖夜はまだしばらく続くのだろう――。



