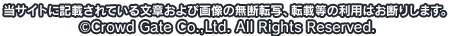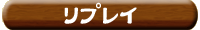 秀吉、丹後国司について思いを巡らす
秀吉、丹後国司について思いを巡らす
 |
■イベントシナリオ担当:安原太一 対応レベル:フリーlv 難易度:易しい 成功報酬:4 参加人数:4人 サポート参加人数:-人 冒険期間:12月11日〜12月11日 リプレイ公開日:2008年12月17日 |
|
●オープニング
京都御所――。先日、丹後宮津藩の藩主である立花鉄州斎が京都を訪れ、秀吉のもとを訪問した。鉄州斎は都からの救援を求め、秀吉への臣従を誓ったのである。秀吉はこれに応え、イザナミ軍の侵攻を受ける宮津へ援軍を送った。
‥‥数日後、また丹後から秀吉を訪ねてくる者があった。丹後舞鶴藩の藩主、相川宏尚である。
秀吉には舞鶴藩主の来訪の目的が大方見当がついた。
「此度の黄泉人の進軍につきまして、何卒、秀吉公のお力をお貸し下さい」
宏尚はそう言って平伏する。もし黄泉人たちが舞鶴まで押し寄せるようなことがあれば、救援の軍を派遣して欲しいと。現在宮津ではイザナミ軍との決戦が進行中だ。舞鶴に黄泉人が押し寄せるとは、少なくとも決戦にイザナミ軍が一定の勝利を収め、宮津が陥落している可能性が高いが‥‥。
「分かり申した」
秀吉は頷いた。
「現在丹後に派遣している武将達に、万が一の時は舞鶴を死守するように伝えましょう」
宮津での決戦に敗れた場合、舞鶴が最後の砦となるであろう。秀吉の言葉を宏尚は重く受け止めた。
いずれにしても、こうして舞鶴藩主も秀吉の傘下に入り、丹後諸藩の大名たちは全て藤豊家に臣従したことになる。
‥‥舞鶴藩主が帰った後、一服しながら秀吉は丹後国司の件について考えた。全ての藩主が藤豊に臣従した今、丹後国司を秀吉の裁量で決める下地も出来たと言えよう。
もっともイザナミ軍を始めとする黄泉人の猛威、丹後半島の盗賊団の件、そして丹後南東を牛耳る大国主など、丹後には自力で解決できない問題もあるから今すぐにと言うわけにもいかないだろう。
また誰が国司に相応しいかは即断出来るものではない。丹後の民にとっては大きな問題であり、秀吉も熟慮の末に決めたいものだ。
「都の者たちの意見も聞いてみるか‥‥」
秀吉は茶を置くと、近侍を呼びつけ、冒険者ギルドへ使いを走らせた。
依頼は今後の丹後国司の件について冒険者達の意見を聞いてみたいというもの。
秀吉も今すぐに丹後国司を決めるつもりはない。丹後の現状も踏まえて最終的な結論を出すつもりだ。
国司の候補者は以下の通り、さて、冒険者は誰を推す? それとも国司は置かず、現状の四藩による統治を続けていくのか‥‥それとも他の選択肢があるなら秀吉に進言してみよう。‥‥とは言え今回は数は力であるのも確かである。
【関連情報、丹後国司候補者】
立花鉄州斎:二十代後半の若き宮津藩主。天津神や丹後の物の怪と交流があり、宮津でお稲荷さんを祀っている。しばしば不死者を撃退した勇猛な青年だが、イザナミ軍の侵攻には最悪藩を放棄することも辞さない構え。
中川克明:四十代の強面の峰山藩主。不死者の攻勢の矢面に立たされ、何とか凌いでいたが、イザナミ軍の侵攻で藩の大半を失う。多くの民を宮津へ逃がした。今は藤豊家の援助を受け、反撃の機会を待っている。
相川宏尚:三十代後半の細面の舞鶴藩主。丹後の盗賊と手を結んでいるなどという風聞が立っていたが、現在は諸藩と連携してイザナミの脅威に立ち向かわんとしている。
京極高知:四十代で、丹後南部に居を構える武士の頭領。南の流浪王などと揶揄されることもあるが、侍衆を束ねて大江山の鬼から民を守っているれっきとした武人。
●リプレイ本文
閑古鳥が鳴いていた。会合の席で、一人秀吉は酒を飲んでいた。丹後国司の件で広く呼びかけたのだが、今ひとつ反応がない。「ふむ、無駄な時間であったようじゃのう‥‥この件については当分見送るか」
秀吉もいつまでも一人待っている訳にもいかない。近侍の者を呼びつけ、宴の席を片付けておくように申し付け、立ち上がった――。
四名の冒険者達が席上に姿を見せたのは秀吉が帰ろうかという時であった。
「おお、良く来たな。誰も来ぬかと思っておったわ。で、お主らだけか?」
「は‥‥どうやらそのようです。殿下には貴重な時間を割いて頂き恐懼の極みですが‥‥」
恐れ入る藤豊家臣のアラン・ハリファックス(ea4295)に秀吉は笑ってみせる。
「なんの、丹後国司を決めるはそもそもわしの仕事じゃからの。まあここまで反応がないのも意外であったがのう」
すると同じく藤豊家臣のベアータ・レジーネス(eb1422)が進み出て一礼する。
「丹後国司の件は私どもも気にかけてはおりますが、私達がこう言ったからと言って決められるものでもありませんし、みな遠慮したのではないでしょうか」
「左様か。民には関心の少ない事であったかな」
秀吉は扇を弄んだ。冒険者ならば、国司選定に忌憚のない意見が出るかと考えていたのだが、これは秀吉のあてが外れたと言えよう。
それから秀吉は白翼寺涼哉(ea9502)とチサト・ミョウオウイン(eb3601)に目を向ける。
「お初にお目に掛かります。京都の医師、白翼寺涼哉にございます。丹後に関わる機会が増えて参りました。以後お見知りおきを」
「丹後に縁あるチサト・ミョウオウインと申します‥‥宜しくお願いします‥‥(ぺこっ)」
面子が揃ったところで、秀吉は彼らの意見を聞くことにする。たった四人の冒険者の意見を、秀吉が国司選定の参考材料にするかは疑問だが、逆に云えば、皆が関心を示さなかった所にやってきた四人である。
アランはギルドで手に入れてきた丹後関係の報告書を秀吉に差し出した。
「秀吉公にはご存知かも知れませんが、いずれの候補者も丹後の土着の豪族であり、前国司が滅亡した後は競って丹後の覇権を巡って対立したと言う経緯があるようです」
「なるほどな‥‥いや、わしも丹後の内情は最近になって知ったばかりじゃ。前国司の死後、荒れた話は耳にしていたが」
「丹後国司は置くべきでしょうが‥‥現状では誰が適任かは判断の難しいところです」
白翼寺は思案顔で提言する。
「僭越ながら申し上げれば、差し当たり選考基準を設け、候補者達に機会を与えるべきかと。と言って丹後において無用の対立が起きぬように配慮する必要があるでしょうが‥‥」
「もっともな話じゃ。今は人同士が争っている場合ではないからの。選考基準は今の段階ではわしの胸にしまっておくべきかのう‥‥」
秀吉は報告書に目を落としながら言った。
チサトも選考基準を設けるべきとの意見には賛成であった。今後の状況を見極めた上で、国司の選定は判断すべきであると。
「選考基準を明確にし、その基準によりまかり間違っても互いに足の引っ張りあいをなさぬよう縛りをかけ、互いが力を出し惜しみせず、最善を尽くす事がこの難局を乗り切る原動力になるのではないでしょうか‥‥」
チサトの切なる願いを秀吉は真摯に受け止めた様子である。
「そなたはどう思うか、選考基準についてこれと思うところを申してみよ」
「はい‥‥恐れながら‥‥」
チサトは穏やかな口調で述べる。
一、民の安寧の為、身を粉に共にこの難局に取り組む姿勢
一、個の利益を捨て、大局の為に不利益すら甘んじる姿勢
一、領民を犠牲に己が利益を追求する様な者は国司の器に非ず
一、藤豊家自体への恭順の有無は無関係
「白翼寺殿にも提案がおありかな」
「私が重要視するのは、藩主としてのカリスマ性はもちろんのこと、領民を守る姿勢でございます。当然イザナミや大国主等の敵勢力と渡り合える度量も求められるでしょう。後は私見になりますが、他藩に甘く見られないだけの外交手腕、公と民とのバランス感覚を持った人物が相応しいかと」
「妥当なところじゃが、中々理想の藩主を求めるのも厳しすぎるであろうな。どの藩主も民のために奔走しているのが丹後の現状であろうが‥‥アラン、そなたはどう思うか」
「は‥‥私も白翼寺殿とチサト殿の意見に賛成です。私が重視する点は血筋や家柄、天津神などとも付き合っていける人物の懐の深さでございます‥‥もっとも、血筋や家柄については、先に申し上げたとおり、誰が有利とも思えませんが‥‥」
ただし、とアランは付け加える。
舞鶴藩主は妻が突如大国主の下に走ったという点と、民からの不信もあり盗賊団と結託していたという噂もある、以上のことから油断のならない、最も国司より遠い人物であると評した。また、おいおい極秘裏に身辺調査も必要との見方を示したのである。
「‥‥意外に切れ者のようじゃの。変心した理由が今ひとつ分からないが」
秀吉は報告書を読みながら呟いた。それから秀吉はベアータの意見も聞いた。彼も選定基準を設けることに賛成であったが――。
「国司を配置した場合ですが、真っ先に起こるのは『ジャパンの王』を名乗る大国主神の軍勢による反抗と思われます。丹後諸藩やそこに住まう住民達をよくまとめ、イザナミ軍、盗賊団、鬼の軍勢等の内外の脅威から住民達を護り、大国主神率いる亡霊軍団や大国主神に心酔する住民達と渡り合える国司、となると人選は慎重に行うべきかと存じます」
「大国主か‥‥確かにあ奴は厄介じゃのう。丹後の民心を掴んでおるようじゃ。まあ、本物であれば大神じゃからな、それも当然といえば当然かの」
都から大国主に打つ手は現状ない。ただ大国主はイザナミ軍とは違って今は積極的に戦を仕掛けてきていないので後回しになっている‥‥丹後の大名たちにとっては脅威であろう。
「いずれにしろ、時間はあまりございませんが、何卒熟慮の上ご判断の程をお願い申し上げます」
ベアータはそう言って締めくくった。
そうして一通り話を聞いた秀吉は冒険者たちに酒を勧めた。一段落して関白と歓談する冒険者達。
「さて‥‥ではそろそろ幕引きかの。こう見えてわしも何かと仕事が多くてのう。誰か代わってくれんかのう」
秀吉が立ち上がったので、冒険者達も慌てて立ち上がり一礼する。
「丹後の件は今しばらく置くとしよう。このたびは大儀であった」
秀吉はそう言って、会合の終幕を告げた。