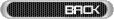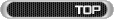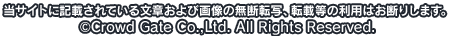楽士たちの歌・企画編ヨーロッパ

| 種類 | ショート |
|---|---|
| 担当 | 香月ショウコ |
| 芸能 | 3Lv以上 |
| 獣人 | フリー |
| 難度 | 普通 |
| 報酬 | 7.9万円 |
| 参加人数 | 7人 |
| サポート | 0人 |
| 期間 | 08/10〜08/14 |
●本文
●静寂と音楽の満ちる世界そこは街から遠く離れた、自然の奏でる音以外存在しない、雑音の無い世界。
マリアンネ音楽学院。創設者の名が冠されたこの学院には、クラシック音楽の道の先頭を歩きたいと願う若者が集う。
学院は全寮制で、学院の生徒達は親元を、都会の喧騒を離れて、仲間と、ライバルと切磋琢磨しながら己の腕を磨いていくのだ。
マリアンネ音楽学院。
そこは街から遠く離れた、自然の奏でる音以外存在しない、雑音の無い世界。
の、はず。
音楽学院の敷地の一角、弦楽器科では‥‥
●雑音と活気の満ちる世界
「クラウス! あんたの辞書には『学習』って言葉はないの!?」
「悪い、くしゃみが出そうになってさ」
「この僕、エルハルトの記憶によれば、その言い訳は2時間前にも使ったね」
「アウレリア、今日の昼食代貸してー」
学院は6年制。生徒は4年に進級すると、学院側の決定した他の3人の生徒とカルテットを結成し、練習に勤しむことになる。
結成されたカルテットにはランクがつけられ、それは毎月の演奏会の結果によって変動していく。その変動していくはずのランク制の中で、全くランクの変動の無いカルテット。
カルテット『Z』。クラウス、リーゼロッテ、エルハルト、アウレリアの4人で構成される、学院の落ちこぼれカルテット。
彼らと彼らを取り巻く人々を中心に繰り広げられる舞台。
舞台演劇『楽士たちの歌』の企画が始まった。
●好奇と熱気の満ちる部屋
「と、いうわけでね。その舞台の脚本を書くにあたって、皆さんから案を募集したいと思ったのだよ」
と、いうわけで、簡単な設定だけが載せられた紙を片手に笑顔で言うのは劇作家のヘラルト・リヒタ。
「キャストに関しては、カルテット『Z』以外は生徒でも教師でも用務員でも親でも誰でもいいと思っているよ。そのあたりは応変に考えてくれて構わない。で、シナリオ案なんだが、絶対ではないが3つから4つ、テーマが違う物を作ってもらえるとありがたいな」
どうか、よろしく頼むよ。と人懐っこい笑顔を浮かべたまま、ヘラルトはもう片方の手でカップを持ち、コーヒーを口に含んだ。
●リプレイ本文
●第1楽章・出会い「‥‥今回は畑違いが混じってすまない。高校の時に部活で仲間と下手なりに頑張った頃を思い出して‥‥な」
そう話す春乃(fa3572)に、ヘラルトは微笑んで。
「構いませんよ。寧ろ大歓迎です。自分の想い出に基づいた言葉は、ただの作り話より強く心を打ちます」
第1話となる『第1楽章』では基本的な世界観を構築しなければならない。ここでの主要人物の設定の大まかな部分は、春乃の案が用いられることになった。
「テーマとして言葉が提示されていると、ひとつひとつの話が構築しやすくなるね」
自分も企画案のカルテットメンバーと同じく音楽学院に通うセシル・ファーレ(fa3728)はこの舞台に親近感を持ち、脚本の仕事は未経験ながらも案を提供する。カルテットは如何にして結成されたのか、メンバーたちの心には何が浮かんでいたのか。セシルの案、そのテーマは『絆』。
――カルテット『Z』のリーダー、クラウス。4年進級時に生じた迷いが演奏を鈍らせている。
――良家のお嬢様、リーゼロッテ。活発な雰囲気の女性で、最近はクラウスを叱咤する日々を送る。
――見た目だけ知的なエルハルト。クラウスの幼馴染みで彼の悩みを知る。本番での失敗癖アリ。
――あがり症のアウレリア。真面目で勤勉だが自信を持てずエルハルトと逆の意味で本番に弱い。
――ある晴れた昼下がり。クラウスはいつもの場所でいつものように昼寝をしようと寝転がる。
――空をぼんやり眺めながら、クラウスの脳裏にふと蘇るのは過去の思い出。4年進級の時期。
――カルテットを結成した自分たち4人。そういえば、何がきっかけで出会ったのだったか。
――いつの間にか眠ってしまうクラウス。響く鐘の音。カルテットでの自主練習の時間になる。
――自分を呼ぶ声にクラウスが目を覚ますと、そこにはクラウスを探しに来たカルテットの皆。
●第2楽章・楽器
「久しぶりやね、先生はん。今日はエミリアはんは居らんようやね。残念や‥‥いや、こっちの話や」
「?」
ヘラルトと親しく話すのは紺屋明後日(fa0521)。以前にロボット談義で華を咲かせた仲である。
紺屋の案は、テーマを『兄弟(姉妹)愛』としたものだ。
「‥‥今回は俺以外女性や、なんか場違いな感じが‥‥」
「大丈夫。僕は女性じゃないから安心してくれ」
観月紫苑(fa3569)は、他の皆とは少し違った案を持ってやって来た。他の話と全く同列に並べるには違和感のある内容だったが、しかし音楽学院という世界観を見ると、美しい話だ。
「この話を、少しこちらの案とミックスしてみるのはどうだろう?」
ヘラルトの指し示すもう片方の案。
――学院に併設された学校。楽器職人育成のための場である。そこに通うZメンバーの弟(妹)。
――卒業した後目標とする職人の元へ弟子入りする事が決まったが、認められるか不安である。
――弟(妹)を励まそうと、弟(妹)の楽器で演奏会を行うことに。演奏の練習も始める皆。
――完成した楽器を受け取ったZメンバーの一人(兄・姉)。音楽準備室で練習を開始する。
――唐突に高鳴る鼓動。その後、様子のおかしくなる彼(彼女)。一心にある楽曲の練習を行う。
――いつまで経っても完成しない曲。やつれていく彼(彼女)。不審に思った他メンバー達は調査する。
――すると、準備室で亡くなった生徒がいたことが判明。その霊が取りついているのかもしれない。
――同時に、曲を完成させられないのは弟(妹)の楽器の不備があることも原因のひとつと分かる。
――自分の作った楽器の不備を修正しながら、弟(妹)は楽器に込められるべき想いについて考える。
――直った楽器を持った彼(彼女)に他のメンバーも加わり、曲を演奏する。還っていく霊。
――『認めてもらえずとも、努力を続ければ必ず認めてもらえる』演奏を聴きそう感じた弟(妹)。
●第3楽章・劣等感
パソコンで打った資料を片手にプレゼンを行うのは織石 フルア(fa2683)。紺屋と同じく以前ロボ談義に華を咲かせた彼女だが、今回の案にはロボは登場しない(当たり前か?)。
「私がテーマとして考えたのは『初心』もしくは『リスタート』。彼らが音楽学院に入学した当初の気持ち、それを改めて思い出して志を新たにするという、そんな話になればいいなと思って書いてみた。‥‥ところで、欧州の入学式は9月でよかったよな?」
「ええ、合ってますよ。まあ、もし違っていても、この学院はそうなんだと言い張ってしまうことも可能なんですがね」
この織石の案に、この案を合わせてみたいとヘラルトが思う案を持ってきた参加者がいた。四條 キリエ(fa3797)である。
「舞台脚本は初めてだけど、こういう裏方も面白いもんだね」
と話す彼女が持ってきた案のテーマは『隠れた努力』。
「自分の主張したい、表現したい世界。その設計図を作ることが出来る。この楽しさは一度味わってしまったらそう簡単には抜け出せませんよ」
四條の案のテーマは、学生達の青春を描くには最適な案のひとつ。ライバルの存在。
――音楽学院の、実力主義のとある教師がカルテットZにした指示。それは、入学式の手伝い。
――万年最低ランク、少しは学院の役に立つことをしろ。そんな教師の言葉に反発し練習するメンバー。
――そこに現れたのは生徒カルテットのトップ『A』。高飛車な態度で接せられ、メンバーは劣等感を抱く。
――挫折を感じたメンバーの一人は、ある夜寮を抜け出し『開かずの間』と呼ばれる古い練習室へ向かう。
――侵入法を知っていた彼(彼女)はそこで物思いに耽るが、他の侵入者の気配に身を隠す。
――侵入者はカルテットAのリーダーだった。彼はここで規定時間外の練習をしていたのだった。
――その実力の裏には、必死の努力があった。ちょっとした事故で二人は鉢合わせしてしまうが、
――その夜のことは内緒の約束で、日常へと戻っていく。
――彼(彼女)はメンバーを励まし、入学当初の希望に満ちていた頃の気持ちを思い出す。
――入学式での演奏の役目。そこをひとまずの目標とスタート地点と定め、4人は練習に打ち込む。
●第4楽章・演奏会
この場面については、第1楽章の人物設定の案を出した春乃の案が用いられた。本番の結果がどうなるのか、その後の4人はどうなるのか。それはきっとこれから詰められていくことになるだろう。
――音楽学院も成績の良くないカルテットをそのまま放置しておいたりすることはない。
――全く状況が良くならないのには何か問題点があるのだろうと、カルテットZへの対応に動き出す。
――突然呼び出しを受けたクラウス。学院長が彼に言った言葉「次の定期演奏会の結果次第で解散」。
――カルテットZは、1ヵ月後の演奏会に向け合宿を行う。そこで明らかになる各自の悩み・想い。
――喧嘩も多かった。辛いこと苦しいこともたくさんあった。でも。思うことは4人とも同じ。
――「この4人で音楽を続けたい!」
――1ヶ月はあっという間に過ぎ行き。4人は運命の演奏会当日を迎える‥‥
●ごちゃごちゃのメモ帳
予定していた時刻を多少過ぎながらも、どうにか舞台演劇『楽士たちの歌』企画会議は終了した。色々な、しかも楽しい有用な案が数多く出たため、ヘラルトのメモ帳には書き込みがびっしり。会議終了後に「ここなんて書いたんだろう?」などと参加者に聞くことまである始末。
後日、正式にこの企画は動き出した。ここから先、企画者達が発案した物語は、人物達はどのような成長を遂げ、どのような生き方を送るのか。今後の動向に注目すべし。