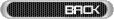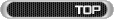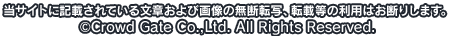演劇習慣中東編第二週中東・アフリカ

| 種類 | ショート |
|---|---|
| 担当 | 香月ショウコ |
| 芸能 | 3Lv以上 |
| 獣人 | 1Lv以上 |
| 難度 | やや難 |
| 報酬 | 8.2万円 |
| 参加人数 | 7人 |
| サポート | 0人 |
| 期間 | 10/30〜11/03 |
●本文
企画『演劇習慣始めよう・劇を忘れた古い日本人よ』略して『演劇習慣』。それは5月に(遊びに)来日したドイツの劇作家で演出家のヘラルト・リヒタが日本の劇団主宰円井 晋とタッグを組んで行った、一週間(平日)を通し連続してそれぞれ別テーマで公演を行い、人々に芝居を見る習慣をつけてもらおうという企画である。ちなみに、週間と習慣がかけられている。この演劇習慣の第2弾がつい先日円井の指揮で日本にて行われた。その第2弾からあまり間をおかず開催が決定した第3弾は、ヘラルトが複数の協力者と共に行う世界同時開催であった。
初回の演劇習慣はひとつの単語が、前回の演劇習慣ではひとつの問いかけがテーマとして提示され、それに基づいた、或いはそれから連想される舞台を作り上げてきたが、今回の世界規模演劇習慣で提示されるのは『色』である。それも『空の色』。
提示された色に含まれた意味、連想される物、情景。あなたにとってこの空の色は、何の色?
●演劇習慣中東編第二週
『セレスト・ブルー』‥‥神居ます至高の青
この世のものならぬ、妙なる空色の美称。似た意味のゼニス・ブルーという青があるが、それよりは多少明るい空の色。
提示されているものはこれだけ。神という単語から場面を設定しても、色の名前の由来を追うストーリーとして関連付けても構わない。この『空の色』に合わせた脚本の作成と、それに沿った舞台演出、音響や照明などなど、舞台に必要な色々の準備が目的である。
なお、この第二週で創られた物語が第四週役者編のストーリーとなる。
●リプレイ本文
セレスト・ブルーを題材にした物語の製作は、まずは色々なところでスタッフをこき使うところから始まった。脚本は裏方陣がエピソードを幾つか提案し、それを白蓮(fa2672)が持ってきた『砂漠を渡り隣町へ向かうバス』の中で繰り広げるという形になる。その決定稿ではない完成版を、少し遅れてやってきた、演出を務めるケイ・蛇原(fa0179)が読み進める。
基本的に、用意されるセットはバスの内部のセット。その後部座席がメインの舞台となる。
バスのセットは、二郎丸・慎吾(fa4946)が指揮を執って作られた。完成が程近いバス内部の装置類は、一部本物を流用している。脚本の概要が決定した段階から何度か廃車置場に足を運び、使えそうで、かつ使っても良いと言われた椅子を引っぺがして持ってきたのだ。やはり長期間放置されていた廃車の座席だけあって埃まみれだったり、金属部分に錆が浮いていたりと散々なものばかりだったが、それも丁寧なクリーニングで新品同様とまでは行かないが現役のバスの座席らしさを取り戻した。舞台上に詰まれる平台などに固定されるその座席は何とリクライニング。快適なバスの旅をお楽しみ頂ける。
ただ、残念ながら必要なだけの数を全て廃車から拝借することは出来なかった。仕方なく、手に入らなかった一番後ろの長い座席だけは二郎丸の自作となる。リクライニングの仕組みを作る必要もなく座れればいいだけの座席だが、二郎丸の中に潜むリアル志向の血が騒ぎ、座り心地以外は本物そっくりの完成品が出来上がった。
全体的な大きな部分の世界を作り上げた二郎丸。これに合わせて、小さな部分で世界を補完する小道具たちを作ったのは八嶋かりん(fa4978)。高い技術は無いものの脚本や演出の意図を予め読み取って作られる道具達は脅威の低リテイク率を誇った。これら小道具類は役者のポケットに入るほか、舞台上にハの字に並べられたバスの座席の後ろに巧妙に仕込まれ、舞台の要所要所で登場する。ちなみに座席の配置は、分かりやすく言うと観客席側が運転席、バスの進行方向型。ガクガクと直線的に配置されたオーケストラのような布陣だ。奥に行くほど雛壇のように組まれた台によって高くなっていく。後部座席に座る役者は落下注意である。舞台両袖はバスの内外を示すため段は組まれていない。逆に言えば、役者は走るバスから飛び降りても。いや、やらないでね?
以上の大きな装置類、数の多い小道具などについては、紗草みりん(fa2632)も手を貸して製作している。彼女の本業は放送作家だが、本分である脚本書きには参加せず、より素晴らしい作品を作り上げるための経験値集めに裏方の雑用全般を引き受けていた。公の場での、名前が人に知られる(裏方だが)表の仕事は初めてということで時々失敗があったりしながらも、それでも何とか初仕事は無事に進んでいった。
バスに関しては、見た目だけでなく音にもこだわっている。興味がある仕事への布石、第一歩として音響に挑戦するのは歌手が本業のラム・クレイグ(fa3060)。彼女は今回の舞台のテーマソング的な歌を作る静流(fa1698)に引っ張られながらも実物のバスの走行音やドア開閉などの効果音を収録してまわった。収録を終えると次は編集作業。混じってしまった余分な音を除去したり、音量を調整したり。コレが実に地道で細かく面倒な作業なのだが、そういったところで手を抜いてはいい作品は生まれない。頑張るのみである。
ところでバスの走行音といえば、現実にはバスが走っている間ずっと聞こえ続けるものである。だが舞台での芝居で流し続けていては耳障りな雑音となり、観客の集中力を削いでしまう。こういった場合はバスの停止や動き始めの前後のみ長い効果音として混ぜ、役者のセリフや他のBGMに紛れさせて次第に消し去るのが常套手段である。音響機材を操作する現場は、精密な操作を必要とするためひたすら神経を削られることとなるが。
「ケイさーん。ちょっとスタッフさんたちとバスの映像について打ち合わせに抜けますんでー」
と二郎丸は何か色々書かれた数枚の紙を持ち、ケイの「了解した」という意味の合図を受けて外へ出て行く。芝居の冒頭部分、緞帳をスクリーン代わりにしてそこに本物のバスが走る映像を写すのだが、その作成を依頼するためだ。
一方では白蓮の物語を読みつつ、一方では全体の確認をしつつ、さらに一方ではやってくる演出案の提案や質問に答える。物凄く多忙なケイだが、頼りにされているからなのだろう。それもきっと年の功だけではなく、様々な要因によって。
「バスが揺れた時の演出を出来ないでしょうか、動く台の上にバス内部の席を設定して、縦揺れは演技でカバーするようにするんです」
「動く台は、上で演技する役者が多少危ないですね‥‥バスの揺れの演出をするだけならば、フロント(フロントライト。客席真上)かシーリング(シーリングライト。客席両サイド)に人を置いて、ライトを繋ぐ棒を用意し、要所要所でそれを軽く小突くことでも見せられますな。ただ、客の目がそっちに向いてしまっては、演出としては失敗ですが」
決定は少し保留。全体の意見も聞いてから決めようということになった。
――バスの名は『セレスト・ブルー』。セレスト・ブルーは『神のいる至高の天空』の色を指し、その名がバスに冠されたのは、砂漠の中、神へ捧げ物を送るための祭壇の近くを通過するため。捧げ物は牛やヤギ、植物、時にヒトの心臓。次の捧げ物の儀式までの平和と豊穣のために、人々は神を崇めていた。
――普通なら、そんな迷信馬鹿らしい、今ならそんな事はしないのにと話は終わる。だがバス内の話は意外な方向へ。
――捧げ物によって得られた平和や豊穣。それは本当に捧げ物のおかげだったのか? いや、その地に住む人々の祈りの積み重ねによるのではないか。捧げ物をした後の時代が運良く繁栄の時代だったのかもしれない。だが人々の努力がなければ、運など容易く逃げていってしまうものだ。
「主人公の青年が、このバスに乗った経緯というのは?」
ケイが白蓮に聞く。
「最後の最後に観客には分かるんですけど、主人公は自分の死ぬための場所を探しにバスへ乗ったんです。自分の不甲斐無さ、愚かさを呪って。そのバスの中で、一緒に乗っている乗客の話を聞くうち、少しずつ何かが変わっていくんです」
――捧げ物、と言えば。語りだした別の乗客。
――生贄ではないが聖歌は神に捧げる歌。修道院や教会で修道女や神父が捧げる祈りは、祭壇で儀式を続け、祈る人々のそれと同じものと言えるのではないか。
――自分にも、神に心を捧げるように、想い心揺らした恋人もいたの。なんて。進む道が違って別れたけれど、それまでに一緒に過ごした時間が無駄だとは思わない。それは大切な思い出。離れてしまった事は淋しいけれど、別れは始まりでもあるから。
「ちょっとそこでストップですね。日本やアメリカ、ヨーロッパなら問題無いですが、地域柄を考えましょう。聖歌やら教会やらは、ちょっと扱うには怖い言葉ですね」
台本の流れを聞きながら確認していたケイが、そう指摘する。確かに、この地域は殆ど皆がイスラム教徒。そこにキリスト教系の話を持ち込むのはちょっと怖いかもしれない。実際のところではどうなのかは分からないが、その実際のところを見ないで済むに越したことはない。
――そのバスは、主人公の青年が見た幻だった。
――死を目指し進む青年に、君はまだ死ぬべきではないと訴える乗客たち。彼らは、青年がこれまでに犠牲にしてきた者たちだった。
――進学のため野球を諦めた。捨てた、野球を続ける自分。
――都会へ出るために愛する人との生活を諦めた。捨てた、愛する人と暮らす自分。
――後に聞いた愛する人の病気、死。地元へ帰ることを捨てた自分、犠牲にした彼女。
――だが乗客たちは言う。自分たちは犠牲になったわけじゃない。今の君を支えている柱だ。悔いる必要なんか一つも無い。
――バスを降りた青年。結論は出た。迷いも、もう無い。
「基本的に、この舞台は主人公の内面を描く劇と理解して構わないのでしょうか? ここまでの流れを見ると、バスというのは自分の意識・思考の中、バス内での会話は自己との対話と言えそうなのですが」
というケイの言葉。これがこの舞台のキーとなる話題なのだが、これに関わるところで静流の作ったテーマソング的な歌の歌詞を見てみよう。
――遠く遠く何処までも 吸込まれてしまいそうな空の色はまるで貴方の瞳の様ね
――貴方の眼差しは あの青空にいる小鳥のような私の心をそっと包み込んでくれる
――神様の所へ上る階(きざはし)の色はきっと貴方の瞳の色ね
――黄金色の砂の海に広がる空
――いつか二人で一緒に見つめたい空の色‥‥セレスト・ブルー
吸い込まれてしまいそうなその色は『貴方』の瞳のよう。『貴方』の眼差しは『私』の心をそっと包み込んでくれる。『神様』の所へ上る階の色は『貴方』の瞳の色。
ここで、セレスト・ブルーのバスが自己の内面を囲む枠と捉えると、自己の内面を覆う蒼は青年の世界観であり『外面』、それが包み込む、内面の中に浮かぶ『私』とは『自己』、『自己』の理想とする答えに辿り着く階段は『きっと』自己の外面の色、と考えられる。
自己の『外面』と『内面』の対話。これと言える答えに辿り着くには、その対話の中で自分自身の決定をしなければならない。それがこの舞台のメッセージとなるのではないだろうか。
きっと世界に神などという超越者はいない。セレスト・ブルーの空には神が住んでいそうだと感じる。それは、自己の中には神がいる、自己こそが世界の中で自分のありようを決められる存在であると、そう告げることが出来るのではないか。それは身震いするほど素晴らしいことであり、しかし時に逃げ出したくなるほど恐ろしい過酷さと葛藤をもたらす。
「神はどこへいくのか。人間の進む先に、でしょうなぁ」
丁度聞こえてきたのはラムの作ったBGMたち。神居ます至高の青を思わせるような荘厳で、壮大な曲。この曲の他で、一部は聖歌を連想させることから作り直しになるだろうが、このチェロとピアノの協奏曲は文句無しの出来栄えだと思う。
「それではこの方向で仮決定として、役者とのイメージすり合わせと保留にしてあるところを早めに詰めて、本格的に動き出すといたしましょうか」
演出のGOサインが出て、裏方陣の作業はさらに速度を増していく。