秋の夕日にアジア・オセアニア
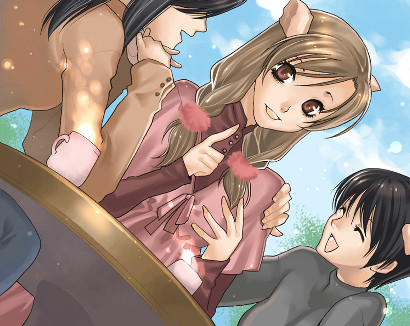
| 種類 | ショート |
|---|---|
| 担当 | 葵くるみ |
| 芸能 | 1Lv以上 |
| 獣人 | 1Lv以上 |
| 難度 | 普通 |
| 報酬 | 0.7万円 |
| 参加人数 | 7人 |
| サポート | 0人 |
| 期間 | 10/16〜10/18 |
●本文
赤い、赤い――楓の葉。くるりくるりとそれが空から降ってくる。
少年は一人立ち尽くし、それをじっと見つめていた。
出会いはほんの一ヶ月前。
学校のベンチに座って読書をする姿がきれいで。
昔、出会ったことがあるような気がして。
「あのっ」
気がついたら声をかけていた。
すると――その少女は、長い黒髪をかきあげ、そしてふわりと微笑んだ。
「恋なんじゃねーの? それってさ」
悪友がけたけたと笑う。彼としては冗談半分に言った言葉なのかもしれない。けれど、そういわれて気づく。
「そうかも、しれない」
意識してしまったら、胸の高鳴りがうるさいくらいになっていた。
「もうすぐ、引っ越さなくちゃいけないの」
少女はそう、少年に言う。
「父の仕事の関係で」
切なそうな声。
「この場所とも、この学校とも、お別れ」
さびしそうな、声。
「‥‥もうすぐ文化祭ですね」
あなたは何か参加するの、と少女は問う。少年は特に今のところ考えていなかった。
「‥‥もしよければ。文化祭、一緒に回りませんか」
少女は微笑む。その笑みがとてもきれいで、少年はうなずいていた。
●青春ドラマ「秋の夕日に」では、出演者とスタッフを募集します。
少年‥‥主人公。名前は適宜。ひと月前少女に一目ぼれし、文化祭を一緒に回る約束を交わした。平々凡々な印象。
少女‥‥名前は適宜。主人公が一目ぼれした少女。転校を間近に控えている。少年と思い出作り(?)のために一緒に文化祭を回る約束を交わす。
悪友‥‥名前は適宜。主人公の悪友で、よくつるんでいる。主人公の本気の恋を、かげながら応援している。
以上三名必須。ほかにクラスメイトや教師、家族などを場合により増やしてかまいません。
物語のメイン部分は「文化祭」です。展示めぐりなどで過ごす一日を描きあげてください。また、恋愛ドラマでもあるので、主人公たちの恋をきれいな形で(OP冒頭につながるような形で)締めくくらせてあげてください。
基本的に主人公と少女の文化祭での行動は「展示めぐり」中心です。よくある学校の文化祭をイメージしてくださるとありがたいです。
では、皆様のご参加、お待ちしております。
●リプレイ本文
●「‥‥あ」
宮下紅葉(渡会 飛鳥(fa3411))は自分の座るベンチにゆっくりと近づいてくる人影に、高鳴る胸をどうにか押しとどめた。
「岡崎くん‥‥来てくれたんですね」
やってきたのは、ごくごく普通の少年(氷咲 華唯(fa0142))。雰囲気も凡庸だが、その笑顔は人に安心させてくれる何かがある。少年――岡崎祐二は、小さく笑う。
「約束破るなんてしないよ。宮下さん」
「そう、そうですよね」
祐二の言葉に、紅葉もくすっと笑いを漏らした。それと同時に、なんともいえない感情がこみ上げてくる。
紅葉の父は典型的な転勤族だった。ひとつの場所にほとんど留まることがない。さらに父親の方針で、単身赴任をよしとしない家だった。だから、紅葉は心から親友と呼べる相手ができるまでひとつところに住んだ記憶がない。友達と仲良くなっても、またすぐに次の引越しを言い渡される。それは幼心にひどく寂しくて、悲しかった。
でも、紅葉はそれでも忘れられない思い出をひとつ、いつも胸に抱えていた。それは、自分の中で一番遠くて、でも鮮烈な記憶。
まだ舌っ足らずだったころに『ゆーちゃ』と呼んで慕っていた男の子がいた。紅葉が引っ越すことになったとき、指きりを交わした。『またぜったいあおうね』と。
その思い出の街こそこの街である。けれどあまりにも幼くて、淡い初恋の相手の顔もうすぼんやりとしか覚えていない。
(「岡崎くん‥‥『ゆーちゃ』なのかな‥‥」)
隣で微笑む少年に、当時の記憶を重ねるけれど、はっきりとはわからない。祐二もそんな幼少時の、一時しか近所に住んでいなかった女の子のことなど覚えていなかったようだし。
でも、と紅葉は手で小さく拳を作る。
「楽しみましょうね。文化祭」
「うん」
紅葉の声に、祐二は頷いた。
●
話は少し遡る。
「また、転校しなくちゃいけなくなっちゃったの」
紅葉はクラス委員長で友人の風間由姫(風間由姫(fa2057))に、弁当を食べながら小さく呟いた。
「え‥‥まだこの学校に転校してきて、一年たってないでしょ?」
由姫は食べかけのハンバーグを飲み込んで、驚いた顔でたずねる。メガネをかけた、やや気弱そうな由姫は、それでもしっかりクラス委員長であろうとがんばっている。周囲に敵わないこともあるけれど。
「うん。文化祭が終わったら、多分すぐ引越し」
紅葉の声が沈む。
「私は慣れてるから、大丈夫だから。文化祭は、参加するし」
紅葉は小さく笑った。由姫は寂しそうな顔をするが、仕方がない。
「そうだね。いい思い出作らないとね」
そう言うと、由姫は弁当箱をしまう。そして声を張り上げ‥‥ようとするが、気の小さな由姫にはなかなか難しい。
「あ、あの、皆さん。今日は午後から文化祭の準備に入るから、そろそろ教室の準備を‥‥」
由姫の声は教室になかなか響かないのだ。と、様子を見に来たのだろう、小うるさいと生徒たちに敬遠されがちな藤田幹子教諭(氷咲 水華(fa3285))がパンパンと手を叩く。
「ほらほら、もう昼休みも終わりよ。あなたたちも早く持ち場につきなさい。クラス委員ももっと声を出して」
藤田教諭のきびきびした物言いに、生徒たちは文化祭の準備に向かっていく。紅葉たちのクラスは文化祭の定番――喫茶店を開く。そのため、教室を飾り立てたりするわけである。もちろん部活動の企画が忙しい生徒も多いけれど。
「アサキせんせー、ちょっと手伝ってよー」
廊下のむこうから歩いてくる教育実習生の神薙アサキ(神代アゲハ(fa2475))に大声で呼びかけているのは隣のクラスの尾形幸也(羽生丹(fa5196))だ。その声に、廊下や教室のあちこちからくすくすと笑い声が漏れてくる。幸也はそういえば祐二と仲がいいんだっけ、と紅葉はぼんやりとそれを見つめる。アサキはその大声にぎょっとしていたが、かわいそうに、そのまま引きずられるようにして隣の教室に連れ込まれていった。
「私たちも準備しなくちゃ。みんな頑張ろう」
由姫の声がやっと届いたのか、クラスメイトたちはわいわいと準備に取り掛かりだした。
●
「ほら、行こう。宮下さん」
そう言う祐二に、紅葉ははっとする。そして、小さく笑った。
「どこから見て回ろうか。せっかくだから一通り見て回りたいよね」
そう言う祐二の顔は、ほのかに赤い。それに気がついたら、急に紅葉も顔が熱くなってきた。
「じゃあ、一階から順に」
「こっちからだね。楽しもうね」
そう言いつつ、二人は校舎に向かう。二人で歩いているのだと思うとき恥ずかしくて、ちょっと紅葉は俯きがちだ。
「お、そこのお二人さん! うちのクラスの射的に‥‥って、祐二かよ」
プラカードを持って声をかけてきたのは幸也だ。
「お前こそ、自分のクラスの奴に呼び込みかけるなよ。びっくりする」
祐二は顔を赤くしながら反論する。と、幸也は二人をじいっと眺めて、そしてぽんと祐二の肩に手を置いた。小声で
「‥‥お幸せに」
と言いながら。途端、祐二の顔は真っ赤になる。
「そ、そんなんじゃ」
「まんざらでもないくせに。えっと‥‥隣のクラスの宮下さんだよな。こいつと付き合ってるの?」
そう問われて、紅葉も顔を赤くする。でも、肯定も否定もしない。
「ふうん‥‥?」
意味ありげな声を出して、幸也は二人をじっと見る。何かが引っかかる、と言う顔をしている。そしてもう一度祐二の耳元で、囁いた。
「お前、気づいてやれよな」
「‥‥?」
幸也の発言に何か不思議なものを感じつつも、小さくうなずく祐二だった。
お化け屋敷では、入るのを拒みたかったけれど、結局悲鳴を上げることもなく無事に出てきた。つい怖くて握った手は、出てすぐにぱっと離した。
でもその感触がなんとなく心地よくて、祐二はそっと紅葉の指をつかんでみた。拒絶はされなかった。
体育館でのバスケットボール部の招待試合では二人で手を叩いて応援した。
武道館ではいつも内気な由姫の合気道の披露を見たし、校庭の模擬店ではちょこちょこと買い食いもした。由姫にちょっぴり羨望のまなざしで見つめられたけれど。
教室展示や講堂での演劇発表なども沢山見たし、教室の喫茶店はほとんどを制覇したのではないだろうか。
保健室の教諭・光武(仲間好色(fa5825))と保健委員が企画した体力チェックでは、祐二が実はかなりの握力の持ち主だと判明したし、図書委員の企画である古本市では紅葉が色々と面白そうな本を嬉しそうに探していた。
二人はこれでもかとばかりに動き回り、驚き、笑い、楽しんだ。
●
後夜祭がまもなく始まります。生徒は体育館に集合してください‥‥。
そんな放送が、あちらこちらのスピーカーから聞こえる。楽しい文化祭も、もうすぐ終わりだ。
と、ふと掲示板に紅葉の目がとまった。
新聞部の展示のひとつで楓の美しい、街のとある場所の写真だ。その光景は幼い日の記憶を揺り起こす。
ここを私は知っている。
『ゆーちゃ』と指きりを最後に交わした場所だ。
「‥‥懐かしいです」
ポツリと紅葉が言葉を漏らすと、祐二はきょとんとした顔でそれを見つめてきた。
「‥‥昔にも、この街に住んでたことがあるんです。そのときに一番大好きだった場所でした、この場所」
そう呟く紅葉の顔は柔らかい笑みを浮かべている。
『ゆーちゃ、やくそくだよ。またあうってやくそくだよ』
そういって指きりを交わしたのがついこの間のようだ。と、後ろから同じ写真を覗き込んで来た者がいる。教育実習生のアサキだ。
「お、こいつは綺麗だ。この街の隠れた名所を見つけてきたな」
アサキは写真の場所を知っているようだ。と、祐二がアサキに問いかけた。
「‥‥この場所、すごく昔に見た覚えがあるんですけど。俺もどこの辺りか覚えてないんですけど‥‥知ってますか」
アサキは頷いて虚空に地図を描く。
「まあ、この学校からはそんなに離れてない。何か忘れてたことでもあるのか」
「いや、それも思い出せないんですけど。大事な約束をしていたような気がして」
大事な約束と言う言葉に、紅葉の心がどきりとする。
(「『ゆーちゃ』‥‥?」)
でも、わからないなら、それなら。
紅葉は震えながらそっと小指を祐二の前に差し出した。すると、祐二はするりとその小指に小指を絡ませてきた。まるでそれが当たり前のように。
「え、あ、あっと‥‥昔、ここで、こういう風に約束をした子がいた気がする。うん。引越しがあるから、最後にって‥‥。名前、忘れちゃったけど、初恋だったんだろうな」
「『ゆーちゃ』」
昔呼んでいたその懐かしい呼び名を唇に乗せる。祐二ははっとした顔で紅葉を見つめた。少女は、泣いていた。
「‥‥やっぱり、『ゆーちゃ』だったのね」
「‥‥! 忘れててごめん。でも、‥‥また会えたね」
●
後夜祭の名物と言えば、キャンプファイヤーを囲んでのフォークダンス。
そして、そこで祐二と紅葉も踊る。手をつなぎ、ステップを踏んで。
「岡崎くん」
少女はそっと小指を差し出す。少年はそれに応えるようにして指を絡める。
「今日は楽しかった、ありがとう」
その言葉に祐二はそっと首を横に振る。
「ううん‥‥俺も、楽しかった。その、好きな人と‥‥一緒に思い出を作れて」
「え?」
言葉を理解するよりも先に、ダンスのパートナーが変わった。けれど、心の中にその言葉が響いている。
「私もだよ、岡崎くん」
紅葉は、微笑みを浮かべた。



