タイトル:遭難 マスター:文月猫
| シナリオ形態: ショート |
| 難易度: やや易 |
| 参加人数: 6 人 |
| サポート人数: 0 人 |
| リプレイ完成日時: 2009/04/25 00:21 |
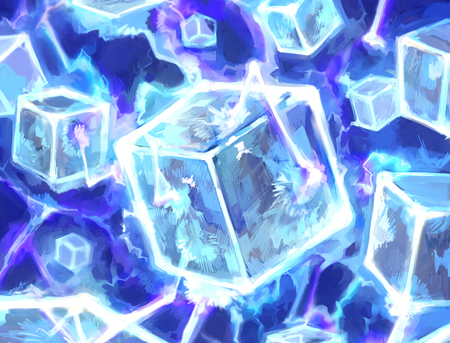
●オープニング本文
「雪崩が発生しただと?!」
その知らせを聞いた、地元の山岳救助隊の隊長は、思わず窓の外に目をやった。
ここら一帯は、ヨーロッパアルプスの中でも特に、春スキーのメッカとして有名で、この時期になっても、多くのスキー愛好家が、雪とゲレンデを求めて集まってくる。愛好家にとって、ここは絶好のポイントなのだ。
だが、季節は4月。当然、気温も高くなり、雪崩の危険も多発する。よって、スキー場の中では、万が一に備え、スキーヤーに注意を呼びかけたり、パトロールを強化したりしている。
「で、誰か巻き込まれたのか?」
隊長は、そばにいた、レスキュー隊員の一人に尋ねた。
「それが‥‥」
隊員は、どう説明しようか悩んでいるようだった。
「おきた場所は、雪崩の危険地帯で、この時期には立ち入りが禁止されている場所なんですが」
と口ごもった。
「ですが?」
すでに、この時点で隊長は、次に言われるであろう言葉を想像できていたのである。
「スキーヤーらしき何人かが現場付近にいたらしいんです」
それは恐れていた事態だった。立ち入り禁止区域に人がいたこと自体、由々しき問題なのだが、ましてや、それに巻き込まれた人間がいたということになると、事態は一刻を争うし、ましてや、関係者の責任問題にもなりかねない。
「それは確か?」
情報が確実であれば、すぐさま行動を起こさなければならない。
「付近のスキー場の従業員が、雪崩が起きた方に向かっていくスキーヤーを見かけたそうです。」
ならば、事は一刻を争う。再び雪崩が発生しないとも限らないからだ。
「で、捜索隊は向かったのか?」
「それが、現場が立ち入り禁止区域であることと、2次災害の危険があって、すぐに動けない状況なんです」
その言葉に、隊長は、半ば絶望感と焦燥感が同時に襲ってくるのを禁じえなかった。仮にもレスキュー隊の隊長として、何も行動できないというのが赦されるわけもなかった。
「何とか、手立てはないのか? 誰か現場へ踏み込む勇気と行動力のあるものは?」
その言葉が、その場にいた隊員たちの頭上をむなしくとおり過ぎていった。
――とそのとき、
「ひょっとしたら」
一人が声を上げた。
「傭兵たちならやってくれるかもしれません」
それは、彼らにとって残された唯一の希望のように思えた。
「早くしないと時間がない。もうすぐ日が沈む」
●参加者一覧
20歳・♂・PN
24歳・♂・GP
20歳・♂・DG
25歳・♂・SN
25歳・♂・FC
21歳・♀・EL
●リプレイ本文
時間は限られていた。傭兵たちが現地に着いた頃には、太陽の影がだいぶ山陰に伸びていた。日没までの時間は少ない。ここへ来る前に、現地の山岳レスキュー隊から供与された、機動力としてのスノーモビル、さらには、上空からの捜索用ヘリとパイロットの助けを受けることができたのは、今後の彼らの行動にとって明るいものとなった。幸い、天気もこのまま持ちそうである。日没までが勝負、ということは、そこにいた誰もが理解していた。現地の山岳レスキューから事前にもらった情報では、夕方になると、温度低下で雪面がアイスバーンのようになり、非常にすべりやすくなるとのことであった。地図で、改めて場所を確認し、捜索分担を決める能力者達。それを遠巻きに見守るレスキュー隊員や地元の住民、スキー場関係者たちで、現場は緊迫感に満ち溢れていた。ヘリもすでにスタンバイし、ローターの回転数を上げていた。(「急がないと」)
能力者の誰もがそう思っていたであろう。雪山救助ということで、皆、防寒仕様である。深墨(gb4129)は、万全を期して、カンジキまで持参している。確かに深い雪のなかでは、非常に便利であるといえる。手早く身に着ける。――春といっても、まだまだスキーができるほどである。雪山は日があたっていても寒い。ましてや、日陰はかなりの寒さであろう事は想像できる。遭難者たちは多分軽装だ。生存していたとしても、体力が心配である。
「現場までスノーモビルで移動しよう」
辰巳 空(ga4698)が、レスキュー隊が提供してくれたスノーモビルに目をやった。現場まではこれで時間が稼げる。ゲレンデのようなところならあっという間に目的地までいけるからだ。能力者たちのうち、ヘリから救援をサポートする、青海 流真(gb3715)以外のメンバーはスノーモビルに乗り込んだ。
「運転は、はじめてなんだけどなあ‥‥バイク経験でなんとかなるよな」
安原 雅人(gb4267)は、初めてにしては巧みな運転で、スノーモビルを操り、ゲレンデを疾走していく。その巨体のせいか、スノーモビルが小さく見える。わだちができ、雪しぶきが上がる。速い。それは、これからの捜索の困難さの、裏返しのような順調な行動だったように見えた。全員、装備を改めてチェックしつつさらに進む。途中でスノーモビルから降り、そこからは歩いて現場へ向かうこととなる。――かくして、能力者たちは、雪崩の危険と向き合う、雪山へと踏み入ったのである。
現場付近に到着すると、さすがに、そこは普通のゲレンデとはまるで異なる大自然がキバを剥き出しにしておそいかかってくる、という表現がピッタリのような光景が広がっていた。雪崩の跡は、はっきりと見て取れる。空気は凛とし、つきささるようだった。ここで、地上から捜索する能力者たちは、3班に分かれて、事前打ち合わせのエリアに分かれて捜索を開始する。当然、定時連絡はかかせない。無線機のスイッチはONである。緊張が走る瞬間。遠くかすかにヘリの爆音も聞こえてきた。――捜索開始。
「無事に帰ってきてくださいね。あと、サポートよろしくお願いします」
と仲間に声をかける雪待月(gb5235)。思うところは皆おなじなのだ。――なんとしてでも助け出す。そして自分たちも無事に帰還する。能力者たちの思いはひとつだった。
ロジャー・ハイマン(ga7073)と安原が向かった側は、雪崩の全貌がよく見渡せる側で、それは、もしここに人がいたら間違いなく、命を失ったであろう規模であることがすぐにわかった。が、もし、運良く雪崩に巻き込まれず、雪崩後にここらあたりを通ったとすれば、残っているであろう足跡や、スキーの後など、何らかの手がかりを求めて捜索を行った。ここらあたりは、ところどころに、天然の雪洞や雪のくぼみのような身を隠すことができそう場所も点在しており、そういったところもくまなくみて回る。特に、人名救助のプロであり、多数のより困難な現場で救助活動を行っているロジャーは、
(「俺の手で絶対に無事に助け出して見せる。この道の専門家ですからね」)
と、心に誓う。そう、今回の捜索が過去のものと同様に、無事成功に終わる事を信じていたし、そうすることがプロの仕事だとの自負も持っていた。
(「日が暮れると、気温も下がり、雪面が凍結すれば、より危険になる。明るいうちになんとかしないと」)
安原は、足場の悪い、すべりやすい危険な場所を慎重に歩みながら、太陽の具合を気にしていた。ひとつ、またひとつ。穴の中を覗いて見るが、そこに人影はなかった。
一方、それと反対側の方へ捜索に向かったのは、深墨と雪待月の2人。
「危険‥‥。だから能力者が必要とされたんですよ」
とは、深墨。持参してきた呼び笛を使って、近くに生存者の反応がないかを確したりもしている。『狙撃眼』も試してみたのだが、快晴の雪山ということもあってか、太陽の光が強烈で、うまく使用できないようだ。
(「時間に余裕はない」)
と心にいいきかせつつ、かといって決してあわてることなく捜索する。山の斜面をいったりきたりジグザグに、確認漏れの場所がないように。――だが、やはり人影らしきものは見あたらなかった。
「こちら側にも人影はありません」
とは雪待月。遭難者の中には女性もいるので、その体力等考えると、もう残された時間はなきに等しい、という思いがあったのだ。丹念に痕跡を探す。だが、見つからない。――やはり、ここらあたりにはいないのであろうか、という絶望感がふと、能力者の心をよぎり始める時間が訪れようとしていた。
そのころ、他の能力者とは別に、単独で捜索を続ける辰巳にしても、状況は同じであった。周辺の捜索を続けながら、他班と定期的に無線でサポートしつつ状況を確認するも、遭難者発見、という一報は誰からも聞かされることはなかった。その上、雪崩の再発、という、最悪の事態にも常に注意を払わなければならなかった。上空を飛ぶヘリの爆音が大きくなったり小さくなったりする、その音が雪山に反響する。それは、更なる雪崩を誘発する大いなる危険でもあったのだ。ちょっとでも兆候があれば、即座に対応しなければならない。いくら能力者でも巻き込まれれば、命の保証はない。しかも、いつ、どこで起きるかわからないのが、今の状況である。一瞬たりとも気は抜けない。『白い悪魔』、はいつ牙をむくかは誰にもわからないのだ。――と、視線を上げたその先、斜面上の雪面から、ぱっ、と白い雪煙のようなものが舞い上がった。それは、みるみる視界いっぱいに広がった。とっさに身構える。
「雪崩!?」
即座に、無線機に手が伸びた。が、それは風に吹かれ、雪煙が舞い上がっただけのようだった。と同時に、爆音とともに頭上を掠めるヘリ。かなりの低空だ。その撒き散らす爆音と風のいたずらだったのか。低空で通過するヘリはまさに一歩間違えば、雪崩を誘発する凶器にもなりかねないが、かといってあまりの高空では、捜索に意味をなさない。まさに、ギリギリの高度なのだ。
「できれば、もう少しでもいいから高度を上げてくれないか」
無線機に伸びた手を返す刀で上空のヘリに伝える。ヘリは若干高度を上げて飛び去っていった。安堵感とともに、言い知れぬ不安さが襲い始めていた。
さて、そんなヘリの機内。
「すご〜〜い。ゲレンデがあんなに小さくみえるなんて」
と、まず景色に感激する青海。操縦はベテランパイロットにまかせ、上空から遭難者の捜索と雪崩の早期発見に努めている。特に、こういった山岳地帯では、乱気流に巻き込まれるケースが多いし、かといって、捜索のため、あまりに高度を下げすぎると、その爆音が振動となって、雪崩を誘発してしまう。そのため、こういった状況でのヘリの操縦は、専門家でないとほぼ不可能だ。
「ねえ、もうちょっと、下げてもらってもいい?」
といったのか、いわないのか、ヘリはまた少し高度を下げた。双眼鏡片手に手がかりを捜索。だが、ヘリから小さな目標を探すのは困難である。ましてや、あたりは銀世界。光の反射が視界をさえぎる。狭いヘリの機内で、右左とキョロキョロ。その体を生かして?機内を動きまわり、どんなてがかりでも見逃すまいと、必死である。それがゆえに、
「へへ。辰巳さんから、高度下げすぎだっていわれちゃった」
などの事態がおきたりするのであった。すでに、捜索開始してから1時間半以上経過。視界は、だんだん暗くなっていく。日没までもう少しだ。
「だめかなあ」
とほとんどあきらめのため息をついたそのとき、ふと、視界右手隅の方で、何か動くものが目に入った。あわてて双眼鏡を向ける。確かに、何か動いている!
「ねえ、もっと右、もう少し下‥‥あ、そこ」
ヘリはうねるように急旋回、山陰へダイブするような形。みると、確かに、岩陰の洞窟らしきところから、人がこっちに手を振っているのが双眼鏡を通してみえるではないか! 遠目から、その格好は遭難者とすぐにわかった。
「あ〜〜〜。やった〜〜〜。人だ。人だ。遭難した人発見!」
手に取った無線機に叫ぶ彼女の声はかすかに震えていた。
「こちらヘリ。遭難者らしき人たちが、こちらに手を振っているのを見つけたよ。場所は‥‥」
――そう。ついに能力者達に幸運が舞い降りたのだ。
ヘリからの知らせで、真っ先に発見現場に着いたのは、深墨と雪待月だった。そこは、山を回りこんだところで、地上班が捜索していた範囲から、さらに奥に位置するところの、雪洞であった。雪崩のあった場所から、かなり奥にはいったところだろうか? 人数は4人。全員生存していたようだ。
「ご無事ですか? お身体は大丈夫ですか?」
雪待月が真っ先に尋ねる。聞けば、一人は、重度の捻挫で動けず、女性は、疲労とショックで動けないらしい。残りの遭難者も、軽い凍傷等おっているらしい。聞けば、昨日からほとんど食べていないとのこと。そこでまず、深墨が持ってきた、コーンポタージュでとりあえず空腹をしのいでもらいつつ、体を温め、救急セットで、けが人の一人を治療。
「安心してください。もう心配ないですから」
笑顔で励ます深墨。すぐさま無線で、ヘリの青海に連絡をとり、直ちに搬送できるように安全な場所での待機と準備をお願いする。
「は〜〜い。おもてなしの準備して待ってますう〜〜」
と無線機の向こうで、明るい声の青海。と、そこへ、ロジャーと安原が到着。救急セットで他のけが人も治療。重度のネンザの怪我人は、どうやら骨折しているかも知れないとの事で、辰巳に無線連絡し、指示を受け応急処置をする。その頃は、すでに太陽は山影に入り、あたりは薄暗くなっていた。ギリギリだったのだ。
「やはり、骨折の可能性が大きいですね」
最後に到着した、医者でもある辰巳は、ネンザの程度を確認しながら言った。元武闘派の俳優とは思えない?丁寧でスマートな対応で、手際よく、持っていたもので簡単な固定具を作り、足を固定する。
「歩けない人は、おぶっていきます‥‥。この俺の図体を生かす機会ですから」
というわけで、歩けない怪我人を安原が背負い、他の遭難者は、能力者のサポートを受け、途中雪崩に注意しつつ、スノーモビルのある場所まで下山する。さらに、そこで待ち構えていたヘリに遭難者全員が乗り込み、ひとまず近くの病院へ向かうことができたのである。
「は〜〜い。みんな、よかったです」
機内では、付き添った青海のチョコと温かいスープのおもてなしがあったことは言うまでもない。――かくして、遭難者は全員救助され、能力者たちは、地元レスキュー隊長からこれ以上ないねぎらいの言葉をいただくことになったのである。
「どうです? 今度、正式にうちのメンバーになりませんか?」
隊長は本当に真顔であった。よほど頼りになると思ったに違いない。
了
