帰れよ山へ
マスター名:ほっといしゅー
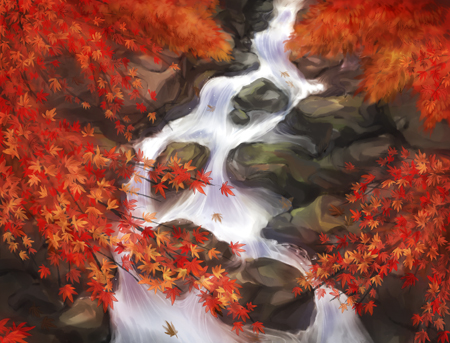
|
|
| ■オープニング本文 遠くに移る天儀の山々が冠雪を迎えるころ、今年もまた、庄屋を通した猟師たちからの報告が、久賀綾継のもとにもたらされ始めた。それはこの付近における熊の情報で、それらによると、今年はいつになく集落の近くまで、熊が出没しているようだった。 天儀に住むひとびとの脅威の最たるものはアヤカシであるが、それ以外に危険なものは数多くある。その中で一番身近なのが、熊をはじめとする、狼や虎などの大型肉食動物であった。 とくに熊は、この時期になると冬眠のため、普段より多くの餌を必要としていた。場合によっては、住処周辺の餌を食べ尽くしてしまい、人里に近いところまで餌を求めて進出することもしばしばである。 空腹のため、里を目指す熊は気が荒くなってい、とくに凶暴な個体ともなると、そのまま村を襲ってしまう可能性すらある。そうならないよう、壱師原の志士は近年、熊の目撃情報を、山の狩人たちから集めていた。 報告を総合すると、今年はいつになく人里近くまで熊が侵入しているようだった。簡単に状況をまとめ上げると、彼は、あるじのもとへ報告に赴いた。 「それで、どうするつもりだ」 彼のあるじ、祁瀬川景詮は、報告を受けると、淡々とした様子で回答を求めた。綾継には案がすでに用意されていた。 「餌となるものを、奥地に運びます」 「量は足りるのか」 「目下、椎や楢の実を集めさせておりますゆえ。まず10俵ほどは集まるかと」 綾継の見立てでは、壱師原では、餌となる団栗は熊には好都合なことに、なぜか不作とはなっていなかった。怪訝に思いながらも、景詮は案を吟味すると、よろしい、と許可を出した。 「だれが運ぶのだ」 「開拓者に任せてもよろしいでしょうな」 「そうだな。しかし、効なくばすぐに駆除せねばならん。筒の用意をしておけ」 団栗で足りないときは、鉛玉をお見舞いしなければならない。むやみな殺生と物資の浪費を避けるためにも、できれば餌だけで、熊を奥に追いやりたいところであった。 綾継は命を受け、仁生のギルドへと足を向けた。 |
| ■参加者一覧 18歳・男・泰 24歳・女・巫 19歳・女・巫 17歳・女・志 20歳・男・サ 17歳・女・サ 24歳・女・吟 12歳・女・志 |
| ■リプレイ本文 いやに平和的な依頼に、開拓者たちはちょっと拍子抜けしていた。熊とくれば次に来る単語は退治なのだけれど、と、小伝良 虎太郎(ia0375)は首をかしげていた。 彼の疑問には、依頼者である久賀綾継が答えた。その説明によると、実際にどれだけの熊が壱師原の周辺にいるかは判別がつかないため、しらみつぶしに捜し出して退治するのには大げさすぎる、とのことであった。もし熊が1頭しかいないのであれば、山狩りなど無駄が大きいし、また、数を把握するためには、時間が足りなさすぎた。 それに、関係のないことだが、と綾継は続けた。ちょうど壱師原の近く、北面と東房の国境地帯で、アヤカシの動きが活発化しているという連絡を、祁瀬川家はつい先日受け取ったばかりなのである。そのため、なにをするにせよ、手勢はできるだけ動かしたくなかったのだ。 「それで団栗集めですか。でも、こちらにはたくさんあるのに、なぜ……」 斑鳩(ia1002)の問いも、至極もっともである。里山へ降りる理由としては、熊の生息する山奥だけがたまたま、餌となる木の実などが不作だった、ということは考えられうる。ただそれでも、それが本当に正しいのか、また正しいのならば原因はなんなのか、まったくの闇の中であった。現に里山には、かき集めるほどの団栗があるのである。 「人を襲うのは、雌から離れた一匹ものの雄だとか。それにしても不思議なことでございますわね」 持ち前の好奇心の強さからか、熊について多少は知識があった陽月(ia0627)にも、はっきりとしたことはわからなかった。ただいえるのは、まず、空腹になった熊はおそろしく凶暴である、ということである。 「熊と戦うのは、ご遠慮願いたいですね」 それを聞き、久藤千依(ib8237)は、できるだけ熊との遭遇を避けるよう提案した。一同には戦闘にまだ慣れていないものも多くい、正面切っての激突では被害が大きくなる恐れがあるからだった。陽月も、それに同意した。 開拓者たちは、用意された団栗の俵を2回に分けて運ぶことに決め、人足を4人ばかり、綾継に頼んで寄越してもらった。日頃の力仕事による屈強な身体が持ち前であったが、熊を相手にするのは、さすがに及び腰である。この人足の守りは、王響和(ib7372)と斑鳩がつとめることになった。 「熊に会ったら、悪いけど荷物は捨てて逃げるからね」 守らなければならないのはもちろんであったのだが、素人に開拓者と同じ行動をさせるのは酷というものであり、人足には自分を最優先して動いてもらうほかない。ただ、地元のものということで、斑鳩の頼みもあり、道案内だけはしてもらえることになった。 「山に慣れて、足も鍛えられて一石二鳥でやんすな!」 山登りに意欲をみせる春吹 桜花(ib5775)をはじめとして、開拓者も俵を背負うことになったため、最初の往復で一気に8俵、つまり2回目の往復には人足の手助けは不要となった。最初の往復で山道に足を慣れてしまえば、運ぶこと自体は苦ではない。 「そうでござるな。精進と考えれば、これも軽いものでござる」 回数を分けたことにより、一度に2俵運ぶことが避けられたので、結城友矩(ib7366)の肩の荷もいささか軽く感じられた。これで、いざ戦いとなったときも、荷物に手間取り相手に後れを取ることはなくなるだろう。相手の出方がわからない以上、念を入れるに越したことはないのだ。 陽月の指示によって、葉月美雨(ib8236)は道中で陶笛を吹く役を受け持つこととなった。これはもちろん、音に敏感であるといわれている熊と、出会い頭に遭遇することを避けるためであるが、狼や虎など、他の猛獣も寄せ付けない狙いがあった。 はたして、開拓者たち一行は、熊が活動的になる時間を避けて、山奥へ向け出発した。美雨が吹く笛の音色だけでなく、全員で呼びかけ警戒する慎重さが功を奏し、最初の道中は危なげがなく進むことができた。もとより人数が多かったのも、熊を避けるのに役に立ったのだろう。 「ちょっと変なところもあるし、やっぱり、調査をしたほうが正解かな?」 俵をひとつ、難なく背負い歩きながら、虎太郎は呟いた。危険を避けながら、ただ荷物を置いてくるだけなら、こんなに簡単な仕事はない。 「そうでやんす。熊の餌が減った原因の解消も、しっかりやっとかんといかんでやんすな。また里に被害が出ては、本末転倒でやんすから」 しだいに急になってゆく山道を前にし、桜花は同意した。山に登りたがるのはどちらかというと彼女の性分のようだったが、それでも、好きこのんでこの重い荷物を背負って、なんども登りたい、というわけではないのだけれど。 「なにか、事情がありそうですね」 斑鳩が、桜花に応じた。事情、と表現はしたものの、彼女の中では、人為的なものかアヤカシかどちらかの疑いが強まっていた。今回はひとの手が入らない山奥のことであるため、どちらかというと後者の可能性が高そうである。彼女は陽月と申し合わせ、交互に結界を張り、周囲の様子を調べていた。 ふたりの結界が示すとおり、最初の往路では怪しく感じられるものは見あたらなかった。桜花と千依の鋭い観察眼も、それを裏付けていた。団栗が少ないと思われた山々も、一見しただけでは、どこが普段と違うのか、まったく区別がつかないほどである。 開拓者たちは、人足の案内によって、団栗を撒く場所は川の浅瀬の近くを選んだ。雑食である熊は魚を採ることもあるため、その際に見付けることを期待してのことだ。まとまりすぎないように適度にばらまくと、人足たちは大きく息をつき胸をなでおろした。 「うちらの仕事は、これで終わりかい」 「ええ、助かりました。村までまたお送りします」 斑鳩が礼を言うと、緊張から解放されたのか、人足たちの表情はゆるんだ。引き続き護衛をつとめる響和の笑顔と、陽月の甘酒の差し入れが、それに拍車をかけた。 小休止のあと、開拓者たちは同じ道を引き返し始めた。先ほどとはうって変わり、復路は荷物もなく、下り坂のこともあって、一行は心なしか、気持ちも軽く進むことができた。とはいっても、足にかかる負担は少なくなく、もう1往復する開拓者にとっては、消して楽なことではない。 「もうすこしでござるな。残りはどういたそう?」 「おいらが持つよ」 「じゃあ、最後はあっしでやんすな」 残った2俵は、虎太郎と桜花が進んで担いだ。山道は枯れ葉で覆われ柔らかくなっているとはいえ、連続して運ぶには、訓練を積んだものの方が確実である、という判断だった。俵を背負わない残り、つまり先ほどは護衛をしていた斑鳩と響和、俵を背負っていた友矩と千依は、今回は陽月の指示のもと積極的に警戒に当たることとし、美雨は引き続き、陶笛の演奏を担当することとなった。 日が暮れる前に全てを終わらせる予定であり、開拓者は休みもそこそこにすぐ山へと発った。冬を迎える山々の日は、すぐに西へ落ちてしまうため、あまり時間に余裕はなかった。1往復目は人足を気遣っていたが、今回は遠慮せず、開拓者の本来持つ歩みで山道を進んでいった。 往復あわせてのべ3回目の道であり、人足の案内がなくても道のりは迷わなかった。落ち葉をかき分けるような勢いは、普通の人間でいう山駆けにも劣らない速度である。目標の場所までは、慣れたこともありほとんど時間がかからないようにも感じられた。 異変が起きたのは、ちょうど団栗を撒く場所へと戻ってきたときであった。 「よし、荷物はこれで仕舞いでやんすな」 「春吹殿、後ろ、後ろでござる!」 団栗を撒いたものの、友矩に指摘され後ろを振り返った桜花は、肝を潰しそうになった。 美雨がずっと警戒の演奏を続けていたにもかかわらず、開拓者の眼前に、熊が現れたのである。それも茂みの向こうからで、距離はかなり近かった。 虎太郎が大音声でブブゼラを鳴らしたが、熊はそれにもひるまなかった。 「睨み返してください! そのまま後ずさるんです」 陽月の指示の通り、桜花と熊は、視線を重ねた。熊に限らず動物には、言葉は通じなくとも目で意図を知らせることができる。彼女は、自分はお前より強いんだぞ、と威嚇の意を込めて、眼を飛ばした。 しかし、熊から返ってきたのは、輪をかけて強い敵視であった。 「――め、めえりやした!」 眼光に射すくめられ、たまらず桜花は飛び上がり、そのまま平伏の姿勢に移行したが、それはかえって熊を刺激する結果となった。躍りかかる姿勢を熊は見せたが、間一髪、斑鳩の放った炎が、間を遮った。 「もしや」 斑鳩は神器を操りつつ、陽月に伝えた。熊のこの不自然な行動は、裏になにかある。彼女のその判断は、当たっていた。 「この熊、アヤカシです!」 かわりに陽月が結界を作り出すと、すぐに反応があった。熊のアヤカシというよりは、もともといた熊がアヤカシと化しているような感触であった。 「桜花さん、しっかり!」 美雨が鋭く、口笛を鳴らす。その音は、炎に驚いて倒れ込んでいた桜花の目をしっかりと覚ました。 「起きて! 熊に死んだふりは通じませんよ!」 「えっ、べ、べべ、別に問題ないでやんすよ! 大丈夫でやんす! あっしは火が苦手なだけなんでやんす!」 相手がアヤカシとあれば、陽月の指摘はいささか合致しないものではあったが、とにかく、桜花は響和の助けを得、平静を取り戻し立ち上がった。 「腹ぺこの熊を退治するのは気が引けたけど、アヤカシなら話は別だね」 拳に巻いていた布を引っ張り、あらためて締め直すと、虎太郎は熊に対して構えた。 それが、お互いの合図となった。 いくら獰猛で大型の熊とはいえ、8人の開拓者を相手にしてはうまく立ち向かえるはずもない。しかし、このアヤカシは別で、勝負がつくまで相当な粘り強さをみせた。 ひとりだけの技では、アヤカシはいっこうに弱る様子を見せなかった。数人でたたみかけてようやく手応えがあったと感じさせるほどであり、開拓者たちがそれに気づくまでの少しの間、戦闘は膠着状態に陥っていた。 「お前の爪になんか、負けてられるかよ!」 糸口となったのは、陽月が空間の歪みにアヤカシを取り込んだあとの、虎太郎と友矩による連続攻撃である。虎太郎の鋭い踏み込みから放たれた拳が、アヤカシの正中線を正確に捉えた。直後、友矩の刀が振り下ろされると、アヤカシは始めてよろめいたのである。 開拓者は勢いに乗り、攻撃の手を緩めなかった。アヤカシの強烈な爪による反撃は、斑鳩の操る、揺らめく業火によってことごとく出端を潰されていた。 千依も響和も、経験が少ないなりに善戦した。しかし、今回の決め手となったのは経験者のひと振りである。待っていたかのように、アヤカシの捨て身の体当たりを桜花は躱すと、紙一重の位置で、鮮やかな反撃をお見舞いした。 「決まりでやんす」 彼女のひと言を残し、アヤカシは瘴気へ還った。 その後、開拓者たちは周辺の調査を行ったが、ここ一帯の熊は多くがアヤカシ化したようである。退治にかなりの時間を費やしたものの、調査中ところどころで感じられた強い瘴気は、夜になるころはすっかり影を潜めるようになっていた。 「アヤカシのせいで、餌がなくなったのかな?」 残っていた団栗を再び撒きつつ、虎太郎が考察した。アヤカシ熊が、普通の熊と比べて目に見えるほど大きく育っていたのが、その根拠である。 「はっきりはよくわかりやせんでやんすが、正しいと思うでやんすよ」 桜花が、持参した苗を植えつつ、頷いた。この苗はこの周辺の木と同じもので、何年かかるかわからないが、いずれは熊の餌をもたらすことだろう。 「里に近づいたのがアヤカシでなくて、よかったです」 斑鳩は団栗を一粒、手にとって眺めながら答えた。団栗は渋を抜かないかぎり、人間が食べられたものではない。しかしこれが、冬を迎える動物たちの命綱となるのだ。森と生きる動物たちの営みがよくできていることに、彼女は感心した。 開拓者たちは、夜を迎え、月の光のもと、麓への道を急いだ。しかしひとりだけ、陽月だけは煮え切らない気分であった。 もし機会があれば、熊の手なるものを食してみたかったのだ。今回はアヤカシ相手だったから実現できなかったが、神楽の都では売られているのだろうか。そう思いつつ、寒空を見上げ彼女は歩いていた。 壱師原はすぐ、冬を迎える。 |


