今日は花を送る日だ
マスター名:KINUTA
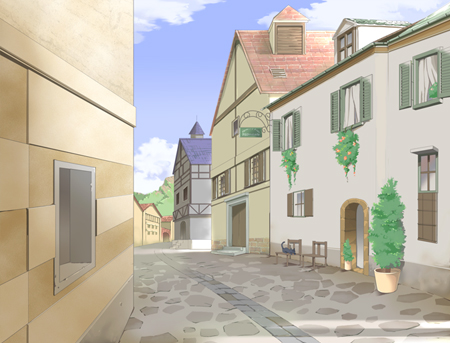
|
|
| ■オープニング本文 バレンタイン。 神教会が出所らしいこの行事が世間に根付いてから、結構長い。 本来は家族間で互いへの愛を確かめ合うという真面目な趣旨のものだった(という一説もある)が、昨今は完全に、ただの告白イベント。もっと言えば製菓ギルドの稼ぎ時と化している。 その傾向が最も顕著に見られるのは天儀だ。 最近彼の地では、『バレンタインの0時0分0秒、手鏡を持って恵方を向いてチョコレートを一気食いすれば、意中の人へ思いが届く』なんていう都市伝説も生まれているそうな――実行した人がいるかどうかは定かでないが。 さて、ところ変わってジルベリア。 長らく神教会が弾圧されていたこの地でバレンタイン特需を受けるのは、製菓ギルドではない。生花ギルドである。 国民性なのか、当地では一般的に、チョコレートでなく花束を渡す。 そして、女→男より、男→女のパターンが多い。 ● 「ぐあー! ムカつくっすー!」 吠えながらマーチン邸にやってきたやんきい女学生アガサ。 庭へ息子カモミールを連れ出していたエリカは、目を丸くした。 「あんたどうしたの、顔真っ黒よ」 「それが聞いてくだせえ番長! 今日バレンタインっすよね!?」 「そうね」 エリカは赤ん坊のカモミールを、高く高く放り投げる。 「あのむかつくストーカーのジルベールが、あたしに花持って来たんすよ!」 カモミールはきゃっきゃ言いながら宙の一点で止まり、落下してくる。 「うん」 「なんか怪しいなと警戒はしつつ、受け取ったんすよ! イベントだからと思って!」 落下してきたカモミールを片手でキャッチし、エリカは、また天に向け放り投げた。 「で?」 「あの野郎花束にスス玉仕込んでやがったんすよ! あたしが受け取った途端、思いっきり爆発するようにしてやがったっすよ! おかげでこの有り様っすよ! あのくそ男大笑いして逃げやがったっすよ!」 再度上がり、落ちてくるカモミール。楽しそうな笑い声が響く。 「はー。そりゃあんたが悪いわね」 「そう思うっしょ、あいつ最悪――ええっ、なんでっすか!? なんであたしが悪くなるっすか!」 「だって逃げられたんでしょ? 甘いわよ。そういう場合はその場で顔面殴らないと」 そこで屋敷の扉が開き、ロータスが走り込んできた。 「何やってんですかちょっとおお!」 腕からカモミールを引ったくられたエリカは、眉を潜めて言い返す。 「何よ、邪魔しないでくれる。せっかく高い高いしてたのに」 「高い高い過ぎるでしょ…? 止めてくださいよそうやって子供に加減知らずの構い方するのは。殺したいんですか」 「…あんた、子供が出来てから本当にうるさくなったわねー」 「…それはねえ、エリカさんが輪をかけて神経ザルになってきてるからですよ。いきおい僕が気を使わなくちゃならなくなってくるんです安全のために」 アガサは気づく。苦虫を噛み潰すロータスが小さい花束を持っているのを。 どうやらエリカに買ってきたものらしいが…それが渡されるのは、一通り夫婦喧嘩が終わってからのことになるだろう。 |
| ■参加者一覧 / マルカ・アルフォレスタ(ib4596) / リンスガルト・ギーベリ(ib5184) / リィムナ・ピサレット(ib5201) / 八壁 伏路(ic0499) / トビアス・フロスマン(ic0945) |
| ■リプレイ本文 「花を召しませ、召しませ花を〜♪」 ジェレゾの町角、鼻歌を歌いながら行くのは八壁 伏路(ic0499)。 今日はバレンタインデー。町の至るところで愛の言葉に乗せ花が溢れる日。商店の飾り窓も、カフェのテーブルも、花盛り。彼の両手にも、むろん花。大きな花束1つと、小さな花束を束にして詰めた紙袋。 キンセンカにカスミソウ、ヤグルマギクにスイートピー、ラナンキュラスとアネモネと、チューリップに至るまで、混乱模様の百花繚乱。 『何かこう、春っ!というフィーリングを醸し出して、おなご受けしそうな花束を見繕ってくれ。あ、なるべくリーズナブルなところでな。バラとかコチョウランとかカトレアとか、そういうのは抜きの方向でな』 という彼のアバウトな注文に、花屋の店員が応じてくれた結果である。 「…しかし、前が見えにくいのう」 せっかく買ったんだもの、引っかけたり転んだりして台なしにするのは避けたい。 であるので繁華街から出て、住宅街へ。 ここはジェレゾのうちでも旧い街区。貴族が多く住み、門扉の立派な邸宅が並んでいる――それぞれ敷地が広いので、あまり『並んだ』印象はないが。 高い塀越しに背を伸ばしている木々の枝では、徐々に蕾が膨らんできている。 馬車も人通りも少ないこの道を通って、港へ行こう。相棒甲龍カタコも、そこに待たせている。 「そういやこのへん、エリカ殿の屋敷があったかのう。確か向こうのほう…」 何の気無しに頭を巡らせた伏路は、賑やかな話し声を聞く。 「あーうるさい! そんなに私のやることが気に入らないなら出て行きなさいよ!」 「何ですかその言い方は! 僕はいっこもおかしいこと言ってないじゃないですか! 赤ん坊ぶん投げるとか普通のあやし方じゃないでしょ! 死にますよ!」 「死んでないじゃないの!」 「死んでないからいいってもんじゃないでしょう! 後遺症出ますよあんな乱暴な扱いしたら!」 夫婦喧嘩が勃発しているらしい。 老婆心とやじ馬根性を発揮し、エリカ邸へ向かった伏路は、門のところにススだらけの足跡があるのを見る。 「物騒な気配がするのう」 入って行けば、ロータスとエリカが庭先で口喧嘩していた。 「あの子があなたみたいに頭悪くなったらどうすんですか! 取り返しつかないでしょ!?」 「あんたみたいに甘やかされて根性腐る方が方が取り返しつかないわよ!」 夫婦の近くにはいかなる理由からか、ススだらけになったアガサがいた。 喧嘩の原因らしいカモミールを抱っこしていたが、伏路を見るなり丁度良いとばかり、バトンタッチ。 「後頼むっす。あたし行くところあるんで」 彼の足元に赤ん坊をおいて、断られないうちに逃げる逃げる。 伏路は渋々カモミールを抱き上げる。花束は横に片付けて。 「こらこら暴れるでない。ぐお! 顎に頭突きは反則…いてええええ…待て待て。えらく元気がええのう。お母上に似て」 このいとけなきものも、いずれ大きくなる。そのときには自分のように花を誰かに贈るようになるのだろうか。 などと顎をさすり未来へ思いをはせている間も、エリカとロータスの言い合いは、果てしなく続いている。 「大体ね、エリカさんは雑! 雑なんですよ! 犬の子猫の子育ててるんじゃないんだという自覚をちょっとは持ったらどうですか! ケガしたらどうすんですか!」 「ツバつけときゃ治るわよ」 「頼むから頭の中を動物段階から人間段階まで高めてください」 エリカよりロータスの言い分の方が、オカン成分多めであるもよう。 (夫婦の役割が逆転しているからかの…愉快なことよのう…) ● トビアス・フロスマン(ic0945)が機械のように正確な歩幅で、廊下を進んでいく。 敷き詰められた絨毯に、窓からの四角い光が、規則正しく並んでいる。 (よい天気にございますな…) 向こう側からメイドが歩いてきた――屋敷のものではない。 腕に花束を抱えている。カトレアだ。大きな白い蝶のような。 メイドはトビアスの存在を認識するや、軽く膝を曲げ礼をした。 「これはフロスマン様、丁度よいところでお会いいたしました。マルカお嬢様はどこにおられますか? この花束をお嬢様にお渡しするよう、お館様から頼まれて参ったのですが…」 「そういえば今日はバレンタインでしたな。では、私がそれをおひい様にお渡ししましょうぞ」 鬼火玉の戒焔は、窓辺で昼寝。 机に釘付けであったマルカ・アルフォレスタ(ib4596)は、ノックの音を耳にし、読んでいた参考書を閉じた。 「おひいさま、入ってもよろしうございますか?」 「どうぞ」 答えに応じ、ドアが開く。 それによって起きた空気の流れで、窓辺にかかるカーテンが揺れた。 「お邪魔でございませんでしたかな?」 「いいえ、一休みしようと思っていたところですから――その花束は?」 真っ白な花の向こうにある厳格な老爺の顔が、緩む。 「お館様からでございます。本日はバレンタインでございますからな」 「まあ、そういえばそうでしたわね。わたくしとしたことが、失念しておりましたわ」 マルカの手が花束を受け取る。 ひんやり冷たく柔らかい花びらが頬を撫でた。 鼻孔をくすぐる甘い匂い。 「カトレア、いい香りですわね」 ぎゅっと抱き締めると、これを贈ってくれた兄の温もりが、伝わってくるように思える。 「花言葉は高貴、優美な女性。おひい様に相応しいですな」 トビアスの言葉はマルカに、控えめな微笑みを浮かべさせる。 「では、花言葉に相応しい女性になりませんと――折角ですから、飾りましょうか」 花瓶へ花を活けると、部屋全体が明るくなった。 窓を開け深呼吸をすれば、頭も軽くなる。 マルカの意識は遠い領地へと飛んだ。 緑なす牧草地、澄んだ小川、小鳥の鳴き声。館の庭にある大きな菩提樹。手入れの行き届いた薔薇園。各儀の珍しい草花を集めた温室。 晴れた日、遠乗りに出掛けた。野の花に囲まれて昼食を食べた。お父様やお母様、お兄様と一緒に。 瞼を閉じれば蘇る、あのときの笑い声。 「…今度の休み、領地の様子を見に行ってみましょうか」 呟いたマルカにトビアスは、うす紅色の花束を差し出した。 「これは私からでございます」 それはプリムラ・マラコイデス。春の先駆けを担う花。 「花言葉は「運命を開く」でございます」 「運命を開く…」 マルカは沈黙した。 自分はいまだ、これから進むべき道を決めかねている。 騎士か、学者か。武を取るのか、文を取るのか。 どっちを選んでも後悔しそうで怖い。 誰かが先を示して背を押してくれれば、と他力本願な気持ちにも陥ってしまう。 だが、それは甘えだ。 「おひいさまが旦那様と奥様の仇を討たれてから、今後の事について悩んでおられるのは承知しております。ですがどのような道を選ばれても、このじいめはおひい様の為に力を尽くす所存でございますぞ」 そうだ、誰かに頼る訳にはいかない。 自分の運命は自分自身で切り開かねば。 (決めるのは、わたくし…ほかの誰でもないわたくし…) 責任という重みを体全体に受けながら、マルカは、トビアスの手を取った。 「ありがとう…これからもよろしくね、じいや」 ● 「なんとぉー! やるではないかリィムナ!」 「リンスちゃんこそ!」 ここは、リンスガルト・ギーベリ(ib5184)の屋敷。 人妖カチューシャとエイルアードの声が響いている。 「しっかりー、姉様−!」 「リィムナ、ケガしないようにしてくださいよー!」 彼らの前では、屋敷の主であるリンスガルトと、その恋人リィムナ・ピサレット(ib5201)が、模擬戦をやっている。 それぞれの奥義披露も兼ねた遊びだ。 接近しては離れ、離れては接近し、拳と蹴りが応酬されるたび、ぱん、ぱん、と空気が弾ける。 もう1時間近くやっているが、一進一退でなかなか勝負がつかない。それだけ実力が伯仲しているのだ。 とはいえ、リィムナはそろそろ飽きてきた様子。 「ねーリンスちゃん。お腹がすいてきたんだけど、おやつの時間にしないー? あそこにさっきから、用意してあるし」 リィムナの視線は東屋にあるティーテーブルに向いている。 ケーキスタンドに盛ってある焼きたてのスコーン、ビスケット、一口サイズのシュークリームやエクレアや、カップケーキ。付け合わせのジャムと蜂蜜。 「ちょこっと小腹を満たしてさ、それからまた試合再開ってことで…」 リンスガルトは前髪をかき上げ、厳しい顔で、いかん、と首を振った。 「まだじゃ。まだ我が奥義の神髄は見せておらぬからの」 「えー…お茶が冷めちゃうよう」 「そういう雑念に捕らわれているうちは、妾に勝てぬぞえ!」 リンスガルトは脇を締め、両拳を固めた。全身が黄金色のオーラに包まれ、髪が逆立つ。 カチューシャは黄色い声を張り上げた。 「キャー! スーパーお姉ちゃま降臨ですわ!」 エイルアードは敷布を広げ、リンスガルトの覇気によって巻き起こる風から、ティーテーブルを守る。 「リィムナ、油断しないようにー」 そこは言われるまでもない。 斬撃苻が放たれ、黄金色に輝くリンスガルトに当たる。 直後リィムナはバク転をし跳び下がった。今当てたのがリンスガルトの本体ではないと察して。 足に痛みが走ったが無視する。それよりも、距離を取る方が先だ。 (…質量を持った残像…これが神龍煌気の神髄か…!) 体勢を立て直し、斬撃苻を続けざまに放つ。 だがリンスガルトは、それらを紙一重で避けた。 このままではまたやられる。 ならば一発勝負、起死回生の策に出るまで。 「敵に不足なし! いっくよー! インフィニットミラー!」 リィムナの輪郭が二重になった。 いや、事実2人になったのだ。 その2人が左右に離れる。 「何…次元反転分離攻撃だというのか!」 やや色の薄い方が式だというのはリンスガルトにも分かった。が、だからといって特に有利になるわけでもない。リィムナが現在使っている術によって生み出された式は、本人と寸分違わぬ攻撃力を持つのだから。 「「くらえっ!」」 二重音声と斬撃符の十字砲火が、リンスガルトに浴びせられる。 「ぬわああっ!」 さしもの彼女も二方向作戦には勝てず。身のあちこちを裂かれ、あと一歩で刀が届くという間合いで、膝を折る。 時を同じくしてリィムナの式が消えた。 「ま、参ったのじゃ…まだまだ修行が足りぬのぅ」 悔しげに零すリンガルトの姿に、リィムナは鼻高々。えへん、と胸を張る。 「ふふふふ。イェイ! あたし、最きょー…」 その途端足から力が抜け、後ろ向きにバタンと倒れる――彼女も彼女で、力の限界に達していたのだ。 相棒たちはそれぞれの主人を、助け起こしにかかる。 「姉様、大丈夫なのー」 「リィムナ! しっかりしてくださいよ!」 どっちも傷だらけ泥だらけ、汗まみれ。 とりあえず彼女らは、取り急ぎ治癒を終わらせた後、やっとおやつにありついた。 ● 夕暮れが迫るヤーチ村。一番星が空に出た。気温もぐっと冷え込んでくる。 そこに降りてくるのは甲竜カタコ、そして伏路。 「やれやれ、思ったより夫婦喧嘩、長引いてしもうたな。犬も食わんとはあのことだの、カタコ」 返事の代わりにカタコは欠伸。翼を縮め、のそのそ歩き、勝手に家へ戻っていく。 新しい住処はゆったりして住み心地がよく、彼女はいたく気に入っているのだ。 「あ、カタコ。お帰りー」 「どこ行ってただ」 村人たちからマスコットのように扱われ、声をかけられたり頭を撫でられたりするのも、気に入ってる。 伏路は1人で村めぐり。 ご近所さんたちに遅ればせながら、引っ越し蕎麦ならぬ引っ越し花。紙袋に入れた小さな花束を、全部配って回る。 「ご挨拶遅れましたがの、ま、よろしければ。今後ともなにとぞよしなに」 さて、その次こそが本命。一路ミーシカの家へ。 「ミーシカ殿ー、おられるかのー」 残った大きな花束を抱え訪ねてみれば、目当ての少女は庭先で薪割りをしていた。 「おお、ミーシカ殿」 「お? なんだ伏路か。なんか用か」 斧を降ろした彼女に近づき、花束を差し出す。 「バレンタインだからの、どーぞ」 「…へーえ、お前意外と気が利くな。ありがとさん。しっかし配るの遅いな。私はもう朝のうちに渡したぞ。エマに」 「さよか。手回しいいのお」 いつもは凛々しい横顔が、花に埋もれると妙にかわいらしく見え…伏路、照れてしまう。 「で、どんな花束を渡したのだ? 麓まで買いに行ったかの?」 「まさか。わざわざ買いになんて行かねえよ」 鼻で笑ったミーシカは、一旦家に入った。 次に出てきたとき、その手に花束はなかった。 代わりにふわふわした花弁を持った、白灰色の花があった。 「えーと、これは確か、エーデルワイスとかいう奴かの?」 「ああ、そうだ。森を歩けばな、どこにでもこれが生えてるよ」 その言葉はウソである。確かにこの花は森に咲いているが、どこでもここでもというわけではない。ある程度身を入れて探さなければ見つからない。 「やるよ。エマの花束作ってたら、1本余ったんだ」 伏路の右耳の上に、花が挟み込まれる。 余り物であっても、とっといてくれた心意気がうれしい。 伏路はますます照れる。気も大きくなってきて、お誘いをかけてみる。 「のう、ミーシカ殿、パブに行かんか。わし先日にょろんにょろんとしたアヤカシを相手に獅子奮迅の活躍をしてな、懐が暖かいのだ」 ミーシカは伏路の額に親指と人差し指を近づけ、弾いた。 「ぐへっ!」 「調子のんな」 色よい返事をもらえる日は、まだまだ遠そうだ。 ● 「そういえば妾たち、まだ風呂に入っておらんな」 「うーん、別にいいんじゃないかな。どうせこれからまた汗はかくことになるんだし♪ その後から入ったほうが、効率的でいいじゃない♪」 「何という卑猥なことを…このこの、このぅ」 「きゃー、リンスちゃんくすぐったーい♪」 寝室へ向かう主人たちの甘ったるい掛け合いを、エイルアードとカチューシャが見送る。 「仲がいいっていいことですね」 「全くですね」 台詞に棒読みの気があるのはともかくとして、バレンタインデーという日の意義については彼らもよく知っている。 なので慣習に従い。 「あ、そうだ。カチューシャさん、これどうぞ」 「ありがとうございますエイルアードさん。ではこちらからもどうぞ」 お互い花束を贈りあう。 義理チョコというか友チョコというか、そんな意味合いのやつを。 寝室に入ったリィムナは、目を見張った。ベッドの上に、豪華な薔薇の花束が置かれていたのだ。 「わ…すごい花束…」 赤白黄色、桃色緑と色とりどり。きっとうん万文はする代物に違いない。 近づいてみれば花束の下にはチョコレート。 「妾からのプレゼントじゃ♪」 リィムナはの瞳は潤んだ。 次の瞬間リンスガルトの首ったまに齧り付き、キスキスキスの嵐。 「リンスちゃん…ありがとう♪ うれしい、愛してるー!」 「ふははは、もっと言ってたもれ、もっともっと♪」 すっかり鼻の下を延ばしてしまうリンスガルトから一旦離れ、クルリと背を向けるリィムナ。 「実はあたしもプレゼント用意してきたの。あたしからは…はいっ♪」 一瞬の早業でスカートをまくりパンツを下ろす。 「菊の花のチョコ添えだよ♪」 正確には菊の門のチョコ詰めだ。 現在閉じているそこからリボンが垂れ下がっている。多分これを引けばチョコレートが出てくるのだろう。 リンスガルトは無の境地に至った目をして、呟く。 「リィムナ…流石にドン引きじゃぞ…」 「えっうそっ。好きかなと思ってたのに…」 引かれたことに多少のショックを受け涙ぐむリィムナ。 と、そこでリンスガルトが、ぱっと表情を変えた。 「というのは嘘じゃ! このお下劣変態娘が!」 「わあっ!?」 たちまちのうちリィムナを押さえ込み馬乗りになった彼女は、薔薇鞭を取り出し、びんと両手で張った。 「くく、お仕置きが楽しみじゃ♪ それも相当きついのが入り用じゃのう…妾がたっぷり躾してくれるわ!」 「うん…いっぱいお仕置き、して…♪」 鞭が白いお尻に食い込み、赤い筋を作る。 「あぐっ! 痛ああい♪」 悲鳴は、とっても嬉しそうな響きを帯びていた。 「ふははは! もっと泣くのじゃー! さっさとチョコレートを出してみせい、この変態め!」 「うわああん! リンスちゃんごめんなさああい! あううっ! おっきすぎて出ないーっ!」 バレンタインの夜は、倒錯のうちに更けて行く。 ● 青白い月の光が部屋を照らしている。 マルカの前には2つのものが置いてあった。剣と、学術書と。 長い間瞳を閉じた後、彼女は、学術書を手に取った。恭しく捧げ持った。 唇が開く。自分自身へ決意を示すために。亡き父母へ告げるために。 「わたくしは…この道を行きます。この道を、選びます」 |


