【浪志】梅は咲いたか
マスター名:周利 芽乃香
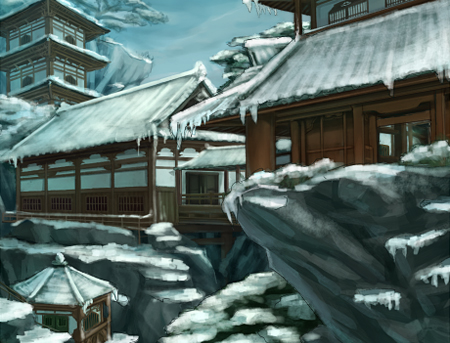
|
|
| ■オープニング本文 あした判らぬ浮草暮らし 傭兵稼業は風次第 弥生三月 花見月 末は千鳥で 二人で行こかいな ●婆娑羅姫、御機嫌斜めにつき 神楽、森家所有の私邸。 その日、婆娑羅姫の異名を持つ猛々しい娘の御機嫌は非常に芳しくないものであった。 「これか? 浪志隊の隊服ってェヤツは」 部屋に運ばれて来た、たとう紙に包まれたそれを酔眼でちらと見て、手元にあった鉄扇の先で捲る。現れたのは黒地に赤の文様が鮮やかな羽織袴一式だ。 「地味だな」 人によっては大層派手にも感じるだろう隊服を、一言ばっさり斬り捨てて、森藍可(iz0235)は興味なさげに大杯の中身を煽った。 つまらない。 規律だの隊服だの、決まりごとなど、くだらない。 望むのは、酒と喧騒、争いと血の昂ぶり―― 北面を襲った災厄に一旦の区切りが付いて以降、藍可の周辺は平穏無事な日々が続いていた。 勿論、有象無象の小競り合いはある。しかし何処か面白くない。 藍可は大杯が空になったのを不機嫌に投げ捨てる。慌てて側に付いていた者が大杯に酒を満たして差し出したのを当然とばかりに受け取って、藍可は最近見ない顔を思い出した。 「そう言や、源右衛門の奴ァ、まだ東房か‥‥」 安田 源右衛門(iz0232)、藍可配下の傭兵である。 元々は藍可の父に雇われた傭兵だったのだが、藍可が気に入って武天から引き連れて来た者の内の一人であった。 蝮党の塒襲撃以降、手持ちの金子で楼港通いをしていたのだが、何処で如何稼いだものやら遂に身請けしたらしい。長月の頃だったか、東房に家を借りたと報告があったきり、消息が絶えていた。 「あの野郎、東和の戦いにも面ァ出さなかったな」 藍可は眉を潜めた。 元々は父が雇った傭兵ではあったが、藍可の側に付かず離れず従っていた男であった。少女期の藍可に槍術の初歩を教えたのは源右衛門であり、彼自身藍可を妹のように見ている節もあった――というのに。 女が絡むと、こうも簡単に疎遠になるものか。 「面白くねェ」 大杯の中身を一気に煽ると、藍可は側付を開拓者ギルドへ走らせた。 「源右衛門の伸びきった鼻ン下、ひっ掴まえて連れて来やがれッ!!」 ●とある浪人夫婦の日常 一方、そんな事とは露知らぬ安田 源右衛門。 東房某所に家を借りて、質素ながらも幸せな生活を営んでいた。 全盲の男が凄腕の傭兵とあれば身元が割れようと、近所には視力を失い浪人になったと説明している。退職時の餞別金と、小唄の師匠をしている妻の稼ぎでささやかに暮らしている――そういう事になっていた。 「源さん、今日はええ菜の花が手に入ったわ」 妻の於歌が、上がり框から声を掛けて来た。どれ、と近付けば、於歌の腕に抱えた笊から青々しい菜の匂いが立っている。 揚げもんにする? 御浸しもええね、などと迷う妻に、源右衛門は調理方法は任せると返して、言った。 「旨い酒が呑めそうだ。燗で、多めに付けてくれ」 一緒に呑もうと誘う夫に、於歌は幸せそうな忍び笑いを漏らした。 この一見何の変哲も無い浪人の家庭に開拓者達が押し入るのは、それから暫く後の事である―― |
| ■参加者一覧 21歳・女・魔 36歳・男・砲  神座真紀(ib6579)
神座真紀(ib6579)19歳・女・サ  キアラ(ib6609)
キアラ(ib6609)21歳・女・ジ 28歳・男・砂 15歳・男・陰 |
| ■リプレイ本文 ●東房某所 安田 源右衛門の新居へは、藍可情報が開拓者達に伝わった事もあって容易く辿り着く事ができた。 「ご同僚の方々ですか‥‥お気の毒でございました」 村人に古い知り合いだと言い繕えば、親身な返事が返って来た。 お気の毒とは如何なる状況かと朝比奈 空(ia0086)は内心焦ったが、村人が続けた言葉に合点する。 「安田様は奥方様と共に、心静かに毎日を過ごしておられます。気丈な御方ですね」 そう言えば、急な失明を機に退役したという触れ込みになっているのだったか。 改めて開拓者の身分を伏せて話しかけた事を正解と感じつつ、曖昧に頷いた空は、無愛想と聞く源右衛門夫婦の印象を知るべく探りを入れた。 「元々愛想の無い質の男でしたが、ご近所の皆さんと上手くやっていますか?」 「ははは。ご同僚の方に申し上げるのは恐縮ですが、お武家様の無愛想は今に始まった事でなし」 しかも今は浪人の身、気難しくもなりましょうと村人達は寛大に受け止めているらしい。 「浪人さんなんて、あんなもんでしょう」 「そう言っていただけると助かります」 社交性に欠ける源右衛門を補い近隣住民との接触を担うのが細君の於歌。人あしらいに長けた彼女は村人達とも上手くやっているようだ。 「しっかり者の奥方様で、ご亭主をよく助けておられますよ」 武家へ行儀奉公に出ていたのだろうか、立ち居振る舞いに歌舞音曲、物の審美眼など素晴らしい女性なのですと村人は言った。近隣住民との交流がてら近所の娘達に所作を教えたり、三味線や小唄の稽古を付けたりしているらしい。僅かな礼金のほか、青菜が採れただの鶏をばらしただの、近所付き合いならではのお裾分けの遣り取りで生活しているようだ。 「安心しました。どうか今後とも彼らをよろしくお願いします」 「こちらこそ良い隣人と巡り合えました。これからも良き関係でありたいものです」 ご丁寧にどうもと頭を下げて、空が訪問者で賑わう安田家の土間へと足跡を運ぶと、夫婦と旧知の者達が再会を喜び合っていた。 「まさか本当に東房に居を構えるとはな」 複雑な表情を浮かべるマックス・ボードマン(ib5426)に、源右衛門は「勧めてくれたのはお前だろうに」と柔らかく言葉を継いだ。 「お陰で穏やかな日々を過ごしている」 これがあの安田 源右衛門なのだろうか。彼と会ったのは花街、楼港の混雑の中であったが、もっと他者を受け入れぬ雰囲気を醸しだしてはいなかったか。 「お聞きするまでもないようですが‥‥今、幸せですね?」 幸せか、と尋ねるつもりでいたキアラ(ib6609)だったが、質問でなく確認になってしまったのは様子に滲み出ているからだ。勿論、源右衛門は確りと肯定した。 (しんこ‥‥っ!? バカップル!?) リア充だ、リア充がいる。 皆の後ろにちょこんと佇むラビ(ib9134)は、表向きおどおどとして見せながら内心では苛々し始めていた。幸せそうな男女を見ると、どうにも故郷の両親を思い出してしまって腹立たしい。 ジルベリアに生まれ育ったラビの母は天儀の獣人だ。遠く離れた儀の者同士、どのようにして出会い、愛を育み、障害を乗り越えて――今、自分が生を受けているのか、彼は物心付いた頃から散々聞かされてきたし、その両親は現在進行形でバカップル真っ盛りだったりする。 両親の様子を見るに見かねて家を出た反抗期の少年にとって、『新婚家庭』という言葉は地雷にも等しい。しかし彼は世渡りするだけの才覚は持ち合わせていた。 (い、依頼なんだから、ちゃんと、お、お仕事、するんだ!) ぶんぶんと頭を振って、気持ちを切り替える。 「んとっ、は、初めましてっ、し、新米陰陽師の、ラビ、ですっ!」 ぺこっと元気に頭を下げた勢いで、黒い兎耳もぴょこんとはねた。 「あんたの事は、そう知ってる訳でもねぇが、ここまで幸せボケた空気の男じゃ無かった、よなぁ‥‥」 しかしながら、げに恐ろしきは女の悋気―― 藍可が言う程やに下がった顔ではないにしろ、源右衛門を包んでいた他者を寄せ付けぬ達観した雰囲気が薄れている。やれやれ中てられそうだとくすりと笑んで、イーラ(ib7620)は捻じ曲げられた運命の帰着へと視線を向けた。 「おう‥‥於歌さん、言うんやね。良かったね‥‥おめでとう」 新妻に花束を手渡す神座真紀(ib6579)の目が潤んでいる。名は初めて呼ぶが、真紀と於歌の間には涙ぐんで祝福するだけの出来事があった。 「おおきに。ほんま皆さんのおかげです」 夫婦の道行きを知る開拓者の祝福に、於歌の目頭も熱くなる。花束に顔を埋めて涙を隠した於歌は、真紀の耳元へ囁いた。 「そうやの、今はオウタ言うんよ。オウカと音が似てるやろ?」 内緒話をするように囁いて、くすりと笑う。オウカは死んだ女の名であった。 ●用向き 「わあ、ジルベリアのお茶やね。おおきに。御酒を召し上がれない方に早速淹れさせて貰いますね」 マックスが手土産にと差し出した香り高い紅茶を、於歌は殊のほか喜んで微笑んだ。 そのまま厨に下がろうとするのを少しの間引き止めて、近況を尋ねる。 「あれから四ヶ月か‥‥此方の生活には慣れたか? 困った事はないか?」 「おかげさまで何とかやってます。ご近所さんも良うしてくれはって、源さんが目ぇ不自由やからって色々助けてくれますねん」 生活上の不便はないようだ。 声を潜めてマックスは更に問うた。 「私達以外に、知った顔や余所者が訪ねて来る事はあったか?」 「‥‥いいえ、おかげさまで」 真意は伝わったらしい。声を潜めて於歌は――柊歌は追っ手の影を感じる事はないと返した。 (今の所は大丈夫か) 於歌とて気配を読む程度の修練はしていよう。ひとまずは安心かと、マックスは於歌に目礼して席に着く。於歌は茶葉を手に喜ぶ若妻の調子で言った。 「ええお茶やわ‥‥楽しみやわぁ。御酒はお先にどうぞ。肴は菜花の和え物でええかしらね?」 ちょうど良いのが手に入ったんよと、於歌は茶葉を大事そうに抱えて厨へ消えてゆく。何かお手伝いしましょうと、空がその背を追って消えた。 夫婦で晩酌するつもりだったのだろう、ちゃぶ台には誂えたように燗徳利が置いてある。 冷えない内にとキアラの酌で遠慮なく呑み始めた。 「しかし身を隠すにはいいんだろうが、魔の森は近いわ王が坊主で堅苦しいわで‥‥住み難かないか?」 「住めば都と言うだろう、傭兵には過ぎた都よ」 「ふふ、於歌様がおられる場所が都ですか‥‥安田様も罪なお方ですね」 ゆったりと酌をして回りつつ、キアラは源右衛門の様子を観察する。 行き先を告げたきり、森藍可の許に戻らない理由。 (新妻が可愛くて離れる事が出来ないという理由なら可愛いのですけど‥‥) その割には源右衛門は落ち着いて見える。以前が無愛想の極みだっただけに随分と丸くなったと言えば丸くなったようなのだが。 「‥‥藍可は、息災か」 杯持つ手を止め、源右衛門が問うた。 気付けば数ヶ月新居に居続けている。雇い主に無沙汰を詫びるほど源右衛門は殊勝な性格ではなかったが、長年共に過ごした妹のような主に対しては懐かしむ気持ちも湧いた。 「気になりますか」 その時、良い香りを立てた茶器を運んできた空が、ラビにカップを送って単刀直入に切り出した。 「実は、その森さんから源右衛門さんを連れ戻せと依頼されまして‥‥」 「‥‥‥‥」 黙っている源右衛門をラビは凝視した。 依頼として聞いている話では、この男は森藍可の従者だという。妻を娶り、以後主の許に戻っていないのだという。何か事情があるらしいが、そんなのは彼の知る所ではなかった。 紅茶の芳香を胸に満たして、ラビは口を開いた。 「たとえどんな事情があろうとも‥‥」 強い語気で言いかけたそれをマックスが制した。事を荒立てては説得できるものでもないのだと、少年は瞬時に理解して引き下がる。 黙り込む源右衛門の表情を見つめ、マックスは言った。 「無駄だとは思うがね、これも仕事だ。私達も無理矢理連れて帰ろうとは思わん」 そして同じ思惑で様子を伺うイーラ。 (日がな一日外へも行かねぇのは、名張を警戒して離れられねぇからなのか) 名張の法は裏切り者を決して許さない。行方不明推定死亡の形で終わらせた柊歌の生涯を、名張は報告通りに信じたのか、あるいは裏に気付いた上で知らぬ顔をしてくれているのか―― (あちらさんが本当に気付いていないのなら‥‥いつシノビの情報網に掛かるとも知れない) 判断できない現状、源右衛門が警戒していても不思議はなかった。 於歌が見るに、周辺に名張の影はないらしい。顔を出すなら今の内かもしれぬとマックスは思う。 「ま、偶には顔を出してやれ。それに嫁に食わせてもらうばかりでは格好がつかんだろう」 「‥‥‥‥」 「戻るとなったら奥さんはどうする‥‥という事になってしまいますし、無理強いはしません。でも」 言伝をいただけませんか、と空はやんわり促した。連行はしないが手ぶらで帰る訳にもいかぬ。真紀が「そやね」と引き取って請う。 「せめて手紙でも書いたってくれん? もし不都合あるんやったら於歌さんの代筆で」 詳しい事情も知らず行き先しか教えられていない藍可にしてみれば、突然降って湧いた於歌に源右衛門を取られたような、面白くない心持にもなろう。 文字は人を表すという。於歌の手跡で彼女の人柄が伝われば少しでも両者の距離が縮まるかもしれないと、真紀は考えた――それに。 (楼港での出来事に森さんを巻き込まん為に伏せてるとしても、誤解は解いておきたいやん?) そうこうしている内に料理が運ばれて来た。和え物を口に運びつつ、そういう事なら於歌に代筆を頼もうかと源右衛門は言った。 ●主であり妹であり 源右衛門が言う要点を、於歌が文にしてゆく。 「えーと‥‥拝啓 花冷えの頃、日頃の無沙汰申し訳なく候‥‥」 森藍可への文は、至極簡潔にしたためられた。 夫婦共に息災である事、此方では退役武士と触れ込み暮らしている事、居住に不自由は特に無く近隣住民とも摩擦を起こさず過ごしている事―― ある意味、惚気だ。キアラが促した。 「森様をどう思われているのか、そのお気持ちをお聴かせ願えれば、と‥‥」 「藍可か? 雇い主で、妹のような、長年の付き合いで、腐れ縁のような‥‥」 困っている。 源右衛門が困ると代筆の於歌の筆も止まってしまう。暫くして真紀が助け舟を出した。 「大事な人なんやね」 「‥‥そうだな」 漸く考えを纏めた源右衛門は、於歌にこう書かせた。 『藍可に何事かあらば即戻り仕り候』 墨跡も黒々と、於歌は文を書き終えて筆を置いた。 有事の際には主の許へ戻る。それは当然の事だと解っていた。今共にあれる事自体が何よりの仕合せなのだと。 筆を置き、寂しさ隠して凛と佇む於歌の姿が、イーラには健気に見えた。 運命に翻弄され、死をも享受せざるを得なかった哀しい遊女の『今』、幸せな新妻になった『今』を、彼は一時の夢にしたくはなかった。消える前に救える夢なら手を伸ばして掬い取りたい。 とは言え、ここは和やかな新婚家庭。湿っぽい思考を語るは野暮というものだ。 「さて、と」 だからイーラは殊更にさりげなく言葉を継いだ。 「折角邪魔したんだ。力仕事でも使い走りでも、適当にコキ使ってくれや」 対価は美味い飯と酒があれば充分。面倒事だって手を貸すぜ、と。 ●梅は咲いたか 文を受け取り、依頼の面目を保った開拓者達は思い思いに過ごしていた。 イーラは屋根瓦を見てくると言い残して姿を消し、真紀は於歌に三味線の稽古を付けて貰っている。 「こないだ芸妓に扮して潜入してんけど、またあるかもしれへんし」 腕を磨いておかなくてはと構える姿は、なかなかどうして様になっている。なら少し併せましょかと於歌が先導して爪弾き始めた。 演奏を心地良く耳にしつつ宴は尚も続いている。 ちょこなんと座って紅茶を啜るラビの向こう側では、大人達が酒を呑んでいる。 「この歳になって、初めて家庭というものを知ったような気がする」 「家庭‥‥ですか」 しみじみと語る源右衛門を、空は微笑ましく眺めた。 彼が以前どんな人物だったのかは知らないが、旧知の者達との会話や近隣住民の反応から、現在の生活が幸せなものである事は充分に伺える。 (どちらも、大切なのですよね‥‥) 奥方様も、森様も。 神楽に戻って藍可にどう報告するか、キアラは考えを巡らせていると、ついでのようにさり気なく、マックスが森藍可周辺の近状に触れた。 「ああ、一応伝えておこう」 「‥‥何だ」 「あんたにとっても大事な話のはずだ。浪志隊だが、何ともきな臭い」 浪志隊――蝮党殲滅を切欠に藍可が係わり合いを持つようになった武装集団か。 「‥‥‥‥」 「事によると割れるかもしれん。ま、退屈してる森の姫さんとやらには、待ってましたの展開かもな」 難しい顔をしている源右衛門にそう言って、マックスは情報を与えただけだと言葉を添えた。 「この前と同じだよ。あんたがどう受け取るか次第さ」 「あたしにも、その内ええ人できるんかなぁ?」 曲の切れ目にぽつり漏らした真紀の呟きを、於歌は「勿論」と微笑して頷いた。 「縁は必ず見つかるわ。あたしは縁を皆さんに繋ぎ止めて貰ったんよ」 ありがとう。もう一度微笑んで、於歌は声を張った。 梅は咲いたか 桜も近し 花が繋いだ 人の縁―― |


