 たんすながもち
たんすながもち
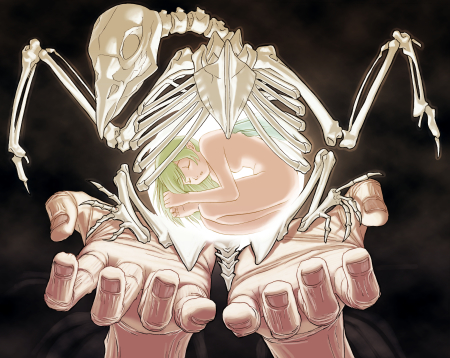 |
■シリーズシナリオ担当:蜆縮涼鼓丸 対応レベル:1〜5lv 難易度:普通 成功報酬:1 G 35 C 参加人数:4人 サポート参加人数:1人 冒険期間:08月20日〜08月25日 リプレイ公開日:2005年08月28日 |
|
●オープニング
蝉が鳴いていた。触れば火傷をするくらいに屋根瓦を焼いていた太陽も、今は空を夕焼け色に染め、吹き抜ける風もだいぶ涼しくなっている。午睡のまどろみから覚めた千歳屋の女主人は、緩みきった縞の着物の前を合わせ、帯を締めなおす。そして傍らに目を向けた。軽いいびきを立てながら、脱ぎ捨てた着物もそのままにふんどし一つで転がっている逞しい男。肩口から胸板、息をするたび上下する腹まで、順になめるように見、ふふ、と、うれしそうに目を細めた。
「‥‥ん? どうした?」
視線に気づいたのか、目を覚ました男が訝しい顔で見る。女はさらりといなし、薄く形の良い唇を、上向きの紅い三日月の形に歪めた。両の腕を男の首筋にゆるりと回し、艶のある声で言う。
「みんな、あんたの為にしたことよ。そうでなければあんな恐ろしいこと、しやしないわ。この千歳屋を乗っ取るために、私は手を汚したんだから。もうみーんな私の物。ううん、あんたと私の物、ね。だからあんたも‥‥お願いね? まさかあの人が遺言書を」
厚い胸板の匂いを嗅ぐように顔を摺り寄せる女の頬を愛しそうに男は撫ぜた。
「こごめ、お前は本当に怖い女だ‥‥亭主に毒を盛って殺してしまうのだからな。そしてお前は本当に‥‥可愛い、俺の女だ。約束は、守る。必ずな」
ぐい、と女の身体を引き寄せ、その柔らかな体をきしむほどきつく抱きしめると、女の体から微かに麝香の香が漂って、男の鼻孔をくすぐった。
おどろおどろしい看板が何枚も立ち並ぶ、見世物小屋の前の通り。
「さあさあお立会い、寄ってらっしゃい見てらっしゃい、御用とお急ぎでない方は、これを見なければ一生の損!」
派手な呼び込みの声が響く。つられて覗き込む客もいる。
「親方、張り切ってるなあ」
目の鋭い男は商売道具の投げ小柄を磨きながら、側の女に言う。女は大きな石に腰掛け、足をブラブラさせながら返す。
「この場所で小屋を張るのも今日が最後だからね。明日からは小屋の解体と挨拶回り。あたし達も忙しくなるわね」
「それにしても急な話だな。親方に話を聞いたの、一昨日だぜ」
「それだけおいしい話なんじゃなあい? さあさ、余り油売ってると、またどやされちまう‥‥あ、ゆか坊、もう掃除はすんだのかい?」
ゆか坊、と呼ばれた女の子は、歩いている所を呼び止められて立ち止まったが、女におざなりに頷くと、またすたすた歩いて行ってしまった。
「なんだいありゃあ?」
普段はあんなにそっけない素振りはしないのに、と女がぼやくと、男は磨き終わった小柄を懐に仕舞いながら、さあな、恐らくは友達に別れの挨拶でもしてくるんだろうよ、と、瞳に哀れみの色を滲ませた。
「あら、ねえあんた達、うちの子見なかった?」
奇妙に太い、しなを作った声に二人が振り返ると、派手な化粧に振袖を着たいかつい男が柳眉をひそめて立っていた。身の丈はおよそ八尺、二人は大男の顔をうんと見上げた。
「鳴神太夫か。ゆか坊なら遊びに行った様だぜ。ここらの友達とももうじきお別れだ、今日くらいは羽根を伸ばさしてやったっていいだろう」
「‥‥まあ、それはそうなんだけど。ちょっと気になることがあるのよね」
「ミオヤさんもゆか坊のことになるとお母さんの顔になっちゃうのね」
女のほうに茶化されると、偉丈夫はやはり太い声で、
「だってあたしはあの子の母親ですもの。例え血の繋がりがなくったってね」
と、大真面目に答えた。
お糸は呆けた顔で、我が子の前でへたり込んでいた。
愛娘のゆかりは5つになる女の子で、今はお糸の目の前ですやすやと寝息を立てている。いつも首にかけている藍色の守り袋を、娘の寝しなに、首に絡まるといけないからと外してやった。外して見ると、藍色だったはずの守り袋が何故か鶯色になっていて、お糸は驚いた。
その古びた守り袋に、お糸は見覚えがあった。今の夫と一緒になり、ゆかりを産むよりももっと前、お糸はもう一人、娘を産んでいた。事情があって捨て子にしてしまい、それきり行方も知れず、てっきり死んだものとばかり思っていた、その娘の首にかけた物がその緑の守り袋だった。鶴亀の刺繍も記憶のままに、年経た分だけ磨り減ったり汚れたりはしているが、確かに間違いない。
あの子が。生きていたんだ。きっとそうだ、そうでなければここにあの守り袋があるはずはない。
意を決したお糸は我が子をそっと揺り起こし、守り袋のことを尋ねた。
「さて、依頼の話でやんすが」
ギルドの係員を務める小男は、大柄の冒険者たちに負けまいとしてか、背を反らせ気味に立ちながら依頼書を読み上げた。
「娘の友達を探してほしい。名前は分からないが年は7つくらい、どこに住んでるかもわからねえが、首にかける守り袋を持っていて、藍色の地に鶴亀の刺繍がしてあるんだそうでさ。もともと娘の方がそれを持っていたんだが、友達のほうも同じような守り袋を持っていて、取り違えてしまったらしいと言う事でやんす。自分の手で返してやりたいので、所在を突き止めたら教えてほしい‥‥ってこってすな」
依頼書を読み上げ終わると、係員は皮肉な笑みを口の端に浮かべた。
「依頼人はお糸さんってぇ人ですな。大工のかみさんで、こないだもうちに依頼を持ってきてくれたし、まあ良いお客様ですな。頑張っておくんなさいまし」
係員は冒険者達に頭を下げつつ、にいっと笑って記録棚を指差した。
「‥‥そういえば、こないだもやたら似たような依頼がありましたかね。もしかすると関係があるのかも知れやせんねえ。記録を調べるんだったらどうぞご自由に」
●今回の参加者
ea1959 朋月 雪兎(32歳・♀・忍者・パラ・ジャパン)ea9703 グザヴィエ・ペロー(24歳・♂・ジプシー・人間・ノルマン王国)
eb1807 湯田 直躬(59歳・♂・陰陽師・人間・ジャパン)
eb1817 山城 美雪(31歳・♀・陰陽師・人間・ジャパン)
●サポート参加者
湯田 鎖雷(ea0109)●リプレイ本文
●どのこがほしい?朋月雪兎(ea1959)は湯田直躬(eb1807)と共に、湯田の息子である湯田鎖雷を伴って集合場所に現れた。伴って、というよりもむしろ、迷子癖のある朋月のために送り届けに来た、というのが正しい。ついでに息子は父親にほいと包みを手渡す。にやりと笑う息子と父親の間に、微妙な色の火花が散った。
傍らで山城美雪(eb1817)は巻物を手に念じていた。目を閉じて集中するが、しばらくすると僅かに眉間にしわを寄せながら、ため息をつき、天を仰いだ。
「どうなされた?」
湯田に問われ、山城は手にした巻物を湯田に見せる。未来を知る魔法、フォーノリッジのスクロール。
「これを使って『藍色のお守りを持っている子供』を見ようとしたのですが、うまくいかないのです」
「ああ、ならばもう少し簡単に対象を指定せねばの」
グザヴィエ・ペロー(ea9703)も頷く。
「専門的な方のスクロールならそういう指定でも大丈夫だと思うけど、初級だと『犬』とか『つぼみ』とか、そのくらいじゃないかな?」
「『ゆかり』でやってみてはどうだろうか。藍色の守り袋を持っている子供というなら、お糸さんの娘さんも見世物小屋のゆか坊もどちらもあてはまるのだし、同じではないかな?」
陽の精霊魔法を知る二人から助言を受け、なるほど、と山城は眉間のしわを伸ばした。改めて巻物を手に集中すると、山城の体をうっすらと金色の光が包んだ。
山城のまぶたの裏側に『未来』が写る。藍色の守り袋をもつ小さな手がちらりと見えた。それから、視界は一気に真っ赤に染まった。山城は目を開けた。
「今のは‥‥血飛沫?」
物騒な言葉に、朋月は目を大きく見開いて一歩後ずさる。先の依頼で目の当たりにした、血だまりの中に男が倒れている光景が頭をよぎった。
「そうならないために、僕たちがいるんだから」
「‥‥うん。そうだよね、あたしだってれっきとしたくノ一だもん、しっかり護衛しなくっちゃ!」
グザヴィエにぽんと肩をたたかれて、朋月はきゅっとこぶしを握り、気を引き締めた。
●お布団かぶって
見世物小屋のゆかりの友達を探し出したグザヴィエは、子供たちと一緒に遊びに興じていた。
無心に影踏み鬼をしているように見えるが、ただ遊んでいるわけではない。打ち解けていくうちに子供たちからゆかりがどこへ行ったのか、見世物小屋が移動した先を聞き出そうとしていた。
鬼が一巡したあたりで一息つき、頃合を見てグザヴィエは子供たちに尋ねる。
「君たち、ゆかりちゃんからどこに行くか聞いてない?」
子供たちが顔を見合わせる中、一人だけ、額の秀でた少女が、
「あたし、知ってるわ」
と得意気な顔で言った。
「江戸から西に行く大きな道があるでしょう? 朝からずうっと行って、夕方に渡し舟で川を渡って、津麦村っていうところに行くんだって」
その子の頭をなでてやり、ありがとう、と言うと、少女は役に立てたことが誇らしいのか、胸を張った。
グザヴィエは西の空を眺めやり、目を細めた。津麦村、と村の名前を口の中で繰り返す。
そろそろ行かなくちゃ、じゃあまたね、と子供たちに手を振って、グザヴィエは仲間たちのもとへと向かった。
ほぼ同刻。
山城は、朋月と一緒にお糸の家に向かっていた。お糸の義理の兄である六助を尋ねるためである。
六助は斬られてから寝付くようになっていた。長屋の奥側の部屋に入ると、すぐに換気があまり良くないのだと感じた。朋月のほうはさらに忍び特有の鼻の良さがあったから、余計に病人の匂いを感じ取ったようだった。
「刀傷の予後が良くなかったのでしょうか、少し体を動かすとすぐに熱が出て。お医者様は、ひどく怖い思いをした時には特にそうなりやすいのだとおっしゃって」
お糸の表情も曇りがちで、ぽつりぽつりとそんなことを話した。
夏場だが布団の中の男は震えているようだった。顔は赤く、息も荒い。男の額に乗った濡れ手ぬぐいをお糸は枕元にあるたらいの水に漬け、固く絞ってから、また男の額に戻した。
まともな答えが返ってくるかは怪しかったが、山城は六助に尋ねてみた。
「お聞きした限り、どうも腑に落ちません。遊び歩いていた際にはどこから資金を捻出されたのでしょう、弟さん以外の方から何がしかのお金を頂いたとしか思えないのですが」
「し、知らねえ‥‥俺は何も知らねえ、話さねえぞ‥‥」
半ばうわごとのように六助は呻く。ちら、と病人に視線を落とし、なお表情を変えることなく山城は畳み掛けた。
「それと。何かお隠しになっていることはございませんか? このままではまた襲われるかもしれませんね」
「そんなことはねえ‥‥俺は話さねえ‥‥四十九日が過ぎれば」
そこまで話すと、六助はまた意識が朦朧としてきたのか、乾いた唇からはもう言葉は出てこず、ただはあはあと荒い息ばかりを吐くのだった。
「そういえばゆかりちゃんはどこにいるの?」
朋月はお糸に尋ね、娘が遊びにいっているのを知ると、あわてて追いかけようとした。
「大丈夫ですか?」
山城が冷めた目で見る。尋ねているのは朋月の方向音痴のことだ。
「うん、雪風も吹雪もいっしょだもん、大丈夫っ!」
元気いっぱいに答えると、朋月は家の前で待たせていた鷹と犬とを連れ、軽快に走り去った。もっとも、一分後に方向違いに気が付いて、同じ道を逆走することになったのだが。
●お釜そこぬけ
グザヴィエの得た情報は仲間にも伝えられ、お糸にも伝えられた。お糸は、ぜひ自分の手で守り袋を渡したいと冒険者たちに懇願した。
一日あれば目的地には行ける。お糸が家を空けたいと言った時、お糸の夫は複雑な表情を見せ、なかなか首を縦に振らなかったが、お糸の必死な態度に根負けしたのか、とうとう
「仕方ねえな」
と言った。なぜか寂しげな声色だった。ゆかりも行きたいと泣いたが、お糸は娘を抱きしめて父親と残るように説得し、最後にはしぶしぶゆかりもうなずいた。
翌朝、お糸を連れて江戸から西へ、冒険者たちはほぼ一日の行程をたどり、太陽がだいぶ西に傾いたころ、宿場からそれほど離れていない小さな村に着いた。
しかしどこにも見世物小屋は見えず、そもそも見世物小屋が巡業に来るほど賑やかな場所でもない。宿場にもっと近い場所のほうが明らかに客は来ると思われた。
一軒の戸を叩き、見世物小屋のことを尋ねると、確かに来ているという。村長に聞いてくれ、と言われて村長宅に案内してもらうと、聞き覚えのある声がした。村長は奥に声をかけ、顔を出した見世物小屋の親方は湯田を見て、ほう、と驚いた顔になった。
「なんだね、また変な踊りを披露しに来たか?」
「いいえ、私たちは冒険者で、こちらのゆかり様に用事があって参りました。お会いしてもよろしいでしょうか?」
山城がさっと言葉を挟む。親方はもう一度驚きの声を上げた。
「こんなところで立ち話もなんですから、あなたたちもどうぞこちらへ」
村長にそう勧められ、村中の人間が集まれそうな広い三間続きの部屋に一行は通され、そこでゆかりたちの一座と顔を合わせることになった。
ゆかりはそわそわしながら冒険者たちの前に座る。
「その前に、親方にちょっとだけ話を聞いてもいいですか? 見世物小屋に移動は付き物だけど、江戸には長く居ましたよね。でも今回はずいぶん急に移動したんですね。ゆかりちゃんも友達がたくさん出来てこの地に馴染んでいたようだったのに‥‥。何か事情でも?」
「事情‥‥まあ、ないわけじゃあないが」
親方は言いよどみ、その場ではそれ以上のことは聞き出せなかった。グザヴィエは一度引いて、代わりにお糸に前へ出るよう促した。
お糸は、穴が開くほどゆかりを見つめた。
「ゆかり様。ゆかり様は、こちらのお糸様の娘さんと、お守りを取り違えてお持ちになっているのではありませんか?」
「うん。でも、間違えたんじゃないよ? ゆかりちゃんがどうしても欲しいっていうから、とりかえっこしたの」
そういってゆかりは首から下げていた藍色の守り袋を外して、自分の前に置いた。お糸も持参した鶯色の守り袋を取り出してその横に並べる。二つの守り袋は色違いなだけで、鶴亀の刺繍から何から、本当によく似ていた。
「‥‥これって、ただの偶然なのかな」
グザヴィエが呟いた言葉は、その場に居たほとんどの人間の問いかけでもあった。
お糸が静かに、だがきっぱりと
「偶然ではありません」
と言った。その目から涙があふれ、こぼれ落ちた。
湯田はそっと部屋を出て行く大きな影に気付いた。同じようにそっと部屋を出て、そのあとを追う。身体は大きいが身のこなしは洗練されていて、足音はほとんどない。
廊下を抜けて、縁側に佇み、女物を着た大男はじっと星を見上げた。しばらくそのまま男は立ち尽くしていた。
「鳴神太夫さん」
湯田が声をかけると、男は一瞬肩を震わせ、振り返った。
「夜風は身体を冷やすもの、そんなところにずっと居ても夏風邪の元になりますぞ。中に入りましょう」
「‥‥戻りたくないわ」
「では、ゆかりちゃんのいないところで少し話でも」
鳴神太夫、つまりゆかりの『母親』は湯田の顔を穴が開くほどじーっと見つめた。それから上から下までじっくりたっぷり何往復もなめるように眺めて、ぽっと頬を赤らめた。
湯田の胸にいやな予感が走った。
鳴神太夫のたくましい手が湯田の手首をしっかりつかみ、引きずられるように湯田は一室に連れ込まれた。
中に入ると、鳴神太夫は身をくねらせながら湯田の胸をつーっと指でなぞる。
湯田の毛穴がざわっと開いた。
「また会えるなんて、思ってもみなかったわ、湯田さん‥‥ううん、直躬さん、って呼んでもいいかしら?」
「いや、その、鳴神太夫さん、私は子供を持つ親同士色々と話をですな」
「直躬さんのほうからゆかりのいない所で‥‥慰めてくれる、だなんて。そんないやーんどうしましょう私ったら心の準備がぁ〜ん」
たぶん鳴神太夫は湯田の言葉を聞いていない。
かーん、かーん、かーん。
湯田の頭の中で、危険を知らせる半鐘の音が激しく鳴り響いていた。
引きつった笑顔のまま、湯田はじりじりと戸口のほうへすり足で移動するが、潤んだ瞳の鳴神太夫は湯田と同じ速度で移動して、距離を開けさせなかった。のみならず微妙に位置を変え、いつの間にか鳴神太夫は戸口を背に、逃げ道をふさぐような位置に立っていた。
「直躬さん。‥‥実はね、あたし、初めて見たときから」
決して小柄ではない湯田の体に、さらに一回り大きな体が迫る。
‥‥以下略。
●ふるさともとめて
広い部屋でお糸が語ったのは、自分の過去、捨てた娘の首に掛けた鶯色の守り袋のことから始まり、父親である竹蔵という男のこと、今自分がどんな暮らしをしているか、もう一人ゆかりと言う名前の娘が居ることなど、とてもたくさんの事柄で、長い話になった。だが、ゆかりはまっすぐお糸の目を見て話を聞き続けた。
「竹蔵さんも、今はきっとのれん分けをして店のひとつも持っているはず。とても子供好きな人だったから、娘が居ることを知ったらきっと喜んでくれるに違いないし。だから、ゆかりちゃん、私と一緒に江戸に戻ってほしいの」
「いや、待ってくれ。そいつはちっと難しいな」
親方が渋い顔で話に割って入った。
「そもそも俺たちがここに来たのはある人に頼まれたからでな。一ヶ月の間、一座の人間全員、江戸を離れて欲しい。そうしてくれないと恐ろしい事が起きるからってな。」
「恐ろしい事? 誰に頼まれたの?」
朋月が問い返すと親方は首を振った。
「分からん。手紙と一緒に20両届いたんだ。20両だぞ、20両。大金だ。返そうにも返しようがねえし、たまには骨休めするのも悪くなかろうってんでここまで来た訳だ」
「でも」
ゆかりはうつむいた。
●はないちもんめ
布団を並べて眠りに付く直前、ゆかりが細い声で母を呼んだ。
「おっかさん」
「なあに?」
「あのひとがね」
そのまま口をつぐんでしまった娘の頭を、鳴神太夫は大きな手で撫でてやる。
「ゆかり。あんたが好いと思ったことをおやんなさい。あたしはいつだってあんたの味方なの。だって、あたしは」
穏やかな微笑を浮かべて鳴神太夫は娘を抱きしめる。
「あたしは、あんたのおっかさんなんだから」



