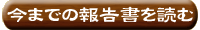【灰神楽】 露の答/屋代島
【灰神楽】 露の答/屋代島
 |
■キャンペーンシナリオ担当:紺一詠 対応レベル:11〜17lv 難易度:難しい 成功報酬:25 G 58 C 参加人数:8人 サポート参加人数:-人 冒険期間:10月28日〜12月03日 リプレイ公開日:2006年11月05日 |
|
●オープニング(第2話リプレイ)
●海「俺はもう何が出ても驚かないぞ」
アリアス・サーレク(ea2699)、ごろりと船板に寝転がる。雲居の青が、青い眼底に、じん、と、沁みる。少女のあらわした土地へ船を進めるためにこのまま商船の真似をつづける、とは決めたものの、操船手は別にいるから、船の動いている間はとりたててやらなければならないこともない。隠居のようにぼんやりしているのも気が咎めて、船縁からちょいちょい釣り糸たれつつ、思いの外ごつごつした汀線のどこかに影が潜んではいやしないか、きちんと見晴ろうと努めてはみたが、これもまた空しく終わった。たしかに船影のようなものはちらちら見えたが、それが敵味方か、一目で嗅ぎ分けるのは易しくはない。
――金髪の偉丈夫? 虎や鬼にそっくりの?
どうにでもしてくれ、だ。
本人ふてくされたつもりは毛頭なかったものの、そんなふうにみえてもおかしくない有様だったようで、あら、と、鷹神紫由莉(eb0524)が微笑ましげに、水を差す。
「では、昔、一晩付き合った女性が『あなたの子よっ』と言って、赤ん坊といっしょにこちらまで押しかけてきたら、どうなさいます?」
「‥‥それは、少しは驚くかな。というか、いろいろと待ってくれ」
退屈凌ぎに過去を捏造しないでくれ、と、アリアスが半身を起こせば、紫由莉はもうとっくに気はうつろって、熱心に、手元の略図に見入っていた。略図とはいっても、まるで子どもが気の向くままに筆を走らせたような、地図とはとても呼べない代物であったけれども、これも善意の供出であることを思えば、不平も付けられぬ――要するに、まともなのは手に入らなかったので、勘所のよい土地の者が即席でしあげたのを引き取ったのだ。ろくな縮尺ではないから、地名のちらばりようぐらいしか参考にはならないだろうが、ないよりはマシ。
「ラルフだと思うか?」
ふとアリアスが、仰いだ姿勢のままで、沈静を破る。誰が、とは言うまでもない。御神楽澄華(ea6526)のやるせない吐息が、皆の思いを凝らせていた。
「なんとも‥‥ですね」
ほんとうに、さっぱりだ。いっそ仕掛けてきてくれなら、打ち返すことで、何かが知れる。が、片側と別れて以来ほとんど責務を忘却しそうになるくらい、平和で順良な日々が続いている。カヤ・ツヴァイナァーツ(eb0601)もアリアスを真似て船板に仰向けになれば、新しい遊びかと飼い猫がじゃれついてくるので、よぅしよぅし、と、抱き上げてやる。ツヴァイは、アリアスほどには、船路に嫌気がさしていない。べつに無聊をなぐさめてくれる遊び相手がいるからでなく、こうなることを半ば予想していたからだ。
それまでろくな報せを聞けなかったというのに、島へ着いた途端、まるで導かれるように舞い込んできた風説。
蜘蛛の糸をたぐる罪人のように、自分たちは与り知らぬ一つところへ絡繰られている――そんなかんじがする。いい気はしない、という個人的な感情は横においても、そこから導かれる推量はあまりに不愉快で仄暗い。
「サンワードじゃ、名前まで分からなかったもん。似たようなことは言ってたけどねぇ」
あのあとスクロールを使って、ツヴァイ、地図をみせた少女の行く先を探ってみたのだ。すると、金髪の偉丈夫、とやはりいつぞや聞いたような返答で、驚嘆よりも、あぁやっぱり、と理解が勝る。納得はしないが。
「おそらく、あちらには、こちらを呼びたい意図があるのでしょう」
澄華もほぼ同様のことを考えていたようで、この、科戸の風のような日々も彼女の狼狽には値しない――茶番ならば、茶番を突き通すまで。荷の下に包んだ刀を引き出す支度はいつでもできている。一人、気楽をよそおうのは紫由莉、仕入れる予定の柑橘を上機嫌に数え上げている。商人の風の練習かと思いきや、どうやら本気で早稲の蜜柑をねらっているようだ。
そうそう、これから目指す五条といえば、
「桜並木が有名なのでしたね」
温暖な気候だから一面の紅葉とはいかないだろうが、ふさふさと青い葉冠を揺らす梢を見やるのも、それはそれで目に涼しい。桜は、一年を通じて、桜だ。野暮ったい艶消しの樹皮の下は、来るべきに備えて、
「黄色いサクランボでもなっておりませんでしょうか」
「サクランボ?」
まぁ、この時代では、まだまだ珍しい果物なので。
●陸
一方で、陸路は苦々しい道のりになった。
海沿いを東回りに進んで途中から降下、と、決めたのはよかった。が、屋代島の農業が柑橘栽培が中心になっているのは、逆にいえば、稲作にまったく向かない土地だからである。浜へぴたりと丘が接着したような地勢には平野が少なく、河川がないので淡水の確保が容易でない。これはそのまま、旅歩きの難しさにも繋がる。
「めひひひひん、あともうちょっとで休めるぞ」
まして、京の周囲ではない、初めてにも等しい路程だ。湯田鎖雷(ea0109)の飼う頑丈な馬匹ですら一日の終わりには水に浸かったように青息吐息、蹄をもたぬかよわい二つ脚の身ならば尚更だろう。道祖神様も、こればっかりは、どうしようもありませんしね――まぁ、天候に祟られなかっただけ御利益はあったとしましょうか。風のない黄金の夕刻。高槻笙(ea2751)は石灰のような艶の額を拭う。不快な湿り気が音を立てそうに、白い指をじっとりと伝った。
「約束どおりの期日に合流するのは、少々難しいかもしれません」
「‥‥和佐へ行くのは、あきらめたほうがいいでしょうか?」
山本佳澄(eb1528)が綿入れのようにふくよかな乳房を上下させる――と、そこらに、ぼとり、と、判で押したような染みが付く。ぼとり、ぼとり、と、汗染みはたちまち膨れて、そこに揚羽蝶でも休んだかのように、ついには一面に展翅する。熱い風呂につかりたい、と佳澄はぼやく。この島では、それが、真夏に氷雨を口にしたい、というのと同程度の贅沢であるとは分かっていても。
まぁ、陸路をとってよかった、という思いもある。ぽつ、ぽつ、とではあるが、五条の宮のものではないか、という打ち明け話も舞い込んできたからだ。百のハズレの中の、一のアタリ。空振りのほうが多かったけれども、細小波を払い除けながら――笙はふと都での出来事を回想した。
「どうして長州は五条の宮を預かることになったんでしたっけ?」
それについて鈴鹿が特に言明しなかった理由は、言うべきことがなかったから、だ。長州が五条の宮を引き受けたゆきさつは消去法、関東は上州の叛乱等でそれどころではない、北陸は五条の宮に荷担した豪族が多く不向き、九州は長崎や大宰府があるから持ち掛けにくい、四国はどこも引き取りをいやがって――と、まぁ、こんなかんじで、済し崩しに長州と決まった。が、鈴鹿は、こういうふうにも付け加えた。
『国同士のやりとりの真相を、私一人から聴き出したといって、分かったつもりになる方が危険だと思うがな』
それぐらいで白日に晒される真実ならば、そもそも暗躍や計略などおこなわれる意味がない。――そのとおりだ。だからこそ、笙、こんな地の果てのような閑地にまで、望んできたとはいえ、追いやられたも同然で。鈴鹿、五条の宮の祖父の配流先を知らないか、との問いには、知らぬ、と、あっさり切り返した。
『公家の連中が懸命に晦ましている節があるからな、深く掘り起こすと身が痛むらしいぞ』
五条の宮の祖父について触れようというのは、公家のあいだでは、禁忌に近い振る舞いであるようだ。現在、都で安穏をむさぼる貴族の中にも、先祖の代、彼に荷担したりしなかったものは多い。昔の罪を又候呼び覚ましてとばっちりを受けるのはごめん、と、そんな事情らしい。志士が力を持つようになったのは至極近年の出来事だから、鈴鹿が知らないのもとりたててムリはない。
予定の二分の一を越えるか越えないか、の道のりで、辿り着いた集落に一時の安らぎを借りる。鎖雷、愛馬から荷、酒だ、を一つ切り崩すと、それと藁の交換を申し出る、その駆け引きがてら、なにげなく訊きだした。
「この島への行きに賊らしい船を見て驚いたが、水軍は陸に帰ったら何処で何しているのだろうか」
「知らないのか?」
問いに、問いで、突っ返される。何を、と、訊いても、それ以上は教えてもらえそうにない雰囲気だった。――その晩は、ともかく、安息に入る。気持ちの良い藁で身体を拭いてやると、愛馬はすぐに寝入る。対称的に、鎖雷、ずっと起きていた。寝込みを襲われても、かなわない。
「‥‥鎖雷さん」
「寝ていなかったのか」
天幕に潜り込んだばっかりだというのに、笙、ごそごそと間もなく起き出してくる。疲れが溜まりすぎて、睡眠にまでとうとう変調をきたしたらしい。
「無理矢理に寝たほうがいいぞ、どうもこの調子があと何日も続くらしいからな」
「いったい何が真意なのでしょうかね」
いいや、それ以前の問題で。誰の、というところから、見えなくなっているのかもしれない。
二人そろって、ほぅ、と、つくづく夜を眺める。秋の星宿は、恥じらいを知る乙女のように、華やかではないがつつましい。
「鎖雷さん」
「ほんとうにもう寝たほうがいいぞ」
「私が寝たあとでしたら、紫黒を頭に載せてみてもかまいませんよ。私は見てませんから、遠慮なく」
「この世が終わるまで、寝かしつけてやろうか」
――ところで。出しなに、鈴鹿は、言っていた。
『屋代島はそもそも海賊のねぐらだ』
と。
それはつまり、島の住人が海賊の存在を許容しているという裏返しでもあった。海賊の狙いの殆どは海路を往復する米や荷にある、湾岸の貧しい漁村など襲っても仕方がないからだ。逆に、海賊らは島のものにそれらの収穫を分け与えることもある、罪深き財など要らぬ、と、突っぱねられるほど清貧を貫ける民草ばかりではない。
要するに。
――彼等に悪気がないことは、あらかじめ付け加えておこう。島の住人は、はじめから、海賊の身内も同然だった。彼等に海賊のことを尋ねる、それだけで、こちらの動向が筒抜けになる可能性は高かったのだ。鎖雷に限らず、海路を選んだものも、道すがら海賊について尋ねまわった。この結果、彼等が分断して動きまわっている、という現実は島の海賊衆にとって瞭然としたところとなり――‥‥。
それは、やがて――‥‥。
●
陸路は想像以上の時間がかかった。一方、海路はあべこべに、想像以上に安らかな日々。この差は大きい。五条に近い浜辺。――海を往くものたちがそこに行き着いて数日、しかし、陸を辿るものたちが姿を見せる気配はまったくなく、アリアス、とうとう極まった感のある退屈を投げだそうとでもするように、両腕をふらふらばたつかせる。
「どうしようか?」
もはや、心底やることがない。紫由莉はせっせと商いごっこをつづけていたが、柑橘を仕入れるふりも一つところでは限度があろう。はぐれた片割れらと連絡の付かないのを不安に感じた澄華、両腕をふらふらとばたつかせる。
「先の港へ戻りましょうか?」
場合によっては京へ非常事態を告げに戻っても――と、が、京へ戻ってからではいくらなんでも遅すぎるだろう。第一、これは冒険の一環だ。京へ連絡を付けても援軍を寄越してもらえるとは限らない、むしろそうしないために冒険者が雇われた、と、考える方が正しい。
「ここまで来て、何も見て帰らないというのも‥‥」
紫由莉、ちろりと視線をさまよわせる。地元のものらとやりとりを続ける中で、五条の宮が住まっているとおぼしき庵の位置はすでに聞き及んでいる。ここでいったん撤退すれば、同量、いや場合によってはそれ以上の危険と苦難を支払わなければ、再びここへは立ち戻れない。と、アリアスが折衷案を出す。
「所在のみ、確かめてくるというのはどうだ? 無駄な騒動は避けるに越したことはないが」
「そうだね、見るだけ見てこよっか」
その周辺だけでも様子を見て回る、というのは、悪くない案に思われた。が、けっきょく、ツヴァイの思惑は、彼にとって真逆といっていい形で裏切られる。
庵は寂しく、静かであった。火宅の掃きだめへ打ち捨てられたように、いや、そのものであったから。
「これは‥‥」
彼等、用心に用心をかさねて、庵の間際まで近付く。そこには何の気配もなかった。それは、もうすっかり古寂びていた。五年、いや、十年以上も人が住まったことのないように見える。穴の空いた障子、外れた柱、伸び放題の茅。
「欺されたのか?」
「‥‥分かんない」
危惧していたのは、自分らに五条の島脱けの嫌疑を掛けられること。が、見せつけられたのは、まったくの望外。
「でも、どうして?」
ひとまずその場は引く。船へ戻ってじっくり理由を見繕うとしたとき、とうとう、不安が現実にやってきた。海賊衆の襲来。
一方と合流も果たせぬうちに。――つまり、戦力を分割した状態で。海賊衆らの手際は良いとは云えなかったが、何しろ数が多く、それも地の利、いや、水の利は向こうにある。澄華がとうとう血にまみれる。だが、彼等は船を出すことすら、かなわなかった。まだ鎖雷らが戻ってきていない、彼等と寄り合うまで(或いは見捨てることを選択するまで)船を死守せねばならない。
最悪だった。が、それ以上に最悪なのは――。
陸のものたちが取り決めの刻限に間に合わなかったのには、むろん理由があった。――‥‥否。それは理由など生やさしいものでなく、悪夢という命数、数奇という不運。
「はは‥‥」
鎖雷、『彼』を前にして後じさる。『彼』の放つ圧倒的な鬼気に容赦も我慢も差し込まれる余地はない、と、本能で悟ったものの、箱の中の最後の光にすがりつくようにして、なけなしの反駁を試みる。
「な、なぁ。酒があるんだ。これで勘弁してくれないか?」
「いらん」
鬼か虎と呼ばれた男――冒険者にとっては大して珍しくもない金髪が、血糊でも塗りたくったように、やけに禍禍しく映る。獣となんら変わるところのない嘶きを挙げながら、彼は豪速で刀剣を振り落とす。致死量にあと一歩とどかぬ剣筋が、鎖雷の着物を割った。赤い線――裂傷。
単身で城を落とし、名うての冒険者が数人どころか十数人がかりでも押さえつけられず、四面楚歌の激戦のさなかをそれでも生きて逃げだした男。
名を、ラルフ、という。
鬼というより、もはや鬼神。虎というより、もはや妖獣。
「‥‥参ったな」
とうとう出たかよ。遊ばれている。いたぶるような浅い傷が、何よりも雄弁に彼の思想を語っている。
「っくしょ、生きて帰ってやるんだよぉ!」
「まったくですね」
笙、佳澄が蒼い貌になって剣を握るのを横目にしながら、ぼんやりと嘆く。真実を知りたかった、しかし、今は、これが何よりの真実。これと戦って活路を切り開くしか、道は残されていないのだ。片手の指にもとどかぬ人数で。
最悪な、真実だった。
●今回の参加者
ea0109 湯田 鎖雷(36歳・♂・浪人・人間・ジャパン)ea2699 アリアス・サーレク(31歳・♂・ナイト・人間・ノルマン王国)
ea2751 高槻 笙(36歳・♂・志士・人間・ジャパン)
ea6526 御神楽 澄華(29歳・♀・志士・人間・ジャパン)
ea8545 ウィルマ・ハートマン(31歳・♀・ナイト・人間・ロシア王国)
eb0524 鷹神 紫由莉(38歳・♀・志士・人間・ジャパン)
eb0601 カヤ・ツヴァイナァーツ(29歳・♂・ウィザード・ハーフエルフ・ビザンチン帝国)
eb1528 山本 佳澄(31歳・♀・志士・人間・ジャパン)
●リプレイ本文
●死の一その男に向かって、高槻笙(ea2751)は切々と訴える。我々は宮を弑逆する為に訪れたのではなく、安否を、真実を見極めに来たのです、と。
あなたは誰の手引きで島に辿り着いたか。
何故、戦いを望むのか。
高杉・吉田の名はご存知か。
この国にやってきた理由は何か
笙、まるで千年も説教節を解きつづけたように、喉が干涸らびるのを感じた。が、それらを言い終えるまでラルフが待ち構えたのは、最後の憐憫だったのだろう。そして、彼はこれ以上の憐れをかける必要をおぼえなかったらしい。
「‥‥ならば、死ね」
と、答える。冷えた低音。洞穴を渡って鍾乳石を響かせる、行き止まりの風をおもわせる。
「神は俺より博識で寛容だろう。神に、尋ねろ」
城壁のように堅牢たる拒否。交渉などやはりムリなのか、と、軽い絶望、それと同時に覚悟する。見せかけの道具と運んでいた酒樽が遂に役立つときが来たか。
しかし――それより、一瞬速く、ラルフの刀が唸りを上げて、笙が取り上げようとした先を切り落とす。
湯田鎖雷(ea0109)を回復のために下げたのは笙自身であり、山本佳澄(eb1528)は魔法の詠唱の時間を稼ぐためにやはり後衛に下がった。ラルフとの相対に実質的な前衛として接近するのは、笙一人、ましてたった今、会話を試みた相手だ。笙の一挙一動にラルフが警戒を払うのは自然、不意打ちが不意打ちとしてなりたつだけの横着があろうはずがない。
たしかに酒は、ラルフにもささやかに掛けられた。が、それをはるかに過ぎる嵩が笙のやにわに半身に塗抹され、あらわになった酒精にくらりと霞む。これでは、ラルフに火を掛けるどころではない――‥‥、
火?
火打ち石は背嚢の中だ。だのに、笙、すぐ身近から火の手が轟々とどよめくのを聞く。――あぁ、それはたしかに火柱にもよく似て。刀傷とは思えぬほど太い線が、胸を斜めに裂いた。
「‥‥っ」
「下がれ、笙!」
煤のような土煙を蹴り上げて、鎖雷、佳澄から譲られた薬水で平復した身体で躍り込む。佳澄の手から撃ち出される雷霆が青味を帯びてほとばしるのを背に、くちなわの鞭を細く鋭くラルフの足元に叩き付ける。ラルフの意思はすでに示威の段階を越している、だから、鎖雷の攻撃も威嚇の鎧を剥いだ。撫で斬るように、横へ払う。
「おまえは海賊なのか、どうして俺たちを狙う!」
「だから言った、神に訊け、と」
うるさい蝿を追うようにラルフが腕をまわせば、癒えたばかりの傷がじわりと開く。
――‥‥京に籠もることの多かった彼等は、もしかすると、負傷の不利を真に悟っていなかったのかもしれない。
流刑地となるほどの僻地だ、周防大島は。蘇生を取り仕切る高僧なぞ臨むべくもなく、治癒をもたらす薬水にも不足する。まさに「死ねば、一巻の終わり」の地だ。そして、手傷で痛め付けられるのは自分の肉体のみではない。布陣、だ。たった三人の軍営にとっては、尚更で。――そう、たとえば、軍勢の常識をあげよう。負傷者は治療の手間がかかる故に、死者よりよっぽど負担が大きい。
三人が陥った状況は、それ、であった。一人の傷を癒やす間を稼ごうとして別の一人が前に出るたび、更なる深い傷を負う、悪循環。
時間稼ぎすら惜しいぐらい、時間、そしてなにより生命にも余裕はなかった。。この場を引く、と、見たのは正しいだろう。が、隙を突いて駆け抜ける、という決断は、それでも遅すぎるくらいだ。それは、隙ができるまでの待機を意味する、では隙ができなかったときは? そう、先程、笙が為損じたように。ラルフの行動が散じるまで、彼等が持ちこたえられるという理屈もない。
「あれ、ほんとうに人間ですか」
「‥‥訊いてみるか」
「遠慮します」
ようやく見出したほんのわずかのとき、を、安らぐために軽口に費やす。佳澄、かぶりをふって、笙に新しい薬水を手渡す。
笙は、別れて海を往った冒険者らに連絡を取りたいと考えた。が、今は、落ち着いた文章をしたためるどころか墨を擦るいとまもない。笙は悩んだ末、すでに千切れた被服のはしきれのみを結びつけて、彼の鷹・蒼穹を雲居に放り上げる。呆れるほど心静かな青みに点となってぱっと掠れる、猛禽。
ふ、と、吐血の消えた息を、笙は吐く。
ラルフを追えば五条の宮はそこにいるのだろうか、と、考えた。
だが、実際に追われているのは自分たちだ。質量的な圧倒の前に、彼等は段々となすすべを失う。
●死の二
ざん、ざん、と、樽がまたひとつ、ひとつ、波頭に白い泡を生んで溶けてゆく。鷹神紫由莉(eb0524)、船上、下、ところかまわず、目に付くはじから船荷を海面に投げ入れていた。多くは、酒。島で少々入手した柑橘に、これがいっとう彼女の心を掻き回す、茶葉。別に荷を守れ、という命を受けていないとはいえ、お気に入りの着物をみずからちぎってゆくようで惜しい。
「なんだか、もったいないねぇ」
思いは、皆、同じ。カヤ・ツヴァイナァーツ(eb0601)、そんな悠長な場合ではないと重々知りつつも、波の花となり欠片となって消える荷たちへ、最後の挨拶をたむけた。――とりあえず、海を眺めるかぎり、血は見ないですむ。今は、流されるものより、流すもののほうが多いから。
「海賊の狙いは、荷ではないか、と思われます。もしかすると、荷の方を回収を先にと考えるやもしれませんし」
「うん、僕もそう思うけど‥‥。樽、沈んでるよ」
今、取りに行くのは危ないし、僕ならあとでゆっくり拾いに行くけど。いっしゅんぴたりと動きを止めた紫由莉、名残惜しそうに、渦巻く海上を見やると、投げ入れを再度開始した。
「‥‥船も軽くしなければいけませんし。船足の確保が大切です」
「だね」
ツヴァイ、き、と、前方を見張って――いや、船の舳先を正面とするなら、彼の見据えたのはどちらかといえば左だろう。が、気持ちは前向きで、生の断崖に押し遣られそうな今すら、差し向かいになっている。が、実際の肉体までそうするには、彼はいろいろと難儀の多いハーフエルフだったので、現実は板を立てた物陰から、こっそり戦況を窺うのが関の山だったけど。
「矢掛けが多い‥‥じゃ、できるかな」
「弓矢を持ってくるんだったな」
アリアス・サーレク(ea2699)のぼやきは、もっともだ。海賊らの攻撃は、野戦の王道をいっていた。合間合間に、折を見て、船へ板を渡して乗り込んで来ようとする不埒な輩を、アリアス、シャスティフォルの神聖なる煌きで攻め返した。現在、冒険者等がまともに抗していられるのは、直の攻め寄せが本格的に開始されていないからだ。真っ向勝負、一対一では、断然、冒険者らの実力が海賊のそれを上回っている。が、相手はそれを越え、地の利をこころえて頭数をそろえている。要するに、時間がたてばたつほど、冒険者らの不自由は増す。
アリアスの左手から芽吹く、羽根のように軽い盾が、また新しい矢をはじいた。オーラエリベイションは燃え付く士気を血筋の隅々にまで流し込み、まるで消耗戦だ、と、考えた己の弱音を消し飛ばす。
――消耗など、冗談ではない。
生きて、帰るのだ。なんとしても。五条の宮の所在を確認する、と言う目的は果たした。だが、それだけが彼等の使命のすべてではない。この身を無事に持ち帰らなければ、報告だってままならない。生存こそが、たった今、果たすべき務めとなった。
紫由莉から借りた薬水を呑みきり、御神楽澄華(ea6526)は、ようやく人心地つく。紫由莉への礼もそこそこにアリアスの補助に向かう。傷は癒えたが、地虫でもたかったように、閉じられたばかりの皮膚がじくじくと疼いた。やはり消耗戦だ、と、澄華も考える。いっそ、こちらから向こうの船に飛び移ってやろうかと考えたが‥‥だが、海賊らは小型船を分散させて周囲を取り囲む、どれへ飛び移るべきかさっぱり見えてきやしない。いや、可能性の高いのは、おそらく主艦はここからいっとう遠い箇所にあるのだろう。
「このままでは‥‥」
ぎり、と、歯を食いしばる。先程と共通の苦みが、赤い舌をより赤くさせる。血の味。これ以上の不覚をとるわけにはいかない、と、焦慮と緊張が彼女の至る所をくべた。気持ちだけが車軸のない鐶のように空回りする――方法が見えてこない。と、ウィルマ・ハートマン(ea8545)、ふとかったるく首を上げ、海賊と接舷するのと逆の船縁に引き摺るように近付けば、ぼとり、と、墜落する。陸――浜辺の側へ。その、一本通った意思のない行動に、もしや手傷を負わされて混乱したか、と、狼狽して澄華は彼女を見下ろすが、着陸したウィルマは意外に平気な顔をしていた。
「船を出せ、これでは持たん」
「ウィルマ様は?」
「死ぬ気は、ない」
――‥‥答えに、なっていない。澄華が問いただそうとしたそのとき、出し抜けにアリアスの手元へ、飛礫のような、だがそれよりずっと正確な放物線が巻いて転げ込んできた――蒼穹。アリアス、面喰って、鳥の翼を返す。文はなかったが、脚を飾る上等な織物の加減には見覚えがあった。笙のものだ。
「なにかあったようだな」
「予想はしてたけどねぇ」
綽然とした声色とは裏腹に、ツヴァイ、ひどく重い顔になる。それと対称的なのが、ウィルマ。
「やはりな」
むしろ満足げに、ウィルマ、ひとしきり肯いた。
「別働隊には私が知らせる。最初に上陸した港の沖だ」
では後でな。うまく振り切れ。
そうしてニヤリとあくどい笑みを残せば、ウィルマ、承諾も受けぬうち、口笛なぞ吹きつつ、小気味好い足取りで山へ踏み入った。そのあとをボーダーコリーやまだ全然輪郭の整っていない埴輪が追いかけるのは、なかなか非現実的な風景だ。
「‥‥ウィルマさんの助言に従った方がよさそうですわね」
紫由莉、ほぅ、と、息をつく。重いものを運び続けて、肩が、痛い。しかし、それ以上にかかる負荷――彼等の状況は、籠城戦に似ていた。長引けば長引くだけ、内側に立てこもるもの現実の荷重を失ってゆく代わり、時間の負債を背負わされるのだ。紫由莉、一度、「この荷ばかりはさしあげますから」と、おさだまりの命乞いをやってみたのだが聞き入れられなかった。おそらくはそう命じられているのだろう、それを決断できる責任ある地位に就くものがそうそう前線に出てくるとは思えないのだし。そういえば、ツヴァイ、悪戯心に近い感情でファンタズムで周布政之介を作ってみたが、これもまったくの無反応――彼等が三下であると考えれば、それもまた当然だ。
思考を、切り替える。船は、死守したい。この船を失えば、彼等は京へ戻る手段をほとんど失うのだ。‥‥海賊にはきっと縄張り意識があるはずだ。離れよう、きっと巡り会えるはずだから。
「じゃ、いっくよー」
高速の詠唱。彼の資質によく馴染んだ地の精霊力が、温かな色彩を零して、ツヴァイの全身から引き出される。ローリンググラビティー。入道が分け入ったがごとく、豪胆で野太い水柱が、青い空に向かって手繰し込まれる。間髪おかず、ツヴァイはくるりと操舵手をふりかえった。
「ほら、とっとと行っちゃって!」
絶対に生きて帰るんだから――‥‥、
「鎖雷さん、生え際談義はまだ終わってないんだから。ここで『負け逃げ』したら、それこそ全禿決定だからねーーっ!」
●死の三
遂に、最後の薬が切れた。佳澄、数だけは備えてあると思ったんですけれども、と、切れ切れの声音で嘆く。
「‥‥数じゃない、ということですね」
笙が請け負う。――ラルフの行為に、理屈がないように。鎖雷は無言を貫いた。脈拍が規則的に鼓膜を打ちつける、目を閉ざして重低音に耳を澄ましていた。己の心臓をこんなに近く聞くのは、初めてだ――いや、ずいぶんと昔、こんなこともあったかもしれない。淫欲のはるか以前、胎動、胎内で聞いた――粘壁に包まれて、やさしく。
魂を賭け代にする闘争は、情炎めいて嫌いじゃない。――けれど、もう、いい。今は、ただ、母の胸に抱かれるがごとく手厚くされたかった。
「鎖雷さん!」
「‥‥眠い」
「しっかりしてください」
砂を蹴り上げてラルフをくらまそうという試みは、半ば、成功した。こうして、しばし身体を休められるぐらいには。だが、それに支払った体力は厖大、鎖雷を介抱しようとする笙ですら、時折強烈に襲い来る怠惰をはらいきれずにいる。そして、薬水は切れたのだ。怪我は彼等から迅速を取り払う。せっかく汲み出した距離が徐々に詰められる予感――いや、きっと、それは事実なのだろう――に佳澄は、喘ぐ。
「あぁ、めひひひひんの息子が見たかったなぁ。めひひひひんは?」
「無事ですよ、だから、鎖雷さん」
「死ぬつもりはねぇけど‥‥」
脚を、もう、動かすこともできない。頽れて滞留する彼等は、追い込まれておびえる鼠だった。
そこへ、がさり、と、草を分ける音。
二つは同時にあらわれた。
ラルフと――ウィルマ。
ウィルマの登場には、さすがにラルフも面喰ったようだ。柔らかいものへ突き刺すように、ラルフの裸出を、ウィルマの矢は易々と必中する。けれど、こんな幸運は長くは続かない。
「畳み掛けろ! 無理ならさっさと! 下がれ!」
だが、彼等はすぐには動けなかった。苛立ったウィルマが、血の混じった痰を吐く。
「死にたいなら、死ね。俺を巻き込むな」
そして、彼等は最後の、最期の、逃亡へ突入する。
●死を越えて
それからの道のりが平坦であった、とは、言い難い。死者のでないのが不思議なくらい、熾烈、の一言に尽きた。
しかし、彼等は辿り着いた。死者はなく、それにもっとも至近の刻印を全身にことごとく喰らいながら、しかし、彼等は港へ入った。ちょうどなにがしかの用事で港へ姿をあらわしていた鈴鹿に、
「申し訳ありません。宮の所在もしれず‥‥」
いるかもしれない、と、言われた場所がもぬけの殻であることを確かめただけ。
そこが本当に宮の所在地であったかどうかを確実に知ることはできなかったことが、澄華には大層悔しくてならない。動脈の分断より、元の繋がりのしれぬ骨折より、そっちのほうが重要だった。
「いや、充分だ。‥‥長州が口約束を守らなかった、それが分かれば、いい」
休め、と、当然のはなむけをかける。逆らうように、アリアス、それだけは尋ねずにはいられなかった。
「また、大戦になるのか?」
「‥‥いや、そんなことはさせない」
が、決意を語るには、鈴鹿の声色は自信の火もなく、弱々しすぎて、紫由莉は悟る。
起こるのだ。
物証はない。敢えて言うなら、星の巡り合わせ。炎の身動ぎ。そんな自然の一つ一つが、動乱の気配をただよわせている。そして、彼等を撫でる傷も、また。
「大したオチだ、全く」
血濡れのなかから、くすくすと、拗けた笑みをつくるウィルマ。
――それはまるで何かの象徴であった。或いは、未来という名の、暗黒に。