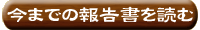【臥竜遊戯】−奥の細道−
【臥竜遊戯】−奥の細道−
 |
■キャンペーンシナリオ担当:津田茜 対応レベル:7〜13lv 難易度:難しい 成功報酬:18 G 69 C 参加人数:6人 サポート参加人数:-人 冒険期間:04月29日〜06月04日 リプレイ公開日:2006年05月07日 |
|
●オープニング
「其方の命、儂にくれ」いっそ悲愴を帯びて告げられた重い響きに、身体が震える。
遂に、この時が来た。
主君たる漢の活路を背負う。
武人として、これほどの僥倖はない。――心の芯から湧き立つような高揚と同時に、それほどまで追い詰められているのだという事実に愕然とした。
つい先日まで、鼎は磐石であると信じていたのに。
「地続きとはいえ、平泉は幾重にも山を隔てた北の最果て。それだけに奥も深く、侮れぬ。――彼の者どもの懐の裡。正直、儂にも測りがたい」
上州、そして、西国に不穏を抱えた今、北の黄金郷にて栄える大国は、江戸の行く末に無視できぬ翳を落とした。
白河以北――
百年の泰平と豊富な黄金がもたらす富に栄える北の大地は、古くから名馬の山地としても知られていた。厳しい冬に耐えて山地に根ざす我慢強く朴訥な民もまた、ひとたび武器を持てば屈強の兵士に代わる。
味方として助力を得ればいかにも心強いが、敵に回ればこれほど恐ろしいものもない。
「其方だけが頼り‥などと持ち上げられては、薄気味悪くも思うだろうが‥‥」
送り込んだ密偵は、悉くその消息を絶ったという。
何ひとつ確かな便りを持たずして知られざる地に向かうのは、徒手空拳で敵地に乗り込むのにも等しい。
生きて江戸に戻る事ができるかどうか、それさえ疑わしかった。
「‥‥忠隣‥」
あるいは、自らの身を切るような苦渋が洩れる。
低く嘆息とともに落とされたその声に、彼は深く額づいた。
■□
春風が巻き起こした桜色の珍騒動もどうにかこうにかひと息ついて。
祭の余韻にも似たどこか気だるい倦怠に浸る《ぎるど》の奥座敷にて、訪れた嵐の予感はまったりと茶をすすりつつ空を仰いだ。
「‥‥北緯の桜もまた見事であるそうな」
見てみたいとは思われませぬか?
おっとりと水を向けられて、座に招かれた口入係は返答に窮する。――興味がないとは言わないけれど。
うっかり同意などした日には、果たして何を言われる事やら。
何故か場に同席する幡髄院をちらりと横目に伺う手代の様子に、老いた男はくつくつと笑みをこぼした。
「申し送れました。我輩は気の向くまま旅に遊んで連歌などを嗜む楽隠居にございます‥‥世間では蕉翁などと呼んでくれる者もおりますが」
何処かで聞いた響きであるような、ないような。
考え込む風に首を捻った口入係に、蕉翁と名乗った老爺は細かいシワが刻まれた目尻に愛想の良い笑みを浮かべて言を繋げる。
「こちらは弟子の‥‥曽良‥と、申す不得手者‥」
手代の視線に固い会釈を返した漢は、どう見ても《曽良》なんて可愛らしい町人者には見えない。ピンと伸びた背筋など、どう見ても武芸者のそれだ。
手代の表情に不審を見て取ったのだろう。
老爺はそれ以上の言及を避けるかのように、話題を変じた。
「このご時勢に暢気者よと謗られましょうが‥‥」
そう、ひとつ前置いて。
蕉翁はおもむろに核心を切り出した。
■□
「‥‥陸奥−みちのく−の桜、ねぇ‥」
張り出された依頼を前に、冒険者は腕を組む。
目指すは黄金の理想郷−平泉−最果ての地に百年の泰平を築いた奥州藤原氏の都だ。
さしずめ江戸近郊の名所では物足りなくなったのか。――物好きなのか、熱心なのか。なるほど、花追人とはよく言った。
しきりに関心する男の様子に、同じように依頼を眺めていた若い娘は小馬鹿にしたように鼻を鳴らす。
「そんなの建前に決まってるじゃないの」
馬鹿ね、と。
さらりと投げ出された侮蔑にムッとするものを感じて身体ごと向き直った男に負けじと、娘は傲然と顎をあげた。挑むような強い光が、黒い瞳の中で不敵に揺れる。
「いい? 上州に続いて西国とも雲行きが怪しくなった今、奥州との関係までおかしくなったら、いかに源徳様でもさすがにちょっと荷が勝ちすぎるわ」
派兵など表立っての助力を得るのはムリだとしても。
友好的な関係だけは、維持しておきたい。――と、いうのが、千代田の城にて政をなす者の偽らざる本音だろう。
本来ならば使者を立てて表敬するのが道理だが‥‥
話が公になれば、予断を許さぬ緊張状態の続く上州との関係はますます悪化するのは確実だ。
表向きは平静を装ったまま、奥州との関係強化を取り結ぶには――。
「つまり、密使を立てるってコトか‥」
漂泊の文人として広く知られる蕉翁の名があれば、白河の関を越えても怪しまれる事はない。
北緯の桜――
いかにも、識者を気取る風流人の耳には美しく響く。
とは言うものの、奥州路は幾重にも連なる険しい難所。
仰々しい供を付ければ、カラクリに気づかれる。――さりとて、少人数では心許ない。勘働きの良いモノはどこにでもいるのだ。
奥州に向けて放った隠密が、誰一人、帰還しないという噂も、まことしやかに囁かれているあたり、彼の国はやはり幾重にも引かれた帳の奥にある。
「源徳家との縁(ゆかり)が薄く、臨機応変の融通が効く上に、少人数での護衛や旅を得意とする者‥‥」
つまり、《冒険者》の出番というワケだ。
●今回の参加者
ea1170 陸 潤信(34歳・♂・武道家・人間・華仙教大国)ea3988 木賊 真崎(37歳・♂・志士・人間・ジャパン)
ea6388 野乃宮 霞月(38歳・♂・僧侶・人間・ジャパン)
ea6769 叶 朔夜(28歳・♂・忍者・人間・ジャパン)
ea7179 鑪 純直(25歳・♂・志士・人間・ジャパン)
ea7209 ロゼッタ・デ・ヴェルザーヌ(19歳・♀・ウィザード・エルフ・イスパニア王国)
●リプレイ本文
白河以北――《奥州》、あるいは、《陸奥−みちのく−》と。
京の都より見渡したその距離の遠さゆえ軽視されがちなその地域は、ジャパンのおよそ三分の一を占めようかという広大な国である。
無論、その内に仙台藩や南部藩、霊山城といったいくつもの国や城が存在し、其々の領主が治めているのだが、その内実についてはほとんど知らされていなかった。
――(京の)都を掌中に収めた者が天下に号する支配者たる。――
その認識が諸侯の目を奥州より遠ざけ、人々の関心もまた薄い。
俗に、奥州十七万騎。
源徳・平織・豊藤の三巨頭に単独で対抗し得る力を有する唯一の勢力だと囁かれて尚、そこに危機感を抱いた者は少数だった。――それほどまでに、白河の関を間に挟んで対峙する国に寄せる人の心は乖離している。
●白河の関
思えば、《道》とは不思議なものだ。
陸潤信(ea1170)は、いくらか遠のいた木造の関所を振り返って思う。
隣り合う国の事情がどうであれ、突然、途切れたりはしない。――武装した兵士が護る巨大な関所の向こうから姿を現したのは、連綿と伸びる変哲もない街道だった。
得体の知れぬ未開の奥地へ踏み込むような覚悟を要求しておいて‥‥。
無論、何も見当たらぬから安全というわけではないのだけれど。
「この辺りで少し休みましょう」
セブンリーグブーツを履いてはいても男の足に合わせればいくらか遅れがちになるロゼッタ・デ・ヴェルザーヌ(ea7209)とそれを気遣う鑪純直(ea7179)にはんなりと視線を投げて、蕉翁はおおどかな笑みを浮かべた。
荷を降ろした師弟に倣って、叶朔夜(ea6769)も些か安堵を浮かべて背負った荷を降ろす。木賊真崎(ea3988)と野乃宮霞月(ea6388)のふたりも、其々、荷を引く馬の轡を弛め、草を食ませた。
早朝に湯本の宿を発ってから、歩き通して半日余り。――いかに古来より文人たちの雅趣を誘う《白河の関》を目前に逸る気持ちを抑えられないといっても、大した健脚。とても、還暦を過ぎた老人のそれとは思えない。
顔合わせの折、握手を求めるふりをしてそれとなく武門の出自であることを確かめた曽良だけでなく、蕉翁自身もひとかどならぬ心得がありそうだ。
花を追い、風雅に浸る旅にしてはずいぶん性急なのも気に掛かる。
「ここが白河か‥」
異郷の旅人である陸やロゼッタにとっては、坂東と陸奥を隔てる国境のひとつくらいの認識にすぎないけれど。
多少なりと文壇に心得がある者ならば、無関心ではいられぬ場所だ。
密偵の目を欺くために馬廻りの風体に身をやつした鑪も、その《白河》を越えた感慨に思考をひねる。
ちょうど花の盛りに行き合わせたのか、可憐な花を揺らせる街道脇に茂った卯の花に目を細め、鑪は自らの詩心を省みる。沫雪を思わせる白い花は、ところどころ残った雪と相まっていっそう白く、ともすれば雪の季節に戻ったかのような錯覚に陥りそうだ。
「‥‥む。いざとなるとなかなか思いつかぬものだな‥」
眉間にシワを刻んだ鑪の吐息を引き継いで、叶は蕉翁の隣で汗を拭う曽良にちらりと思わせぶりな視線を向けた。
「蕉翁殿の弟子というのなら曽良殿も、それなりの詠み手なのだろう?――是非、一句。お手並み拝見とはいかないだろうか?」
「や、某は‥‥」
固辞する姿勢を見せた漢は、叶と、他の者たちの視線に諦めたように吐息を落とす。
「‥‥むかし、竹田大夫国行がこの関を越える折、能因法師の歌に敬意を表して冠をかぶり直し、衣服をと整えたというが‥‥」
――卯の花をかざしに関の晴着かな 曽良い
「我らには身を改める用意はないが、せめて卯の花を髪に飾って関を通るとしよう‥か、‥‥なるほど‥」
何度か口の中で復唱し歌意を噛み砕いた野乃宮の傍らで、ロゼッタはいつでも使えるようにとゆるく封を切っていた《アースダイブ》の経文をしっかりと巻きなおす。
「関所を破るのに必要かと思っていましたけど、あっさり通していただけましたね」
数日前に陸が訪れた時と事情は同じ。
国境に近い辺境は江戸から流れてきたと思われる難民たちの姿があった。――横行する国抜けに神経を尖らせている関所の代官を欺くために思いついたのが《関所破り》では、火に油を注ぐような気もするが‥。
「‥‥でも、あの通行証には何が書いてあったのかしら?」
蕉翁が差し出した手形とその裏書に目を通した途端、関守たちの態度が豹変したのだ。
「おかげで荷を調べられるコトもなかったし」
隠した忍者刀を背嚢から引っ張り出して、叶も訝しげに首をかしげる。何事もなかったのだから良しとするべきなのだろうけど――
「やはり、何かあると見るべきですね」
●放たれた矢
急変したのは、白河を越えた夜のコトだった。
抑えが揺らいでいるとはいえ白河以南は源徳家の威光が届く。――まるで、彼らが関を越えるのを待ち構えていたように。
「起きろ。囲まれた」
低く押し殺した尖った声に、唐突に眠りより引き上げられる。旅の疲れが溜まっていたのか野宿にも関わらず、深いところへ沈みこんでいたらしい。 パチパチとはぜる焚き火の音が、やけに大きく耳に響く。
「敵って‥」
「‥‥しぃ‥」
問い返したロゼッタは、決して寝ぼけていたわけではない。それでも、囲まれたというこの状態を俄かに信じることができなかったのだ。
尾行の対策に《アッシュエージェンシー》などの魔法で足跡をカモフラージュしてきたし、斥侯の技術に長けた叶と陸のふたりが常に周囲を警戒している。
にも、かかわらず――。
それだけで、敵がいかに手錬であるかが窺い知れた。焚き火に照られた蕉翁の顔にも、緊張の色が隠せない。
「‥‥さて、いかがしたものか‥」
問われた先には弟子であるはずの漢。
もう少し背を丸めるといい、など。木賊に町人らしく見せる術など口添えされていた漢は、今は、完全に侍の顔をしていた。
「戦場ならば、退けと言いたいところですが。‥‥大役を任された身。逃げ帰るワケにも参りません」
「大任?」
ただの花見ではないことは、陸だけでなく、皆が薄々感づいている。
では、彼が背負っているものは何なのか。――聞きたいことは山ほどあったが、今はそれを論じている場合ではない。
短い逡巡の末、陸は重く沈黙する闇を睨んだ。
「討って出よう」
元々、それほど気の長い性質ではない。金属拳をはめた手をぐっと握り締めた陸に、野野宮は僅かに懸念をうかべた。
「しかし、囲まれているのだぞ?」
僧侶である野乃宮と、ウィザードのロゼッタは基本的に接近戦を得手としない。
「‥‥だが、このままではジリ貧だ。撃退するのが難しい以上、突破して体勢を立て直すしかない」
木賊の言葉に叶と鑪のふたりも頷いて、得物に手をかける。
刹那、
―――ヒュン‥ッ
夜を引き裂いて飛来した矢が、赫々と燃え盛る焚き火に突き刺さり、パッと鮮やかな火の粉を散らした。
「来るぞ!!」
白くきらめく刃物をかざして飛び込んできた影を金属拳で受け止めて、陸が叫ぶ。金属同士のすれあう骨に滲みる衝撃が拳から腕へと広がった。
始まった剣戟に驚いて立ちすくむ馬の鞍へロゼッタの華奢な体躯を押し上げ、鑪は手にした日本刀の柄で馬の腹を突く。
「しっかり掴まっておられよ! ――走れっ!!」
「きゃあっ?!!」
叫びにも似た嘶きがロゼッタの悲鳴に重なって夜を震わせた。狂ったように駆け出した馬の蹄に蹴散らされ、包囲の一端が崩れる。
生まれた混乱に乗じて飛び出した曽良を名乗る漢の白刃が一閃し、暗がりになお黒々とした飛沫を飛ばした。
その豪快な太刀筋は、やはり鍛錬を怠らぬ侍のもので‥‥
「捕縛よりも足を止め、退くことを考えられよ」
その端的な指示と判断力にも、
人の上に立ち、令を出す事に慣れた者特有の有無を言わせぬ力があった。
●遣北使
大久保忠親――
明かされた名に冒険者たちは顔を見合わせる。
追跡者の包囲を突破し、夜を徹して駆けた疲れも吹き飛ぶほどの衝撃が、その名前に秘められていた。
只者ではないと思っていたけど。
「‥‥源徳家の譜代の家臣がなんで‥って、聞くまでもないか」
頭を抱えてその場にへたり込んだ叶の呟きに、皆、其々の表情でその胸の裡を表す。
上州上杉家が起こした争乱に加え、平織虎長暗殺への関与を疑われるなど。源徳家を取り巻く情勢は、悪くなる一方だった。
「上州攻めを控え、平織との確執が表面化した今、戦さの懸念も懸念では済まされぬ――」
そう言って、大久保は血泥に汚れた固い表情に沈痛な色を浮かべる。
追い詰められた源徳にとって唯一残った絆が、奥州との同盟関係なのだ。《平泉》へ出向いて陸奥の守と会談し、友好関係を確認した上‥‥可能であれば上州攻めへの協力を取り付ける。
それが、この旅に課せられた本当の使命であった。
「では、さっきの連中は‥‥」
誰にともなく落とされた叶の呟きに、彼らはただ小さく首肯する。
上州の密偵か、
争乱を持ち込まれることを厭う輩が動いているのか、
あるいは、他に――
「それにしても、思ったより早うございましたな」
そして、強い。
蕉翁の言葉がいっそう重く、場に沈んだ。
「それで、コレからどうするつもりだ?」
平泉へ向かうのは、違えられないとしても。
このままでは、早晩、先刻の連中の餌食となってしまうだろう。役目をまっとうできないどころか、命さえ危うい。
野乃宮の問いに、大久保は蕉翁と視線を交わした。――すでに、いくつかの対策は立てていたのだろう。
「拙者と蕉翁殿はこのまま、漂泊を装う旅を続ける」
「まさか帰れと仰るわけではありませんよね?」
ここまできて。
ロゼッタの強い語気に、大久保は少し驚いたように瞠目した。それはロゼッタだけの言葉ではなく‥‥冒険者たちの眸に宿る不羈の光に、彼はかすかに口元をほころばせる。
「いや。貴殿たちには《遣北使》として平泉へ赴き、源徳公の名代として陸奥の守との会談に臨んでいただきたい。――むろん、可能な限り我々も平泉を目指すが‥」
万が一の場合は、その大役を果たして欲しい。
「‥‥そんな‥っ?!」
陸の反駁を視線で封じ、大久保は背負った荷より奥州の絵図と書状を取り出した。
「直接、平泉へ向かうのはやはり危険だと思われる」
白河と書きこまれた場所を指した指が、線をなぞる様にすべり少しはなれた地点を指差す。
「霊山城。奥州将軍・北畠顕家公。――武家ではなく公卿の一門である北畠殿は、奥州在来の武将とはそのあり方‥‥性格を異にしていると聞く」
あるいは‥、と。
絵図をなぞる指は、さらに北を指し示した。
「青葉城。仙台藩主・伊達政宗殿。皆もご存知のとおり、奥州の独眼竜と名を馳せるお方だ」
陸奥公の麾下にあって強い発言力を有する武将の助け得ることができれば、会談を阻止しようと企む輩も迂闊には手が出せまい。
「‥‥し、かし‥」
それでも言葉を濁した木賊の手に、大久保は絵図と一緒に取り出した書状を握らせる。
「源徳公、直筆の奥州公に宛てた書状だ。これを示せば無下に扱われる事はない。――もちろん、出す相手を間違えなければの話だが‥」
地侍や、農民にとってはただの書状に過ぎないが、地位ある者には無視できぬ対面というものがあるのだ。
「そなたたちの働きに、源徳――いや、江戸の命運が掛かっているのだ。どうか‥‥」
このとおりだ、と。
源徳家の直参を勤める侍に頭を下げられ、嫌だと言えるだろうか。
いや、それよりも‥‥江戸に戻る道中もまた、同じ危険が待っているのだ。
行くも帰るも同じ事なら、腹を括るしか道はない。