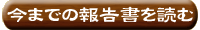【臥竜遊戯】−奥の細道−
【臥竜遊戯】−奥の細道−
 |
■キャンペーンシナリオ担当:津田茜 対応レベル:7〜13lv 難易度:難しい 成功報酬:18 G 69 C 参加人数:6人 サポート参加人数:-人 冒険期間:05月13日〜06月18日 リプレイ公開日:2006年05月21日 |
|
●オープニング(第1話リプレイ)
白河以北――《奥州》、あるいは、《陸奥−みちのく−》と。
京の都より見渡したその距離の遠さゆえ軽視されがちなその地域は、ジャパンのおよそ三分の一を占めようかという広大な国である。
無論、その内に仙台藩や南部藩、霊山城といったいくつもの国や城が存在し、其々の領主が治めているのだが、その内実についてはほとんど知らされていなかった。
――(京の)都を掌中に収めた者が天下に号する支配者たる。――
その認識が諸侯の目を奥州より遠ざけ、人々の関心もまた薄い。
俗に、奥州十七万騎。
源徳・平織・豊藤の三巨頭に単独で対抗し得る力を有する唯一の勢力だと囁かれて尚、そこに危機感を抱いた者は少数だった。――それほどまでに、白河の関を間に挟んで対峙する国に寄せる人の心は乖離している。
●白河の関
思えば、《道》とは不思議なものだ。
陸潤信(ea1170)は、いくらか遠のいた木造の関所を振り返って思う。
隣り合う国の事情がどうであれ、突然、途切れたりはしない。――武装した兵士が護る巨大な関所の向こうから姿を現したのは、連綿と伸びる変哲もない街道だった。
得体の知れぬ未開の奥地へ踏み込むような覚悟を要求しておいて‥‥。
無論、何も見当たらぬから安全というわけではないのだけれど。
「この辺りで少し休みましょう」
セブンリーグブーツを履いてはいても男の足に合わせればいくらか遅れがちになるロゼッタ・デ・ヴェルザーヌ(ea7209)とそれを気遣う鑪純直(ea7179)にはんなりと視線を投げて、蕉翁はおおどかな笑みを浮かべた。
荷を降ろした師弟に倣って、叶朔夜(ea6769)も些か安堵を浮かべて背負った荷を降ろす。木賊真崎(ea3988)と野乃宮霞月(ea6388)のふたりも、其々、荷を引く馬の轡を弛め、草を食ませた。
早朝に湯本の宿を発ってから、歩き通して半日余り。――いかに古来より文人たちの雅趣を誘う《白河の関》を目前に逸る気持ちを抑えられないといっても、大した健脚。とても、還暦を過ぎた老人のそれとは思えない。
顔合わせの折、握手を求めるふりをしてそれとなく武門の出自であることを確かめた曽良だけでなく、蕉翁自身もひとかどならぬ心得がありそうだ。
花を追い、風雅に浸る旅にしてはずいぶん性急なのも気に掛かる。
「ここが白河か‥」
異郷の旅人である陸やロゼッタにとっては、坂東と陸奥を隔てる国境のひとつくらいの認識にすぎないけれど。
多少なりと文壇に心得がある者ならば、無関心ではいられぬ場所だ。
密偵の目を欺くために馬廻りの風体に身をやつした鑪も、その《白河》を越えた感慨に思考をひねる。
ちょうど花の盛りに行き合わせたのか、可憐な花を揺らせる街道脇に茂った卯の花に目を細め、鑪は自らの詩心を省みる。沫雪を思わせる白い花は、ところどころ残った雪と相まっていっそう白く、ともすれば雪の季節に戻ったかのような錯覚に陥りそうだ。
「‥‥む。いざとなるとなかなか思いつかぬものだな‥」
眉間にシワを刻んだ鑪の吐息を引き継いで、叶は蕉翁の隣で汗を拭う曽良にちらりと思わせぶりな視線を向けた。
「蕉翁殿の弟子というのなら曽良殿も、それなりの詠み手なのだろう?――是非、一句。お手並み拝見とはいかないだろうか?」
「や、某は‥‥」
固辞する姿勢を見せた漢は、叶と、他の者たちの視線に諦めたように吐息を落とす。
「‥‥むかし、竹田大夫国行がこの関を越える折、能因法師の歌に敬意を表して冠をかぶり直し、衣服をと整えたというが‥‥」
――卯の花をかざしに関の晴着かな 曽良い
「我らには身を改める用意はないが、せめて卯の花を髪に飾って関を通るとしよう‥か、‥‥なるほど‥」
何度か口の中で復唱し歌意を噛み砕いた野乃宮の傍らで、ロゼッタはいつでも使えるようにとゆるく封を切っていた《アースダイブ》の経文をしっかりと巻きなおす。
「関所を破るのに必要かと思っていましたけど、あっさり通していただけましたね」
数日前に陸が訪れた時と事情は同じ。
国境に近い辺境は江戸から流れてきたと思われる難民たちの姿があった。――横行する国抜けに神経を尖らせている関所の代官を欺くために思いついたのが《関所破り》では、火に油を注ぐような気もするが‥。
「‥‥でも、あの通行証には何が書いてあったのかしら?」
蕉翁が差し出した手形とその裏書に目を通した途端、関守たちの態度が豹変したのだ。
「おかげで荷を調べられるコトもなかったし」
隠した忍者刀を背嚢から引っ張り出して、叶も訝しげに首をかしげる。何事もなかったのだから良しとするべきなのだろうけど――
「やはり、何かあると見るべきですね」
●放たれた矢
急変したのは、白河を越えた夜のコトだった。
抑えが揺らいでいるとはいえ白河以南は源徳家の威光が届く。――まるで、彼らが関を越えるのを待ち構えていたように。
「起きろ。囲まれた」
低く押し殺した尖った声に、唐突に眠りより引き上げられる。旅の疲れが溜まっていたのか野宿にも関わらず、深いところへ沈みこんでいたらしい。 パチパチとはぜる焚き火の音が、やけに大きく耳に響く。
「敵って‥」
「‥‥しぃ‥」
問い返したロゼッタは、決して寝ぼけていたわけではない。それでも、囲まれたというこの状態を俄かに信じることができなかったのだ。
尾行の対策に《アッシュエージェンシー》などの魔法で足跡をカモフラージュしてきたし、斥侯の技術に長けた叶と陸のふたりが常に周囲を警戒している。
にも、かかわらず――。
それだけで、敵がいかに手錬であるかが窺い知れた。焚き火に照られた蕉翁の顔にも、緊張の色が隠せない。
「‥‥さて、いかがしたものか‥」
問われた先には弟子であるはずの漢。
もう少し背を丸めるといい、など。木賊に町人らしく見せる術など口添えされていた漢は、今は、完全に侍の顔をしていた。
「戦場ならば、退けと言いたいところですが。‥‥大役を任された身。逃げ帰るワケにも参りません」
「大任?」
ただの花見ではないことは、陸だけでなく、皆が薄々感づいている。
では、彼が背負っているものは何なのか。――聞きたいことは山ほどあったが、今はそれを論じている場合ではない。
短い逡巡の末、陸は重く沈黙する闇を睨んだ。
「討って出よう」
元々、それほど気の長い性質ではない。金属拳をはめた手をぐっと握り締めた陸に、野野宮は僅かに懸念をうかべた。
「しかし、囲まれているのだぞ?」
僧侶である野乃宮と、ウィザードのロゼッタは基本的に接近戦を得手としない。
「‥‥だが、このままではジリ貧だ。撃退するのが難しい以上、突破して体勢を立て直すしかない」
木賊の言葉に叶と鑪のふたりも頷いて、得物に手をかける。
刹那、
―――ヒュン‥ッ
夜を引き裂いて飛来した矢が、赫々と燃え盛る焚き火に突き刺さり、パッと鮮やかな火の粉を散らした。
「来るぞ!!」
白くきらめく刃物をかざして飛び込んできた影を金属拳で受け止めて、陸が叫ぶ。金属同士のすれあう骨に滲みる衝撃が拳から腕へと広がった。
始まった剣戟に驚いて立ちすくむ馬の鞍へロゼッタの華奢な体躯を押し上げ、鑪は手にした日本刀の柄で馬の腹を突く。
「しっかり掴まっておられよ! ――走れっ!!」
「きゃあっ?!!」
叫びにも似た嘶きがロゼッタの悲鳴に重なって夜を震わせた。狂ったように駆け出した馬の蹄に蹴散らされ、包囲の一端が崩れる。
生まれた混乱に乗じて飛び出した曽良を名乗る漢の白刃が一閃し、暗がりになお黒々とした飛沫を飛ばした。
その豪快な太刀筋は、やはり鍛錬を怠らぬ侍のもので‥‥
「捕縛よりも足を止め、退くことを考えられよ」
その端的な指示と判断力にも、
人の上に立ち、令を出す事に慣れた者特有の有無を言わせぬ力があった。
●遣北使
大久保忠親――
明かされた名に冒険者たちは顔を見合わせる。
追跡者の包囲を突破し、夜を徹して駆けた疲れも吹き飛ぶほどの衝撃が、その名前に秘められていた。
只者ではないと思っていたけど。
「‥‥源徳家の譜代の家臣がなんで‥って、聞くまでもないか」
頭を抱えてその場にへたり込んだ叶の呟きに、皆、其々の表情でその胸の裡を表す。
上州上杉家が起こした争乱に加え、平織虎長暗殺への関与を疑われるなど。源徳家を取り巻く情勢は、悪くなる一方だった。
「上州攻めを控え、平織との確執が表面化した今、戦さの懸念も懸念では済まされぬ――」
そう言って、大久保は血泥に汚れた固い表情に沈痛な色を浮かべる。
追い詰められた源徳にとって唯一残った絆が、奥州との同盟関係なのだ。《平泉》へ出向いて陸奥の守と会談し、友好関係を確認した上‥‥可能であれば上州攻めへの協力を取り付ける。
それが、この旅に課せられた本当の使命であった。
「では、さっきの連中は‥‥」
誰にともなく落とされた叶の呟きに、彼らはただ小さく首肯する。
上州の密偵か、
争乱を持ち込まれることを厭う輩が動いているのか、
あるいは、他に――
「それにしても、思ったより早うございましたな」
そして、強い。
蕉翁の言葉がいっそう重く、場に沈んだ。
「それで、コレからどうするつもりだ?」
平泉へ向かうのは、違えられないとしても。
このままでは、早晩、先刻の連中の餌食となってしまうだろう。役目をまっとうできないどころか、命さえ危うい。
野乃宮の問いに、大久保は蕉翁と視線を交わした。――すでに、いくつかの対策は立てていたのだろう。
「拙者と蕉翁殿はこのまま、漂泊を装う旅を続ける」
「まさか帰れと仰るわけではありませんよね?」
ここまできて。
ロゼッタの強い語気に、大久保は少し驚いたように瞠目した。それはロゼッタだけの言葉ではなく‥‥冒険者たちの眸に宿る不羈の光に、彼はかすかに口元をほころばせる。
「いや。貴殿たちには《遣北使》として平泉へ赴き、源徳公の名代として陸奥の守との会談に臨んでいただきたい。――むろん、可能な限り我々も平泉を目指すが‥」
万が一の場合は、その大役を果たして欲しい。
「‥‥そんな‥っ?!」
陸の反駁を視線で封じ、大久保は背負った荷より奥州の絵図と書状を取り出した。
「直接、平泉へ向かうのはやはり危険だと思われる」
白河と書きこまれた場所を指した指が、線をなぞる様にすべり少しはなれた地点を指差す。
「霊山城。奥州将軍・北畠顕家公。――武家ではなく公卿の一門である北畠殿は、奥州在来の武将とはそのあり方‥‥性格を異にしていると聞く」
あるいは‥、と。
絵図をなぞる指は、さらに北を指し示した。
「青葉城。仙台藩主・伊達政宗殿。皆もご存知のとおり、奥州の独眼竜と名を馳せるお方だ」
陸奥公の麾下にあって強い発言力を有する武将の助け得ることができれば、会談を阻止しようと企む輩も迂闊には手が出せまい。
「‥‥し、かし‥」
それでも言葉を濁した木賊の手に、大久保は絵図と一緒に取り出した書状を握らせる。
「源徳公、直筆の奥州公に宛てた書状だ。これを示せば無下に扱われる事はない。――もちろん、出す相手を間違えなければの話だが‥」
地侍や、農民にとってはただの書状に過ぎないが、地位ある者には無視できぬ対面というものがあるのだ。
「そなたたちの働きに、源徳――いや、江戸の命運が掛かっているのだ。どうか‥‥」
このとおりだ、と。
源徳家の直参を勤める侍に頭を下げられ、嫌だと言えるだろうか。
いや、それよりも‥‥江戸に戻る道中もまた、同じ危険が待っているのだ。
行くも帰るも同じ事なら、腹を括るしか道はない。
●今回の参加者
ea1170 陸 潤信(34歳・♂・武道家・人間・華仙教大国)ea3988 木賊 真崎(37歳・♂・志士・人間・ジャパン)
ea6388 野乃宮 霞月(38歳・♂・僧侶・人間・ジャパン)
ea6769 叶 朔夜(28歳・♂・忍者・人間・ジャパン)
ea7179 鑪 純直(25歳・♂・志士・人間・ジャパン)
ea7209 ロゼッタ・デ・ヴェルザーヌ(19歳・♀・ウィザード・エルフ・イスパニア王国)
●リプレイ本文
風が騒ぐ。白く連なる峰を越えて吹き颪す大気のうねりは萌え始めた緑を揺るがし、雪下の眠りより醒めて間もない沃野を突き抜けて海へと奔る。
時に、人の営みをも薙ぎ倒す形なき力は、緩やかなる泰平を覆さんと波立つ時勢の気運にもどこか似て‥‥。
「申し上げます」
地の底、陽の射さぬ陰より湧いて出た声に、急勾配の頂に建つ山城にて緑立つ平地を睨下する男は、わずかに顎を引くことで沈黙をもって先を促した。
「彼の者等、矢吹より二手に分かれ、尚、行脚を続ける模様」
帰郷を促す恫喝程度の襲撃では、退かぬ。
並々ならぬ豪の者が揃っているのか、あるいは、退くわけにはいかぬ理由があるのか。いっそ愚かしいまでの直向さが、北を‥‥平泉を目指す彼らの真意を垣間見せてしまうのだけれど。
「蕉翁師弟は、物見遊山の外聞を崩さぬ腹か――」
先を急ぐ風もなく、名所、史跡にて足を止め、逗留先の心得者の求めに応じて句を披露することもあるという。
永らくの安定は、そこに生きる人の心にも余裕をもたらし、
天下にその名を知られる俳聖の名は、その後背を拝む者たちの姿を借りて襲撃者よりの盾となった。
「‥‥殊更、名を挙げて見せるのも、策のひとつやも‥」
隠し切れぬ名ならば、いっそ――
高名を囮として、本命を生かす。
あるいは、さらにその裏をかき泰然を装っているのかもしれない。
途上で道を分けた随行者たちにも、人目を忍ぶ風はないという。――むしろ、日のある内は街道にて距離を稼ぎ、夜は野営を避けて宿に泊まるという旅慣れた様子で追撃の手を鈍らせていた。
「昼間の街道筋といえば、無論、人目もございます。‥‥彼の者たちも攻めあぐねている模様」
孤立無援の敵地といっても過言ではない土地ではあったが、そこに暮らす者の全てが敵ではない。
揺るぎない泰平を信じて日を送る働き者で善良な農民が殆どである。――平和だとされるこの地では、野盗、山賊の凶行を装うには限界があった。
「なるほど。堪えきれば彼奴等の勝ちということか。‥‥だが‥」
平泉へは、まだまだ遠い。
思案にも似た太い笑みを口元に刻んだ漢に、声は淡々とその観測を摘み取る。
「いえ。直接、平泉を目指すのではなく、霊山城へ――」
「ほぉ。霊山‥!」
は、と。
思わず吐き出された笑声には、心底、愉快そうな色が宿った。
芽吹いたばかりのやわらかな青葉に飾られた城下に今いちど視線を投げて、漢は勢い良く踵を返す。
「馬を引け! 平泉へ参じる!!」
●霊山城
天を突き刺して聳える断崖の奇岩怪石をぽかんと見上げ、ロゼッタ・デ・ヴェルザーヌ(ea7209)は言葉を失くす。
「‥‥あれが、霊山‥?」
どこか神秘的な匂いのする文字を当てる地だと思っていたのだけれど。
おそろしく険阻な岩山は、城というより要塞といった趣が強いかもしれない。――攻めるための拠ではなく、守るための城だ。
「まさに絶景、だな‥」
地上からほぼ垂直に立ち上がる黒い火山岩の岩壁を彩る淡い緑に、野乃宮霞月(ea6388)も吐息を落とした。決して平坦ではない道を文字通り切り開いてきた目には、どこか拒絶されているような心細さも確かにあって――
ひとまずの目的地を目の前にした安堵と、先行きの不穏がない混ぜになって胸に飛来する。
大任を背負ったことで、先を急く心とは裏腹に。追っ手の目を逸らせるために道を分った蕉翁と大久保の負担を減らす為に、こちらも漂泊を装い、物見遊山の旅を演じる。
寺があれば立ち寄り、町を覗いて奥州の世情をうかがい。
隙を見せれば牙を剥こうと付きまとう追撃者の影にも、絶えず気を張って‥‥
江戸を発った時より、尋常な旅ではないと予想はできた。
だが、その覚悟を遥かに上回る極限の不穏と緊張が積み上げていく疲労は、思った以上に体力と精神力と削り取っていく。
そして、ようやく辿りついたその城は――彼らが目指す壮大なる結末へと続く第1の扉でしかなかったけれど――確かに未来へ繋がる扉であるように思われた。
縫い込んだ書状の存在を頼り、無意識に着物の襟に手をやった木賊真崎(ea3988)も託された使命の重さに強く奥歯を噛み締める。
江戸の総命を活かすも殺すも、
この書状‥‥引いては彼らの挙動に全てが掛かっている。
ともすれば、深く沈みがちになる思考を断ち切ったのは、明瞭な犬の鳴き声だった。
これまでの旅で何度も彼らに危険を報せ、勇気を与えてくれたその声も、今はどこか嬉しげで。
顔を上げれば、陸潤信(ea1170)と叶朔夜(ea6769)
のふたりがちょうど斥侯より戻ってくるのが目に入る。その顔色にも、精彩が戻ったようだ。
「急げば今日中に霊山に入れそうだ」
「道は?」
鑪純直(ea7179)の問いにも先の見えた明るさが籠もる。
「聞いてきた。霊山城に入る道は幾つかあるが、馬が通れるのは1ヶ所だけだそうだ」
「そこが正念場か‥」
馬を連れている以上、その道を通るしかない。
馬廻りの身には分不相応にも見える《霞刀》を強く握り締めた鑪に、叶は思慮深げに首をかしげた。
「霊山城下は、もう北畠公の直轄だ。――奥州将軍の膝元で、騒ぎを起こすとは考えにくい気もするが」
それもそうだ、と。
ちらりと笑い、ふと思いついて鑪は自らの姿を検める。
「北畠公と対面する前に、衣を改めることはできるだろうか?」
北畠氏といえば、神皇家を祖とする公家の名門。
さすがに馬廻りの形のままでの対面は、失礼かもしれない。――仮に、そういった体面にこだわらぬ人であっても、鑪にだってそれなりに見栄というものがあるのだ。
●北の公達
ずいぶん華やかな経歴の持ち主であると思う。
あるいは、貴族というのは大概にしてそういうものなのだろうか。
ロゼッタと肩を並べて謁見の場となった霊山寺の境内を歩きながら、奥州将軍・北畠顕家という人物についての情報を集めていた陸は思わず吐息を落とした。
権中納言家の嫡子として生まれ、14歳で参議、左近衛中将に任じられて殿上人に。
16歳で奥州将軍としてこの地にやってきたのだという。――宮廷内の権力闘争から距離を置くことで、見えたものがあるのだろうか。今も、陸奥の守・藤原秀衡麾下の将として奥州にある。
この公卿将軍は、城下の者たちには人気があった。
若くて都の香りのする公達であるから当然といえば、当然のような気もするが。――遙任を善しとせず、都から見れば地の果てのような場所へやってきたのだから、あるいは潔い人なのかもしれない。
「大久保様は『奥州在来の武将とはそのあり方を異にしている』って、仰ってましたわよねぇ」
それは、どういう意味なのだろう。
異邦人であるロゼッタや陸には、奥州に限らず日本における武家の在り方がいかなるものであるのかはよく分らないのだ。
公家、あるいは、武家と。
言葉では明確に分けているのだから、それに基するものがあるはずなのだが。――その線引きを見つけられないロゼッタだった。
「一般論とは逆の姿勢を取りたいということでしょうか?」
「‥‥それじゃ、単なる天邪鬼だ‥」
●国の在り様
「豊かだな」
何気なく落とされた野乃宮の呟きは、木賊の心にも深く落ち着く。
豊かで、そして、穏やかだ。
要塞でもある霊山城を廻ることは叶わなかったが、その城下やここに至までの道中立ち寄った町を見れば判る。
山地が多く、気候も厳しい。
江戸や東海道のあたりと比べれば、技術的には遅れていそうだ。――それでも、禾倉には備蓄で満たされ、馬も、武器も不足ない。
何よりも。
この地では、誰も街道を行く騎馬や兵士の姿に不安げに顔を曇らせたりはしないのだ。
百年をかけて、奥州が手に入れたもの。
その時の長さを思い知る。
『‥‥ば、奥州に野心を抱く者はなくなる‥』
遠い記憶を手繰りよせ、鑪は胸に支える棘に気づいた。
誰かがそんなことを言った気がする。
野乃宮もまた、昨冬の大火の折、謀略のひとつを止めるべく奔走した従姉妹の言葉を思い出して眉をしかめた。
平泉へたどり着くことができたなら――
奥州を理想郷だと信じてやまないあの野疾に会うことができるのだろうか――
●奥州将軍
忍び込んだ天上裏から、叶は北畠顕家なる人物を眺め下ろした。
木賊、野乃宮、鑪の3名と対峙する奥州将軍は、その高位からすれば驚くほど若い。――せいぜい叶と同年かそこら。将軍職を任じるだけあって貴族的な脆弱さを感じさせない白皙の美丈夫である。
御前にて陵王舞を披露するほどの名手であったと噂を聞いた。
その覇気と圭角で他を圧倒する独眼竜を《動》だとすれば、この漢は《静》。冷たい水を湛えた深淵のような、静かな‥‥それでいて、揺ぎない強さが秘めた人物だと思う。
「先ずは目通りをお許しいただいたこと。御礼申し上げる」
鞘を掴んだ右手を左手で押さえ――利き手で鞘を持つことで抜かぬ意思、さらにその手を聖なる手とされる左手で封じるという最上級の礼を尽くしてた木賊に、顕家は軽く会釈してみっつ置かれた床机を差した。
3人が音を立てぬよう注意深く腰を下ろすのを見届け、若い公卿武将はおもむろに口を開く。
「源徳公よりの使者だと聞き及んだが、その言、相違ないか?」
「相違ございません。――ここに書状を預かっております」
大久保より託された書状を証し、木賊はそれを目の前高さに掲げて差し出した。
本来ならば、陸奥の守以外に見せるべき物ではないのだが‥‥あえて書見を許す事で相手を陸奥の守と同列に扱い、重視しているのだとほのめかす。
書状を受けようと動きかけた近習を視線で制し、顕家はその口元にほのかな笑みを浮かべた。
「その書状は源徳公より陸奥の守様に託されたもの。陸奥の守様にお渡しするが筋であり、其許の役目というもの」
「‥‥よろしいのですか?」
よい、と。
明瞭な答えが返る。
さすがに反応に迷い、戸惑い気味に書状を下げた木賊と、隣席にて視線を交わした野乃宮、鑪を順に眺めて、顕家はゆっくりとタネを明かした。
「実は、其許等を待っていた」
「「「えっ??」」」
危うく床机から腰を浮かせそうになり、野乃宮は慌てて両の手で膝を抑え、口を突いた声を押さえる。
「白河を越えてよりの其許等の動きは掴んでいたのがまずひとつ。――伊達政宗殿より使者が参った」
源徳よりの使者を名乗る者が霊山城に辿りついた暁には、その者たちを平泉へ送り届けてほしい。
伊達家の使者は、そう告げてきたのという。
「確かに。あの者の真意がどこにあれ、対話の機会は逃すべきではないと思う」
自力で建つ力を持つ自力で起つ力量持つ奥州が、江戸と上州の諍いに手を貸すに利は無い。むしろそれに乗じて、双方を攻め落とせる位置にある。――だからこそ、源徳も捨て置くわけにはいかないのだ。
「‥‥僭越ながら、北畠卿は他の武家とは異なり神皇家に近しきお方。今上様の叔父上に当たる源徳侯へのご助力には特別な意味がございましょう」
「確かに。形だけを見れば、其許の言は理に適う」
木賊の言に深く首肯したものの、公卿にありながら将軍の地位を持つ漢は静かに水をさす。
「たかだか武蔵国を治めるにすぎぬ武家の血が神皇家に入り、その年端ない童が他を押しのけて帝位にあるコト。その過程に、漠然とした歪みを感じる」
歪みより生まれた理に、正道はあるのだろうか?
都の権力闘争より遠く離れた地にあって初めて見えてくる歪みなのかもしれないし、政にも嘴を挟みはじめた武家の台頭を快く思わない公卿の驕りなのかもしれない。あるいは、若さゆえの潔癖さであるようにも思えた。――思いがけない返答は、対面した三人だけでなく屋根裏部屋にて仔細を耳にした叶の胸にも波紋を投げる。
「この騒乱の風をいかように治めるか。その見届け方を決めるのは陸奥の守殿の裁量となろう」
平泉までの道の平坦は、この顕家が保証する。
後は、その目、その心にて奥州の声を聞かれるがよい。――開かれた扉の向こうから姿を顕したのは、尚も厳しく長い道のりだった。
この道が続く未来を選び取る任を託されたのは‥‥
果てしなく、そして、あまりにも重い未来に眩暈がした。