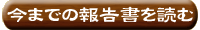【蓑虫騒動】 水の底を揺らす風
【蓑虫騒動】 水の底を揺らす風
 |
■キャンペーンシナリオ担当:津田茜 対応レベル:11〜lv 難易度:やや難 成功報酬:35 G 91 C 参加人数:6人 サポート参加人数:-人 冒険期間:03月29日〜05月04日 リプレイ公開日:2008年04月04日 |
|
●オープニング(第1話リプレイ)
これを壮観と言って良いものか。一足ごとに深く、しかもべったりとまとわり着いて重くなる足元の泥濘から視線をあげて、陣内晶(ea0648)はやれやれと肩をすくめた。
突然、暴れ出した川の氾濫で堤防が決壊したとは、一応、話に聞いていたのだけれども。
雨上がりのようなやわらかく濡れた路面から始まって。
気がつけば、あたり一面、水浸し。――街全体が泥田の中に浮かんだようなこの状況は、聞きしに勝る。
「はわっ! 川の氾濫なんて、大変ですよ〜」
泥濘に足を取られて苦労する驢馬の頭からふわりと宙に舞い上がりぐるりと周囲を見回したアイリス・フリーワークス(ea0908)の視界に映るのも、田起こし前ののどかな田園風景ではなく‥‥見渡す限り、泥の海。
街の向こうで、轟々と逆巻き流れているのが境川なのだろう。
堤防を押し流して周囲を呑み込んだ水はさすがにいくらか引いているようだが、その勢いは相変わらずだ。――台風一過、橋の上から覗き込んだ大川の流れにも似た濁流の勢いに、アイリスは思わず首をすくめる。あの日の水精は、勇み、笑っていたけれど。
今は、誰かの強い怒りを感じる。
水精の呼吸を読み取るのは、御神楽紅水(ea0009)ほど得意ではなかったが‥‥精霊魔法の使い手、あるいは、妖精としての感覚が受け止めるこの感情はとても判りやすい。
怒っているのだ、この川は。
「なんだか怖いですよ〜」
しょんぼりと驢馬の頭に着地したアイリスに、田之上志乃(ea3044)は少し考え込んだ。
一刻も早く、奈良屋茂左衛門を江戸へ連れ戻して蓑虫茶寮の蔵を開いて欲しいのだけれども。――いろいろと一筋縄ではいきそうにない波乱の予感がする。なにしろ‥‥
「‥‥大丈夫ですか〜?」
ぴいすけと名づけられた翼のない巨鳥からなるべく距離をとるよう心がけつつ、陣内は肩越しに暮空銅鑼衛門(ea1467)を振り返った。――強暴とまでは言われぬものの、暴れ馬と同程度では、手を貸そうにも危なくて。
もちろん相手が女性であればいちもにもなく駆け寄って手を取るところだが、残念ながら小柄とはいえ暮空は男‥‥それも、あと2年もすれば還暦に手が届こうかという立派な御歳。
「‥‥な‥んの、これ‥しき‥‥」
小柄で年相応に小太りのオジサンが、大量の荷物と泥に埋もれてうんうん呻っている様は、見ようによってはある意味、可愛らしくもあるのだけれど‥‥残念ながら陣内の嗜好にはヒットしない。――若葉屋の店長代理という社会的地位を思い起こせば、久しぶりとなる冒険の図というより、何だか別のものに見えなくも‥
「とっても重そうですよ〜」
「んだな、むちゃして腰を痛めねばええんだが‥」
心配そうに見守るアイリスとの隣で、陣内同様、これが女性であれば何らかのリアクションを起こしたと思われるレイナス・フォルスティン(ea9885)は、その不吉な予言にちらりと眉を顰めた。
「腰は男の命なのに――」
客人を待たせるのは、商人の心得によれば禁忌だが。
この泥の湿地をものとせず万難を排して駆けつけた一行の様子を見れば、到着の遅れた言い訳も立つ。
通行手形と茂左衛門への書付を届けにやってきたのが、奈良屋の番頭でなかった幸運に感謝しなければ‥‥
●奈良屋の秘密
「茂左衛門さん、あなたって人は! どうして温泉郷で、助けを呼ばないんですか!」
どうにかたどり着いた川辺郷の旅籠にて。
泥と旅の汚れを落として、感動の初顔合わせ‥‥の、開口1番。江戸屈指の豪商との対面を心待ちに構えていた暮空が口を開くよりも早く、口惜しげな恨み言が座敷に響いた。
温泉作法生活なる称号を有するフォルスティンではなく‥‥温泉より、むしろ混浴(ここが肝心)露天風呂を愛する男、陣内である。
「だいたい、僕らが此処にたどり着けるってことは、その気になれば自力で帰って来れるでしょうに」
「バカ者! せっかく疲れと汚れをさっぱり洗い流したというのに、泥を漕いで戻っては温泉を堪能した意味がないではないか!!」
確かにそれはご尤も。
そして、やっぱりお金持ちは我儘だった。
旅籠をひとつ借り切ってその奥座敷で踏ん反りかえる痩身の老人は、威厳、気概共に矍鑠と壮健そのもの。未だ、当分は第一線で頑張れそうだ。
「とかなんとか言って、ホントは僕らを呼んだ理由があるんじゃないですか〜?」
一筋縄ではいかぬ御仁だからこそ、何か裏があるのかもしれない。
ちらりと眇めた陣内の視線に、茂左衛門は少し気まずく視線を逸らせる。――当たらずとも遠からずといったところか。
「‥‥ないことも、ない‥」
ほら、やっぱりね!
ぐっと勝利の拳を握り締めたいところだが、さすがにそれは我慢する。陣内に代わり、暮空が膝を進めた。
「それで、ユーがこの川に何かしたということは?」
「それはない。――偶然とも思いにくいが、儂の目的がこの異変に関係があるという確証もない」
「大番頭さァは、旦那さァが何ぞ思案あって留まっとらっさるつぅとっただども。もし依頼さ関わる事だら、詳しく教えて欲しいだよ。‥‥秘密は守るだ」
いつになく真摯な志乃の表情に、茂左衛門は思案げに視線を宙に泳がせる。いくつかの懸念と結果を想定し、最善と思われる策を選び出すのは彼の得意分野であるはずだ。
束の間の沈黙。
そして、茂左衛門はゆるゆると息を吐く。
「この川の上手に山があってな。その頂に、ちょっとした社がある――街の者に訪ねれば、詳しいことは教えてくれるだろうが――なんでも山の神だか、天狗だかを祀っておるそうだ」
そこへ、行きたい。
それ以上の理由は、曖昧に笑うばかりで答えてはくれない。――彼らはまだ、茂左衛門にとって役に立つ‥‥駒だとさえ、認められていないのだから。
●境川の昔話
「やっぱり、なんだか怖いですよ〜」
志乃が綱の端を握る大凧に掴まって舞い上がった青空の高みで、アイリスは相変わらず衰えぬ流れを見下ろす。
魔法の凧に頼らずとも、アイリスにとって空を飛ぶのは簡単だけれども。見知らぬ場所で、迷子にならない自信がない。――こちらの方が、狼煙を上げてもらうよりずっと確実だ。
相変わらずアイリスのスカートの中が気になって仕方のない陣内だが、凧と同じ高さまで上がってしまえば、もう下穿きなんて見えやしない。優良視力のひとつも鍛えておけば良かったと悔やんでも遅いんだからねっ。
高いところから見下ろすと、川の流れは一目瞭然。
重なり合う山から流れ出したいくつかの流れが、寄り合わされて大きな川に。――冬期に眠る灰緑の大地に青い筋が蛇のようにうねり横たわっている。その腹を割くように堤を切ってあふれ出した濁流は、さながら流れ出た血のようだ。
冬場は、雨が少ないのだという。
実際、この日も天候は晴れ。湿り気程度の雨はあっても、川が増水‥‥まして、堤防の決壊を心配するほどの降水はない。
にも、関わらず。川はあいかわらずの荒れ具合で――
やはり、彼は怒っているのだと思う。
「‥‥彼? 川の精は女性じゃないんですかぁ?」
それも、若くて美人の。
ここが肝心だと強く言い切る陣内に、志乃は少し考え込んだ。――確かに、川姫と呼ばれる精霊の存在は、詳しい者の間では良く知られているけれど。
世間には、男川、女川と喩えられる河川も多いのだ。
「ああ。それなら、境川の神さんは男かもしれんなぁ」
そう言ったのは、急な増水で漁ができず、手持ちぶさたに網を繕っていた川漁師のひとりで。境川について聞き込んでいた異邦人が珍しかったのか、足を止めたフォルスティンを相手に、何やら意味ありげな笑みを投げて寄こした。
「嫁取りにずいぶん苦労したらしいから‥」
ひとりと言わず、ハーレムに暮らしたいなんて野望を持つフォルスティンにはなんだか敬遠したい話題かも。
なんて言っても、この辺りではちょっと知られた昔話であるらしく。フォルスティンだけでなく、境川についての伝承や昔話に興味を示した暮空や志乃の耳にも、川の神と村人たちの頓知話は容易く飛び込んできたのだった。
=====
昔々――
これは神と魔と精霊が相争い、混沌と麻の如く乱れた大地がようやく落ち着き始めた頃のお話です。
××郡、川辺の郷というところに、太郎坊という川の神がおりました。
太郎坊は陽気で、勇ましく‥‥神魔騒乱の頃にはたいそう活躍もした神さまでしたが、少しばかり乱暴者で、田畑に水の恵みをもたらしてくれる半面、怒り出すと手がつけられなくなるので、川辺郷の人々も皆、手を焼いていました。
=====
「なるほど。そんな乱暴者には、神様でも嫁のなり手がなかったとゆーワケですな」
御伽噺というのは一見微笑ましいのだが、何故か所々妙に現実的で。素直に笑って良いものかどうか迷ってしまう。
ため息交じりの暮空の嘆息に、陣内とフォルスティンも神妙に顔を見合わせた。――そう、明日はわが身かもしれない。
問題は‥‥。
これは、何も太郎坊ばかりではないのだけれど。‥‥上手く行かぬその根源を己の非にあると理解しているとは限らないという点だ。自分を愚かだと知っている者は、馬鹿ではない。そうでない者が多いから、世の中はままならぬのだけれども
嫁のなり手もいないので、川の神は荒れてますます乱暴者になる。
思わず、ため息を付きたくなる悪循環。
だが、ここはとりあえずめでたく収まるのがお約束の御伽噺なので、川辺郷の村人たちに力強い味方が現れないと。――奈良屋茂左衛門が木に掛けていた社の主、山の神様の登場である。
======
困った村人たちは、山の神様に相談しました。
相談を受けた山の神様は、この山に古くから生えていたナナカマドの神木から美しい娘の人形を作り出し、村人に与えます。
村人たちはこの娘に花嫁装束を着せ、祝言の酒やご馳走と一緒に竜神淵より川に流したところ、川の神はこれを喜び‥‥以後、境川は穏やかに治まりましたとさ。
めでたし、めでたし。
======
「え、ええ〜? め、めでたいのですか〜?!」
思わず頭を抱えたアイリスを通り越し、志乃と陣内は顔を見合わせる。
アイリス同様、フォルスティンも話の理解に苦しむけれど。暮空にとっても、ある程度はお馴染みの内容だ。
御伽噺としての筋は、一応、通っている。
あとはこの話の裏に隠された秘密の鍵をいくつ見つけ出せるか。――相談の席で、人柱、若い娘と言い合ったのは、もちろん冗談だったのだけども。
●山の神と風の声
その風は、西から吹いてきたのだという。
茂左衛門が温泉郷よりこちらの宿場に戻る、ちょうど前日のことだ。
江戸の御大尽ん逗留するというので、旅籠ではお店を挙げて歓迎の支度に追われていたちょうどその頃‥‥目が回るほど忙しかったこともあり、誰も深くは受け止めなかった。
ただ、思い出せないほど、ありふれた出来事でもなくて。
変わった事はなかったかと問うた暮空に、洪水の後片付けに追われる手を止めて首をかしげた者がいる。
風は西から吹いてきた。
ざわざわと心を揺さぶり、落ち着かぬ気分にさせる風だったという。――街の者の中には、誰かが慌て急き立てるような声を聞いたと言う者もいた。
天狗風。
そう呼ばれる風は、凶兆‥‥あるいは、吉兆の前触れであるとか、ないとか。
「聞けば、西国では神の目覚めが噂されておるそうな」
座敷でひとり碁を並べつつ冒険者たちの話を聞いた奈良屋茂左衛門は、ふむと思案を宿した視線を居並んだ者たちへと向ける。
「なるほど、と。思うての」
それで、様子を見ようと街に留まれば、川が氾濫してこの有様。
ますます、好奇心が沸いたということらしい。――神が居るというのならば、会ってみたいと思うのは道理だが。
奈良屋だけでも《フライングブルーム》で江戸に送り返したいとの暮空の目論みは、宛がはずれそうな雲行きだ。と、いうか。いくら矍鑠としているといえ年寄りひとりを異国の乗り物――どう見ても箒――で、帰すというのは無理がある。何のための迎えだ、と。奈良屋から苦情が出るのはたぶん、きっと間違いない。
「でも、どうして山の社なんですかね〜」
可愛らしく小首をかしげたアイリスに、茂左衛門は笑みの形に歪めた唇からからからと笑声を吐き出した。
「そりゃあ、川の神が目覚めたのなら、山の神も起きておろう。――聞けば、川の神の無体を止める方法を知っておるのは、山の神だと言うではないか」
それは、確かにそうなのだけれど。
それだけでない、何か。――この老人の腹の中には、もっと別の企みが隠されているような。
わずかに眇めた志乃の視線の先で、茂左衛門は懐から小さな巾着を取り出して眺め、また懐の裡へとしまいこむ。
「とはいうモノの、山の神とやらも鬼がでるか蛇がでるか‥‥道理の通るモノだとは限らぬのでな。悪いとは思うたが、そなたらを利用させてもらうことにしたのだ」
『腕の立つ者』には、そういう意味もあったのだ。
こんなこともあろうかと想像はしていたけれど。――川の神と山の神。話が通るのは、さて、どちらだろう。
●今回の参加者
ea0009 御神楽 紅水(31歳・♀・志士・人間・ジャパン)ea0648 陣内 晶(28歳・♂・浪人・人間・ジャパン)
ea0908 アイリス・フリーワークス(18歳・♀・バード・シフール・イギリス王国)
ea1467 暮空 銅鑼衛門(65歳・♂・侍・パラ・ジャパン)
ea3044 田之上 志乃(24歳・♀・忍者・人間・ジャパン)
ea9885 レイナス・フォルスティン(34歳・♂・侍・人間・エジプト)
●リプレイ本文
その日、朝一番の早馬で旅籠に到着した客人の姿を見つけ、アイリス・フリーワークス(ea0908)は歓声を上げて二階の窓から飛び出した。
よく晴れた空と同じ青い羽根が、春の日射しに機嫌よく微風を紡ぐ。
「紅水さ〜ん! 間に合ったですね〜 心配してたですよ〜」
仲間の到着を喜ぶアイリスの声に、田之上志乃(ea3044)も朝餉の箸を放り出して階段を駆け下りた。驚いて退ろうとする紅桜の轡を両手で捕まえ、志乃は馬上の御神楽紅水(ea0009)に笑顔を向ける。
「無事に着いただな。時間になっても来ねェもんで、何かあったのでねェかと心配しとっただよ」
「うん。手紙出したつもりなんだけど、届いてなかったみたいで。――心配かけて、ごめんねぇ」
騒ぎに何事かと二階の窓から顔を覗かせた陣内晶(ea0648)とレイナス・フォルスティン(ea9885)も、紅水の到着を喜んだ。
「いらっしゃい、お待ちしていましたよ。いやもう、紅水さんがいないと、ほら‥‥潤いが足りなくて‥‥」
何しろ、シフールと子供と、枯れた老人。‥‥残りは、野郎ばっかり。
面子に不満があるワケではないけれど、やっぱり女の子は多いほうが断然、やる気の出る陣内である。――そして、今度は暮空銅鑼衛門(ea1467)を不幸が見舞った。
●山の神に会いに
さて、山登りである。
依頼人の意向とはいえ、なんだか振り回されているような気がしないでもないけれど。
ともかく、旅籠に頼んでお弁当を作ってもらい、ますます水嵩を増して荒れ狂う川の水ガ溢れ出さないうちに早々と街を発つ。
川の変異で仕事にならぬ船付場の人足と話をつけて、山までの駕籠も確保した。奈良屋としても、温泉はともかくとして覗きの片棒は担ぎたくなかったらしい。――山ノ神の祠までは細いなりに道もあり、危険な魔物が出るという話は聞かないが、万が一、ということもある。
哨戒役のアイリスを先頭に、前衛を申し出たレイナス、志乃と奈良屋を挟んで紅水、殿に陣内という布陣(?)で、細い参詣道を登ることになった。
「川の神様に、山の神様ですか。ジャパンには神様がたくさん居るですよ〜」
見えそうで、見えない。山道の哨戒と皆の応援を兼ね、陣内をやきもきさせる高さをふよふよと漂いながら嘆息するアイリスに、志乃は物知り顔で頷いた。
「おっしょさまの話によるたァ、八百万はいなさるっつぅ話だべ」
「は、八百万ですか〜」
うっかりすると江戸の人口より多いかもしれない。
確かにそれは凄いと驚くフォルスティンに、紅水も曖昧な笑みをこぼした。
「善い神様ばかりじゃないんだけどね‥‥」
暴れ川と変じた境川の流れも、絶えれば人はたちまち困るのだから。
善くも悪くも尋常なる力を持つモノを、総じて《神》と呼ぶ。――とりあえず祀っておけば、悪さもするまい。そんな安易さもどこかに伺えた。あるいは、昔の人々にとって《神》はもっと身近なモノであったのだろうか。
「でも。山の神様ってどんな方なんでしょうね〜」
くれぐれも美人でありますように。祈りつつ奈良屋の腰を押して九十九折の階段を上る陣内の呟きに、紅水はどうだろうと首をかしげる。
「‥‥山の神様は女の人だって話は聞くけど‥‥醜女が多いって言うよね‥」
そして、とても嫉妬深いのだ。女性の立ち入りを禁じる山は多く、また、そんな山の神を安心させるために、祭事にオコゼ(虎魚)を供える地方もある。
「まぁ、白山さんみたいにえれェ別嬪っつぅ話もあるだけんどなァ」
尤も、準備を兼ねて調べてはみたものの、こちらの山の神様には残念ながら、その手の話は残されていなかった。
薪や茸、山菜、薬草などを採りに訪れる者たちが折りに付け手入れはするが、何か大きな祭事があるわけでもなく、川の神同様、御伽噺に語られるだけの存在である。――川の神を治めた功から、厄除けや縁結びにご利益があると言う者もいた。
「天狗なら男に決まっとるだら」
お供え用に酒と牡丹餅を携えた志乃の言葉に、陣内と紅水は無言で顔を見合わせた。
言われてみれば、女性の天狗というものは聞いたことがない。‥‥まあ、あまり見てみたいとも思わないが。
●奈良屋の秘密(2)
たどり着いた山頂はまだ少し肌寒さも残っていたが、見下ろす景色は春らしく暖かい。
大地を這う川の流れを眼下に見下ろす開けた場所に、山ノ神の祠はあった。――古い切り株が昔話を彷彿とする。
「そういえば、奈良屋さんが山の神様に会う目的って聞いてなかったよね?」
ふと口にした紅水の素朴な疑問に冒険者たちの視線が奈良屋に集まった。
好事家として知られた男である。――よもやこの祠に、珍しいお宝が置かれているなんて話を聞きつけて、コレクションに加えるつもりじゃあ‥。
幾人かの疑惑のこもった視線に、奈良屋は少し渋い顔をした。少し考え込むように眉を顰め、ゆるゆると息を吐き出す。
「‥‥誰にも言わぬと約束したのだが‥。まあ、ここまで来て蚊帳の外ではお主らも落ち着きが悪かろう」
言いながら、老人は懐から小さな包みを取り出した。
絹の袱紗に包まれたそれは、先日、旅籠の座敷で冒険者たちがちらりと垣間見たモノに間違いない。
「コレを捨てに来たのだ。‥‥理由は知らんが、江戸に置いては善くないモノだと言われたのでな‥‥おっと。中身は山の神を探してからにした方が良いだろうの」
旅立つ前は半信半疑であったものが、江戸から持ち出した先で奇異に出会いなるほどと得心した。
得心はしたが、ただ捨てるだけでは不安が残る。それで、山の神を頼ってみようと思い立ったのだ。――本当に山の神が現れるかどうかは、半分、賭けであったのだけれども。
「でも、肝心の山の神様はどこにいるですかね〜?」
きょろきょろと周囲を見回したアイリスに、奈良屋は肩をすくめて古い切り株に腰を下ろすと煙管を取り出した。白い煙がふわりと青空に香り立つ。
「それを探すのも、お主らの役目ではないか」
「ええ〜?!」
まったく、我儘な雇い主だ。
顔を見合わせ、吐息をひとつ。
まずは、お神酒とお餅を祠に供え‥‥それから、アイリスの笛と紅水の神楽舞でお出ましを願ってみることに――
これでダメなら、川の神に直談判が必要かも。
■□
先刻まで、確かに誰もいなかったのに。
踊る紅水の動きに合わせてひらりひらりと宙を舞う巾を目で追いかけた‥‥その、一瞬。
皆の視界から外れた祠の上に、彼は静かに立っていた。
「―――っ!!?」
山伏の装束に、一本歯の高下駄。驚くほど鼻梁の高い、白髪の老人。――思わず、ぽかんと口を開けて立ち尽くした冒険者たちの視界の中で、彼もまた、興味深げに彼らを見下ろす。
「‥で、で‥た‥‥」
悲鳴を上げて逃げるのもあり?
会えなければ、困ったことになるのだけれど。――出会ってしまったら、それはそれで大変な‥。
先刻までの長閑さが豹変し、ぴりぴりと肌を引き締めていく緊張感に思わずそんなコトまで脳裏をかすめる。
最初のひとことを紡ぐのに、ずいぶんと時間が掛かった。
●解けた魔法
「境界に異変を感じて参じてみれば‥‥なるほど、あヤツが目覚めたか‥」
境川の異変を訴えた一行の言に、天狗は深い眼窩の奥から川を眺める。
彼の眼には、怒れる川の神の姿が見えるのだろうか。
「――それで、川の神が怒っている理由に心当たりはあるのか?」
とりあえず話のできる相手でよかったと安堵しつつ、フォルスティンはゆっくりと剣にかけた手を離した。
怒りの理由が明らかになれば、それを静める方法も見えてくる。フォルスティンの問いに天狗はのんびりと首をかしげた。
各地で神の名を冠されたモノが目覚めの声を上げている。――覚醒を促した理由は、他にあるかもしれない。だが、
「おそらくは、術が解けたのだろう」
「術?」
「――おんしらは、昔話を頼りに此処へきたのだろう? 儂が川辺郷の者たちにしてやったことと言えば、ひとつしかあるまい」
面白そうに問い返されて、志乃と紅水は顔を見合わせた。
川の神様に手を焼いた村人たちは、山の神様に相談し‥‥彼らの願いを聞き入れた山の神様は‥‥
「人形を作ったんだっけ?」
「いくら神木とはいえ所詮は『木』、長い時が過ぎれば朽ちて『土』に還るのが理というものだ」
「‥‥そういえば、嫁取りに苦労したとか言ってましたよねぇ」
ようやく手に入れた花嫁が、儚く消えてしまったら。
落胆する気持ちは、理解る。なんだか少し川の神様が可哀想になった陣内だった。
「んだば、川の神様を鎮めるにゃあ、新しい花嫁さ拵えてやったらええっつぅことか」
「それが、1番手っ取り早い。無論、人形である必要はないが‥‥」
若い娘が生贄に身を差し出すのも、もちろんアリだ。
重い言葉に、紅水は口を噤む。それで、全てが上手くいくのなら‥‥そう思わないでもないけれど。
ただ、生身の人を差し出せば、ひとりでは済まない可能性もある。
「『人』は『木』よりずっと保ちが悪い。――とはいえ、最近は呪いに耐えられそうな古縁を持つ神木もそう簡単には見つからぬ」
「いっそ川の神を排してしまうのはいかがかの?」
奈良屋の言葉に、どきりとしたのはきっと志乃だけではないはずだ。
ここにいる冒険者たちの力を持ってすれば、あるいは『神殺し』も不可能ではないかもしれない。――ひどく大それて聞こえる提案に、天狗は頷く。
「それも、ひとつだ。まあ、賢い策だとは思えぬが」
アレでもこの辺りの水精を統べる神だ。
水難は確かに除かれる。だが、ひとつ精霊力の均衡が崩れれば、その次に何が起こるか‥‥想像がつかない。
「困りましたよ〜」
はぁ、と。しょんぼりと肩を落としたアイリスの嘆きに、陣内とフォルスティンもどうしたものかと思案を巡らせる。
何か良い方法はないだろうか。
どこか思いつめた風な紅水の顔色に、声をかけようとした志乃の言葉を遮ったのは奈良屋であった。
「‥‥呪いに使えそうな神木に心当たりはないが、これは使えぬかの?」
差し出された袱紗に、視線が集まる。
ゆっくりと開かれた包みの中から現れた小さな茶色の塊に、志乃は目を見開いた。――志乃だけではない。アイリスと紅水、そして、陣内もまた思わず息を呑む。
ずっと探し続けていたもの。
心を残し、気に掛けて‥‥彼らが、今、此処にいる理由のひとつにも通じる琥珀の玉が‥‥目の前にあった。
●琥珀玉
《蟲封じの玉》――そう呼ばれていた。
光に透かせば深い飴色の琥珀の内に、一匹の蟲が閉じ込められているのが確かに見える。
その異形か。あるいは、神体として納められていた遺跡の性質が、琥珀に由来したのかもしれない。
「‥‥江戸にあってはいけないものだ‥」
虫干しの日、蓑虫茶寮の庭先に現れた少女は、縁の先で埃を払っていた小間使いに言ったのだという。
年の頃は、十かそこら。晦日の闇夜を思わせる光のない眸と、抜けるように色の白い、どこか人を怯ませる雰囲気を持った子供であった、と。小間使いの少女がひどく怯えたせいで、ちょっとした騒ぎになった。
無論、俄かにその言葉を信じたわけではなかったのだが、
大火に見舞われ、
源徳公が江戸を追われ‥‥立て続けに続く騒乱に、その言葉を重ねても不思議はない。
「そんで、捨てる場所を探しとったつぅことだべか‥‥」
危ないところだった。
何事も起こらぬまま、奈良屋の帰りを江戸で待っていたらと思うとぞっとする。ただ、安堵ばかりもしていられない。
「なるほど。大地より生み出された宝玉とは面白い。神体であったというなら、尚、好都合‥‥朽ち果てぬ分、神木より使えそうだが‥‥さて‥‥」
そう太鼓判を押し、天狗はちらりと複雑な色を浮かべた冒険者たちに視線を向ける。
この災難を収める新たな礎とするか、あるいは、別の手法で切り抜けて琥珀玉を江戸へ持ち帰るべく知恵を捻るか。
選ぶ道は、ふたつにひとつだ。