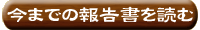二つの理想
二つの理想
 |
■クエストシナリオ担当:みそか 対応レベル:‐ 難易度:‐ 成功報酬:- 参加人数:31人 サポート参加人数:-人 冒険期間:2007年11月01日 〜2007年11月31日 エリア:イスパニア王国 リプレイ公開日:02月17日20:56 |
|
●リプレイ本文
●ナバーラ〜エステーリャ城名実共にナバーラ国王となったジュリオの出席。
護衛を含めて、従者は各々2名のみ。会談が終了するまで、双方の軍勢は弓矢の届かぬ距離まで後退――それが、アラゴン側の軍使から提示された停戦交渉の条件だった。
現在、ナバーラ・アラゴン国境地帯ではアルベルト率いるナバーラ軍と、先の会戦で壊滅的な打撃を被ったアラゴン軍が「暫定的休戦」といった状態で対峙している。
敗れたとはいえアラゴン側国境には未だ国王ペドロ4世自ら指揮する予備の軍勢が控え、さらに西方にはカスティリアの将・ベルトロ率いる「犬狼騎士団」を主力とした大軍が不気味な沈黙を守ったまま布陣している。
いずれの陣営も下手に先走って攻撃を仕掛けられない、いわば典型的な三すくみである。
「奴ら、何様のつもりだ? あれだけの大敗を喫しておいて!」
腹を立てて真っ先に反対したのは、ゼナイド・ドリュケール(ec0165)だった。
つい先日‥‥これは決して比喩的表現ではなく、戦いを続けていたアラゴン王国が体制変化を理由に突然停戦・共闘宣言である。
彼女が憂慮するように、アラゴン軍が戦の敗北を帳消しにするためジュリオの拘束、もしくは暗殺という非常手段に出る可能性もある。
「考えは分かるが‥‥可能性は低いだろう。いまさらジュリオを暗殺したところで、アラゴン側に何か得があるわけでないしな」
同じく釈然としない表情を蓄えながらも、彼女をなだめる氷雨 絃也(ea4481)。
「連中にとっていま最大の脅威は、カスティリアの犬狼騎士団だ。体面を気にするペドロ4世のこと‥‥おそらく国王同士の会談で『名誉ある和睦』という形に持ち込み、あわよくばカスティリア軍に対する共同戦線を張ろう――まあそんなところだろう。えらくムシのいい話だとは思うが」
「別にそうだとしてもかまわん‥‥」
王座の上で手を組み、じっと考え込んでいたジュリオが口を開いた。
「いずれにせよ、これ以上アラゴンと‥‥どことも戦う余力などない。とにかく会談の方へは私が赴き、アルベルトは呼び戻す。弟には‥‥やって貰わなければならない仕事が別にあるからな」
「‥‥ポルトガル軍の迎撃か」
どこか不安を秘めたジュリオの言葉の意図を汲む氷雨。
「ちょっと待てよ! それじゃ、もうハナからポルトガルと一戦構えると決めつけてるみたいじゃないか!?」
カジャ・ハイダル(ec0131)が憤りも露わに叫んだ。
「ポルトガル艦隊がこっちに向かってるって話は聞いたよ。‥‥だが、まだ戦争になると決まったわけじゃない。皇女が生きてる以上、まだ交渉の余地はあるんじゃないのか?」
「さて、そいつはどうかな‥‥穏やかにすむなら、先日の大立ち回りなどなかったはずだ」
壁際にもたれかかり、腕組みしたままルシファー・パニッシュメント(eb0031)がふっと笑う。
(「真に裏から操っているのは――」)
黒き鎧をまとった聖騎士は、トマスが死に際に漏らした言葉を思い起こしていた。
「俺とクレアの話を聞いてなかったか? デ家の裏の顔――そいつがポルトガル提督、ホアン・デ・ララ。しかもヴァウルと同じ複合魔法の使い手ときた。奴が今までの事件を陰で操ってきた真の黒幕だとすれば‥‥有無をいわさずこのナバーラに攻め込んでくる。皇女の生き死にに関係なくな。‥‥もっとも、俺はそっちの方が好みだが」
ポルトガル艦隊の一般兵士達は、おそらく皇女の顔など知るまい。せいぜい式典の時などに遠くから眺めた事があるくらいだろう。つまり、皇女自身をポルトガル軍の前に立たせた所で、司令官のホアンとヴァウルに「こいつは偽物だ」といわれてしまえばそれまでだ――ルシファーは淡々と諭した。
「ホアン提督がデ家の裏の元締めだって話は信じよう。だが、その背後にさらに黒幕がいたとしたら? 俺は、そいつこそカスティリア王、ペドロ1世だと思う!」
これはアンリエッタの警護にあたる一方、密かに過去の記録を調べ抜いた上でカジャが達した彼自身の結論だった。
「そうよ。ポルトガルを止めよう!」
鷹杜紗綾(eb0660)も声を上げた。
「たとえペドロ3世がデ家の傀儡だとしても、子を愛する親心は失ってないと信じたいわ! 気まぐれでも良い、今からでも遅くない‥‥父王がデ家より娘を護る道を選ぶように‥‥あたしたちで奇跡を起こしてみせる!」
ポルトガルとの開戦だけは何としても避けたい。彼らにとってもはや「家族」にも等しい存在となった幼い皇女、アンリエッタの故国を敵に回したくない――それがカジャや香月 七瀬(ec0152)、そして皇女を守るため傷ついた紗綾や早河恭司(ea6858)の悲痛なまでの願いでもあった。
だが――。
「気持ちはわかる。‥‥だが‥‥どうしようもないこともある」
ジュリオはカジャを見つめ、冷厳ともいうべき面持ちで答えた。
「この度の戦乱が何者かに操られたものであるとしても‥‥私には、それがペドロ1世だとはどうしても思えないのだ。彼は『残虐王』などとも呼ばれているが、同時にその公正さから『審判王』の二つ名を取る一角の武人でもある。仮にあの王が本気で大陸の支配を目論んだとすれば‥‥陰謀などという姑息な手段は取らず、配下の軍勢を動かし堂々と攻め込んできたことだろう。カスティリアには、それだけの国力があるのだから」
「陰謀‥‥聞こえはいいが、追いつめられてもいない者がとる手段でもないということか」
ゼナイドの言葉を聞いた後、ジュリオは言葉を切って再び思案し、
「そもそも‥‥この戦で最も漁夫の利を得ているのは何処の国だ? カスティリアはその領内深くまでポルトガルに攻め込まれ、中央ではデ家派勢力による反乱。我がナバーラは内戦で疲弊し、アラゴンもまた1万を超す兵を失った。残るは‥‥」
「だが、ジュリオ王!」
(「本当に‥‥私たちの手で‥‥終息させる事が‥‥できるのでしょうか‥‥?」)
王座の前で言い争う冒険者達の声を聞きながら、シェリル・シンクレア(ea7263)は暗い気分で思った。
デ家‥‥同じ血族のアンリエッタをも襲う家系。
今、ナバーラに向けてポルトガル船団を動かしているイスパニアの血統。
アラゴンで狩られる‥‥血。
真の黒幕は‥‥真に討つべき敵はホアン・デ・ララか? ペドロ1世か?
幾多の戦いをくぐり抜け、ようやく一つにまとまったはずの仲間達が、再び真っ二つの意見に別れて衝突している。しかもその選択を誤れば、今度こそ確実にこのナバーラは亡国の道を辿るだろう。
(「それでも‥‥私たちが去っても落ち着くように、手札や種を。ジュリオ陛下たちに多く渡せられるように。最後まで頑張りましょう」)
間もなく母となるエルフの少女は、新たな命が息吹く臨月の腹を愛しげに撫でつつ思った。
「もうよい。‥‥まずは、アラゴンとの会談だ」
放っておけば果てしなく続くであろう議論を打ち切るように、ジュリオが立ち上がった。
「お待ちください。陛下に親書を書いて頂ければ、私が――」
再びアラゴンへの密使を志願しようとした大宗院透(ea0050)の言葉を、ナバーラ王の片手が遮った。
「黒幕とやらが何者であれ、アラゴンを引き込むことで内乱を起こし、この国を荒廃させてしまったのは‥‥他ならぬこの私だ。国王には、国王の仕事がある」
「‥‥わかりました。ならば、護衛としての仕事をしましょう」
そう。王座と引き替えに背負った、もはや取り返しのつかぬ己の罪。
いまさら、他に悪の権化を求めて帳消しにできるようなものではない。
だからこそ――。
「私自らペドロ4世と会い、この内乱を本当の意味で終わらせる。それに今回の会談を提案してきたコモディンとかいう軍師にも興味があるしな‥‥ポルトガル艦隊への対応は、その後でもよいだろう?」
ジュリオが護衛として指名したのは、絃也と透の2人だった。
一瞬、不満そうに眉をひそめたゼナイドの髪を優しく撫で、若き王は微苦笑した。
「すまないな。おまえには、私が不在の間この城と皇女を守って欲しい。それに――」
ゼナイドの耳に口を近づけ、他の者には聞かれぬよう、そっと囁いた。
「万が一にも、死なすわけにはいかんからな。‥‥あの指輪を受け取ってくれた女を」
●カスティリア〜北部海岸
「おせーよシリル! 刻一刻を争う事態なんだぞ!」
「元気ですね‥‥水を得た魚というか」
追っ手の最後の一人を足ががりに跳躍し、人気のない岸壁沿いの道を、ポルトガル陣営から失敬してきた馬に再び乗り、クリムゾン・コスタクルス(ea3075)は背後に続くシリル・ロルカ(ec0177)に怒鳴った。 陣営の将軍から盗み読みした手紙によれば、カジャたち冒険者が皇女アンリエッタを拉致してナバーラへ逃亡したというが、これはとんだ言いがかりであろう。
一方、ポルトガル側はあの東洋人の剣士――「琥珀」を追っ手としてナバーラへ送り込み、さらには提督ホアン・デ・ララ自ら率いる大艦隊が本国を出航したという。
今さら琥珀に追いつくのは無理としても、せめて艦隊が到着する前にナバーラへ駆けつけ急を知らせねばならない。
返事がないのでふと振り返ると、相棒のシリルはなぜか崖っぷちに馬を止め、青ざめた顔で海の方を見つめている。
クリムゾンは慌てて手綱を引き、馬の足を止めた。
「おい! 何をグズグズ――」
「見てください!」
シリルが真っ直ぐ指さす先に目をやり、クリムゾンも言葉を失った。
嵐の前兆のようにどんより曇った空の下、遙か海上を何十隻ともしれぬ大船団が、ナバーラの方角へ向かって進んでいく。
断崖の上を、音を立てて身を切るような強風が吹き抜けていった。
●ナバーラ・アラゴン国境付近
「これはジュリオ陛下。わざわざのお越し、恐悦至極に存じます」
天幕の中で待っていた男は、ジュリオの顔を見るなり立ち上がり、恭しく一礼した。
年齢は30半ば過ぎというところか。笑顔が地になったような穏和な顔立ち。純白のローブに身を包んだその姿は、軍師というより何処かの賢者学院の気のいい教師といった趣がある。
だがジュリオの背後に付き従った絃也と透は、決して油断はしなかった。
目の前にいるこの男こそ、現在アラゴン本国において異端審問を口実にデ家の粛清を進めている軍師、コモディンなのだから。
透は素早く天幕の周囲と内部に目を走らせ、伏兵やトラップが存在していないことを確かめた。
絃也もまた、コモディンの背後に護衛として従う2人の聖騎士の力量を目で図る。
(「‥‥どちらも、かなりの使い手だな」)
おそらくコモディン自身も手練れの魔法使いであろう。
万一交渉が決裂した時は軍師とアラゴン王を人質に取る強硬策も考えていたが、どうやら賢明とは言い難いようだ。
「ペドロ4世はどうした? 国王を交えた三者会談と聞いていたが‥‥」
訝しげにジュリオが尋ねた。
「申し訳ございません。実はペドロ4世陛下におかれましては、急に体調を崩されまして‥‥今は療養のため本国に戻られました」
コモディンはアラゴン王直筆の委任状を差し出し、
「――ですから、この度の会談、不肖このコモディンが国王代理としてお話しさせて頂きたく存じます」
(「‥‥!」)
絃也と透、そしてジュリオもその意味するところを悟り、慄然とした。
病気を口実にペドロ4世を何処かの地に幽閉し、その間にアラゴン本国のデ家勢力を一掃する――つまりは事実上のクーデター。といっても、あるいは単にペドロ4世から敗戦処理を押しつけられただけなのかもしれないが。
いずれにせよ今は目の前にいるこの男が、名実共にアラゴン王国を代表する人物と見て良いだろう。
「では‥‥二者会談ということだな」
円卓の前に置かれた3つ目の空席に視線を落とし、ジュリオがいう。
「いえ‥‥3人目の客人ももうじき見えますよ。私がお招きしましたから」
天幕の外から、蹄の音と軍馬の嘶きが近づいてくる。
間もなく、入り口を覆う布が荒々しく開かれ、2人の護衛を連れた騎士が姿を現した。
甲冑の胸に刻まれた、カスティリアの国章と狼の紋章。
「‥‥あんたがナバーラ王ジュリオか。思ったより若いな」
片眼を黒革の眼帯で覆った将軍、ベルトロが鋭い隻眼でじろっとジュリオを睨んだ。
(「役者が揃ったな‥‥」)
絃也は無言のまま、隣に立つ透と目配せしあった。
カスティリア王が最後の切り札に送り込んできた将とあって、この男もまた超越クラスの剣士と思われる。単純に力で取り押さえられるような相手ではない。
「無意味な殺気は控えてもらいたいものです。停戦を申し出たのはそちらです‥‥」
「‥‥ごもっとも、それでは始めよう」
大宗院の言葉に、眉を動かすことなく頷くコモディン。会談の前の静寂が、場を支配する。
(「黒幕はペドロ一世か、ホアン提督か‥‥どちらが白で黒か、はたまた両方黒か確かめねばならんか」)
「結論から申し上げましょう。現在このイスパニア全土を覆う戦雲‥‥直接のきっかけは『狡猾王』カルロス1世の崩御から始まったナバーラ内乱とはいえ、その後の展開はデ家の‥‥いえ、厳密にいえばデ家を裏で取り仕切るポルトガル提督、ホアン・デ・ララの筋書きによるものだと」
全ての前置きを省き、単刀直入にコモディンが告げた。
(「やはり‥‥な」)
絃也は我知らず瞑目する。
もはやポルトガルとの開戦は不可避――。
この悪い報せを、エステーリャ城で待つカジャ達に届ける時の事を思うと気が重くなった。
「ジュリオ陛下。もしやあなたのお城に、フォルテュネさんというご婦人を匿われているのでは?」
「ふむ、いたとしたら? どうするつもりだ?」
コモディンの問いに、ジュリオは相手の心の中を見据えるように呟く。
追っ手を繰り出したことに、アラゴン王国が無関係であたっとでも言うつもりかと問いかけるようだったが‥‥その言葉が口から出ることはなかった。
「‥‥幽閉されていたからと言い訳をするつもりはありません」
「ほう‥‥事情は知らないが、そいつはぜひ、会ってみたいもんだなぁ」
横目でジュリオを見やり低い声で呟いた後、ベルトロはコモディンに向き直った。
「――で、だからどうだってんだ? まさか今までの戦は全部デ家に唆された事だから、水に流してくれとでもいうつもりかい? アラゴンの軍師さんよ」
「ええ、まあ‥‥できればそうして頂ければと」
「舐めるんじゃねぇっ!!」
ベルトロは怒声を上げて円卓を殴りつけた。
背後の部下に指先で何やら指示し、麻袋に包まれた瓜のように丸い荷物を受け取るや、無造作にコモディンの方へ放り投げる。
「土産だ。ペドロ4世に返してやんな」
袋の中身――苦痛に歪んだイラムスの首――を覗き、コモディンは哀しげに眉をひそめた。
「気の毒に‥‥彼は優秀な若者でしたが、功を焦りすぎました‥‥せめてあと十年、経験を積み己を磨けば、アラゴンの将来を担う武人となったでしょうに」
「何を人事みてぇにほざいてやがる! 何ならてめぇの首もその袋に詰めて、俺様がバルセロナまで届けに行ってやろうか!?」
「どうぞ、ご随意に」
円卓の上で手を組み、コモディンは敗軍の将とも思えぬ不敵な笑みを浮かべた。
「我が国としては、これ以上の戦いを望むものではありませんが‥‥もし本土決戦を挑むというなら是非もありません。神の御名の下、我らアラゴン王国の総力を挙げてお相手致しましょう」
ベルトロが口許を歪めて悔しげに舌打ちするのを、絃也達は見逃さなかった。
兵力こそ大きいものの、現在東部国境に展開しているカスティリア軍の大半は、半ば強引にかき集めた傭兵と民兵だ。とてもアラゴン本土を直接攻略できるほどの統制と兵站は持ち合わせていないのだろう。
敗走するイラムスの部隊を容赦なく全滅させた残忍非情な戦いぶりも、実は数に物をいわせた短期決戦でアラゴン軍の主力を叩き、カスティリア領内への侵攻を頓挫させるための、いわば際どい賭けであったに違いない。
――といって、中核をなすベルトロと「犬狼騎士団」が侮れない脅威であることに変わりはないが。
「ならば‥‥主導権はどちらにあるか」
小さく大宗院が耳打ちをしたのを皮切りに、氷雨が口を開く。
「勝手に話を進めるのは勝手だが‥‥この会談、挑発合戦で終わらせるには惜しいものだと思うが‥‥ジュリオ様?」
「ああ、手駒を見せたくなるのはわかるが、ただの自慢なら別の場所でやってくれ。‥‥こちらも暇ではない。この戦線において、優位を保っている勢力がどこであるか、諸君もわかっていないわけではあるまい。イスパニアのものではないが、十数人の精鋭はこちらが有している」
ジュリオの呟く言葉。ともすれば、この場で戦うことも辞さない‥‥あるいはこの会談の場での戦力差が、局面での全体戦力差であることを彼と背後の冒険者二人は如実にあらわしてみせた。
「‥‥ッ! なら、どうしようってんだ? 停戦してくれってからには、そっちもそれなりの代償を用意してるんだろうな。領土か? 賠償金か?」
「ええ。ジュリオ様のご指摘どおり、出し惜しみはしないでおくましょう‥‥情報ですよ」
コモディンは懐から2枚の書状を出し、それぞれジュリオとベルトロに渡した。
「これは‥‥?」
「アラゴン、ナバーラ、カスティリア、そしてポルトガル。イスパニア各国に潜伏するデ家の要人と、その協力者たち‥‥ここ半年ほどかけて、私が調べ上げたリストです」
口許に微苦笑を浮かべ、
「完全であはりませんが、エンリケ様が残してくれたものが幸いしました。ジュリオ様がお持ちの書状の影に隠れてはいましたが‥‥いや、あるいは影に隠れていたからこそ、手に入れることができました」
恭しく礼をするコモディンに、ジュリオは内容を一瞥する。
中にはエステーリャ城で彼に仕える側近達の名前がずらりと並んでいる。
「あと二週間早ければな‥‥」
あの晩、自分やアンリエッタを狙う刺客たちがなぜ易々と城内へ侵入できたのか――分かってはいたが、食い止めることはできなかった。
「こりゃすげえなあ‥‥貴族や軍のお歴々が目白押しだ」
逆に、ベルトロは愉しげに口許を緩めている。その胸の裡で、いずれカスティリア国内で始まるであろう、デ家残党狩りの凄惨な光景を思い描いているのだろう。
かつて「セビリア事件」においてデ家一族の追放という手ぬるい処分で済ませたことが、カスティリアに今回の災いをもたらした。
「残虐王」ペドロ1世に、もはや2度目の慈悲はありえまい。
「‥‥こいつらで全部か?」
「先ほども言いましたが、完成品ではありません。ですからここから先はお二人の協力と‥‥書状をいただきたい」
(「大詰めか、此処が正念場だな」)
アラゴンの軍師が手札を晒してきた事で、絃也もまた温存していた切り札を出す決意を固めた。
「残念だが先刻まで争いをしていた国に切り札をくれてやるほどお人よしじゃない。だが‥‥複写程度であれば構わない」
氷雨はジュリオが自分の発言を止めないことを確認すると、大陸の運命を決する言葉を放つ。
「ただし、停戦は当然として――他に2つ条件がある。一つはいまナバーラに迫っているポルトガル艦隊迎撃への援軍。もう一つは‥‥アラゴンで行われているデ家の粛清を止めて、せめて捕縛に留めて欲しい。ポルトガルに対しても同様だ」
「ポルトガルだと? 奴らがこっちに向かってるのか!?」
ベルトロが驚いたように叫んだ。カスティリアにしてみれば、現在西の要衝サマランカに迫りつつあるポルトガル軍は最大の敵だ。
ここでナバーラを占領され東からの侵攻を受けるはめになれば、緒戦でアラゴン軍を大敗させた大博打も無駄骨に終わる。
一方、コモディンはやや不思議そうな顔で絃也を見やった。
「援軍の件はともかく‥‥なぜデ家を庇うのです? 今までの経緯を考えれば、むしろあなたがたの方がデ家への恨みは大きいと思いますが?」
「そうだ、ペドロ一世の名の下に、処刑は当然の構だ。特に、全体を指揮したホアンとヴァウルの罪は‥‥」
反論をしようとする二人を睨みつける氷雨。二人は思わず隠し持っていた武器に手をかけようとしたが、拳を握り締めるだけに留める。
「おまえの話が真実なら、ホアン・デ・ララの身柄を押さえれば全ては片付くはず‥‥何もデ家の人間を皆殺しにする必要はあるまい。そういうやり方は好きになれん――それだけの事だ」
「現在、アラゴンがよい状況であるとは思えません‥‥。大儀を重んじるなら、ナバーラと停戦でなく、逆に協力するという懐が大きいアラゴンを見せるべきではないでしょうか‥‥」
訥々とした静かな口調で、透も口添えした。本来なら密使としてペドロ4世に直接いうつもりの言葉であったが、もはやアラゴンの実権を握っているのが目前のコモディンであるなら同じ事だ。
天幕の中が重々しい沈黙に包まれた。
ナバーラ、アラゴン、カスティリア――それぞれの国の運命を担う男達が、互いの腹を探るように油断無く視線を交わし合う。
直に剣こそ交えないものの、彼らが囲む狭い円卓は「外交」という名の戦場に他ならなかった。
「どうやら、他に選択肢はないようですね‥‥敗国、アラゴンの将として‥‥ここまで持ち込めたなら上出来でしょう。エンリケ様の面目も保つことができた」
ややあって、コモディンが口を開いた。
「つい昨日まで、我々は互いに血を流して戦ってきました‥‥しかし今、ようやく闇の奥から這いだしてきたデ家の首魁――ホアン提督の率いるポルトガル艦隊に対しては、3国で共闘する事が良策でしょう」
「決まったな。調停式の準備を」
言葉から間髪要れず、部下に指示を飛ばすジュリオ。
ベルトロだけが拳を握り締め、何かを話そうとしていたが‥‥結局、彼の口から言葉が発されることはなかった。
●ナバーラ〜北部海岸
「ポルトガル組の交渉が上手くいって、この準備が無駄になる位が理想なんだが‥‥カルロス1世じゃ無いが、激戦の決着だなんてロクなもんじゃあ無いからな」
「ほぅ、意外やな〜〜。てっきり如月さんなら楽しいっていうかと思ってたわ〜」
海岸線に防御陣地を築くナバーラ兵達の姿を馬に乗って見回りながら、ため息をつく名無野 如月(ea1003)に飛火野裕馬(eb4891)は言葉をかける。
「そりゃ、楽しくもあるさ。‥‥だが、そういう気持ちは戦っている時の麻薬みたいなもんさ。あたいらは戦うが、戦った先の結末なんてのは‥‥大抵ろくなもんじゃない。あんたと話せるのもこれで最後になるかもしれないしな」
相手はイスパニア最強と謳われるポルトガル艦隊。こちらから海戦を仕掛けるのは自殺行為に等しい。
したがって、いったん上陸させたあと陸戦で迎え撃つ水際戦術が基本となる。相手任せ極まりない戦術は、結果として海岸線に殆どの都市が固まっているナバーラの都市を犠牲にすることになる。
復興作業も嫌いじゃないが、平和な酒場でいいオトコと酒を酌み交わす快楽に比べようもない。
「戦場に‥‥なるのね」
不安げに声を発するセクスアリスブレアー(ea1281)。
せめてもの救いは、南部国境における会談でアラゴン、カスティリア両国との停戦が実現したこと。そして意外にも、アラゴン軍、さらにカスティリアの一部が援軍としてナバーラ陣営に加わった事だった。
ジュリオ・アルベルト兄弟が指揮を執る統一ナバーラ軍にアラゴン・カスティリアの援軍を含め、その数およそ3万。
(「昨日の敵は今日の友‥‥か。ま、連中にもそれぞれ思惑があるんだろうけど‥‥この際、味方が多いのに越したことはないさね」)
「ナバーラ軍内部にも調子が良すぎると不満の声はありますね。‥‥もっとも、それは相手も同じことでしょうが」
風に髪をなびかせながら淡々と答えるシリル。
コモディンがもたらした情報とその後の調査により、ナバーラ国内に潜伏していた虫――デ家の内通者達も相次いで捕縛された。
アンリエッタを襲撃した刺客の生き残りは、アイスコフィンが解けた瞬間に舌を噛み切り自決してしまったが、プロの暗殺者でもない一般人のスパイ達は拷問にかけるまでもなく観念し、残らず情報を吐き出した。
その結果、ポルトガル側が今回の上陸作戦に投入する陸兵はおよそ5千と判明。侵攻兵力としては思いの外少ないが、彼らはナバーラ軍の主力が未だアラゴン国境付近にいるものと信じているのであろう。
そこでヴァーレーンが一計を案じた。捕縛したデ家内通者の命を助ける代償として、彼らから仲間内の暗号や連絡手段を聞き出し、ポルトガル側に偽情報を送らせたのだ。
すなわち、『現在、ナバーラ軍はエステーリャ城近郊でアラゴン軍と激戦中。北部海岸に敵兵の影なし』――と。
「ま、気休めだろうがね。‥‥3万の敵が待ち受けてるとは知らねぇだろうが、相手も用意なしにのこのこ上陸してくるわけじゃねぇだろう」
「戦とは所詮だまし合いだ‥‥どの道、事実は残酷だ。あの皇女にとても‥‥カジャたちにとってもな」
如月と馬を並べたカミロ・ガラ・バサルト(ec0176)が、先の対アラゴン戦で刃こぼれしたため研ぎ直したロングソードの刃を改めつつ、答えた。
思えば何かを求めるような心境で故郷の地に戻って以来、幾多の戦いで血にまみれてきたこの刃――。残念ながら、まだまだこの剣を用いなければならない事態が残っている。
戦闘に勝つ、負けるのは構わない。
戦いが起こる以上、妥協して戦いを終結させない以上、どちらかが勝ち、どちらかが負ける。
だが、たとえ勝利したとしても‥‥ナバーラの国土を争いの場所として、果たして勝ったといえるのだろうが。
既に、戦場に近い海岸沿いの民達は避難させてあった。
もっとも傭兵国家であるナバーラは若い男女の殆どがそのまま兵士として動員できるため、後方の安全地帯まで待避させたのはよほどの老人と子供達に限るが。
その一方で、叶 朔夜(ea6769)はやはり捕縛者から得た情報に基づきポルトガル軍の編成、旗艦の位置や艦隊が停泊する海域を推定。また地元の漁師たちへの聞き込みにより海底と海岸の地形を把握し、予想される敵上陸地点もほぼ絞り込むに至っていた。
海から上がってきた敵を先陣切って迎え撃つアルベルトの部隊には如月やカミロはもちろん、遠路カスティリア西部から駆けつけたクリムゾンら冒険者達も加わる予定だが、これにカジャ達ポルトガル組のグループが猛烈に反対した。
コモディンの話を聞いてもなおペドロ1世を「黒幕」と信じるカジャらは、アンリエッタを仲介としてポルトガル側の誤解を解き、むしろこの期にポルトガル・アラゴンとの三国同盟を成立させカスティリアを牽制するべき――と強く主張したのだ。
結局ジュリオの裁定により、これまで皇女護衛にあたってきたグループにシリル、飛火野を加えた7名を、開戦前の最後の使者としてポルトガル艦隊に向かわせる事が許可された。
会見の場所を海上と決めたのは、此方の防備体勢を見抜かれぬ用心である。
「気持ちは判るけど‥‥やっぱり無謀だよ。アラゴンの軍師の話じゃ、もう黒幕がホアンだってのは九分九厘確実なんだろ? 止めるべきだったかも知れないねえ」
「理屈で割り切れる問題ではないからな。俺達がアルベルトに対してそうであるように、連中にも皇女とポルトガルに対してはそれなりの思い入れがある。せめて悔いを残さぬよう‥‥好きにさせてやろう」
そんな風に語り合う如月とカミロのすぐ側で、セクスアリス・はただ1人海岸に立ち、不安げに海上遙かに迫ったポルトガル艦隊を見つめていた。
「心配かい? 飛火野のことが」
如月の言葉に、こくんと頷くセクスアリス。
この前夜、突然「俺もホアン提督に会いに行くわ」と言い出した祐馬に対し、彼女は最初は必死で引き留め、それが無理と判ると、
「なら、私も一緒に行く!」
と言い張り、挙げ句の果てに大喧嘩となってしまったのだ。
『大きな流れに逆らえへんとしても、やるしかないやろ』
最後にそう言い残し、祐馬は船に乗り仲間達と沖へと出航していった。
「まあ、大丈夫だって。あの男は滅多な事じゃ死ぬようなタマじゃないからさ」
如月にそういわれても、
「祐馬さん‥‥お願い、無事に帰ってきて」
セクスアリスは目に涙を浮かべ、ただ海の彼方を見つめるばかりだった。
●ナバーラ沖海上
「大丈夫? 寒くない?」
「‥‥うん」
軍使であることを示す白旗を掲げた小舟の上で、紗綾は厚手のマントを羽織ったアンリエッタの小さな体を案じるように抱き締めた。
同じ船上には、今まで共に皇女を守ってきた仲間達に加え、シリル、祐馬らの顔もある。
紗綾にとってもう一つの気がかりは、琥珀との戦いで瀕死の重傷を負った早河 恭司(ea6858)の体だった。
幸い一命を取り留め、その後城付きの魔法医の治療により何とか動けるまでには回復したといえ、彼の体調はまだ万全とは言い難い。
やがて、小舟はポルトガル側から指定された旗艦へと横付けされた。
舷側から縄ばしごが下ろされ、まずカジャが先頭に立ち、他の冒険者達も皇女の前後を守る形で旗艦へと乗り込んでいく。
「どうだ? この通り皇女様を連れてきたぜ! 事情はこれから説明する。とにかく、俺達は戦う必要なんかないんだ!」
紗綾に手を引かれたアンリエッタが甲板に降り立つなり、カジャは艦上に居並ぶポルトガル兵達を見回し大声で告げた。
しかし――。
なぜか、兵士達の反応は驚くほど冷ややかだった。‥‥いや、同情的であると言っていいのかもしれない。
ある物は全くの無表情。またある者は、小馬鹿にしたような冷笑さえ浮かべている。
そして広い甲板のほぼ中央に、冒険者達を待ち受けるかのように3人の男が立っていた。
「おじ様‥‥!」
思わず走り出そうとしたアンリエッタを、慌てて紗綾が抱き留める。
男達のうち、副提督ヴァウル、副官マルケスの顔は冒険者達も知っている。
第三の人物――提督服に身を包んだ齢70を越そうかという老人こそ、ポルトガル海軍提督にしてデ家の裏の総帥、ホアン・デ・ララであろう。
「これは皇女殿下‥‥お久しゅうございます」
老提督は表向き、恭しく頭を下げた。
「本物だって事を認めるんだな!? それなら――」
カジャの言葉を聞き流しながら、ゆっくり上げられたホアンの皺だらけの顔には、満面の――そして名状しがたい邪な笑みが湛えられていた。
「無事皇女を連れてきた諸君らには、心から感謝しよう。‥‥何しろ、わざわざ3度目の刺客を送る手間を省いてくれたのだから」
「事実というのは、残酷なものなのだよ‥‥残念ながらね」
ホアンの手が高く挙げられ、ヴァウルの口から言葉が発せられると見るや――。
視界を覆う熱砂が、皇女と冒険者達目がけて降りかかってきた。
●ナバーラ〜北部海岸
旗艦と思しき帆船の上で火の手が上がるや、それを合図の様に無数の上陸用船に乗ったポルトガル兵達がナバーラの海岸目指して漕ぎ寄せてきた。
「‥‥始まりましたね」
ちょうど海岸部一帯を見渡す丘の上で、コモディンが馬を並べるジュリオにいった。
「イスパニア最強の海軍か‥‥ケッ。鮫が陸(おか)に上っちまえば、それまでよ」
やはり傍らで馬に跨ったベルトロが、口許を歪めて嗤う。
「では打ち合わせどおり、ベルトロ殿の軍には左翼からの攻撃をお願いします。カラトバ騎士団でもポルトガル軍と戦えるところ‥‥見せていただきましょう」
「おまえらの指図は受けねぇ。俺達は好きなようにやらせてもらうぜ‥‥今回は手を貸してやるが、いつまた敵に回るか、知れたもんじゃねぇからな」
吐き捨てるようにいうと、カスティリアの将は馬を返し、自軍の陣営へと走り去って行った。
「では兄上、私も‥‥参ります」
甲冑を身にまとい、ジュリオの前に跪いていたアルベルトが、兜を抱えてゆっくり立ち上がった。
上陸してくるポルトガル軍を最前線で迎え撃つ切り込み隊長。数の上では優位にあるといえ、敵も背水の陣を敷いた歴戦の精鋭である。
あるいは、これが兄弟の今生の別れとなるやも知れぬ。
「死ぬなよ、アルベルト‥‥このナバーラの未来にとって、おまえは必要な人間だ。おそらく私以上に」
兄の言葉を受け、まだ少年のようなあどけなさを残した若き将軍は、はにかんだような微笑を浮かべたまま無言で一礼し、自らの乗馬にうち跨って海岸目指して駆けだしていった。
「‥‥良い弟君を持たれましたね」
ふと、コモディンがジュリオにいった。
「この戦いが終わったら‥‥私は本国に戻り、今回の戦について改めて調べ上げるつもりです。我が国がデ家と結んだ密約、トマスやイラムス将軍の所業、『悪魔の連隊』の詳細など‥‥全てを明らかにした上で、戦場で行われた背信と非道の罪に対しては公正な裁きを下さねばなりません」
「‥‥」
「貴国と我が国の間に生まれた数々の遺恨と不信は、そう簡単に拭えるものではないでしょうが‥‥それでもなお、私は信じましょう。あなた方兄弟の手で復興を遂げたナバーラと、我がアラゴンが‥‥いつの日か、真の意味で盟邦と成りうることを」
ポルトガル艦隊から飛翔したペガサスの群が、上空から矢を射かけるべく地上のナバーラ軍に襲いかかかる。
そのとき丘の背後から無数の羽ばたきと嘶く声が起り、アラゴン本国から呼び寄せられた新手のペガサス部隊が、大地を蹴って離陸するやポルトガル側のペガサス群に突撃していった。
陸に、海に、空に――。
剣戟の鳴り響く音と風切る弓矢、兵士達の雄叫びと悲鳴が轟き渡る。
ナバーラ内戦の終幕となる、最も長い一日が始まろうとしていた。
●エピローグ
夕刻の迫る浜辺に、数知れぬ骸が横たわっている。
戦いは既に終わりを告げていた。
もともと強引な進軍。
連合国を相手に、勝利の可能性は薄かったが、ホアン・デ・ララの死亡により勝敗は決した。
あるいは被害は少なくすんだと形容すべきであろうか。
ヴァウルの撤退の一言により、両軍とも、被害は本来あるべきものより比べるべくもなく、軽微なものですんだのだ。
カスティリア北部の海岸一帯に、ポルトガル艦隊の残骸と思しき流木が打ち上げられたのは、戦いが収まって数日後のことである。
波に洗われ、巨獣の白骨のごとく累々と砂浜に積み重なった流木の山。
それらが歴史の証人となりながら、大陸は新しい歴史へと歩んでいく。
<了>