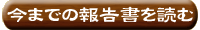若き獅子たちの伝説
若き獅子たちの伝説
 |
■クエストシナリオ担当:秋山真之 対応レベル:‐ 難易度:‐ 成功報酬:- 参加人数:8人 サポート参加人数:-人 冒険期間:2007年11月01日 〜2007年11月31日 エリア:ビザンチン帝国 リプレイ公開日:12月03日18:54 |
|
●リプレイ本文
若き獅子たちの伝説■第10回リプレイ:美しい季節
●軍議
敵が押し寄せてくるという報告があった今、グスグスしている暇はない。戦闘に入ったら話し合わなければならないことを話す時間もなくなってしまうだろう。
わずかな時間しかないが、それをできるのは今だけだった。
「さて、決めるべきことを決めようか。一番重要なのは聖都をどうするかだな」
「私はよくわからないので皆さんの意見に従います」
ショートボウの点検をしながらテオフィロス・パライオロゴス(ec0196)が仲間達に意見を求めると、真っ先に秦美鈴(ec0185)が応じた。
「あえて言うなら、封印に一票、ですね。分不相応な力は持つべきではないと思うのですよ」
魔法アイテムが大好きな美鈴でも、今回のそれはさすがにどうこうしようと思えるものではなかったようだ。それよりも、たとえ管理できたとしても制御できなくなった時のことを思うと、手を出さないほうが賢明だと思ったのだ。
この遺産に触れるには、まだ人類は未熟なのかもしれない。
もし触れるとしたら、きっといつかの遠い子孫だろう。
リョウ・アスカ(eb5646)もそれに同意した。
「俺も最終的な決断はお任せしますが、個人的には封印を希望します。‥‥手にしたとしても扱えそうにないですから」
「確かに、個人では持て余しそうですな」
独占は無理です、と皮肉っぽく唇を歪めるイワン・コウルギ(ec0174)。
独占しようと考えてたのか、と周囲の人々が目で訴えたがイワンはそれらの視線に気付かないふりをした。
「となると、私の立場上、封印という形で落ち着けたいですね」
アリー達をチラリと見てイワンは言った。
まだ意見を言っていない仲間達へテオフィロスが視線を送れば、手持ちアイテムの整理を終えたイーシャ・モーブリッジ(eb9601)が顔を上げてかすかに苦笑をこぼした。
「‥‥宝物は、私が想像していたものと違いました。必要としている人に譲ります、私はいりません。もちろん封印でもかまいませんよ」
「ダビデの血を受けし者達が、共に聖都と神の祝福を得られたことを喜び、それが長く続くことを祈ろう。帝国とアラビア教徒の双方の平和を守ろうと思う。‥‥つまり、封印だ」
ガルシア・マグナス(ec0569)はそう言ってアリー達に微笑みかけた。
「私も、皆さんと同じです。同じ『イブラーヒームの末裔』同士であればなおのこと、子同士が相争うを望む親がいましょうか? それに‥‥」
と、言葉を切った長渡昴(ec0199)は周囲の遺跡の具合を見渡してから、目に憂いを見せて言った。
「よく見れば、この遺跡は敵手により滅びたのではなく、自ら滅びたようにも感じられます。まるで、この地にあるものを敵に渡さぬように。ピタゴラス教団のような輩の悪手から遺産をお互いで守護するのが先人の遺志を尊び、神の正義を守ることに繋がるのではないでしょうか」
みんなの意見が出たところでテオフィロスは頷いた。
「それじゃ、聖都は封印しよう」
「テオフィロス殿はそれでいいのですか?」
昴の問いかけにテオフィロスははっきり首肯した。
そしてアリー達に一瞬気遣うような目を向けてから続ける。
「アラビア教徒の手に渡りさえしなければ、帝国としては充分だろう。それに、ダビデの力をもってしても滅んだ国があるのだから、頼りにしてばかりもいられないだろうし。これはみんなも言ったけど、人の手に余る強大な力ならば使うべきではないと俺も思う。最後に、何故破壊しないのかというと、この力自体は神の御意志によるものだと思うからだ」
次に敵にどう対処するかを話し合った。
敵はできるかぎり祭壇へ近寄らせるべきではない。
とりあえず伝承を信じるとしてテオフィロスが豆をまいて敵の進路を誘導することになった。さらにそれがただの迷信だったことも考え、行き止まりへ追い込むことも頭に入れておく。
ただしテオフィロスは杖を継承しているため、豆で誘導するのは他の誰かがやることになるだろう。
弓を扱える者はそれで進路妨害をするなり戦力を削ぐなり、接近戦に備えて行動することになった。
「気になるのは『されど彼の者は兄弟にはあらじ』‥‥さながら『人ではない』とでも言いたげですね。デビルと彼らに関わりでもあるのでしょうか」
まるで角笛に答えが隠してあるかのようにそれを見つめながら、独り言のように呟く昴。
「ピタゴラスの逸話‥‥月や陽の精霊魔法に長けた印象を受けます。その教養を奉じる彼らもまたその使い手を考えるのが妥当ではないでしょうか」
何か対策が必要だ、と昴は言う。
たとえば、範囲のある魔法を仕掛けられた場合、かたまって迎撃するのは危険だ。
相手の動きと仲間の位置をよく見て動くことが重要ということだ。
彼らは二班に分かれることにした。
一方がテオフィロス、イワン、昴、スフィル、アリー。もう一方がガルシア、リョウ、美鈴、イーシャである。
●鼻の侵入口
風が吹いてきた。風は黒い雲を呼び、雨を呼んだ。
鼻の侵入口を固めるのは、ガルシア・リョウ・美鈴にイーシャ。
時計回りの回廊を利して、左の壁を盾に使う。こちらも豆を敷いて守りを固める。
「私は切り結ぶのが苦手です」
イーシャは弓を手に後方支援の位置。
「この中で一番の手練は‥‥」
リョウの回りを見渡すあたり、謙虚と言うかなんと言うか。
「良い心がけだリョウ殿。エル・レオンたる者、生きて復命するのが第一である。叙任のおりにも言われたが、足を失えば這ってでも、加えて腕まで失えば転がってでも、生きて帰る事がその努め。徒(いたずら)に玉と砕ける事は許されぬ」
ガルシアは頼もしと誉めた。
「その点。自分には勇ましく散る事が許されて居る。主の為に戦死することは過分の誉れだ」
「ガルシアさん、死に急いじゃ駄目ですよ」
美鈴があわてて突っ込む。
「まて。自分は天国泥棒になる積もりはないぞ」
テンプルナイトの殉教的戦死には、天の御国の通行証が附帯する。とは言え、そのような誘惑に身を任せるほど無責任ではない。
美鈴は祭壇の回廊、すなわち両方の侵入口から防衛ラインを突破し浸透して来る敵を迎え撃つ形だ。狭い場所での乱戦こそ、無手の術に秀でる美鈴の真骨頂。その局面まで武勇を温存しておくのが第一の努め。
「こぉぉぉ」
吐く息吸う息整える。その息吹たるや怪鳥の如く、しなやかな体躯を折り敷く様や、虎の獲物を狙う雌伏に似たり。
「どうやら、来たようだ」
ガルシアが告げる。
「おいでなすったか」
リョウが剣を構える。豆の障壁が敵の動きを縛っているらしく、想定方向から突っ込んでくる。
ひょうと放つイーシャの矢が、戦いの嚆矢。吶喊してくる二番手が地に伏した。
「お見事!」
ガルシアの声。守って守って守りを固めて敵を伐つ。
「愚かな。目的に貢献せぬ討ち死になど、何の意味もない」
ガルシアは極めて冷静。見ていて微塵の危うさもない。人に倍する膂力が繰り出す一撃は、焼けたナイフでバターを切り分けるように敵を屠る。打ち下ろす煌めきが頭蓋を砕き、薙ぎ払う一陣が敵の血飛沫を巻き上げる。灼熱の鍋に落とした水滴が、湯玉となって爆ぜるように、敵の最初の吶喊は弾け飛んだ。
●額の侵入口
額の侵入口を固めるのは、イワン・昴・テオフィロス。そしてスフィルとアリーの兄弟である。
びっしりと石畳の地面に豆を敷き詰め、その直中に陣取る。右からの通路にも豆を敷いた。
「ジャパンの北辰流の稽古に、豆試合と言うのがあります」
昴は簡単に説明する。北辰流では竹刀稽古で対応を学び、個人の長を延ばすことから始めるが、そのままでは我流に近く伸び悩む。我流に居着き掛けた中級者に、正しい足捌きを体得させる稽古が、豆試合である。
「豆を敷き詰めると、踏めば痛いし足を滑らせ転倒することもあります。それを避けるためにはすり足が肝要」
素足故に嫌でも身に付くと言う。斯様に豆は侮れない障壁となる。まして、ピタゴラス教団が戒律に縛られているならば、少なくともむ時間稼ぎには成るはずだ。
「来るぞ」
テオフィロスは身構える。襲いかかる一隊の足が、数十歩先で止まった。豆が障壁と為っているようである。
「矢か!」
矢叫びは疾風の如く猛り狂う。右手の回廊に身を隠すや否や、元居た地面に矢が生える。石壁の隙間に立つ矢有り、火花散らして折る矢有り。
「うっ」
突然よろめく昴。
「大丈夫。ほんのかすり傷です」
恐らくはムーンアロー。但し、大した手練れで無い証拠に極めて軽微な昴の負傷。
「大事にならぬ内に、ポーションを」
駆け寄るイワンを制し、昴は言った。
「いえ。それには及びません。それよりも固まると危険です」
ムーンアローが使えるなら、シャドウボムも繰り出す可能性がある。密集するのは命取りだ。月魔法や陽魔法は、味方が使うときにはあまり大したことがないように思える物も多いが、使いこなす敵は難敵と言える。魔法の射程が何にも増して長いのである。
身を隠しているせいか、矢は止んだ。
「有り難い。一息着ける」
今の内にとテオフィロスは武備を整える。
「モーセの杖よ。俺が相応しき者であるとは思わない。だがおまえが、主が世人(よびと)を救うために創られた物であるならば、頼む。この俺に力を貸してくれ。叶うならば、俺達の命を狙う奴らをも、主の御心ならば救っておくれ」
如何なる力が、杖に宿るかは知らない。しかし、聖書にはいくつもの奇跡が証しされている。葦の海を二つに割りて道を拓き、巌を打ちて清水を湧かせた。荒野の中に切り立つホレブの山に赴くモーセの手にあり、十戒を授かりし場にも立ち会った杖である。
古びた杖は応えない。なぜかは知らぬが手に馴染むだけである。
イワンも聖ヤコブの剣を取りだした。既に雷霆を繰り出す剣であることは知っている。
「アリー殿。あなた方のほうがお詳しいようだ。この剣は如何なる力を秘めているのか知っていますか?」
「剣を握り天地の創り主に委ねよ」
その通りにすると、
「何をします!」
おもむろにアリーが投げつけた礫は、イワンに吸い込まれたかにみえたが、意志を持った獣のように、自ら躱すと後ろの石壁にぶつかり爆ぜた。
「味方の矢玉がおまえを傷つけることはない」
「噂に聞く、エクスカリバーのようなものだな」
「過信はするな。躱しようのない物は別だ。変化の者のように身体を抜けて行くのではない」
「つまり、範囲魔法とか落石とかですか?」
「害意ある者がおまえを狙って放った場合も同じだ。前からであれ後ろからであれ、敵の矢玉が自ら躱す事はない。おまえも以前の持ち主、エルサレムを回復せしマカベアの如く勇敢なれ」
「気を着けましょう」
頷くイワン。この土壇場で戦いの選択が増えるのは好ましい。味方の支援の矢は、決して自分を傷つけないならば、槍襖ならぬ矢襖を背負って敵と切り結ぶ事が可能だ。味方の援護射撃が自分に当たらないと言うのは有り難い。
イワンは、進入路の最前線に身を置くことにした。
テオフィロスは奥に下がり、祭壇の前に位置した。
「馬鹿正直に通路を通ってくれる敵ばかりでもあるまい」
重要拠点である。先入主で高を括っては不可ない。ピタゴラス教団の目的が、宝の奪取ならば良いが、破壊と言うこともあり得る。近くには一隊アラビア教徒。弓を持つ者と短槍を持つ者、合わせて20。
「先にも言った通り、俺は封印を望む。ダビデ‥‥諸君がダーウードと呼ぶ聖王のように、常に主に帰る者ばかりではない。余人に勝る賜物を手にしたら、それが罪の根となる。ソロモン‥‥スレイマンを見よ。治世の始まりにあれほど主の目に適った者が、多くの側女に惑わされて、遂には偶像の祭壇を造ったではないか。アブラハム‥‥イブラーヒムの神・主の祝福に相応しき者が現れるまで、封印されるべきだと思う。忌まわしき者の手に渡さぬように」
角笛を携える昴は、スフィルと共に脇の通路に位置した。
「教えて欲しい。ピタゴラス教団はただの異教徒ではないだろう?」
昴の問いにスフィルは短く、
「イブリースの眷属だ」
と答える。時には憎しみを持って殺し合う、ジーザス教徒とアラビア教徒。しかしそれは兄弟喧嘩だとスフィルは言う。
「兄弟は共に暮らすことが出来る。だけど仇は滅ぼさねばならない」
「イブリースって‥‥」
「主から断たれし者だ」
人間を指して神から断たれし者とは言わない。どんな不信仰の者も、人間であれば主に還る特権を与えられている。
「‥‥つまり、悪魔や悪魔に魂を売った奴らか!」
昴の悪い予感が的中した。
●ニスロク
遺跡の辺りは激しい嵐に晒された。冷たい雨と激しい風が、容赦なく体温を奪う。
戦いは何時しか乱戦となった。剣の嵐を踏み越えて、駆ける昴とスフィル。
「回れ霞刀、私の上に。闇を断ちきる光のように」
面に憤怒、内に慈悲。不動明王の化身の如く昴は征く。背はスフィルに任せてあるので微塵も迷いはない。
「きぇぇぇぇぇぇ! チェーストー!」
昴の剣には常識が通じない。剣を受け止め、その力を利用して切り返すのが西洋剣の極意だ。しかし、刀盤で敵を倒すとは当にこの事。受け止めた剣があまりの打ち込みの凄さに、峰を頭蓋骨に食い込ませる。
「ぁぁぁ‥‥」
信じられないと言う顔で、お一人様、ピタゴラス教団の天国へご案内。
気が付くと、辺りに敵の姿は無かった。
戦いは一進一退。持ち場を守る個々の勇士の働きは見事の一言に尽きるが、倒されても倒されても、亡者の如く迫り来る群。だが、勇士らの働きはめざましく、遂には後退を始めた。
と、信じられないことが起こった。後退した敵が、なんと自ら剣で身体を傷つけながら、口々に祈りの言葉とも呪文とも聞こえる異言を発して、一つの名前を呼び始めたのだ。
呼びかける相手が、ニスロクと言う事だけは判った。
「危ない。下がれ!」
切り込んで行こうとする昴を、スフィルが呼び止めた。アリーもまた、鼻の侵入口の方に走り、呼ばわる。
「こっちへ! イブリースが来る!」
イブリースとは悪魔を指す語である。
「予め聞いておく。昨日、何度礼拝をした?」
アリーの質問に
「起床時、朝・夜の食事時、正午・就寝前で5回かな」
と、テオフィロス
「私は不信仰な者ですから、1度です」
何事かとイワン。
「3度ですね」
そう答えるのは昴。
「その数を覚えておけ。アッラーが一人一人の行いを記録するために着け給うた天使が、おまえをイブリースから護ってくれるだろう」
アリーはコーランを謡みながら、とっておきの魔法を使用した。輝く光が皆を包み。そして消える。
アラビア魔法・インシャラー。実際にこの目で観るのは初めてである。
稲妻光る黒い空。その間から現れし物。一言で言うなら巨大なドラゴン。闇より冥き身体に、白く光る牙。サソリ座のアンターレスのように赤き眼(まなこ)。鉤爪は剣(つるぎ)の様に鋭く、百獣を驚かす咆吼に、死の呪いが込められている。
ドラゴンは大きく息を吸い込むと、美鈴目掛けて急降下。
「まじぃ!」
美鈴はタジタジ。ドラゴンの灼熱のブレスが放たれる。
「伏せろ!」
ガルシアは美鈴の上に覆い被さる。二人は炎に包まれた。
勝ち誇るドラゴンの叫び。しかし、二人は無事だった。
テオフィロスは、杖を手に庇う位置に進み出た。
「美鈴は隠れて」
なにせ、神に祈る習慣を持たないので、いつものようにのほほんとしていました。と言っていた彼女だ。インシャラーの恩恵は彼女には存在しない。
「残り2回か‥‥」
そしてその効果は今体験したとおり。その身を盾にしたガルシアに、微塵も損害はない。
イワンの剣が雷霆を放つ。ドラゴンは鞭を食らった羊のように呻き声を上げる。報復の鉤爪の一閃。イワンは辛くもデモンズシールドで防ぐ。防いだが、10歩ほど跳ね飛ばされて、神殿の土台の石壁にぶちあたる。
「う‥‥」
左腕が上がらない。あまりの衝撃で折れたか麻痺したか。襲いかかるドラゴン。
「おぉりゃ!」
横合いから全速力で突進し宝剣ティワイズを叩きつけるリョウ。流石音に聞こえた名剣。そして常人の3倍になんなんとするその膂力。剣は堅い鱗を破りて血を啜り、勢い余って石畳を深々と切り裂いた。ごろんと前に転倒しつつ、跳ね起きるリョウ。剣は僅かも刃を損なうことなく、彼の手に輝いている。その時。
「ぐぁぁぁ!」
ドラゴンの左の横面に突き刺さる矢。イーシャの放った一撃だ。ドラゴンは大きく息を吸い込むと、手傷を与えたイーシャ目掛けて灼熱の炎。
「イーシャさん」
炎に飲み込まれるイーシャ。生憎離れた位置で、カバーに入れる者は誰もいない。確か、彼女もインシャラーの恩恵の外にあった者だ。テオフィロスも昴も、悲痛な声を上げ顔をしかめた。
「ぐがががか!」
悲鳴を上げたのはドラゴンの方。見ると、右の目に深々と矢が。
「おあいにくさま。目尻に皺が増えるかも知れないけれど。そんな時では無いですね」
何時の間にか反対側に回ったイーシャは、もう、エウリュトスの弓に次の矢を番えている。
「脅かすな!」
リョウはイワンを助け起こしながら叫んだ。
「角笛を! 角笛を吹き鳴らせ!」
アリーが昴に向かって叫ぶ。
何のことか合点が行かぬまま、昴は胸一杯に息を吸い込むと、息吹を込める。
響き渡る角笛の音。
「がぁぁぁぁおぉぉぉん!」
リョウに斬られた時よりも、イーシャに目を潰された時よりも、痛々しい叫びが発せられた。ドラゴンは身悶えし、翼をばたつかせた。角笛の音が彼を苛んでいるようだ。
「これでも食らえ!」
イワンの放つ雷霆が左の翼に命中。神殿の遺跡の一部を崩し、ドラゴンを大地に引きずり降ろす。
その時、角笛は途絶えた。
「はぁはぁはぁ」
物が角笛だけに、吹き鳴らしっ放しと言うわけには行かない。昴の息が上がると、ドラゴンは呪縛から解けて力を取り戻す。それが判る昴は、再び息を吸い込むと角笛を吹き鳴らした。
昴の角笛に苛まれるドラゴンに向かって、総員あらん限りの武勇を振るう。リョウもガルシアも、またイーシャも。勿論テオフィロスも美鈴も。
やがて、イワンの剣が雷霆を放てなくなり、昴もふらふらになり、全員の矢が撃ち尽くされる。ドラゴンは強い。皆、少なからず傷を負った。特に、インシャラーの加護を受けられぬ美鈴の傷は深く、立っているのが奇跡であった。
しかし、ドラゴンが支払った代償も高い。左の翼はイワンに切り落とされ、右の翼は美鈴にもぎ取られ、リョウとテオフィロスとガルシアによって満身創痍。二つの目はイーシャに射抜かれて仕舞った。
「杖を掲げて!」
アリーに促されたテオフィロスは、モーセの杖を天に掲げる。光が波紋の様に辺りを満たし。その中ドラゴンは、石像のように固まり。やがてさらさらと砂となって崩れて行く。吹きすさぶ風が砂を散らし、夢で出来たいい加減な建物のように、跡形もなく消えてしまった。
●ダビデの宝
皆から戦いの興奮が醒めた。
美鈴は、はたと我に返り、自分が手にしたロバの顎骨に唖然。地に伏し呻く声を耳にする。
昴は懐紙で刃を拭うが、白研ぎの刃に所々刃欠けを発見する。
「研ぎ直さねば為りませんね」
ガルシアの前に屍(かばね)は胸壁を成し、地は血潮で泥濘と化している。
「驚いた。こんな事は初めてだぞ」
剣を拭おうとしたガルシアは、指が固く張り付いて、剣が離れぬ事実に気付いた。
イーシャは矢を撃ち尽くし、イワンもテオフィロスも、また同様であった。魔法やポーションを使い傷を癒し、拾い矢をし剣を拭う。水を飲み食物を口にし、失われた体力を呼び戻す。万全ではないにしても戦う力を甦らせた。再度の襲撃が無いとも限らないのだ。
「さて。何とか守り通せた訳だが」
テオフィロスは皆に呼びかける。
「封印するで問題ないな?」
念を押す。アラビア教徒も仲間達も、皆一様に頷く。
祭壇に供える物は三つ。テオフィロスの杖にイワンの剣。そして昴の角笛。
封印には封印の手順があるのだ。
定めの位置に収め、祈りを捧ぐ。
「天地の創り主、万軍の主、力ある神、全能の神よ。我らはしもべ、イブラーヒームの裔。願わくば、生ける主の誓われし祝福をお示し下さい」
アリーが主に語りかける。
すると、漸く晴れてきた雲間から、光が射し込み虹が現れた。
「ノアの徴だ」
ガルシアが感嘆の声を上げる。二度と地上を洪水で滅ぼさぬと、主が誓った証文である。その虹の端がすっと伸びて祭壇の上に掛かった。誰も見たことのない虹の橋立の基(もとい)が目の前に現れる。
礼拝などやったこともない美鈴の目にも、神の御業が証された。何時しか跪き、拝している自分に気付いて驚く。じっと眺めるだけで、ただ眺めているだけで、君も判るだろう。神様の存在を。
イワンとテオフィロスと昴の耳に、呼ばわる声がした。他に、その声を聞いた者はイーシャのみである。
(「私はルカ。主の民の一人です」)
「ルカ! 君は誰なんだ」
久しぶりに聞くルカの声に、テオフィロスは問うた。
(「主の怒りの杖が王国を打った後、多くの者が自らの背きの罪で主の民から除かれました。生き残った者の殆どが、ニスロクに仕えて主を忘れたのです。私たちは主の御手に導かれ、故国で蔑ろにした主に立ち返りました。ユフラテ川に差し掛かった時、アロンの末裔(すえ)が、主の命じるままにモーセの杖を掲げると、主はかつて葦の海を開かれたように、私たちが通り過ぎるまで川の水を開かれました。主の御導きによる1年半の旅の後、私たちはここアルサレスに至ったのです。私たちはダビデの子らと合流し、今に至ります。私は、来るべき帰還の日が来る迄この地に留まる守人です。真のエルサレムを継ぐ者の為に、標(しるべ)となるのが私の役目なのです」)
(「寝ずの番人?」)
イーシャは心の中で思い出した。
(「あなたにも聞こえるのですか?」)
ルカの声。
(「私は以前、こう言う文書(もんじょ)を手に入れました。『アシュラの使徒、ガイの戦士クロトよ。凍れる時の呪法を解け。寝ずの番人の呪いを解くは汝のみ。彼は癒えぬ呪いを受け、永き時を流離う』と。寝ずの番人とは、ルカさんあなたのことですか?」)
(「お気遣い感謝します。幸いなことに、私は癒えぬ呪いを受けては居ません。また、流離う事もありません」)
どうやら違うようだ。
「では、真のエルサレムの鍵を預かる者か?」
テオフィロスは皆を代表して言う。ルカはそれを肯定した。
「ならば、俺達はそれを放棄しよう。まだ時は満ちない。今それを我が手に、帝国の物にしようとするなら、必ずやアラビア教徒達との激しい戦(いくさ)になる。主は、主を我が砦と依り頼むアブラハムの子らが、血を流して争うことを望まれはしないと思う。100年、いや200年‥‥あるいは1000年の後。主を信仰する者同士の争いが絶える世が来る日まで、この地を堅く閉ざしては貰えないだろうか? 恥ずかしながら、今は一人の義人も見いだせぬ世だ。そもそも、この俺など何で資格を与えられたのか見当も付かない穢れし者だ」
(「他の方もそうですか?」)
イワンは言った。
「凄い力を秘めているのかも知れませんが、大き過ぎます。かと言って、帝国の安全に責任を負う者として、アリーたちアラビア教徒に譲ってしまうわけにもいきません。封印するのが、誰もが納得する話でしょう」
一時でも、独り占めしたいと思ったことは秘密である。
(「あなたは?」)
昴は威儀を正し、吐く息吸う息整える。
「人の手で御しきれるかどうかも定かになく手に余れば国の害となりますし、放置すれば必ず新たな争いの火種となりましょう。我らが神の子供であれば尚のこと、子供同士が相争うを望む親が居ましょうか?」
(「みなさん。それで宜しいのですね」)
ルカの念押しに、テオフィロスは呼ばわる。声が聞こえぬ者達のために。
「兄弟達よ! 遺産の番人は尋ねられておられる。ダビデの遺産を、帝国の物でもありアラビア教徒の物でもある物とするため。時が満ちて、我らが再び一つ宇(いえ)の者となるその日まで、封印しても宜しいか!?」
既に了解は取れている。善(よ)しの声が一斉に上がった。
(「では、この地を閉ざしましょう。主の栄光が世に満ちるその日まで」)
祭壇に供えられた3つの品は、虹の光に乗っかって天に昇って行った。
●美しい季節
終わってみれば、何もかもが夢だったようで。
けれど、夢ではない証拠にリョウはエル・レオンであり、今は次の命令までの空白期間である。
昨夜、酒場で会った旅の冒険者と意気投合してしまい、ほぼ徹夜で飲み明かして騒いだツケがきていた。リョウのまぶたと脳みそに猛烈な抗議をしている。ついでに喉の渇きもひどい。
それなら部屋でおとなしくしていればいいのだが、そうはせずリョウはフラフラと小高い丘まで出て来ていた。
午後の明かりが目に痛い。まるで目潰しのようだとリョウは手でひさしを作った。
そよ風だけが味方のようだ。
数呼吸の間、風を楽しむと草の上に寝転ぶ。眩しさに閉じたまぶたの裏に、筋のような雲の残像。
こんなところで眠ったら風邪引くかな、とリョウは思ったが部屋のベッドの上よりはいくらかマシだ。ここのほうが空気が良い。
ふと、昨夜の冒険者はどうしろうかとリョウは思った。
酒はあまり呑めないんだと言いながらけっこうなピッチでグラスをあけ、結局二人で何本のワインをあけたのだったか。酒場のマスターが押しかけて来ないところから、支払いは済ませてあるのだろう。どちらかの財布から。
情けないことに、途中からの記憶がない。
自分がいつ宿に戻ったのか。一人で戻ったのか、あの冒険者と戻ったのか。そうではないのか。
うーん、と唸っていると、ふと閉じたまぶたに感じていた日差しが翳った。
薄く目を開けると、好奇心に満ちた目がリョウを見下ろしている。
「あれ、フィッダさん」
「こんなところで寝るなんて‥‥死にたいの?」
感覚の違いだろうか。
リョウは風邪引くくらいですむと思ったが、フィッダの感覚では死に繋がるらしかった。
でも、よく考えてみるともう真夏ではないのだ。
フィッダの言うことのほうが正しいかもしれない。
リョウは体を起こしたとたん襲ってきた頭痛に顔をしかめながらも、自分の横を叩いて座るように促した。
彼女が座ると同時にリョウはその膝にごろんと転がる。
「あっ、ちょっと」
「ま、ま、ま。いいからいいから」
「足がしびれたらどうしてくれるの」
「さすってあげますよ」
「‥‥いじめ?」
何て陰険なの、と言いながらもその声はリョウを許している。
フィッダはゆるくため息をつくと、膝の上でくつろいだ表情をしているリョウの髪に指を通した。
それが気持ち良かったのかリョウはしだいに意識がどこか遠いところに引っ張られていくのを感じた。逆らわずに身を任す。
次に目が覚める時には、きっと気分爽快間違いなしだろう。
秘められた遺産の大いなる力よりも、愛しい人が注いでくれる身近な愛情の何と偉大なことか。
少なくとも、真の聖都に二日酔いは癒せまい。
●世界の涯てまで
その頃。ガルシアは七つの教会に聖遺物を届け、通信使の職務を全うした。旅立つその日、アラビア教徒の友人達も立ち会う礼拝の中で、ガルシアは世界を巡り平和の為に尽力する事を誓い。全会衆に向かって語り始めた。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
聖書は、「主ジーザスと契約すれば永遠の命を受ける」と言っています。「それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである」と記されています。
さて、では我たちの信仰の先祖であるアブラハムは、一体どんな契約を結んだのでしょうか? 主は、アブラハムが信仰の歩みを始めるとき、このように祝福して下さいました。
「わたしはあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる」
主は約束を必ず守る真実なお方です。本当にアブラハムは全ての信仰者の信仰の先祖となっただけではなく、彼自身も沢山の祝福を受けました。あなたもこのような祝福を受けて、あなたの名も祝福と為るよう祈ります。
アブラハムは牧畜をする人でした。彼は族長と言うべき人でありました。しかし王でも将軍でもなく、私たちと同じ者。そのアブラハムをアビメレク王が将軍のピコルを伴って訪ねて来ます。彼らはアブラハムよりも地位が高く、権力も持っている人でした。でも、一体どうして彼らはやって来たのでしょう。今も昔も、権力者は人を呼びつけるものです。彼らが負う責任や務めで忙しいせいもありますが、自ら進んで訪ねて行くと言うのはよっぽどのことです。それでは何故、彼らは訪ねて行ったのでしょう。
それはアビメレクの言葉に現れています。「アブラハムが何をしても主がアブラハムと共におられる」と言うただ一つの理由のためでした。
主と共にある人とは、頭がよい、有能な人を指すのではありません。どこに行っても、何をしても、主が彼と共に居られる人を言うのです。そしてそれを全ての人々、特に不信者たちが見るというのです。
主を信じない人から、あの人には、あるいはあの教会には、本当に主が共に居られると言う言葉を聞くなら、その人は真(まこと)のジーザス教徒であり、その教会が本当の教会なのです。
ともあれ、アビメレクは単なる移住者の頭であるアブラハムに懇願します。
「それで今、ここで主によって私に誓って下さい。私も、私の親類縁者達も裏切らないと。そして私があなたに尽くした真実に相応しく、あなたは私にも、またあなたが滞在しているこの土地にも真実を尽くして下さい」と。つまり、他国へ来て暮らすのに、そこの王様がわざわざ訪ねてきて、頼んでいるのです。
アブラハムは「私は誓います」と言った後、アビメレクのしもべ達が奪い取った井戸の事で抗議しました。驚いたアビメレクはこう答えます。
「だれがそのようなことをしたのか知りませんでした。それにあなたもまた、私に告げなかったし、私もきょうまで聞いたことが無かったのです」
聖書はこのように記しています。しかし、本当は、彼は自分のしもべ達がアブラハムの井戸を奪い取った事を知り、アブラハムと共に居られる主を恐れて訪ねて来たのです。
私は、この時のアブラハムの「私は誓います」と言う言葉に、彼の信仰の柔軟性を見ます。アビメレクは異邦人で異邦人の王です。そしてアブラハムは主に選ばれた人でした。そうです、ここは主と共にある人が異邦人と契約を結ぼうとしている場面です。アブラハムは躊躇うことなく異邦人と契約を結びました。後の時代、彼の嫡子の民族は異邦人を犬のように扱って、一緒に食べることさえしませんでした。彼らは異邦人の隣の席に座ることさえ避けて、主の選民である事を自慢しながら暮らしていました。しかし、信仰の先祖アブラハムは、異邦人だったアビメレクの提案を受けて契約を結んだのです。私たちは彼のようにあらねば為りません。
ともすれば、信仰深き者は世人(よびと)と交わりを持たない変人になりがちです。さらに、交わらぬだけでは無く忌諱し、自分が主に選ばれし特別な者として振る舞い出すと不治の病。そのような者達は、徒に不信者達を主から遠ざけているのです。これは主がお喜びになる行いではありません。これが世の人達にとって、主を信じられない要因となるからです。
ジーザス様はアブラハムが異邦人を受け入れたように、パリサイ人達が穢れし者と遠ざけた、遊女・取税人・悪霊に憑かれた人・呪われし者と考えられていたライ者。彼らと身近に交わるだけではなく癒されました。
私たちは宗教の名で、実は人間的な考えで神様を制限することが多いのです。しかし、主は、私たちの神であると同時に、全ての者の神です。信者で無いと言う理由で彼らを拒んでは不可ません。
さて、話を戻しましょう。アブラハムの主な仕事は牧畜でした。地域を移動しながら牧畜をしたのです。このためには餌となる草が不可欠でしたが、もう一つ。水が重要でした。今も昔も、彼の生きた地方は雨が少なく、地上で水を得るのは難しかったのです。それでアブラハムは、自分の家族と家畜のために井戸を掘ったのです。
古代に於いて井戸を掘るのは簡単なことではありません。掘ったからと言って必ず水が得られると言う保証も出来ない状況でしたから、金と時間と労力の掛かる冒険的な投資だったのです。今でも事情は同じです。砂漠地帯では、勝手に井戸の水を飲むことは殺されても仕方ない罪なのです。
その貴重な井戸をアビメレクのしもべ達に奪われました。しらを切ったアビメレクに、アブラハムはどう対応したでしょう。
聖書にはこう書かれています。
『アブラハムは羊の群から、七頭の雌の子羊を選り分けた。するとアビメレクは「今あなたが選り分けた七頭の雌の子羊は、いったいどういうわけですか?」とアブラハムに尋ねた。アブラハムは、「私がこの井戸を掘ったという証拠となるために、七頭の雌の子羊を私の手から受け取って下さい」と答えた。それゆえ、その場所はベエル・シェバと呼ばれた。その所で彼ら二人が誓ったからである』
井戸はアブラハムが掘った物で、奪われた物でありました。しかし、アブラハムは返せとは言わず売って欲しいと願ったのです。七頭の雌の子羊がその証でした。それ故に、アビメレクは井戸を、なんのわだかまりも無く与えることが出来たのです。
放置すれば品物は、いつも強い者の所有になるものです。アビメレクの子孫に至っては、契約がどうなるかも知れないのです。そこでアブラハムは、井戸をあなたが私に売ったという証拠を確かにしようとしたのです。この賢いやり方に、アビメレクは契約を結びます。ベエル・シェバは誓いの井戸となりました。しかし、アブラハムはこの事をここで終わらせなかったのです。柳の木を植え、契約の証としたのです。
人はこの木を見るたびに、七頭の子羊を与えてこの井戸を買った事を思い浮かべるでしょう。そしてアブラハムは記念植樹にとどまらず、主に祈りました。ここで初めて契約は、永久(とこしえ)に確かなものと為ったのです。
私たちは、何をしようが彼のように柳の木を植えねばなりません。不信者でも理解できるよう。何をしようが、永遠の主がここに居られることを宣言しなければ為らないのです。畑を耕しても、商売をしても、政治をしても、学びをしても同じです。
「あなたがたは行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして、父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け」と主はお命じになられました。これは全ての信者に与えられた絶対命令です。ですから、私たちは全ての国、民族、人々に福音を伝えねば為らないのです。対象を制限せずに、民族を限定せずに、男も、女も、子供も、老人も。いえ、あなたが憎む者であっても分け隔てなく行かねば為りません。
人を受け入れるのに柔軟でありなさい。しかし同時に、信仰の妥協をしては為りません。信仰の先祖アブラハムのように。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
信仰の先祖アブラハムの話はアラビア教徒達にも届いた。この教会が主と共にある本当の教会である限り、彼らアラビア教徒達は真(まこと)の福音を信じる啓典の民、信仰の友とみなすであろう。
今回のクロストーク
No.1:(2007-11-05まで)あなたは前日、何回礼拝をしましたか?
No.2:(2007-11-05まで)
絶体絶命の時、どちらを選びますか?
1.あくまでも自分の力で切り抜ける。
2.大きな代償があっても、利用できるものは全て利用する。