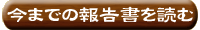熱砂の地にて
熱砂の地にて
 |
■クエストシナリオ担当:高石英務 対応レベル:‐ 難易度:‐ 成功報酬:- 参加人数:19人 サポート参加人数:-人 冒険期間:2007年04月01日 〜2007年04月31日 エリア:エジプト リプレイ公開日:04月27日12:29 |
|
●リプレイ本文
■暗き太陽昇る時エジプト総督ヘンリー・ソールト(ez0187)の手により、歴史と砂に眠る遺跡を調べるべく組織されたエジプト南部探索隊。だが、一行が目的と思われる遺跡を発見し、順調に探索が開始された矢先、大規模な襲撃により探索は中断を余儀なくされた。
謎の襲撃が終わってすぐに探索隊は、隊長のジョバンニ・ベルツォーニ(ez1112)と副隊長のシェセル・シェヌウ(ec0170)の指揮の下、カイロの総督府と連絡を取り体勢の立て直しが計られたものの、襲撃の爪痕は大きく、1週間の後の今でも探索は再開されていない。
「やはり、ギーレン将軍の話はかなり広まっていますね」
空いた時間を有効に利用る、遺跡近くのアマルナの街への情報収集と買い出しの途中。いつものところで昼食を取りながら、アルフレッド・ディーシス(ec0229)はシェセルに噂の内容を告げた。
「アトンが操るという噂の怪鳥も追い返され、各地で起こっている反乱のうちカイロ周辺のものは、将軍により手もなくひねられたそうですよ」
「そうか。アトンも焦っているだろうな。先日の襲撃者も、もしかしたら、奴らかもしれん。‥‥可能なら、共同で事に当たれればよいのだが」
先日の襲撃者の正体は未だつかめず。だがこの時に、遺跡を探るものを襲撃してくるのであれば、その相手は遺跡を狙うものに限られることは明白だった。シェセルはその思いの元、落ち着いた声で自分の策をつぶやく。
「まあ、まだ、相手の正体はわからないんですし〜」
二人の話を耳の端に聞きながら目の前にパピルスを並べて、ユイス・アーヴァイン(ea3179)はうなっていた振りをやめてにこやかにつぶやいた。
「しかし、よく調べましたね」
「時間だけはある、ってことでしょうかぁ」
アルフレッドも驚くその幾枚かのパピルスには、かなりの数に上る王族と神官の名が載せられていた。もちろん偽者、疑わしきものものも数あろうが、それでも資料としての価値は低くはない。
「王の伝説か‥‥そのような不吉な伝説を残すのであれば、悪魔に騙され魂を売ったものと見るのが正しいところだろうが」
シェセルは目の前に広げられた数多の名前のうち、一つをじろりと凝視し、つぶやきを紡ぐ。
「アマルナを築いた王は、太陽の神に取り憑かれたそのような人物であったとは聞いているが、それが、本当に真実かどうかはわからない」
「そうですね〜」
男のつぶやきににこやかにユイスは応え、そして王名表の一部、シェセルの見ている同じ名前に視線を移す。
その視線の先には、シェセルの思う名と、ユイスの気にする名が、並べて書かれていた。
「アマルナを築いた王といえば、確か‥‥アトンに愛されしもの、イクナートンと呼ばれた王でしょうね〜。伝説でも、やはりそうではないかと思えますよ。でも‥‥」
「でも?」
「神と呼ばれるほどのモノを封じたとなると、その呪いをかけた神官たちは、どれほどの力の持ち主だったんでしょうね〜」
アルフレッドの問い返しに軽く答える男を見て、シェセルは静かに目を閉じ、自らが属する民がたどった歴史に重ね合わせる。
「イクナートン、か‥‥悪魔に魅入られたのは、果たしてどちらだったのだろうな‥‥」
シェセルの問いかけに答えられるものは、今、その場にはいなかった。
天空に浮かぶ細き月が人々の思いを食んで、その身を育てる夜の空。
その月の遥か下には、一人の口から紡いで漏れる鈴の声が響いていた。
渡る砂の海 そは遥かに広がり
見えぬ果ての果て 旅人は思いとともに進む
永劫の時 遥けき距離を
離れて思う その身と心 いつでも安らかならんことを
安らぎと平穏を願ったフェネック・ローキドール(ea1605)の魔力を込めた歌声は、緊張で高ぶる周囲の者たちの心に染み通り、安らぎを与え、緊張を解きほぐしていく。
「いい歌よね」
「‥‥確かに、の」
焚き火より離れたところで自らの処遇に愚痴こぼしの合間、渋々と動物たちの世話をするアナスタシヤ・ベレゾフスキー(ec0140)は、サラのふとしたつぶやきに静かに同意した。
その足元にじゃれる、目の前の子猫。ともかくもケヴァリム・ゼエヴ(ea1407)のいない間にと世話を見るようになってから、その子猫は女に懐き、肌を親愛の情でよく舐める。
「ところで、サラ」
テティニス・ネト・アメン(ec0212)は水仕事の終わり、まくった袖を直しながらサラの側に寄って耳打ちする。
「あの人の隠し事は何か‥‥わかったかしら?」
「いいえ。ぜーんぜん」
投げかけられた言葉に肩をすくめてサラは答えると、続けて大きくため息をついた。
「あの人がここまで隠し事するなんて、ほんと、これまでにないくらいの大事よね。‥‥私に大目玉くらうの嫌がってるのか、それとも‥‥」
「それとも?」
猫をあやしながらも獣の世話は向いていない、とお嘆きのアナスタシヤの疑問に、サラはやや離れた場所でシェセルと打ち合わせる夫に視線を向ける。
「私を巻き添えにしないよう、気を使ってるかよ、ね。太陽の遺跡なんて、もうそれそのもの、ってのが出てきちゃったんだし」
「‥‥太陽の遺跡、のう」
そんな女たちの思いをよそに、朗々と月を歌う歌姫の声は、夜闇を静かに滑り行く。
「冷えますな」
「‥‥ああ」
月の光に包まれた鈴の声が響く中、思案するベルツォーニはシェセルの声に気がついたように、改めて絵図面に視線を落とした。
「何か、悩み事でも?」
「別に」
「‥‥総督閣下のことですか」
新たな人員と物資の手配が済み、まもなく再開する探索の打ち合わせの途中、気の入らぬ隊長の心を見透かした副隊長に、ベルツォーニは目を細め、ため息とともに見返した。
「わかるか?」
「いえ。しかしサラ殿は気づいておられるようですし、隊長と総督閣下の仲は、多少は耳に入れています」
「たく、あの、おしゃべりが」
口調とは裏腹の照れた苦笑を浮かべるベルツォーニに、シェセルは話を区切り、絵図面をたたみながら尋ねかけた。
「総督閣下と隊長は、昔からの間柄とか。その時の武勇の話など、聞いてみたいものです」
「‥‥くだらねえ話さ」
男の顔に浮かんだ表情は、それまでの自信に満ちたものと比べれば、自嘲にあふれていた。酔ったかのようにやや饒舌に、芝居がかった雰囲気で、ベルツォーニは滑らかに言葉を紡いでいく。
「奴とは、古いなじみの冒険者。どこぞの遺跡でケルトの宝が見つかっただの、バイキングの末裔の残した遺物だの。ジーザスの聖遺物なんていくつ作っていくつ見つけたことか!」
冒険者時代の流浪の二人は、体のよい詐欺師と山師。それが二人の関係を表す最適な言葉だという。
「だが、その詐欺師もどうやったかは知らねえが、今では中東の総督様。実力がない張子の虎じゃあねえが‥‥まったく、どこまで行くつもりなんだろうかな」
「‥‥蓄財は、まだ続けるつもりなのでしょうか」
「だろうな」
シェセルの問いかけにベルツォーニは苦く笑い、すぐさま肯定する。
「あいつにとっちゃ、このエジプトも売り物、財貨の一つよ。だがそのためには傀儡ともいえる今の状態じゃねえ、糸を引きちぎる、それ以上の力を必要とする‥‥」
「‥‥まさか?」
「‥‥今のは、心の棚のどこかにしまっておきな。ちょっと、過去を懐かしんだだけだ」
そうして一瞬微笑んだ男の顔は、どこか寂しそうな表情だった。
「ところで、ギーレン将軍とは、どのようなお方なのでしょうか?」
「そうね‥‥面白い人物と言えるかしら」
エミリア・メルサール(ec0193)の問いにエセル・テーラー(ec0252)は少し悩み、そして短いながらも見識をくわえて、そうつぶやいた。
新たに集った冒険者たちが、南部探索隊に合流するべく旅立つまでの短い間。カイロの町並みを楽しむように歩くエミリアを、総督府の客分としてあるエセルと山本建一(ea3891)は案内する。
「武人ではあるけれど、道理はわきまえている‥‥もちろん、その道理は中東の帝国に忠誠を捧げた者の、それではあるけれど」
「その噂を聞いてから、一度、手合わせしてみたいと思っているんですが、なかなか難しいようです、ね」
山本は交わされる二人の会話を耳に挟み、静かに感じたことを口にする。
「難しいとは、なぜでしょうか」
「この地の反乱の騒ぎは、どんどん大きくなっているから、でしょうね。鎮圧のために兵を繰り出し東奔西走、忙しいようです」
エミリアの疑問に答えた山本は、沈んだ面持ちのエセルに気づき、じっとその表情を見つめた。その視線の意図するところに気がついたのか、思い悩んだ表情のままで、女はつと、思いをこぼす。
「エジプト出身の官僚や、それになろうとしている民衆がいるということは、この国を動かしているのはエジプトの民だということ‥‥つまり、この国は民たちの手にあるということになる。でも一方で、彼らはあくまで、サラセンの一部でしかないわ」
「国は、人が持つ強い伝統と力の結晶。‥‥今この時のその姿も、エジプトの姿ということでしょうか」
健一の記憶から紡がれた言葉に、二人の女はふと男の顔を見ると、男は照れたように笑いを浮かべた。
「ただの、メハシェファの受け売りですよ。あの人は、今のこの大きな混乱も新たな世の糧と言っていました‥‥そうだ、お茶の時間です。どうです、これから」
天空の陽の高さを見れば、すでに午睡の時間は過ぎ、お茶の時間に近づこうという頃。山本はにこやかに二人を誘い、総督府へと戻る道を向けば、昼下がりの散歩もひと段落というところだろうか、二人の女もそれに従った。
「‥‥」
冒険者たちがその場を去ってより、ややしてから。影から影へと渡るように、その場より立ち去る人影が一つ。ハサネ・アル・サバーハ(ec1600)はその身を翻すと、耳そばだてた言葉を胸に刻み、雑踏の中へと消えていった。
「よく戻ってきたな、小さき者よ」
「‥‥!」
目の前にそびえる黄金のピラミッドにたたずむスフィンクスの言葉に、楠木麻(ea8087)は自分の胸に視線を落とし、即座に周りを見回すと、とりあえず近くの土佐聡(ec0523)を殴りつけた。
「‥‥いってぇ〜!」
「見るな!」
「何をだよ!」
「静かにしないか」
突然のことに涙でジト目で睨みつける少年をぶすりと涙目で無視する少女に、シェセルはしょうがないという風に息をついた。そのまま男は正面を向くと、面白そうに見つめる陽の精霊と向き合う。
「小さき者よ、新たにこの場に戻りしは、妾がかけた謎、解いたがゆえかえ?」
それは偉大なる神にひれ伏す者。全てのものが従えしもの。
それは神に従うがゆえに神なき時は存在すること能わず。
だが神が去れば、その身は解けて消えるもの。
悲しき我は、果たして誰か?
「‥‥でしたか」
間髪入れずのアルフレッドの問い返しに、獣の体に乗った女の顔は、満足そうに艶然と微笑み、麗々と声を漏らした。
「その通り。‥‥さて、汝らの答えはなんぞ?」
「簡単な話ですね。影、でしょう?」
「偉大なる神とは、太陽のこと。それさえわかれば簡単じゃ。神にひれ伏し、いなくなれば姿を消す。太陽に関わりの深いもの、じゃ」
アルフレッドの答えに続けるよう、アナスタシヤが解説を加えると、ユイスは気づいたようにうなずき、そしてぱちぱちと祝福の手を叩く。
「いかにも、その通り‥‥答えは影。太陽に従うもの。運命の者には、簡単な謎じゃったかのう」
「‥‥なぜ、あなたはここにいるのでしょうか」
笑んでゆっくりとピラミッドを降りるスフィンクスを見、その言葉を聞いて、アルフレッドは疑念を尋ねると、その女の顔は答えとしてくいと、あごでピラミッドの上を指し示した。
「妾は、妾が主の命により、永劫の時の中、この遺跡を守りし者。この遺跡に眠りしは太陽の影。太陽の神が永久に求めし者」
「‥‥一体、どういうことだよ?」
聡の問い返しにその精霊は答えることはなく、ただ微笑みとともに遺跡へと導くのみ。その様子に周囲に警戒を向けながらも一行は遺跡を登り、上部にある扉の前にたどりつく。
「‥‥これは?」
「何かの名前のようですねえ」
目の前にある扉に刻まれていた象形の文字を目にして、シェセルが疑問の声を上げるやいなや、ユイスが即座に答えを返す。
「どうやら、王名表、という奴でしょうね〜。‥‥ほら、この遺跡の初めの、大きな石扉にあったものと、ほぼ同じ内容ですよ」
さらさらとユイスは流れる水のように答えると、そのまま象形文字をなぞり、つと指を下へ向けて滑らせた。
その下がった指の先には、先日奪われたと目される王名表が書かれた石扉と同じ場所が削り取られ、名を無くしていた。
その様子を確認しつつもシェセルは周りのものにうながすと、改めて扉に手をかけ開け放つ。
石の扉が重々しい擦過音を響かせて開いていくと、幾百、幾千の時を越えたせいだろうか、ひんやりとした冷気が中より漏れだした。
「これは‥‥」
外の暑さとは、さらには日の射さぬ遺跡の冷たさとは、さらに一線を画した寒さが辺りを覆い、遺跡の中へと漏れだしていく。
陽の光も少なき暗闇の奥に目をやれば、天井にある工夫された明かり取りの窓からだろうか、白銀の光が射し込んで広がり、部屋の中央を照らし出していた。
それは、黄金で飾られた棺であった。エジプトの遺跡より発見されるそれらの数多の例に漏れず、人の、ミイラの形をかたどったその棺桶は、顔の部分だけが切り取られ、臆することなく中をのぞかせていた。
「‥‥人がいるぜ」
「‥‥ほんとだ」
好奇心とともに近寄った聡と麻はその顔の部分にあいた穴より中を覗き込んで、一言、光景を口にする。
その荘厳な棺の中には氷で包まれた、見目麗しい女性が、今にも生きて動き出しそうな雰囲気を持ったまま、氷付けにされていた。
「‥‥ラミ、ア?」
面食らうような麻の言葉に、中の女を見た一同は記憶を奮い起こし、やはりその通りであったかと思い直す。
その驚きの言葉にもかかわらず、氷の中の眠り姫は起きることなく静かに、安らかな眠りについたままだった。
柔らかに思える陽光の中、ナイルの波に逆らい、船は上流へと進んでいた。その帆にはエジプト総督府の紋章が飾られ、船の所有者がヘンリー総督であることを堂々と知らしめている。
「あまり、目立ちたくはないですね」
「同感です。でも、そうも言ってられないのでしょう」
ナイルの川面に浮かぶ船の上の人となったネフェリム・ヒム(ea2815)は感想をつぶやくと、息を吐きながらティレス・フォンターヌ(ec1751)もそれに同意した。船には、エジプト南部探索隊への補給物資と、追加の人員‥‥アンデッドの出現が報告されたためか、クレリックがそろっている‥‥が乗っていたが、それを喧伝するのは、エジプト総督府がまだ健在であるとのことを示すためだろうか。
アトンやそれ以外の便乗した人々、夜盗の活動が活発化している昨今、あまり気分のいいものではない。
「ガルゥくんが、無茶をして怪我でもしていないか、心配ですね‥‥」
「お知り合いがいるのですか?」
髪を静かに撫でる風に向けてヒムが一言つぶやいた言葉を、その背丈の半分にも満たないエミリアは聞きつけて、男に尋ねかける。
「ええ。ちょっと、ね‥‥結構無茶しますからね、心配ですよ」
そうして言葉を交わし、仲を深める一行が、ルクソールを過ぎて早数日。
その事態は唐突に訪れた。
「これ以上進めない?」
突然の船長の言葉に、一同が驚きをあげる横、水夫たちは積み荷を、一時預けの倉庫へと運び、船の帆を畳んで陸にあげようと忙しく働いていた。
「ああ、当分の間、ここから先には進まない予定だよ」
「一体、なぜです?」
突然のことにティレスは呆れ、ネフィリムは冷静なつもりでその理由を問うた。
「詳しくはわからないんだが‥‥どうやら、この先のナイル沿いに、魔物が出るらしい」
「魔物?」
エミリアの声に船長はうなずくと、貴重な地図を開いてみせる。
エジプトの大地を東西に割る大河ナイル。そのナイルの上流、アマルナに向かうまでのところで、魔物が現れ、船が襲われているらしい。近隣の村々の中には連絡が取れないところもあり、混乱は静かに広がっている。
「アトンのせいじゃないのかしら。村を襲って物資を確保するとか」
「それにしても規模が違いすぎるのでは‥‥」
「ともかく!」
地図を前に頭をつきあわせ相談を始める一同に、船長は語気荒く声を上げて地図から一同を引っぺがし、、一言、突きつけた。
「ここから先に向かうのは、船じゃあお断りだ。先に進むんだったら、総督府にラクダでも用意してもらうんだな!」
それは暗き黄泉への道行きか、あるいは絶望が希望に姿を変えてそっと手招きしているのか。岩砂漠の真ん中にぽっかりと、それは口を開いていた。
「どうやら、ここのようですねえ」
目の前に散らばる破壊された石扉の破片をちらりと見て、烏哭蓮(ec0312)は前に立つ天城烈閃(ea0629)とアフロス・エル・ネーラ(ez0193)を向いて嘆息した。その視線を受け止めるまでもなく、ネフィラは先頭に立って歩みを進めると、二人も辺りを警戒をしつつその後に続く。
一行がアトンたちを留め、向かった先は、アトンのリーダー、アデムサーラ・アン・ヌール(ez0192)が向かったという遺跡。その遺跡には彼が手に入れたという、エジプトの栄光を担う太陽の神が封印されているらしかった。
その真実はどうであれ、ギーレン将軍という強敵を迎えた今、アトンはリーダー不在のままの烏合の衆として動くことはできない。そう感じた3人は、遺跡の探索も行うために、アデムサーラの跡を追った。
入口からたいまつを灯して入れば、暗闇は坂とともに下へと続き、永劫に終わることがないかのようにも思われた。
「まるで、黄泉比良坂だな」
「さて、冥界の力を求めたのはあなたでしょう」
天城のこともなげな言葉に、忍び笑いで烏は返すと、一行は広間と、その奥にまっすぐ傾くことなく続く通路へと、逡巡することなく歩む。
「‥‥下僕を、増やしておきますか」
盗掘者か殉教者か。広間に数多く倒れる、どちらかわからぬ近くの死体に目をやりながら、烏が死者の法術を唱えると、むくりと冥界よりの使者が周りに立ち上がる。
それらを前に置いて一行が暗い通路を進んでいけば、目の前から暖かな、地底にはありえない太陽の光が漏れて見えた。
「‥‥あれは、何なのかしら」
「時刻は昼だが‥‥あそこはどう考えても地下のはずだ」
はるかな地価で起こる異様な現象に、明らかな疑念が生まれるものの、戻る理由も見つけられず、一行は歩みを進めた。
果たして陽光の先には、荘厳な雰囲気の漂う広間が横たわっていた。
それは謁見の広間というべきだろうか。丁寧に処置され、装飾と武装を施された数十のミイラが、道の両側に槍を交差させながら立っている。その道の奥、10mほど先には、祭壇へと上る小さな階段と豪華な玉座がしつらえられ、謁見の準備が整っていた。
「あれは‥‥」
「なんなのかしら? でも、何か嫌な予感がする」
天城のつぶやきに、額に汗をにじませて、ネフィラが答えた。その小さいはずの声が反響すると、祭壇の前に見えた数名の人影が、誰何の声とともに振り返る。
「誰だ?」
「おや、目当ての方のようですね」
面白くもなさそうに卯が答えた相手はアデムサーラ。面食らうという意味では同様に、男も怪訝な表情で尋ね返す。
「なぜ、ここに‥‥? アトンのみんなはどうした」
「そのことで話がある」
アデムサーラの尋ねる声を遮るよう、天城は声を上げ、そして辺りを見回した。
「‥‥ここは俺に任せて、早く戻るんだ」
「? わからん‥‥ここが私たちの探していた太陽の遺跡だ。そこについたのに帰れ、と?」
烈閃の突然の言葉に、怒声をあげながら男は答えると、すぐさま玉座へと振り返る。
その玉座は古きエジプトに伝えられる戦女神の守護獣、獅子の皮で彩られ、数多の象形文字に囲まれていた。松明の灯りが静かに照らせば、それは張られた黄金によってまばゆく、永久の時など関係ないように輝きを発する。
「もう少しで、この遺跡に封じられていた力を手に入れることができる‥‥偉大なる太陽神の力だ」
「それを求めて、どうするのです」
「もちろん、私たちの理想を成し遂げるためだ」
烏の鋭い瞳を正面から見据え、アデムサーラは鋭く切り返す。
「君たちの力添えは感謝している。だが、私たちが本当にこの地を、私たちの手に取り戻すには、神の威光が必要だ‥‥中東の者たちの神に匹敵するような」
「神、ですか?」
烏の声に軽くうなずき、アデムサーラは答えを続ける。
「アラビア教の神、アッラー。その力を持つ神官、神官戦士がいるという。ギーレンの手品の種も、おそらくは、な」
「そういえば、あの男が傷つくと同時に、周りの別の者が倒れていたりしてたようですねぇ」
「まもなく、神の威光が蘇る。私たちの崇める偉大な太陽‥‥アトンが」
「待つんだ。本当に、それは求めるべき力なのか?」
アデムサーラが祭壇に戻ろうとした時、天城はその肩をつかんで、歩みを止めさせる。すぐさまその手を払いのけながら、アデムサーラは静かに、極東より来たる戦士を見つめた。
「何を‥‥」
「太陽の神については、栄光が蘇るだの、苦難に導くだの、不可解な情報だけがあって、真実は不明だ。それが、どのような力かも俺たちにはわかっていない」
「だから、どうした」
アデムサーラは忠告と言える言葉を見据えて、しかし無視して玉座に向かう。
「アデムサーラ!」
「これだから、猿は‥‥!」
二人の様子にネフィラが駆け寄り、烏は下僕たる木乃伊を動かした。烈閃も一歩、さらに踏み出すも、アデムサーラとともにあった戦士二人が割って入り、機先を制する。
「‥‥太陽の神の名の下に、今こそ黄泉還れ、偉大なるエジプトの栄光よ!」
混乱の中、アデムサーラの朗々とした声が響き渡り、一瞬、黄金に彩られた壁面が太陽の山吹色に彩られると、天井より目も眩むような光が射し込んで、辺りを明るく染め上げる。
「これは、太陽?」
煌々と輝き遺跡の天井に座するは、まさに小さな太陽そのもの。現れた陽光と炎の塊は、その体から炎の触手をたぎらせながら、悠々と地に伏せる者たちを睥睨する。
「あれは、陽精霊? ‥‥今はもう、名も知られぬものの一つ」
「アトン! 偉大なる太陽の神よ! 我々の栄光のために、その力をお貸しください!」
ネフィラのつぶやきに応えるよう、天を仰いで敬虔に、アデムサーラは祈りを捧げた。
だが。
「う、うわぁ!」「アデムサーラ! 何だ、こ、こいつらは!」
カタカタと音を立て、戦士に組みかかる干からびた腕。その腕はゆっくりと衣服を切り裂き、革の鎧に傷をつける。
その叫びにあわせて見渡せば、倒れ伏していたミイラの数々が、ゆっくりと大地に手をつき起きあがり、手に手に槍を取って並び出す。
「哭蓮!」
「残念ですが私ではないですけど、ねっ」
挑みかかるミイラの一撃を刀で受け止め声上げる天城に、烏は下僕を前に距離を取った。
「控えよ」
突如、重苦しい声が明るきその部屋に満ち、そして威厳は形を取って玉座に生まれ出でた。
その身を包むは古びた包帯、だが香油は体を清め、堂々たる体躯を見せつける。その尊顔は黄金にて、遠きを見つめる瞳はそのまま、その場にある一同をねめつけた。
「貴様は、何者だ!」
「‥‥控えよ、愚民が!」
それは王の偉容か、古代の呪いか。一喝とともに漏れだした瘴気は空気を闇色に染めて、周囲を侵食する。
「ひ‥‥うわぁっ!」
誰何の声を上げた戦士が、その重圧と恐怖に耐えかねて、剣を抜いて斬りかかった。だがその一撃はミイラの手にした巨大な杖で反らされると、開いた残り片手の爪が、鋭く男の体を薙ぎきり裂く。
一瞬後、男の傷が干からびると、衝撃に倒れ、男はひいひいと声にはならない息を上げる。
「どうやら」
背骨と皮膚の間をぞろりと駆け上る恐怖に、烏の額からは脂汗が流れ落ちた。
「あれは、生気を吸い取り万物を塵へと帰すよう、ですねえ‥‥」
意図せぬ震えた声の中、倒れた男に瘴気が絡みつき、その身に帯びた鎧や剣を塵へと返していく。
「よく、我を呼び戻した。偉大なる太陽の申し子よ」
玉座に戻り、そのミイラは厳かに告げて、周囲を見渡す。
「かのアモンを報ずる、邪悪なるものどもに我と偉大なるアトン神が封ぜられてより、過ぎたるは悠久の時。今こそ、アトンを報ずる我、イクナートン、偉大なる王がこの地を治める時なり」
「は‥‥は」
恐怖の重圧が染み渡り周囲が塵に帰る中、アデムサーラは蒼白で頭を垂れ、その場に釘付けとなる。
「まずは、この大地に我の威光を、あまねく広めるため。我とともに永劫の時を仕えることを望みし兵が、愚なる民人を組み敷き、大地に充ち満ちる時は今」
イクナートンの無表情な黄金の仮面が、ほころばぬ口元より思いをつぶやくと、待ち受ける未来の展開に微笑んだように、太陽の光がさざめいたように見えた。
「‥‥させるか!」
プレッシャーと瘴気にその身に纏った仮面をも崩しながら、烈閃が叫び、走り出す。だがその前には、玉座の前に並んだ十数体を越えるミイラたちが、槍ぶすまを形作り、走る男を牽制する。
「‥‥不遜なる者め」
どかりと玉座に体を沈めつつ、イクナートンはその瞳を輝かせる。
「太陽に近づきし愚者は、太陽に焼かれて地に墜ち死する。‥‥灰となれ」
その手が印を結ぶ用に持ち上げられ、瞬時の高速詠唱が行われると、同時にこの空間を満たす太陽の光が収束し、そして放たれた。
白き陽光が空気をつんざき、男の胸に集い放たれると、肉の焼ける嫌な臭いが瘴気に気圧されながらも動きの鈍った男を包み、そして血が辺りに飛び散った。
「‥‥いき、なさい」
その動きにやはり気圧されながらも、すぐさま烏は命令を下すと、数体のミイラが意に従って飛びかかる。だが王の僕たる遺跡のミイラは機敏に槍を操ると、1体を3体で囲むように、すぐさま敵をつるし上げる。
「永劫の僕を持ちたるは、定明の者とて誉れとならん。だが、所詮は付け焼き刃、天に唾する所業」
同じ印を組む様子に、烏は下がって身構えるものの、天より集う陽の光は男を逃がすことはない。
白き死装束は黒き炭と化し、肌より剥がれ落ちた炭はそのまま、王の気に当てられて塵へと化していった。
「‥‥逃げるわよ」
「‥‥仕方ない」
王の隙、ネフィラが呼びかければ、烈閃は烏を助け起こし、血唾を吐き捨てながら、一気に後退する。
「‥‥さて」
生きるものは去り、死すべき時のものは倒れたまま残る場所。ただ、まだどちらでもない、後悔と恐怖に駆られるものが残りし謁見の広間。
古き王はそれを路傍の石と意に介せず、くつろぐように頬杖をつく。
「偉大なる太陽の神が再臨する時。太陽と月がともになりし時、世は新たな世を向かえん‥‥威光を、あまねくこの地に広めるのだ‥‥」
その、ミイラという本来の死体からはわからない笑いだけが、その部屋に染み渡るように広がっていった。
「どうやら、ナイルの上流に向けての川路が封鎖されたようです」
「ええーっ!?」
ホルスと名乗る外套で顔を隠した男が、その主たるローブの人物に告げると、その脇、ひらひらと飛びながらケヴァリムは驚きの声を上げる。
場所はルクソールより数日の、ケヴァリムが軟禁されていた村より数日のところにある、ナイルのほとり。ホルスが告げる通り、いくつもの船がその場所で、ナイルの上流に向かうことを止められ、停滞していた。
その場に留まる船は民間のものだけではなく、エジプト総督府の紋章を掲げた大型のものも見受けられる。
その下、船より下りたところを見れば露骨に船主と船長、船員の喧嘩が起こっており、突然の災害が起きたのかと思わせるには十分であった。
「いきなり封鎖なんて‥‥一体、何があったのさ?」
「のさ?」
「‥‥わからんな」
ケヴァリムが妖精とともに飛んで疑問符を浮かべる中で、ホルスは苦虫を噛み潰したように、かすれた答えを答える。
「突然‥‥モンスターか夜盗かはわからんが、川の途中で大規模な襲撃が起こったようだ」
「もしかして、アトンって奴? ‥‥みんな、大丈夫かな」
シフールの心配を見て、もう一人の男は静かに首を振り、朗とした声音で言い放つ。
「‥‥暗き太陽が昇り始めた。そうだな」
「‥‥おそらくは」
ホルスは、主人の言葉を逡巡しながらも認めざるを得なかった。
ここでNOと言えば全てが無かったこととなるのであれば、男はそうしたであろう。いくらかの迷いの響きは、そう聞こえる。
「ところで、暗き太陽って、一体何さ? 俺、ぜーんぜんわかんないんだけど?」
「そうです」
街の路地の端、人の来ぬところでの話を聞きつける者は、偶然ではなく、その意志があったと思える。それほどの意志を感じる声の主は、ラミア・リュミスヴェルン(ec0557)であった。
その姿は旅でやや薄汚れてはいるものの、可憐なる踊り子姿は健在である。
「それに、私たちを襲ったり、遺跡のものを盗んだり‥‥あなたたちの目的は、一体なんですか?」
その言葉に、険悪な雰囲気が両者に漂い始める。男は静かに瞳を細め、ホルスがゆっくりと重心を移動させた。ラミアは応じて、その腰にくくった魔力あるナイフに手をかけ、そして‥‥。
「ちょーっと、まったぁー!」
緊迫した間にタッシリナージェルとともに飛び込んで、ケヴァリムはくるくる、一同を睨みつけた。
「今は、そうやって争ってるとこじゃないだろ? みんなのことも心配だし、協力できるならそうするべきだと、俺は思うな!」「なっ!!」
「‥‥確かに、な」
「若!」
自嘲にもとれる小さな笑いの後、男は覆面となる布を取り払い、ホルスはその行動に驚きの叫びを上げる。
「暗き太陽が昇りし今、いがみ合う暇はないだろう。今に、それをすることすら、できなくなるかもしれない」
「‥‥えっ?」
「‥‥!」
そのヴェールの向こう、現れた顔にラミアは息を飲み、ケヴァリムは困惑に囚われる。
その顔は、男と女の違いはあれど、まさにラミアに生き写しだった。
「ちょ、ちょっと、一体どーいうこと?」
「太陽に、月を抱かせてはならぬ。王名を蘇らせてはならぬ」
ケヴァリムの問いかけを無視し、男は静かに言葉を告げる。
「太陽が月を伴侶とし、王として新たに即位する時。それこそ真昼の夜が訪れる時‥‥この地が古き妄執の支配によりて、滅びる時となる。我らは力を合わせて、これを止めなければならない‥‥」
今回のクロストーク
No.1:(2007-04-05まで)スフィンクスの謎かけの答えは、一体何か?
No.2:(2007-04-05まで)
今回、あなたは誰/どこのために、どのような行動をするのか? それはなぜか?
No.3:(2007-04-03まで)
あなたは、今のエジプトの治世をどう思いますか? そしてこのエジプトを治めるのにふさわしい人物はいますか?